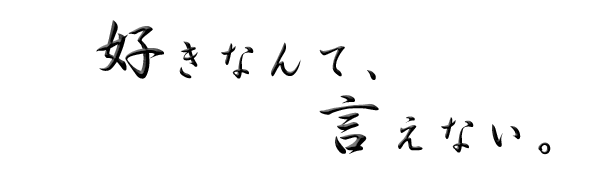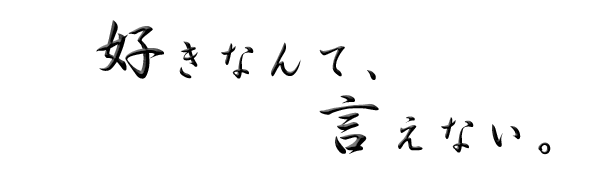|
<3-4>
「まだ起きてるのか?」
もうすでに数えるのも嫌気が差してきた何度目かの寝返りを打った時、不意に声をかけられた。驚いて声の方を振り返ると、藤井がベッドの上に起き上がっている。つけたままになっていた腕時計を見ると、暗い明かりの中で三時を告げられた。
「コウ?」
小さな声だった。もし眠っていたらと思ったのだろう。だけど見ていたのなら分かっているはずだ。俺の寝返りは、起きていたにしては多分多すぎたと思う。
それにしても、藤井は? もう寝たと思っていたけど、まだだったのだろうか?
「……智も、まだ起きてた?」
一度その名を呼んでしまうと、もう呼ばないわけにはいかない。いや、呼ぶだけでほんの少し幸せになれるその名を呼びたいから、省けるものをわざわざ省かずにいる。
「話、していい?」
「いいぜ。こっち来いよ」
なんとなくそばに寄りたかった。どんな事でもいい、話をしていたかった。
そう思って問いかけてみると、藤井はどういうわけか自分の布団をめくって俺を誘う。
……それは、いったいどう解釈すればいいんだろう?
俺は電気をつけて座って話をするつもりだったんだけど……。
「はぁか。何もしやしないよ。こっちに来た方が話、しやすいだろう?」
本当に言葉どおりとってもいいのか分からなかった。何もないなら、わざわざ言い訳めいた事をいう必要もないだろうのに。
だけど。
だけど、俺はこの試験が終ったら藤井には本当の事を言うつもりだ。そうすれば否応なくこの関係は終ってしまうだろう。それなら、そばに行って甘えるような事をしてみるのもいいかもしれない。きっと最初で最後のチャンスだろうから。
起き上がった俺は布団を抜け出して、枕だけを持って藤井のベッドに、彼の隣、腕の中に潜り込んだ。こんな事が出来たのはきっと電気を消したままの薄暗い部屋の中だからだ。まさか本当に来るとは思っていなかったらしい藤井は少し驚いたように震えたけど、そのまま包み込むように俺を抱き寄せてくれた。
「両親が離婚するんだ……」
そのあたたかな腕の中で、ぽつりと呟く。
書類上はまだだったけど、時間の問題。そのままなんと続けようかと迷っている俺の頭を、藤井はただ優しく撫でて次の言葉を待ってくれている。
「それを聞いたのが、あの雨の日。離婚するだろうってことは前々から分かってたけど。目の前で俺のおしつけあいはじめられると、さすがにこたえた……」
本多にもいわなかった事を、俺は何も考えずに口にしていた。いつの間にか藤井の腕が背中に回っていて、俺をぎゅっと抱きしめてくれる。それだけで、心が温かくなる。
「嫌な事って、それか?」
そう問うてきた藤井に、俺はただ頷く。そえ以上何も聞かない優しさが嬉しかった。
「それだって分かってた事だったのに、それでも当たり前に衝撃を受けてる自分にすごく驚いた。自分で何がなんだか分からなくなってたんだ」
そこまでいったところで、藤井は指先でそっと俺の口を塞いだ。もういわなくてもいいと、低い声がささやき、優しい目が俺を覗き込む。
だけど。聞いていて楽しい話じゃないだろうけど。俺は聞いてほしかった。だから、軽く首を振って話を続ける。
「今日は両親と、その再婚相手に会ってた」
落ち着かせるように俺の背をゆっくり撫でていた藤井の手が、ぴたと止まる。それはまぁ、最初の俺の醜態の理由が分かれば、十分驚くに値する理由だろう。俺はあの時ほど落ち込んではいないのだから。
「相手の人も、その子供もすごくいい人で、俺は素直に良かったと思えた。二人ともすごくしあわせそうだったし。だけど、そう思える自分に一番驚いた」
本当に良かったと思う。こんな風に思えるのは、全部藤井のおかげで、俺の目的は成就された。多分、藤井の目的の方も。
だけど、それだけはいえない。言った後で振られるのだけは、絶対に嫌だから。
「……智の、おかげだと思う。ありがとう」
だから。
伸び上がるようにして藤井の首に手をまわして、抱きついて。ゆっくりと唇を重ねた。ありったけの思いを込めて。藤井は何もいわずに俺を抱きしめていてくれる。
「もう俺は必要ないなんて事、いわないよな?」
真っ赤になってしまった顔を隠すために藤井の胸にうずくまった俺に、優しい声が降ってくる。答えを待つように、促すように、落ち着かせるように何度も何度も背中を撫でられた。
「…………おやすみ…………」
質問には答えられなかった。眠れないのも分かっている。だけど、俺にはそう答えるしか出来なかった。
|