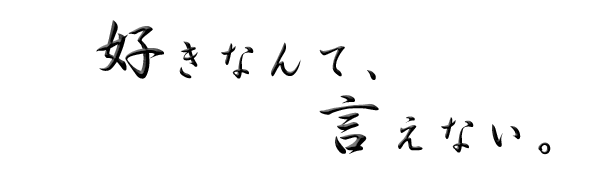|
<2-3>
「……君が、コウくん?」
本多はそれだけしか言えなかった。そのまま黙り込んでしまったのも無理はない。
喫茶店の手伝いを終えた藤井に引き連れられて、俺と本多は彼の部屋に入っていた。中に入って、円を描くようにじゅうたんの上に座り込む。例えようもなく居心地が悪かった。藤井も本多も、お互いと俺をにらむように見比べている。
「……どうして祐一がコウと一緒にいたんだよ?」
やっと口を開いたのは藤井。凄まじく機嫌の悪い声だ。
「なんでって言われても……」
必死になって恋人を探してやった従兄弟に随分な目でにらまれながら、本多は混乱する頭の中を必死で立て直しているようだ。俺の事を何と言うか悩んでいるらしい。彼の一番簡単な答えは、クラスメイトだと言う事だろうのに。
「お前のコウくんを探すのを手伝ってもらってたんだよ。なぁ、幸司」
「あ、うん」
急にこっちを向いて、かなり強い調子で同意を求められて、俺は思わずうなずいていた。うなずいて、すこし落ち着いて分かる。本多は本当の事しか言っていない。俺に訳があると思ったのだろう、全ての選択を俺に残してくれた。あるいは、押し付けたのかもしれないけど。
だけどうなずいたらうなずいたで、そうすればこんどはなんで名前で呼んでいるんだとにらみ付けてくる。正直俺はどうして藤井がこんなに怒っているのか分からなかった。
「……幸司、今日までどうして来れなかったか説明してやれ。こいつ、俺に妬いてやがる」
は? 妬いてる?
言われてる事が理解できなくて、俺は思わず本多と藤井を見比べた。本多は何やらニヤニヤと笑っているし、藤井は心なしか頬を赤く染めている。
妬いてるって。……えっと……。
「風邪で熱が出てて。……家でずっと寝てたから……」
正確に言うと昨日は違う。だけど、本多もその事については口を挟まないでいてくれた。
家で寝てた、とそこまで言ったところで、すこし離れたところにいたはずの藤井が俺の手を急につかむ。泥いて顔を上げると、藤井の心配そうな顔がある。
「コウ、風邪って。もう大丈夫なのか?」
俺が風邪を引いた理由などお見通しだろうに、心配してくれるのがありがたくて俺はとりあえずただ頷いておく。実際にはまだ時々咳が出たりするのだけど、もう寝ていなければいけないほどひどくはない。
「疑いは解けたか、この早とちりが。俺の片思いの相手はお前だって知ってるだろ」
本多が藤井の頭を軽く叩きながら、なんだかとんでもない事を言った。それでも藤井はそんな事を聞き流してしまっているのか、本当に知っていて疑ってもいないのか、ただごめんとだけ謝っている。
しばらく二人で何なら話していたが、やがて端から見ている限りでは本多が藤井を丸め込んだ形で彼を部屋から追い出してしまう。何か飲むものを取りに行かせたらしい。部屋の中には本多と俺だけが取り残された。
「幸司」
かけられた声は、さっきまでよりもすこし冷たいような気がしたのはきっと気のせいではない。思わず肩がびくりと震えるのが自分で分かる。だけど、出来るだけ平静を装った。とても平静でいられないからこそ、よけいに。
「……智を騙してるのか?」
さっきまで藤井と笑っていた顔とはまるで違う。それはそうだ。本多なら、騙されているかもしれない藤井の相手を探すために普段は声もかけないようなクラスメイトにまで助力を申し込んだ本多なら、俺のしようとしている事は許せはしないだろう。
「智を騙して、もてあそんで捨てる気か?」
恐ろしくて本当の事なんて言えなかった俺に、本多はさらに言葉を重ねる。
藤井のそばにいたいと思った。だけど、彼に嫌われるのも恐かった。せっかく話が出来るようになったクラスメイトの手を離すのが怖くて、俺はため息とともに言葉を落としていた。
「年下だとは、言ってない……」
それは、苦しい言い訳。自分でも分かっていた。俺が藤井を騙しているのはまぎれもない事実だ。相手が勘違いしていると知っていて黙っているのは騙しているのと変わらない。そのうえ、俺の気持ちが落ち着いたら別れようと思っているのだから、もてあそんで捨てると言われても、文句など言えようはずもない。
きつく結んだ手を見つめながら、唇を噛み締める。何の言い訳もできないのが辛かった。かたかたと震える体を止める事ができない。多分、俺は藤井の事が……。
「いいのか、幸司。ちゃんと言っておかないで」
……え?
そっと、それこそ年下の小さな子供にでもするように、本多は俺の頭に手を置いた。目を上げるとさっきまでのきつい瞳はもうどこにもない。
「言いにくいんだったら、俺がちゃんと言ってやるから。本当は年上なんだって言っておいた方がいい。どうせあいつが勝手に誤解してるんだろう? お前みたいな奴が嘘をついてるのは、無理だよ」
俺を見て何をどう判断したのか、本多は目を覗き込むようにして話してくる。だが俺が答えようとした丁度その時、階下から足音が聞こえてきた。藤井が戻ってきたらしい。
チッと舌打ちして離れる本多に、俺はただ首を振って答えた。言う必要が出来れば、その時は自分で言う。それまでは今のまま、子供のように藤井に甘えていたかった。年下として彼に会っている時は、人に甘える事が出来た子供の頃に戻れるような気がしたから。
「分かった。したいようにしろよ。俺は味方だからな」
離れ際、本多が耳元で囁くように言い残したちょうどすぐ後、藤井が戻ってきた。カップを三つ乗せた盆を片手で支えている様はまるでバイトをしている最中のようだ。座ってから何も聞かずに俺にココアを、本多にコーヒーを手渡し、自分用に入れてきたらしい紅茶のカップを手に取る。
「コウ、それ飲んだら駅まで送るから」
大好きなこの店のココアを一口、二口とすすっていると、藤井が拒否する事を許さないというような強い口調でそう宣言した。それは問いかけではなく、すでに決定。どうしたものかと思案していると、横から救いの手が述べられる。
「駅までだったら俺も行くから。送るよ。お前は家の手伝いでもしてな」
そろそろ閉店時間も近い店は、後片付けの手を欲している。それが分かっているから藤井も何も言い返せないらしい。
結局俺達はそれぞれの手の中にある飲み物を口に運ぶ事に専念した。その間ほとんど何もしゃべらなかった。妙に重苦しい沈黙を誰も破ろうとしない。
どんなにゆっくり飲んでいてもたかがカップ一杯のお茶。なにもしゃべらずに片付けに入っては十分もかからず飲み干してしまう。カップを干した俺は横の本多に目配せをして立ち上がった。彼の手のカップも既に空になっている。
「じゃぁ、また」
いつ、とは言わなかった。そうするとその俺の姑息さに気付いたのか、藤井は怒ったようにきつい目で俺をにらみ付けてくる。
「明日。また来いよ」
それには曖昧に笑って頷いておく。もともとくる事自体に異論があるわけではない。ただ、状況がここにくる事を許すかどうかが分からないだけだ。
「コウ、キスしていい?」
「ヤだ」
別にいいと言うのに玄関まで送ってきた藤井がそう耳元で囁くのに、俺は反射で間髪入れずに答えていた。藤井はしぶしぶと言うように俺から離れていく。約束が復活している事に、心底ほっとした。
そのやり取りを本多は面白そうに見ていたけど、結局何も口にはしなかった。彼の無言の圧力に負けて藤井は俺を早々にはなし、俺達二人は駅に向かって歩き出した。
|