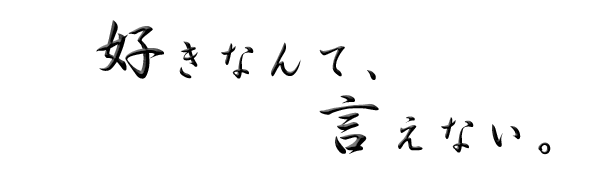|
<2-1>
次の日も、その次の日も。俺は結局起き上がれなくて、学校を休むはめになった。一日寝ているしか出来ず、いろいろな事が頭の中を駆け巡る。両親の事とその恋人の事、学校の事、進路の事、そして……藤井の事。
ただ寂しさを紛らわせるためにそばにいようと決めた。だけどその決定から間を置いて考える時間が増えれば増えるほど、どうしていいのかも、どうしたいのかも分からなくなってきていた。
多分、藤井本人に言ったように、俺は俺を必要としてくれる誰かのそばにいたいのだと思う。子供の頃はそれが両親だと思っていた。俺には両親が必要だったから、彼等も俺を必要としてくれていると思い込んでいた。だからそうじゃないと分かった時にはどうしていいのか分からなくなったのだ。それでも誰も俺を必要としていないのだと理解するのに、たいした時間はかからなかった。そんな環境に置かれてしまった。
そんな益体もない事を考えながら日曜、月曜と二日間寝たきりで過ごしたおかげだろう、火曜日の昼頃にはなんとか体が動くようになってきた。
起き上がって簡単な食事を作って食べて、母さんに電話をした。昼間だから父さんは今家にいないだろうと、まず母さんに。父さんには夕方にでもかければいい。
ほとんどかけた事のない番号なのに、なぜか指は知っていた。何も見ずにかけたその電話の向こうで、母さんの声が林田とは違う名を名乗る。
「話したい事があるから、明日の夜こっちに来て」
帰ってきてと言えないのが寂しいけど、それは仕方がない。彼女は今何のためらいもなく名乗ったように、既に林田ではないのだ。少なくとも、気持ちの上では。そんな俺の気持ちに気付いたか気付かないか、電話の向こうの女は驚いたように息を詰めた。
「……うん。父さんには俺が連絡するから。夕飯作るから、何も食べないできてよ」
言いたい事だけを言って、電話を切った。母さんがうなずいたのだけを確認すれば、もう何も言う事はない。多分話の内容を知りたかったのだろうけど、それを母さん一人だけに言う気はなかった。
これで夜になったら父さんにも同じ電話をすればいい。言う事は決まっている。経済的に負担がかかる事が分かっていても、結局二人は俺が言う通りにしてくれるであろう事も、分かっていた。
それにしても、母さんはいったい何を思ったのだろう? 父さんも呼ぶ事を知って安心したと言う事は、俺が母さんのところに行くと言うとでも思ったのだろうか?
そんなこと、あるはずがないと言うのに。
「さて、と。家の中、片付けよう」
ようやく動けるようになったから、洗濯機をまわして、掃除機をかけよう。日曜日にするつもりだった家の事を、俺はこまごまと片付けはじめた。
そうして夜になって、俺は父さんに電話をする。最初に出たのは多分子供だろう、小さな男の子だった。それでもすぐに父さんと変わってくれて、俺は母さんにしたのと同じ話をする。呼び出す用件をいぶかしみながらも、俺からそんな事を言い出すのが珍しいのもあるだろう、来ると約束はしてくれた。だから、俺はまた明日と言って電話を切る。
すごくしあわせそうな声が後ろから漏れ聞こえていた。子供と、その母親が笑っている。そんな中に居れば、父さんもきっと幸せに違いない。
これで良かったんだと思う事にしよう。全ては明日。話をしてからの事だし。
次の日学校が終ってから、俺はまっすぐ家に帰った。ちらりと藤井の事を思い出しはしたけど、頭を振ってその顔を思考の中から追い出す。会いたいとは思っていた。寝込んでいた分だけ会えなかった事もあって、その思いはよけいにつのっている。自分を必要としている人に会って自信を付けて両親に会うという事も考えないではなかったけど、そうするときっと言いたい事が言えない気がした。こればっかりは、人に頼りたくはなかった。だから無理矢理、思考から追い出してしまう。藤井もまさか、本当に毎日待っていたりはしないだろう。
夕食の準備をして、二人がやってくるのを待つ。きっと、普段の俺がどうやって食事をしているのかなんて事は、あまり心配していないだろう事は分かっていたけど、それでも一人でちゃんと生活が出来るのだと言う事をはっきりと示しておきたかった。まぁ、今でもほとんど一人で暮らしているようなものなのだけど。
六時過ぎに母さんが来た。どうやら恋人が車で送ってきたらしい。ドアベルの鳴る音の前に、車の去って行く音がした。
「いらっしゃい」
何も気付かなかったように、俺はドアを開ける。ちょっと困ったような顔をした女が目の前に立っていた。ほんの数日前にあったばかりだと言うのに、見た事がない人に見えるのはなぜだろう? 俺の母親は、こんな顔をしていたんだろうか?
そんな彼女をなだめるようにして中に入れ、茶を出してやる。話を聞きたがっているのは分かっていたが、とりあえず二人そろうまで待って欲しいと言っておいた。
そうして息のつまる時間がしばらく続いて、やっと父さんがやってきた。二人は俺が用意した食事をただ黙々と食べる。その間いっさいの会話もなく、沈黙だけが場を支配していた。
必死で作った食事は、十分においしかったはずだ。だけどなんだかまるで味を感じない。多分前に座っている二人も同じなのだろう、味についての感想はいっさいなかった。
食事が終ってから応接に移動して、茶を出してから俺は二人の前に座った。
「一人で暮らしたい」
ひとつ息をついてから、俺は二人に向かってきっぱりと言い切った。経済的に負担をかけるのは分かっている。それでもどちらとも一緒に暮らす事は、多分出来ない。そう前置いてから部屋と、大学の事を話すと二人は少しほっとしたようだった。多分俺が今言った方法も、考えた事があったのだろう。
それでも今はお互いに家族がいる。しかもこれから父さんは子供の進学、母さんは出産にとお金がかかる時期になっている。だから一応相談すると言って、二人は帰っていった。それでも多分、話はこれで落ち着く方向に向かうはずだ。彼等にもきっと、他にいい選択肢はないに違いない。
それでいいと思った。
「お前ももう、受験を考える年になっていたんだな。気付かなかったよ」
帰り際に父さんがそう言った。うん、父さんも母さんも気付いていない事は、俺も分かっていた。二人がすでに俺に感心をなくしている事など、ずっと前から知っていた。
「気にしなくてもいい。それよりもさっき言ったこと、真剣に考えてほしい」
多分それがおれたち家族に取って、一番いい方法だと思うから。
木曜日、学校に行くとちょっと信じられないような騒ぎが起こっていた。藤井智と言う下級生が誰かと付き合い出したらしいと言うその噂は教室に限らず、廊下にいてもどこにいても耳に入ってくる。誰かと付き合い出しただけでも噂になるほど彼は有名だったのかと、自分の疎さにちょっと驚いた。その噂自体は昨日も、俺が休んでいた週明けすぐにも囁かれていたらしいのだけど、家の事だけを考えていた俺の耳にまでは届かなかったようだ。
土曜日、俺に付き合えと行った舌の根も乾かないうちに、という思いは不思議と湧かなかった。ああ、やっぱり俺はからかわれただけなのかと奇妙な安堵が全身を覆う。やはり彼に期待してはいけなかったのだという思いは少しの痛みを胸の奥に与えたけど、それを上回る安堵があった。これでもう、俺は悩まなくてすむはずだから。恋人が出来たと言う今でも藤井が俺に会う気があるかどうかは分からないが、ただ自分を慰めるためだけにあの店を訪れる事が出来る。自分の気の赴くままに行動する事が出来る。
熱で倒れていた間は不可抗力とは言え、昨日も彼のもとを訪れなかった罪悪感が、すっと薄れていくのを感じた。顔を見にいくだけだったら不可能ではなかった。それを己の事情で連絡もせずにすっぽかしたのだ。約束をしたのにと言うほんの少しの罪悪感と、会いたかったと言うおもいをかかえて。
「なぁ、林田。ちょっと頼みたい事があるんだけど」
昼休み、食欲もなく目の前に転がしたおにぎりをどうしようかと悩んでいたところに声をかけられた。声には覚えがあるが、名前は出てこない。振り向くと、校内でも人気者と言っていいだろうクラスメイトの顔があった。
「なに?」
本多祐一(ほんだ ゆういち)と言うそのクラスメイトとまともに話をした事はなかったと思う。彼はいつもクラスの中心にいて、俺との接点はまるでなかったと言っていい。別にこれといって仲が悪いと言うわけではないが、つながりもない。急に声をかけられたのは意外だった。
どうも教室では話し辛そうな彼につれられて、俺たちは外に出た。昼飯はいいのかと言う本多に、俺はただうなずくだけで答える。声をかけてきた時の机の上などを思い返せば何も食べていない事は分かっただろうが、彼はそれ以上何も言わなかった。
人がいない方がいいようなので、俺は彼を生徒会室に誘った。生徒会室自体には誰かが居るかもしれないが、頼めば準備室の方をあけてもらう事が出来るだろう。無理矢理ならされた役員だったからこそ、これくらいの役得がなくては困る。
「中等部の名簿、見れないかな?」
出来れば顔の分かるものを、と準備室に入って人払いがすむと本多はそう切り出してきた。椅子を勧める間もなく、詰め寄らんばかりの勢いだ。
「どうして? そりゃ、名簿ぐらい見せれるけど。顔写真のついているものはここにはないよ」
それは職員室、と付け足す。ちなみに卒業名簿なら図書室の閲覧室に置いてあった。高等部の生徒が中等部の名簿を見たいと言うのは不思議な話だが、ちゃんとした理由を添えて頼めば教師も無下に断りはしないだろうにと首を傾げる。
「俺のいとこが惚れた子が中等部に居るらしいんだけど。なんか四、五日音沙汰がないとかでな。連絡先とかを知らないらしくて、調べてやれないかと思った」
さすがに教師には言えなくて、と本多は苦笑を浮かべる。惚れた子、というのは、連絡がつかない事で気にする以上、付き合っていると言う事なのだろう。別にそれくらいの用事ならなにも俺に頼まなくても、そう思って聞いてみると、相手は小さく肩をすくめた。
「相手の名前がハッキリしないんだよ。学年も。付き合う事はOKしたらしいけど、結局その後一度も会えてないらしいし。素性はいっさい詮索しないって約束までさせられてるらしいから、遊ばれたんじゃないかって俺は思うんだけどね」
名前すらハッキリしない相手を探すのは、確かに難しそうだ。それでとりあえず、顔だけでも知っている俺に頼む事にしたらしい。
「まぁ、名簿を閲覧するぐらいは特に何の問題もないけど。運動部やなにかが、スカウト用に見にきたりもするしね」
「なら、良ければ放課後にでも頼む」
頭を下げてまで頼まれて了承すると、両手をしっかり握ってぶんぶんと振り回しはじめた。
「悪いな。林田ってさ、もっと張りつめたようなイメージあった。しゃべりにくそうっていうか。これからも何かあったら頼っていいか?」
生徒会準備室を出て教室へと戻る道すがら、本多は気さくにそう聞いてきた。この、どんな相手の警戒もさっと解いてしまうのが本多のすごいところだろう。かくいう俺も、最初の戸惑いはどこへやら、彼に引かれるものを感じていた。だから、言われた言葉にはすこし傷付いた。
「そんな事知るかって、言われるかもしれないと思ってたんだ。生徒会役員で知ってるのってお前だけだったし、ほとんどしゃべった事もないクラスメートにこんな事を頼まれても迷惑だとは思ったんだけどな」
「別に、そうしょっちゅう無理難題を言われるのでなければ、かまわないよ。これぐらいの事なら」
軽く答えながらも、クラスで一、二を争うぐらい人なつこい男でもやはり俺は取っ付きにくくうつるのかとため息が漏れる。それと同時に、なんだか不思議な気がしていた。自分の事を詮索するなと言いつつも、付き合いを了承したという中学生。そんな妙な条件を出すものが俺以外にもいたのだと妙に安心した。
|