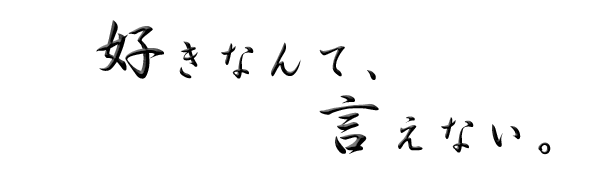|
<1-5>
八時頃、俺は傘を借りる事もなく藤井の家をあとにした。雨はすっかり上がっていて、傘はもう必要なくなっていたのだ。
「また明日、ちゃんと来いよ」
藤井はそう言って俺の髪を撫でて、キスの許可を求めて来た。俺は……多分ほだされていたのだ。あるいはいつ得られなくなるか分らないものを得ようとしたか、手放す時に気まずい思いをさせようとしたのか。なんにしても、つい、さっきみたいなのじゃなければ……昼間、風呂場でしたようなのじゃなければいいとこたえてしまった。
実際に降って来たキスは触れるだけのものなのに、それでも俺は赤くなった顔を隠すようにさっさと逃げて来た。余りにも優しくされて錯覚しそうだ。ああ、いや、いまは本気だろうから、錯覚と言うのも違うのか。どうしてあいつはああもきちんと約束を守るのだろう? もちろん、俺だって守ってもらわなければ困るけど。
もう一つ。藤井は俺に誕生日プレゼントをくれた。もちろん本人にはそんな自覚はない。俺の誕生日だって、知っている訳がない。ただ俺が勝手にそう思っているだけ。ちょうどその日にもらえたものだから、プレゼントだと思う事にしただけのもの。彼はただ似合っているからやると言って、借りたシャツをそのまま返さなくてもいいと言っただけなのだけど。
それでも俺には十分だった。俺の為にくれたものには違いない。彼はきっとそれがどれほど俺を喜ばせたかなんて、気付いていないに違いない。
泣いていたのか。
目が覚めた時に彼は聞いて来た。何も答えなかったけど、多分泣いていたのだろうと思う。嫌な夢を見ていたから。読んでいた童話の景色、テーブル一杯に広げられたごちそうとケーキ。そこかしこにプレゼントが置かれたその状況はすぐそこにあるのに、俺には手が届かない。そうしてケーキにたったろうそくを俺が吹き消そうとした途端、すべてが消え失せる。そのまま真っ暗になって、そこで泣いていた。
だから体を気遣ってくれて、布団を掛けてくれて、御飯を作ってくれて。嬉しかったのだ。シャツをくれると聞いた時には、その言葉を疑いそうになった程に。
でも、駄目だ。この気持ちに溺れてはいけない。彼もきっと父さんや母さんのように俺の前から消えて行く。かわいい女の子であったならともかく、俺は彼と同じ性を持つ。
そう自分に言い聞かせて、はやりそうになる心をなんとか押さえる。そんなふうにして藤井の事ばかりを考えながら歩いていたら、いつの間にか家についていた。
住宅街の中にある、一軒家。明かりのついていない、寂しい家。それでも今の俺に取っては、ここが唯一帰る場所だった。
鍵を開けて中に入ると、ひいやりとした空気が流れてくる。明かりがついていない事から予測していたけど、やはり玄関には誰の靴もない。父さんも母さんも、とうに家に帰っているようだ。もっとも、それを予測していたから、二人が帰ってから帰ろうと思っていたのだけど。
「そう言えば全部放ったらかして飛び出したんだっけ……」
重い気分を引きずって一応キッチンに向かう。何か連絡があればそこに手紙を残すようになっていたから、多分何かが残っているだろうと思う。例えば俺をどうする事になったかと言うような事が。
ドアを開けてすぐのスイッチで電気を付けると、部屋の中が明るくなる。途中だった食事はさすがに綺麗に片付けられていた。ダイニングテーブルに椅子が四つ。その椅子が埋まる事などここ数年にはない事で、だからこそ今朝は画期的な日だった。だがそこに人がいた気配などもちろんすっかりなくなり、テーブルの上には置き手紙がある。特に封筒に入れれたりする訳でもなく、むき出しのままで灰皿をウエイト代わりにして置いてある。誰が見る訳でもないから、隠す必要もない。
幸司へ
まだ決まっていません。
お前にもしたい事があると思います。できるだけ早いうちに返事を下さい。
父 母
手紙はそれだけの簡潔なものだった。いつまで話をしていたのかは知らないけど、結局自分達で答えを出そうとはしなかったらしい。
ふっと、苦い笑いが浮ぶ。そうしてそれに気付いて自分で驚いてしまった。ほんの数時間だけの事で、この問題を冷静に考えられるようになったのだろうか? もちろん締め付けるような胸の痛みは決して消えはしないのだけど。
理由は分かっていた。それ以上に気にかかる事が出来ているのだ。少なくとも、今の時点で。
やはり俺に取っての両親の離婚は、分り切っている出来事だったのだろう。あんなに落ち込んでいても、ほんの少し別の事が起こっただけで棚上げにもできれば、冷静に考える事も出来るようになっている。自分に降り掛かった理解不能の出来事の方が、よほど気になるくらいだから。
「電話は、明日にしよう」
言いたい事は決まっている。だから明日にでも呼び出すなりなんなりして、話をしてしまおう。二人が困らないうちにさっさと決着をつけさせてやろう。
そこまで考えた俺は、眠気に襲われて部屋に向かい、ゆったりした服だというのをいい事に、藤井に貰った服のままベッドに潜り込んだ。
目が覚めると熱っぽかった。喉が乾いていたから無理矢理台所までおりて、やっとの事で水を飲む。そこまではなんとか出来たけど、足元がふらふらとしていてじっと立っている事が辛い。昨日雨にあたり過ぎたのが祟ったのだろう。完全に風邪を引いてしまっている。
「電話は明日だな」
何かをしようと言う気は起こらなかった。体がだるくて、今はただ休んでいたい。本当は何かを食べた方がいいのだとは思う。だけど何かを口に入れられるような気分ではないし、起き上がって何かを作る事も出来そうにない。どうせ喉が乾くだろうとペットボトルごと水を部屋に持ち上がって、俺は大人しくもう一度布団に潜り込んだ。そうして目を閉じると、考える間もなく眠ってしまっていて、次に目が覚めたのはもう昼を過ぎてからだった。
水を少し飲んで、なんとか動けそうだったからもう一度台所におりた。冷蔵庫の中に入れっぱなしにしていた桃の缶詰めを開けて、半分だけ食べる。それから薬を飲んでもう一度ベッドに戻った。
凄く疲れていて眠いのに、何かをする気力なんてまるでないのに、どういう訳だか頭だけは冴えている。考える事を止める事が出来ない。
両親に電話をしなければいけない。こちらから何も言わなければ、多分一週間もすれば向こうから動いてくれるだろうけど。その場合はまた昨日の繰り返しが演じられる事は目に見えている。それで俺自身が傷付く事を自覚している以上、同じ事をしたいとは思わない。
あと、藤井。この服の元の持ち主。
彼の事はどうしたらいいのだろう?
できる限り毎日会いに行くと言ったけど、この調子では今日は確実会いにいけない。明日も、ちょっと自信がない。何日か置けば、彼の熱はさめるだろうか? 今頃は俺なんかにつき合おうと言った事を、後悔しているかも知れない。
「……藤井、智。……会いたい……」
智と呼べばいいと言われた。だけどきっと俺は本人を前にしてその名を呼ぶ事は出来ないだろう。
いつまで続くか分らないけど、初めて俺がいいと言ってくれた人。期間限定だと分かっているから、名前で呼んだりはしない。呼び名を元に戻さなければいけなくなった時に、辛い思いをするのは嫌だから。
またいつの間にか眠っていて、次に目が覚めたのは夜の十時を過ぎてからだった。もう一度なんとか起き出して、残っていた缶詰めを腹におさめる。それから又薬を飲んで、お湯でしぼったタオルで体を拭いてからもう一度布団に潜り込んだ。
藤井にもらった服はかなり汗をかいたこともあって着替える事にする。それでも洗濯機に入れておくのはなんだか寂しくて、ベッドまで持って戻って抱き締めて布団に潜り込む。一種の抱き枕状態だ。
自分自身が分らなくなりそうだった。こんなに藤井にのめり込んだら駄目だと思っているのに、彼の事しか考えられなくなっている。
多分彼に会えたのは正解だったと思う。俺はほんの数時間で両親の事からある程度立ち直っていた。だけど逆に捕われてしまった。余計な事を考えている暇なんて、ないはずなのに。
俺はこんな事でちゃんとやっていけるんだろうか? まだ一年以上時間があるとは言え、来年の受験には何が何でも合格しなきゃいけない。そうしなければきっと、一人で生きて行く事だって出来ない。一人で生活をするのを納得させるためにも、それくらいの事はしなければ。
寝よう。
そうして朝起きれたら学校に行って勉強をしよう。何とか自分の日常を取り戻して、それで大丈夫だと思えるようになったら藤井から離る。しばらくの間だけ頼らせてもらう。彼もそれは納得してくれているはずだから。
家の事もさっさとカタをつけよう。そうして一人でやっていけるという事をもう一度確認する。
だから、今は眠るんだ。
|