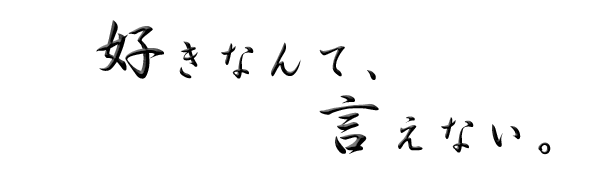|
<1-4>
結局服は乾きそうにないと言う事で、俺は傘を借りて家に帰る事にした。ただすぐには帰りたくないと言うと、藤井は大喜びで部屋で休んで行けばいいという。
「そんなに俺といたいって思ってくれた? でも悪い。もうバイトに戻る時間なんだよね」
「誰がそんな事言ったっ!!」
ふざけて抱きついてくる相手を蹴り飛ばし、部屋から追い出す。今はバイトに戻っていて俺はひとり、彼の部屋でぼんやりと座っていた。暇を潰す材料など何も持たずに出て来ているからする事がない。部屋に散らばっている本を適当に拾って、バラバラとめくる。
図書館にでも行けば良かったのかも知れないけど、明らかに借り物の服を着た格好で外をうろつく勇気は俺にはなかった。夕方を過ぎるまでは家に帰りたくなかったから、それまでの時間をどう潰すかと思っていた。だからこうして場所を与えられたのは随分と有り難い。
それにしても、とっさとは言え俺は良くあんな事を思い付いたものだと思う。確かに一人でいるのは嫌だったけど、どうしても藤井と一緒にいなければいけなかった訳でもない。もちろん自分を好きだと言う相手を側に置いてぼろぼろになった精神を癒すのには良かったかも知れないが、それを今の俺が冷静に受け止める事ができるかと考えると、リスクの方が大きいかも知れない。
「俺も慌ててたってことか」
冷静に考えれば、そういう事になるのだろう。
認めたくはないけれど、寂しくて寂しくて仕方がなかった。だから誰かが側にいてくれると言うのなら、それがどんな目的があって、どんなリスクがあったとしても拒む事が出来なかった。どんな形であったとしても。
「それじゃあ、俺はどうやってコウに会うんだよ?」
許可なくキスをしない、抱きつかない、人前ではべたべたしない……。そういった、友人なら当たり前の普通の事項に関しては、藤井は割合すんなりと頷いた。彼が叫んだのは、俺が連絡先を教えない、身元を詮索するなと言った時だった。
「俺がここにくれば問題ないだろう? 暇な時は下の喫茶に来るよ」
「毎日」
何日かに一度、授業が早く終わって、何の用事もない時にでも顔を出せばいいと思って口にした俺の言葉を、藤井はあっさりと覆した。
「暇な時じゃなくて、毎日来いよ。ほんの五分でもいいから、絶対に毎日顔見せに来い。それくらいいいだろう?」
じゃなければストーキングしてでも家を見つける、と豪語する藤井に呆れながらも、それくらいならと俺もしぶしぶを装って了承した。確かにその方が俺の気がまぎれる事は確かだ。どうせ家に帰っても何もする事がないのだし、藤井が喫茶店の手伝いをしている間は、この部屋にいていいと言っているから、わざわざ図書館に行ったりしなくてもここで勉強が出来る。
そう考えれば、この取り引きは案外お得だったのかも知れない。
「ホント、何考えてるんだろう、あいつ」
利用するだけ利用して、気持ちが落ち着いたらきっと俺はあいつの事など忘れて又一人で生きて行くだろう。そう思うとなんだか罪悪感すら生まれてくる。もちろん向こうがそうさせないつもりでいる事は分かっていたけども。
でも、他にどうしたらいいか分らない。藤井にも利用するのだと言う事ははっきりと言ったし。
一つ大きなため息をついて、クッションをかき集めてベッドにもたれ掛かった。本棚にある本を適当に抜き取り、それを膝の上で開いてみる。藤井はどんな顔をしてこれを呼んでいたのだろう、それは童話だった。こんな話みたいに、すべてがめでたしめでたしで終わればいいのに。
本の頁をめくりながら、俺はいつの間にか眠ってしまっていた。
「おい、起きろよコウ。もう六時になるぞ」
軽く揺すぶられる。
「こら、起きろって」
今度はもう少し強く揺すられた。聞き慣れない声の主が、俺を起こそうとしている。それでも動きたくなくてぐずぐずとしていた。現実感がなかっただけだったのかも知れない。誰かが俺を起こしに来るなんて事、ここ数年なかったから、なんだか夢を見ているようだと思っていた。
諦めたようなため息が聞こえる。その後、なんだか暖かなものが体に降って来た。気持ちよくて無意識にそれを引き寄せる。膝の上にあった重たいものも、どこかにいってしまった。
そうして、何か暖かなものが頬に当たる。
「……え?」
さすがに、おかしいと思ってようやっと俺は薄く目を開けた。ぼやけた視界一面に人の顔が広がっている。
「うわあぁっ!」
吃驚して、思いきり派手な声を挙げて後ずさろうとした。だけどちょうどもたれていたベッドで下がる事も出来ない。
「ちょっとひどくないか?」
目の前の男が、少し傷付いたような顔でぼそりと呟く。俺が目を覚ました原因の頬に置かれた手を、ゆっくりとした動作で放して、それから思い直したようにもう一度手を伸ばしてくる。泣いていたのか、という声と共に、涙のあとがついているらしい目もとが拭われた。
「コウ、キスしていい?」
じっと見られて、囁くように尋ねられて。ぱっと顔から火が出ると同時に目が覚めた。この男がつき合いたいと言って来たのに、俺はOKしてしまったのだ。
「……コウ?」
状況を思い出して固まってしまった俺の目の前まで来ていた藤井の顔が、ピタリと止まる。本当に、ほんの数センチ先に藤井の整った顔があった。息すらかかるその距離に、はからずも心臓が跳ねる。
「だ、駄目っ」
それだけでばくばくと激しく騒ぐ心臓を必死でなだめながら、前を見ている事も出来ずにギュっと目を瞑ってそう答えた。見慣れない、いい男と言って過言ではない顔がアップで目の前にあるのは余りにも心臓に悪く、正視している事も出来ない。藤井の気配はしばらく俺の目の前で止まっていたけど、言葉と態度に失望したのか、残念そうな息を吐いて離れて行った。
探るように、そっと薄目を開けて藤井が離れた事を確認してから、俺も安心して息を吐く。約束をやぶるつもりはないらしい。
「そんなあからさまにほっとされるとやっぱり傷付くんだけど」
「……ごめん」
あんまり傷付いたような表情をするから、俺は思わず謝っていた。だけどよくよく考えてみれば、そんな必要はなかったのかも知れない。
ふと目を落とすと、藤井が掛けてくれたのだろう薄い布団を体に巻き付けていた。読んでいた本も彼の手許におさまっている。
「あの、これ……?」
「ああ」
布団を軽くあげるようにして聞いた俺に、藤井は薄く笑う。
「いくら起こそうとしても起きないから、諦めて寝かせとこうと思って。それなのにほんのちょこっと顔触っただけで起きるんだもんなぁ」
そんなふうに言われると、警戒しているみたいじゃないか。それは……してないない訳じゃないけど。今目が覚めたのは、何回か声をかけられたり揺すぶられたりしていて半分覚醒しかけていたからだ。
まぁ、起きてくれて良かったけど、と笑った藤井は、俺から布団を取ると手早く折り畳んでそのままポンとベッドの上に放りあげる。それから、俺にこれからの予定を聞いて来た。
「急いでないんだったら、飯食っていけよ」
ほんの少し思案する。家に帰って自分で作って食べる事を考えると、とても有り難い申し出だった。まさか母が夕食を作って待っているなんて事はあり得ないだろうし。
「まぁ、夕食って言う程たいしたものはでないけどな」
家族で喫茶店を経営している藤井の家では、食事は自分で作るものらしい。レトルトやコンビニ弁当と言う訳ではないが、簡単に作れるものがメインになってしまっていると言う。
そして食事の話が出て来ると、ぐーっと腹の虫がなった。よくよく考えてみると、俺は結局今日は朝昼共に食べていなかったのだ。朝は食べ始めたところで嫌な話が始まって飛び出して来てしまったし、昼にいたっては雨の公園でぼんやりしていた。
話題になってから気付いた。正直俺は、腹が減っている。
「……俺、腹減ってるみたいなんだけど」
腹の虫を鳴らせておいて、いまさらだった。隠していても仕方がないから、俺は朝昼共に食べていない事を藤井に話した。そうすると目の前の色男は急に表情を険しくして、俺の頬を叩く。痛くはない。ぺちっと小さな音がしたけど、軽く叩かれただけだ。それよりも彼の表情が怖い。
「ほら、起きろ。なんか食わせてやるから」
そう言って、怒っているらしい彼の表情を呆然と見ている俺の手を、苛立たし気に引きながら立たせてくれる。そのままずるずると引きずられるように台所に連れていかれた。下の店とは別にある、ちょっとしたキッチンスペース。部屋の中央のテーブルについているようにとだけ言いおいて、藤井は部屋を出て行った。いったいなんだろうと思っている間に、男は戻ってくる。手にはいくつかの野菜とハム、卵。御飯らしきものの入った器も持っている。喫茶までいって、材料をとって来たらしい。
「座ってろって言ったろ。待ってろ、すぐ出来る」
どうなっているのか分らずに声を掛けた俺に答えて、藤井は水場に向かい俺に背を向ける。
こうしているとどちらが年上かなんて分らない。下手をすると本当に俺の方が年下みたいだと思わず苦笑して、大人しく椅子に腰を下ろす。背中を向けた藤井は、リズミカルに包丁を動かし鍋を振るう。その慣れた姿はやはり意外としか言い様がなかった。俺も生活の都合上、料理は割り合い出来る方だと思う。その俺が見ても藤井は十分に手慣れていた。普通俺達の年代の男子は、包丁など持たないのだけど。
「ああ、そうか」
何も言わずに黙々と手を動かしている藤井の後ろ姿を見ながら、俺は不意に気付いた。何かに怒っているような気がしていたけど、それはもしかしたら俺が食事をしていなかったせいなのではないか、心配してくれていたのではないかと。
「何か言ったか?」
うぬぼれと言えなくもないつぶやきに振り返った藤井が聞いてくるけど、俺はただ首を降るだけで答える。別に、わざわざ言う必要はないだろう。勘違いだったりすると、恥ずかしくもあるし。
「ほら、食え」
暫くすると、本当に美味しそうなにおいのする炒飯の皿が出て来た。御丁寧に、スープまでついている。
「おいしい」
「そりゃよかった」
言われるままにひとくち食べて、思わず呟く。それだけでずっと怒っていたような藤井の顔が崩れた。本当に嬉しそうに、自然に笑顔を浮かべる。思わずドキリとするような笑顔だ。
それでもそれは、本当に美味しかったのだ。味はもちろんの事、たぶんそれが藤井が俺の為に作ってくれたものだったから。母さんは家にいても料理なんてしない。自分で作って食べるしかないから、誰かが俺に料理をしてくれるなんて本当に久しぶりの事だった。
どうしたらいいのだろう? これだけの事で藤井が好きになり始めている。誰かに側にいて欲しいだけだなんて誤魔化す事も出来ないぐらいに、俺は藤井に引かれている。
だけど。
藤井が俺を好きだと言っているのは、きっと一過性のもの。彼自身が言っていたではないか。一目惚れだと。それでも十分に趣味が良いとは言えないが、顔に惚れたと言うのなら見慣れたり、中身が思っていたのと違ってくればその熱はすぐにさめる。なのにそれが分かっていてなお、つき合おうと言ってくれたその言葉に縋りたいと思っている。
ただ体を気遣い、布団を掛けて、食事を作ってくれただけ。
俺はもう一度強く自分に言い聞かせた。
|