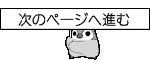姫君の寵愛byダークパラサイト
第九話:「崩壊」
翌日。
やはりと言うか当然と言うか、学校はまたも休みだった。
昨日よりは多く生徒は来ていたが、やはり授業をできるほどの人数が集まらなかったのだ。
それも、生徒が集まらなかっただけならともかく教師まで集まらなかったのでは話にならないと言う事らしい。
シンジ達の通う二年A組でも今日はシンジを含めて五人しか集まらなかった。
まだ数が少ないので出席番号順(あいうえお順)に全て列挙してみよう。
これがクラス全員ともなると書き出すのも嫌になるものだがこの程度ならば苦にもならないだろう。
{男子}
碇シンジ。
鈴原トウジ。
矢倉マサト。
{女子}
菊花ヤエ。
洞木ヒカリ。
以上の五人である。
今日はエヴァの稼動テストやミーティングがあり、アキナが休みを取っているため、シンジは一人だけで学校に来ていた。
そのせいか昨日までのような膜を作る必要がなくなっている。
強がって見せる事も。
自分を無理に貶める事も。
どちらも必要なかった。
ただありのままの自分としてそこにいる。
周囲を見回している。
シンジの見る限りにおいて、それは酷く日常的な光景だった。
仲の良い者同士でグループになり。
相互に間に壁を作り。
異質なものを排斥し。
人数は少なく。
グループは一つしかなく。
あきれるほどに非日常なのに。
それでもその日常は機能していた。
笑いたくなるほどに明確に。
ほんの一欠片の澱みも無く。
いかなる黄金率よりも美しくそこにあった。
すなわち。
彼は孤立していた。
ただ一度だけ。
委員長だと言う洞木ヒカリから会話に混ざらないかと誘われた他は(至極丁寧に拒絶したせいか)誰からの誘いも無い。
だからじっと眺めている。
教室と言う空間の普遍性に呆れ返るわけでも無く。
勤勉な学生を装い勉学に勤しむわけでも無く。
この事件についてあれやこれやと言い交わしている声に耳を傾けるわけでも無く。
読書やゲームや妄想を行っているわけでももちろん無く(耳に刺さっているS-DATのバッテリーはすでに切れている。)
ただ周囲の全てを眺めているだけ。
そういう意味ではシンジは日常にはあまりにも似つかわしくない非日常的な異端者であり。
この非日常の中の日常の中にあってシンジだけは未だ非日常なのかもしれなかった。
だが学校における日常の定義はシンジの内包する非日常と周囲の世界の抱える非日常とを抱えなお、それをも含め日常でありつづける事を可能とする。
学校と言う日常の中ではシンジは転校生と言う異端者でしかなく。
学校を内包する世界の喧騒はその中央の爆心地たる場所にいてもなお遠い世界の出来事だった。
そして、その碇シンジ自身が形成する非日常もまた彼にとっての歪んだ日常以外の何者でもなく。
得てして学校という世界は日常の中にありつづけた。
誰かがそう望んだわけでも。
誰かがそうなるように仕組んだわけでもなく。
学校という空間が異質なものを徹底的に排除し続けた結果がこれだった。
日常と言う狂気が非日常な空間の中で踊り狂う。
ただ、この状況はシンジにとってはむしろ心地よいものであったといえるだろう。
彼は本来友達と話すことも、作り笑いを浮かべる事も、嫌い、といって差し支えないほどに苦手なのだ。
ならばどこか別の場所へ行けばいいと思う人もいるかもしれない。
誰も人がこないところ(例えば屋上)へ、移動すればいいと、そう言うかもしれない。
実際、理論としてはそれで正しい。
シンジとて、アキナがこの場にいれば(そしてそれを彼女が望めば、)迷わずにその道を選んでいただろう。
しかしながら、結論からして今現在の彼はアキナも、数少ない旧友も一緒ではない。
今の彼に、外に対し社交的に慣れるほどの余裕など、ただの一欠片すらも残されてはいないのだ
立ち入り禁止の屋上へ逃げるなどという考えは論外といってもいい。
するべき事など無く。
したい事も無く
ひたすら時間をつぶすだけ。
そうしていれば平穏は壊れない。
日常は壊れない。
そう思っていた。
みんな今でこそ再開ついでに話に花を咲かせているが、もうすぐ帰ってしまうのだろう。
そうなれば変わらない。
自分は昨日と同じように数時間時間をつぶし。
持ってきた弁当を食べ。
姉の車に送られてまた帰る。
・・・それだけだ。
彼らの日常も非日常も。
自らの日常も非日常も。
壊れない。
シンジはそう考えていた。
そうなることを期待していた。
だから、気づいていなかった。
すでに自分にとっての日常も非日常も、彼らにとっての日常も非日常も、完膚なきまでに壊れている事に。
「碇、いったいどういうつもりだ?非常時でもないのにゼロのエヴァへの接触を許すなど・・・正気の沙汰ではないぞ。」
冬月が大きな音をたててゲンドウの机を叩いた。
机の上に乗せられていた数枚のコピーが床に散らばったが、それを拾う者はいない。
無駄に広い総司令室には現在組織のトップ二人以外には誰もいなかった。
ゲンドウはいつもと変わらぬスタイルのままいつもと変わらぬいすに座っている。
対する冬月の大きく見開かれた目は血走り、その下には大きな隈ができている。
今のこの状況だけを見れば正気ではないのは間違いなく冬月のほうだろう。
冷静な態度をとり続けるゲンドウに対し、冬月の姿は明らかに常軌を逸している。
だが、数分前に出された命令は確かに正気の沙汰ではなかった。
即ちゼロチルドレンに対する要観察命令の撤廃、およびエヴァへの無条件搭乗許可の発令。
要するにアキナに対し7年前と同じ自由行動権を与えてしまったのだ。
これにより、アキナの命令に対しての拒否権はゲンドウと冬月を除く全ネルフ職員から剥奪されたということになる。
たかだか十四歳の少女に自分の生死与奪権を握られていると知れば彼らはどんな反応を見せるだろうか?
おそらくはトップへの信頼も、組織への忠誠心もがたがたになるだろう。
どんなに物々しい看板を掲げ、エヴァという強大な力を保有してみたところでネルフも有象無象の株式会社とたいした違いは無いのだ。
職員たちに造反を起こされれば組織として立ち行かなくなる。
ゲンドウにそれが分からないとは思っていない。
馬鹿で安っぽい男だが、個人の実力や状況の見極めぐらいはできる男だと思っていた。
だからこそ、この命令に納得がいかない。
こんなことはありえない、あってはならない。
「説明しろ、碇。いったいなぜこのような暴挙に踏み切ったのか。いや、そもそもなぜゼロがここにいる?彼女はコウシロウが監視していたはずだろう。」
捲し立てる、とでも言うのだろう。
冬月の舌は外見からは想像もつかないほどによく回った。
その様子をゲンドウは静かに眺めていた。
相手が疲れるのを待つように。
まるでスカベンジャーのように。
そして、相手が言葉を切り、息を整えるのを待った後、ようやく口を開いた。
「おまえは賛成してくれると思っていたのだがな、冬月。」
「な・・・・・・。」
絶句した。
まさに二の句が継げなかった。
陳腐な表現をすれば、まるで空気を求める魚のように口を二三度開け、結局そこから意味のある言葉は愚か、意味の無い言葉さえ洩れなかった。
自分がゼロをコウシロウに預けるときになんと言ったのか。
それを思い出せと、そう言われたのだと理解するのにそれほど時間はかからなかった。
「他の誰が理解してくれなくとも、おまえだけは理解を示してくれると思っていたのだがな、冬月。」
にやり、と手に隠された口が歪んだのを冬月は感じていた。
馬鹿にされた。
それはわかった。
だがどうすれば良い?
気が変わった、とでも告げるか?
それとも委員会の件を口にするか?
どちらも現実的な案とは言えない。
後者に至ってはすでに許可が下りている可能性すらある。
「好きにしろ・・・。ただし、計画の遅延だけは起こすなよ。」
結局、冬月はゲンドウの行動を黙認した。
それにより起こる被害、利益、それら全てを計算し、あまりにも無理のある・・・端的に言えば自分に都合のよい・・・結果を導き出し・・・それで良しとした。
だから気づかなかった。
彼女の存在そのものが、計画の遅延と同義であり、彼女の存在そのものが、この計画にとって最大の予定されたイレギュラーである事に。
「は・・・?」
赤木リツコの間抜けな声。
冬月がゲンドウに食って掛かっていたころ、研究ラボにおいて起こっていた事態は少なくとも冬月の思うような最悪の事態に陥ってはいなかった。
だが、それはあくまで最悪ではないというだけで次点、三点ぐらいに悪い結果には陥っていたとも言える。
「な・・・、この訓練には意味が無いってどういうことよ、アキナちゃん。」
「だから、銃なんかじゃ使徒の身体には傷一つつけられない。当然でしょ?」
それほど広くも無いラボの中でリツコとアキナがにらみ合っている。
最も、睨みあっていると言うよりもリツコが一方的に睨んでいると描写したほうが正しいような状態ではあるが、少なくとも温厚な会話をするつもりは二人とも無かったらしい。
「何が当然よ、あなたがちゃんと中和さえすれば・・・。」
「嫌。」
会話はまだ始まったばかりなのだが、早くも平行線の様相を見せ始めていた。
今度はアキナがリツコを睨みつける。
リツコは一瞬たじろぐような仕種を見せた。
見せてしまった。
彼女は、いや、彼女たちは知っているのだ。
本気になって会話をしたとき、どちらが上の立場にあり、どちらがどちらを御し得るのかを。
「どうしても銃を撃ちたいならレイにやらせて。私はそんな事はしない。」
一方的な拒絶だった。
こう言われてしまってはリツコに訓練を強制させられるだけの力は無い。
・・・与えられてもいない。
リツコの手の中に握られていた訓練要綱がくしゃりという音と共に丸められた。
「それだけなの?」
暫く返答を待っていたアキナだったが、無いらしいと分かるや否やくるりと踵を返し研究ラボを退室していた。
「後で泣いても・・・知らないから・・・。」
結局、それがリツコがアキナの背中に投げつけた最後の断末魔だった。
そしてそれすらも鉄よりも硬いアキナの鼓膜を震わせる事はできなかった。
だが、彼女達は知らない。
その言葉が、そう遠くない将来において現実のものとなる事も。
そのころには彼女は今のままの存在ではないという事も。
ただ、今この場において両者の意見が共に正論であるのであればアキナの意見が優先されてしまう事は必然の流れで、それは到底止められるような事ではなかった。
だから気付かなかった。
王の仕掛けた気まぐれに。
神と悪魔の悪意に満ち溢れた悪戯に。
カラン、カラン、カラン、カラカラカラ・・・。
落とした箸が教室の中を転がり、机の角に当たって止まるまで数秒の時間を要した。
その間、シンジは別段慌てるふうでもなく箸を眺めていた。
なんとなく、何をする気も起こらなかった。
食事や睡眠といった動物の三大欲ですら今の彼を動かす原動力とはなりえなかった。
「長門ヌエ・・・か。」
口の中で呟く。
数時間前に出会った少年から言われた言葉が頭の中によみがえってきた。
「強引すぎるんだよ・・・。」
だが、断れなかった。
ほんの一瞬、それが真実であるかのように考えてしまった自分がいた。
「情けない・・・よな・・・。」
外を眺めると、もう夕日が山の切れ間へと沈もうとしていた。
義姉は・・・まだこない。
昼食を取ってからぼうっと過ごした時間は既に五時間を超過している。
(遅いな・・・)
朝は四時ごろに迎えに来るといっていた。
だが、時間は既に六時を迎えようとしている。
(また、か・・・。)
昔も同じような事があった。
母を無くす前は母の帰りを待った。
義姉の家に越していってからは今と同じように義姉の帰りを待った。
遊びに行った二人の少女をずっと待っていた事もあった。
いつもいつも、自分は待つ側だった。
(まあ、いいか・・・。)
いつしか彼は待つという行為に慣れきっていた。
待っていれば、その人はいつでも迎えに来てくれた。
(異常・・・だよな・・・。)
もっとも、落ちた箸はどれだけ待っても絶対に帰ってこない。
シンジはゆっくりと立ち上がり地面に落ちている箸を拾いにいった。
だが、その目線は箸のさらに向こうで吸い寄せられたように留まった。
蒼い制服のスカートがふわり、と広がる。
「シンジ君・・・帰ろう。」
まとめられた長い髪が教室内に吹く微かな風に揺れる。
シンジにとっての非日常が、日常へと帰った。
その事に安堵し、そっと少女の顔を窺う。
少しだけ、不機嫌なように感じた。
「なにかあったの?」
尋ねても少女は首を縦には振らない。
だが、より一層不機嫌になったその顔が何かあったのだと物語っていた。
「晩御飯、何がいい?」
こんなときに何を聞いても絶対に答えてくれない事を、シンジは経験則から知っていた。
だから話の話題を逸らそうとしたに過ぎず、明確な返事は期待していなかった。
「ン・・・・何でもいい。」
「そう・・・じゃあ、昨日は肉だったし、魚にしようか。」
「シンジ君がいいならそれでいい。」
大方の予想通り、少女は明確な答えを返しはしなかった。
少年の言葉に追従し、全面的に支持する。
その姿は一種異様なものにも映る。
だが、それはシンジにとっての日常だった。
それはアキナにとっての日常だった。
両者から剥奪されていた七年前の日常だった。
だから気付かなかった。
少年が忘れた人外の言葉。
その言葉の持つ意味。
内に迫る破局の音に。
三日後。
学校は少しずつ、だが確実に以前の日常を取り戻しつつあった。
教室には生徒が戻り、教師たちもそれぞれの教卓についた。
各個に友の無事を確認し、それぞれに安堵の息を吐く。
こと二年A組に限って言えば、死者の数が千を越えるような大惨事だったにもかかわらず、教室の中でかけた席は驚くほど少なかった。
せいぜいが二、三席あいた程度であり、その席も新しく入った転校生によって埋められた。
結局、ひとしきり悲しまれた後は何の変わりも無い日常が連綿と続いているだけだった。
その事に感謝をするものこそあれ、それをおかしいと糾弾するものはいなかった。
結局彼らは変化が起こる事を恐れていただけであり、其処にたいした変化が起こらないと分かるとそれを受け入れてしまったのだ。
そして、ちょうどそのころを見計らって転校生の紹介が担任の時任ゴロウによって行われた。
教室に集まっていた面々にすれば既に何を今更と言いたいところだったのだが、教師には教師の考えというものがあるらしく一限目を潰しての自己紹介は行われた。
各個に名を告げ、簡単なプロフィール紹介を行い、転校生に質問があるものはそこで質問をする。
だが、教師の庇護下において生徒が本当に聞きたい事を質問する事などできよう筈も無く、また社交辞令的な質問程度ならば教室にいるほとんどの面々がこれまでの学校生活の中で既に終えていた。
そのためこの転校生受け入れのための時間は儀礼的な意味以上のものをもつことなく終了してしまった。
それでも学校という必要以上に秩序と儀式を重んじる空間の中ではこんな時間でも十分な効力を持つものであったらしかった。
女子のコミュニティの中でそれほど嫌われていたわけではなくただある程度牽制されていただけであったアキナはもとより、それまでは誰も話し掛けようともしなかったシンジでさえ休み時間に何とかして話し掛けようとするものは増えていた。
「ねえ、碇君。いっしょにお昼食べない?」
その最たる例とでも言うべきものが今シンジの前に立っている菊花ヤエだった。
アキナやレイに比べるとさすがに見劣りする容姿だが十分な美少女で、大っぴらな性格や独特の話し口調は男子たちの間でも人気は高いらしい。
綺麗なボブカットの頭髪は薄く染められているらしく日の光が強く当たるところだけが少し茶色がかった色をはなっていた。
そして何より、他の面々が無愛想なシンジに愛想を尽かし話し掛けるのをやめていく中で、彼女だけは自己紹介の終わった初めの休み時間から毎時間、終始一貫してシンジに対し話し掛けるというスタンスを崩していない。
「僕はアキナちゃんと一緒に食べるつもりなんだけど・・・。」
「だ・か・ら・よ。冬月さんとお昼一緒に食べようと思ったらあなたを誘わないと話にならないんですもの。」
「何だよ、それ。」
どこか高飛車にも聞こえる彼女の言葉の節々におまえなんか本当は誘いたくないのだ、という本音が混じっているのは気のせいではないだろう。
それでもシンジはある意味では鬱陶しいとも言えるこの少女を嫌っているわけではなかった。
それは仮令この少女がアキナに近づくために自分を出汁にしようとしているのだとしても(そしてそれは半ば異常に核心をついていたのだが)、それはこの少女がそれだけアキナと親しくなろうとしてくれているという事であり、そういった存在の登場はシンジにとってメリットになりこそすれデメリットになる事はない。
何もアキナを占有しようと思っているわけではない。
アキナを縛るつもりなど毛頭無いし、アキナが親しい友人を作ることができるのだとすればそれでいいと思っている。
結局は他人。
要するに、そういうことなのだ。
自分主体で見た世界でしか世界を捉えることができない。
その逆についてなど、考えもしない。
シンジも。
アキナも。
日常的に学校という非日常に触れているはずのこの少女も。
自己を中心に回る世界の中で生きているだけ。
なんという自分勝手。
なんという自己満足。
どれほどに他者への愛を説いてみたところで、それは「自分が出す」愛に過ぎないというのに。
どれほどに思いやりの精神を説いてみたところで、それは自分の中の定義に押し込めた他者を、自分にとって都合のよい形に捻じ曲げた妄想でしかないというのに。
冬月アキナという存在が友人という概念を本当に望んでいるかなど、誰にもわからないというのに。
「で?一緒に食べるの?食べないの?」
少女は強制する。
たった一つしかありえない答えを、それでもなお引き出そうとする。
「・・・・・・いいよ。好きにすればいい。」
「そう?ありがとう。」
言うが早いか少女はシンジの前の席をがたがたと移動させ、向かい合うようにして座った。
既に机の上には弁当包みも出され準備は万全といった風情である。
ただ、少女が現在座っている席は現在手を洗うために席を離れているアキナの指定席といってもいい場所だった。
常ならばアキナがいまヤエのいる場所に座った状態で二人で静かに昼食を取っていたはずであり、アキナが困惑し、不機嫌になるであろうことは容易に察せられる。
そして何より、シンジ自身がそんなヤエの行動に対し少なからぬ困惑を抱いていた。
「少し・・・横に寄れないかな?」
「何で?ここが冬月さんの指定席だから?」
少女に悪気はあるまい。
ただ思った事を口にしただけ。
現にヤエもそれでシンジが頷けばその席をアキナへと譲り渡すつもりでいた。
きっと頷く。
それは確信に近い思いだった。
目の前の少年はきっと頷く。
羞恥など考える事も無く、そうだと言う。
ほんの数日ともにしただけだがその程度にはこの少年たちの事を理解しているつもりでいた。
ある種の期待とともに少年の返事を待つ。
「いや・・・そうだね、別にいいよ。」
だが・・・実際にはそうはならなかった。
その事に逆に面食らう。
なぜ、だろうか?
少年の顔に答えはない。
そのころには既に自分の分とアキナの分。
二人分の弁当箱を机の上に広げていた。
ふと、ヤエの頭に小さな疑惑が生じた。
もしかすると、この少年は見た目ほどにはアキナを好いてはいないのではないだろうか?
だが、次の瞬間教室に入ってきたアキナへと向けられた笑顔を見てその疑惑は氷解した。
飛び切りの、自分たちには絶対に向けられないであろう笑顔がそこにはあった。
(そう・・・だよね。)
この少年たちは常に共にいる。
何故嫌っているものへとこれほどの笑顔を向けることができるだろうか?
「ああ、ごめんね、冬月さん。」
アキナの膨らんだほほを見たヤエは素直に席を譲り渡した。
それからの食事の時間、アキナはひたすらに饒舌だった。
シンジに、ヤエに、さまざまな話題を提供し、横から首をはさんできた女子生徒達とも実によく話した。
いつしかシンジの席の周りには大きな人の輪ができ、その中心にはアキナがいた。
だから気付けなかった。
教室の外に立つ人影に。
舐めるようにアキナを見ていた銀髪の化物に。
あとがき
どうも、最近やった模試の希望大学合否判定でEをたたき出し悲しみに暮れているダークパラサイトです。
・・・・・・・・・いいもん。どうせ必要なのはセンターだけなんだから。
記述型模試の成績なんかどうだって・・・・・・・・。
さて、愚痴はこの程度にしておいて、数少ない感想メールの中に作者の性格がわからない、的なことが書いてあったのでご報告いたします。
作者の性格は、一言で言えば「人の嫌がる事を進んでする」ような性格です。
それ以上は言えば酷い事になるのでやめておきましょう。
ついでに同時に書いてあった作品の書き方についても記しておきます。
①頭の中にその作品が必要とする世界地図、もしくは地球儀、宇宙図、その他のものを書きます。
②性格や人相を記録した人形を脳内世界へと並べていきます。
③世界をシミュレートし、それを見たままパソコンへと打ち込んでいきます。
このやり方は欠点として作者が世界に手を加えにくいという点があります。
なのであまり真似はお勧めしません。
ではまた。
蒼來の感想(?)
傲慢な王、気弱の従者。
共になく、別となれば同じ様な孤独抱く。
彼らの未来は、いまだ闇の中。
・・・つうか五人しか登校してないクラスじゃあ、学組(級)閉鎖にならんか?(前の三行意味なし!!w
まだ、2人は回りに溶け込めてないみたいですね。
まあ、あの感じじゃあ難しそうですが。
冬月さんリツコさん共にに苦労しています・・・両方とも傲慢だしねw
ちなみに蒼來はセンター試験受けてません。
その頃は、目安見たいな感じでしたから。
まあ、今E判定でも夏が勝負!!なんですよ。
・・・1回、3日連続1日13時間勉強なんてこともしたことがありますが・・・発狂せんかったが、次の日は流石に遊んだw
26校(同じ学校で1次2次を別々として数える)連続で落ちましたw>大学
27校目に名古屋の大学に受かったんですけどね。