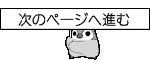楽しんで来い。
そう言って送り出してくれる父がいた。
じゃあ行こうか。
そう言って手をつないでくれる人がいた。
それがかけがえのないものだと、気付かせてくれる友がいた。
それは嵐の前の一瞬の静寂かもしれない。
けれど、こんな世界が続くなら、私はそのほうが嬉しい。
姫君の寵愛byダークパラサイト
第十話:「安穏」
「〜♪〜〜♪」
半分廃墟と化した街の中、調子はずれの鼻歌が街を南から北へと縦断していた。
その音楽というものを冒涜するかのような小さな騒音が今流行りのアイドル歌手の最新曲のハミングであると、気付く事ができた人間が果たして何人いただろうか?
そう思いたくなるほどに音程もリズムもちぐはぐな、有体に言ってしまえばへたくそな鼻歌。
だが、そういうものを歌っている人間とはえてして上機嫌なものである。
風呂場の親父しかり、ラーメン屋の酔っ払いもしかり。
そして、この歌を歌っている少女もその例に漏れず上機嫌だった。
その証拠といわんばかりに手に下げた学生鞄をくるくると回しながら、まだ瓦礫の残された上り坂を歩いていく。
「♪〜〜〜♪♪」
そこから先を忘れてしまったのか、鼻歌はさっきから同じところをループするようになっていたが、そんな事を気にする者はいなかった。
時折すれ違う者は少女を羨ましげに、もしくは微笑ましげに、眺めるだけで各々の先を急ぐ。
だがそれは従者か護衛のようにその後を無言でついて歩く少年の力によるところが大きいのだろう。
幼い少女に振り回される歳の離れた兄。
そんな役割が割り当てられた少年は、忠実にその役目をこなす。
小さなネズミのようにあっちへちょろちょろこっちへちょろちょろと動き回る少女に歩調を合わせ、あるときは立ち止まり、あるときは走りながらも懸命に少女に付いて歩く。
それは恰も真実の家族のようで、絶対に真実などではあり得ない偽りの光景。
全てを知る悪魔王は自嘲する。
ここにいてはならぬ身体が、ここにいてはならぬ少女を見守る。
そのような矛盾、世界にあって許され得るはずが無い。
だが、誰が許さないというのか?
天使か?
神か?
はたまた、世界に数多湧き上がる霊長の群れか?
何れにせよ自分を倒すには非力。
この少女に罪は無く、世界は罪に満ちている。
こんな何の力も持たぬ少女をつぶそうというのならば、世界が許さずとも自分がこの少女を守る。
悲痛な決意は、少年の力と知恵の及ぶ限り現実となり、それ故に悪魔王は自嘲する。
神に次ぐ力を持ち天地天明の全てを知るはずの彼にできる事など、結局はその程度の事でしかないのだ。
破壊に特化した能力ではどれほどの慈愛をもってしても一人の人を守る事がやっとでしかない。
喰らう事はできても、作ることができない。
殺す事はできても、生かす事はできない。
彼はただ使徒がアダムを目指すように少女を目指しているにすぎず、その時この世界がどうなるのかなど、本人にすら分かっていないのだ。
つまるところその点において言えば、彼はこの少女にすら劣る。
この少女は作るために創り、生かすために活かす事ができるのだから。
「何難しい顔し取るんや?ヌエ兄ちゃん。はよ歩かな置いてくで〜!」
少女はいつのまにか上り坂を駆け上がり少年へと手を振っていた。
「・・・・・・ん、すぐ行く。」
万感の想いと、迫りつつある運命。
その両方を受容して、なお先をいく自らの妻。
夕暮れ時の街の中、さまざまな事象へと思いをはせながら、少年はとりあえず今の安穏を手放さないために頷いた。
今はまだ、時に非ず。
だが、開幕の時は限りなく近い。
「えっと、写真をとらせてもらってもいいかな?」
朝、登校してきたばかりのアキナが学校の廊下でそんな風に話し掛けられたのは学校に通い始めてからちょうど三週間が過ぎたころだった。
話し掛けてきたのは男子の出席番号一番、相田 ケンスケ。
アキナの中では授業中に開いているのはいつもカメラかビデオを持ち歩いているという外見印象ぐらいのもので、自己紹介でミリタリーが趣味であるといっていたような気もしたが、それとて確実な記憶とは言いがたい曖昧糢糊な記憶でしかなかった。
つまり、彼女にとってはたくさんいる男子生徒の一人と言う認識のほかにはそれほど重要な人物ではなかったのだ。
そんな人物に突然写真をとりたい、などと言われても反応に困るだけである。
だいたいにおいて彼の言葉には主語が全く無く、何を撮りたいのかもどのように撮りたいのかも、全く分からない。
シンジがいれば分かったかもしれないが、生憎と彼はゲンドウの委員会に対する顔見せへの付き添いで学校を休んでいた。
助けを求められない以上は自分で処理するしかない。
ただ、自分の配下ではない彼が何故自分に許可を求めているのかさえ実はよく分かっていないアキナにとって、この事案の対処は容易なものではなかった。
もし機密や内規に触れるような事なのであればきっぱりと断らなければならないし、逆にここの写真をとりたいので移動してほしいというなら拒否しなければならない理由は無い。
いずれにせよ彼の意向が分からない事には何ともこたえようの無い質問である。
「何の写真をとりたいの?」
仕方なく、彼女は素直に自分が疑問に思う点を訊ねた。
被写体が何かさえわかれば拒否する事は容易い。
そう思っての質問だったのだが、聞いてすぐに彼女は唇をかんだ。
詰問の仕方としては腰が弱かったかといぶかしんだのだ。
が、予想に反し答えはすぐに返ってきた。
・・・・・・彼女の思いもしなかった方向性で。
「あ、えっと君の写真をとりたいんだけど・・・・・・だめ、かな?。」
目の前に立つ少年は徐にビデオカメラを構えたかと思うと、そこでシャッターを切る仕種をして見せた。
そのような質問を想定していなかったアキナは面食らい言葉を発する事ができず、その隙にとばかりにケンスケは自分の主張を続けた。
「その、そんな皆の言うような変な写真とか取りたいわけじゃなくってさ・・・じゃなくて、えっと・・・気になるなら後で見に来てくれてもいいし、結構、自信あるんだ。写真。カメラはちゃんとしたのを使うから・・・・。」
さすがに照れくさいらしく、鼻の頭を掻きながらだったが、さっきの要領を得ない質問よりはだいぶ言いたい事が伝わってきた。
勿論それによってアキナの怪訝が消えたかというとそのような事は全く無く、むしろ疑問は増えたといってもいい。
何故自分を撮影するのか。
細かい理由が全く分かっていなかったのだ。
そもそも、アキナの身体はNERV内では最重要機密であり、学校生活や日常生活が送れるように見られると困るといったたぐいのプロテクトこそかかっていないものの、X線撮影やメディカルチェックは勿論、散髪や遺伝子バンクへの登録さえ許されていない身の上である。
少年が持っているカメラでX線の照射ができるなどとは欠片も思っていなかったが、これが何かの暗喩であった場合は気軽に許可を出すのはまずい。
考えてみれば彼だけは自分やシンジがNERVと関係があるということを確信しているらしい節もある。
少なくともシンジがいないところで受けるにはまずい話だ。
――――駄目、否定。――――
写真に興味が無いわけではなかったが、それよりもNERVの機密のほうが優先されるべきだろう。
無理がある。
「相田君、その・・・。って、何?あれ?」
半ば写真について諦めかけたアキナが口を開こうとしたそのとき、ケンスケの背後にかなり珍妙な物体が見えた。
まるでワープでもしてきたかのように突如現れた「それ」は、先日リリスに対峙した瞬間のサキエルでさえかくやというほどのさっきを当たり構わずに撒き散らしている。
「あ・い・だ〜〜〜!!!あんたついにアキナにまで・・・死ね!!いや、殺してやるからそこで待ってろ!!」
なにやら物騒な科白を毒々しいオーラとともに放っている「それ」は気配を読むという能力に長けているアキナの目には黒い怨念のような物体として映っていた。
というか気配など読めるはずも無い他の人間にもそう見えているらしく、「それ」からアキナ達のいる地点まで間にいた生徒たちが水を分けたように引いていき一本の道となっている。
「げ、菊花・・・。」
先ほどの科白でようやくケンスケも気付いたらしく、彼のビデオカメラをいじる手が止まった。
ぎりぎりかくかくと一昔前のコメディー映画のロボットのような仕種で振り返るケンスケ。
その先にいたのは修羅、もとい剣道場常備の木刀を一分の隙も無い正眼に構え、常人離れした怒気と殺気を放つ一人の少女だった。
アキナでさえそれがいつも一緒に昼食を取っている菊花ヤエであると気付くのにさえ多少の時間を要する。
それほどの殺気をまとった少女をただの根暗なオタクであるケンスケごときが止められるわけが無い。
「相田君、逃げたほうが・・・「ごめん、この話はまた今度って事で!!」・・・・そう・・・。」
ケンスケ自身そのことは心得ているらしく彼はアキナが注意を促そうとするよりも早くすでに戦略的撤退の姿勢に移っていた。
アキナに一言声をあげた後はそのまま背を向けて全力疾走を開始する。
そして、対するヤエもまた一頻り毒を吐いた後ゆっくりと身体を沈め始めていた。
より低く。
より低重心に。
陸上のクラウチングや相撲の立ち上がりを思わせるほどにヤエの身体は地面すれすれまで近寄っていく。
それが彼女の二つ名、「神速の打ち手」の由来にもなっているロケットスタートのための用意動作である事はもはや誰の目にも疑いようの無い事実だった。
「いや、剣道部が木刀はまずいだろ!というか誰か止めて?!あれ、本気で喰らったら絶対死ぬから!!」
さほど速くも無いケンスケが逃げながら周囲に助けを求める音がアキナの耳にまで聞こえてくる。
「こら、待ちなさい!!今すぐ地獄に送ってやるんだから!!」
その後を追うヤエの声がドップラー効果を伴いながらアキナの前を通り過ぎていった。
すり足であるにもかかわらずその歩法は驚くほどに速い。
「後・・・あるのかな・・・・。」
アキナの微かな懸念の声は戻ってきた喧騒に飲み込まれるように消え、誰にも聞かれる事は無かった。
「あ〜〜〜、このように人類はその最大の試練を迎えたのであります。20世紀最後の年、宇宙より飛来した大質量の隕石が南極に衝突。氷の大陸を一瞬にして融解させたのであります。海洋の水位は上昇し・・・・・・・・」
四間目、教室の前では数学担当教諭の退屈な授業が続いていた。
セカンドインパクトは六十近いと思われる彼の教員人生の最盛期に起こったのであろう。
既に数学の授業からは遠く離れ、完全な思い出話へと変わってしまっている。
その話を真面目に聞いているのはアキナと委員長である洞木ヒカリぐらいのもので、それ以外の面々はおおむね別の作業に没頭していた。
睡眠に現を抜かすものがいるかと思えば流行りの携帯ゲームで遊んでいるものや漫画・雑誌に読みふけるものもいる。
そしてそれらに該当しない暇を持て余している大部分の生徒たちは絶対にばれない方法、即ちノート代わりに使っているパソコンにメッセンジャーを開いて授業中の会話を楽しんでいた。
「多分休み時間の延長ぐらいにしか捕らえられていないんだろうな。」というのはこの授業を始めてみたシンジの感想であり、
真、言い得て妙であったといえる。
かく言うアキナや委員長も授業のノートこそ真面目に取っているものの、アキナがこの学園に通学するようになってから数えても既に三度目である教師の言葉を拝聴する事の意義はわからなくなっていた。
どうあっても絶対に意義など見つけられないであろう教師の言葉を聞き流す傍ら、皆と同じメッセンジャーを開き、時折会話に目をやってこの教室内での流行や会話傾向のリサーチにいそしんでいる、というのが彼女達の現状である。
自分から会話に参加する事は殆ど無いが、自分の事が話題に上ったときや他人の悪口を見つけたときなどには時折入力をする事があり、そういう意味では二人とも本当に真面目に聞いているかどうかについては怪しいところだった。
――――楽しい・・・のかな?――――
授業が一段落したことを確信したアキナはいったん手を置き自分の思考へと没頭していった。
――――うん、楽しい――――
答えはすぐに出る。
それだけの事が嬉しかった。
思えば、女子校に通っていたころは本当に通っているだけだった。
無口な天才というキャラが立っていた上入学そうそう暴力事件を起こしたアキナに友人などできよう筈も無く、学校とは叔父たちの下を離れ時間をつぶせる場としての意味以上のものではなかった。
そのころに比べれば、今は少数だが友達と呼べる存在がいる。
縛られる事の無い自由がある。
そしてなにより、シンジがそばにいる。
この状況を楽しいと呼ばずして何というのだろう。
――――シンジ君も楽しいのかな?――――
もう一度自問する。
今度の問いは答えるのに時間がかかった。
彼が今を楽しんでいるかどうかは分からないのだ。
彼が以前何をしていたのか、何処にいたのか。
いろいろな事が会って結局詳しく聞き出せていない。
――――楽しんでくれてるといいな――――
ただ、そう思うことは簡単だった。
そして、本当の答えが聞きたいと思った。
――――今度聞いてみよ―――――
一人ほくそえむ。
だが、ちょうどその瞬間連続した二つのコール音がなった。
――――えっ?――――
場違いなその音に現実に引き戻され、同時にそこに書いてある言葉の真意がわからずに困惑する。
一つは簡単なもので碇君がロボットのパイロットって本当?(Y/N)というもので、差出人は後列の女子生徒。
どこかからそんな情報を入手してきたのだろうがこの質問には素直に答えてもNOであるといえる。
ただ、問題はもう一つのメッセージだった。
ただ一言、:いいかな?(Y/N)とだけ書かれたメッセージ。
差出人は不明だが、IDから相田ケンスケであるということはすぐに分かった。
が、質問の意味がわからない。
振り返るとちょうど手を上げたケンスケと目線があった。
その顔に腫れなどが見られないことを見ると朝のあれは逃げおおせたのだろう。
その手に持ったビデオカメラをアキナにだけ見えるように机の下に見せている。
それを見て、ようやく写真の件なのだと納得できた。
勿論理解できたからといってすぐに返答できるような問題ではない。
先程のヤエの反応から彼がスパイではないであろう事は既に目算をつけていたのだが、そうなるとカスパーと同じ趣味を持つ彼を遠ざけようとするのは少し悪い事のようにも思われる。
――――いい・・・かな・・・?――――
結局、迷った挙句、彼女はYESの返事を返した。
その途端、がたがたっという何かを蹴り飛ばしたような音が後ろから聞こえてくる。
再度振り返るとケンスケがガッツポーズのまま立ち上がっていた。
「こら!相田君!授業中よ!!」
委員長の叱責が飛んだがケンスケには聞こえていない。
ただ、歓喜の踊りを踊りながら万歳を繰り返す姿はどう見ても異様であったが、アキナはそこに不快なものは感じていなかった。
むしろ生温い空気の暖かさのようなものを感じ、頬がほころぶ。
――――帰ったらシンジ君にも・・・――――
証明写真以外の理由で写真をとるのは七年ぶりで、そのころの思い出が残っていたのかもしれない。
どこか浮ついた気分のまま、アキナは微かに笑っていた。
シンジが学校に来ていない日はいつもそうなのだが、今日は殊にシンジに伝える事が多かった。
「ねえねえ、さっき相田が立ち上がったのさ・・あ、おいしい・・あれ一体なんだったの?」
昼休み、アキナは早速ヤエの尋問を受けていた。
シンジお手製のアキナのお弁当を口いっぱいにほおばった即席の尋問官は、先程からずっとそれが気がかりだったらしい。
「あいつも料理の腕だけは中々・・・」などといいながら、さらにアキナを追い詰めるべく料理へと手を伸ばしてくる。
どうやら実益も兼ねた尋問であるらしかった。
「簡単にYESなんていっちゃって・・・あいつけだものよ?変態よ?というか男よ?」
微妙に差別的な発言を含みながらも、遠慮という言葉を地平線の彼方に置き去ってきたヤエの手は煮込みハンバーグの賞味を終え詰め合わせのサラダにまで伸びようとしていた。
どのような原理の元で行われているのか喋りながら食べているというのに全くスピードが落ちていない。
このまま食べ進めていけばお弁当の半分は彼女のおなかの中へと消えてしまうだろう。
「・・・・・・・・・・もう駄目。」
やむを得ず、アキナは前に出していた弁当箱を自分の手元に引き込んだ。
自分の食事を横取りされるのは彼女にとって本意ではない。
話を円滑、かつ平穏に進めるにはどう考えてもそれが望ましい方法だった。
頬を膨らませているヤエの食糧事情にはあえて目を瞑り、逆に叱りつける。
それだけでヤエはしゅん、と肩を落としてしまった。
トウジと同じで根は単純なのだ。
「それと、さっきのは秘密。教えない。」
糧食を確保した上で、アキナは本題へと移った。
ただし、告げた返答はあの後シークレット回線でケンスケと相談して決めたもので厳密に言えば彼女が考えた返答ではない。
朝の惨状を考えるにつけて、この少女に真実を告げるのは得策ではない、という二人の共通理解の元に生まれた苦肉の策だった。
「ええ〜〜!!何よそれ〜!私にも言えないような事なの?」
案の定、というべきだろう。
一瞬きょとんとした顔を見せていたヤエだったが、次の瞬間烈火の如く怒り出した。
日ごろからシンジという圧倒的な例外を除けば一番アキナと深い付き合いがあると公言して止んでいなかっただけにショックも大きかったらしく、食堂から持ってきた割り箸を振り回しながら、そはすっぽんかカミツキガメかといった勢いで噛み付いてくる。
――――アスカみたい――――
小さく首をすくませながら、アキナはそんな事を考えていた。
そして、時間は瞬く間に過ぎ、少女の下に一本の電話がかかる。
三週間目の厄日。
それを知りえた者は眠り、それを知る者はこの場にいない。
故に、食事時に鳴った電話は紫電の少女を悲しませ。
故に何も得られなかった白き抜け殻は笑う。
表舞台で華々しく舞う少女に抜け殻は何を思うのか。
ただ下卑た笑いだけが教室を埋める。
赤の少女は間に合わず。
蒼き少年はその場にいない。
運命は既に途方も無い彼方。
されど捩れの反動は付き纏う。
悲しむのは誰で、喜ぶのは誰なのか。
それぞれの思いが交錯し、各々の運命が交じり合う。
――――第四使徒、来襲。
あとがき
菊花ヤエ驀進中〜って感じ?模試でA判定とって大喜びのダークパラサイトです。
今回の話では原作にもあったイヴェントをできるだけ本作寄りに改変してみましたが如何だったでしょうか。
本来ならトウジとシンジのイヴェントだったこの話ですが、二人とも今回出番は殆ど在りません。
替わりにヤエが大暴走かましてくれちゃってます・・・キャラが自分から動く作品の真骨頂ここにありって感じです。(作者が存外に気に入ったので絵までついてます。大出世。)
これ以上言う事は在りません。
さて、次回はようやく第四使徒とのドンパチ・・・の予定です。多分二部構成になるでしょうが見捨てず、温かい目で見守ってやってください。
ではでは、再見。
蒼來の感想(?)
ヤエさん、獲物を追い詰めるが一歩及ばずってとこかw
鈴菜「おしい!!」
観月「ですわ!!」
ふむ、やはりケンスケには不幸が似合うのに、シリアスだと無理が出るか・・・真面目なケンスケのSSも結構味があっていいんだがね〜
鈴菜「ああ、あの有名なSSだな。EOE後の。」
うん。やはり本編が軽い性格のせいだろうけどね。>不幸が似合う
観月「女性の敵ですものね。」
まあな・・・しかしこの10話まで、このようなほのぼの見たいな話がなかったから新鮮だw
そして・・・大人のお○ち○来襲。
鈴菜「・・・蒼來も女の敵だな・・・(−−メ」
観月「まあ、解り切ってた事ですから・・・・(−−;」
いや、どうみてもイカには見えないんだけど・・・
まあ、今回はギスギスとした感じじゃあなくてホッとしました。
このお話ダークぽいのが多いので、規定では感想つけなくてもいいのですが、付ける時に気がめいらなくて良かったです。
・・・って何してんだ二人とも・・・・
鈴菜「いやあ、蒼來も女の敵だから。」
観月「襲撃の用意ですわv」
ちょwwマテーーーーイ!!