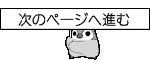もし違う形で出会っていたら、私は君を殺していたのかもしれない。
姫君の寵愛byダークパラサイト
第八話:「風」
「ああ、やっぱりそうか・・・。」
部屋に入るなり、担任教師はそうつぶやいた。
「悪いな、二人とも。君たちを紹介するのはまた今度になりそうだ。」
頭を掻きながら出てきて廊下で待っていた二人に頭を下げる。
「誰も来ていませんか・・・。」
「まあ教師も来ていない者がいるぐらいだからな。今日はどうしようもないだろう。・・・適当に学校内を見学したら帰ってくれてかまわんよ。」
「先生はどうするの?」
すでにその場を去ろうとしている教師をアキナが呼び止めた。
「私は生徒の家を回るよ。安否の確認ができない生徒が私のクラスだけで12人もいるんだ。・・・ついてくるかい?紹介してやるぞ。」
教師はまったく誠実さの欠片もない返事を返してきた。
まるでやめておけとでも言いたげに。
「望まれない訪問はしませんよ。こっちだって馬鹿じゃない。」
シンジはすぐさま辞退した。
今行けば被災者に叩かれているのは目に見えている。
「なら私は行かせてもらうよ。ゆっくりしていきたまえ。」
教師は振り返ることも無く去っていった。
「どうするの?」
「ここに残っていてもしょうがないと思うけど・・・姉さんが迎えに来るまでは帰り道もわからないし。」
「私わかるよ。」
「遠いよ。今度はバイクを盗んでいくわけにも行かないし・・・。」
「じゃあここでいい。」
アキナは誰もいない教室に入っていった。
着込んだ制服のスカートが軽くゆれ、すぐに影に消える。
「広いね。」
中から短い感想が聞こえてきた。
「そう?」
シンジは動かない。
廊下に立ったままじっと窓の外を眺めている。
曇りひとつ無いきれいな窓。
その奥に広がる青い空が原色そのままに目の中に飛び込んでくる。
よほど綺麗好きな学生がいるのかと思いそっと窓へと手を伸ばし・・・気づいた。
窓はあるがガラスが入っていない。
(どうりで・・・。)
あるべきものが無ければ世界はこんなにも綺麗に見える。
それは当然の発見であり。
それは新しい発見でもあった。
シンジも、アキナも、互いがいなければそれぞれに一人の年頃の少年、少女でしかない。
そのことは記憶が戻っていなかった再開の時にいやというほど思い知らされた。
あの時シンジはアキナに対しごく普通の親近感を抱いていた。
それは恋愛感情と言い換えても良いものですらあった。
それは記憶が戻った後もしばらくは残っていたと思う。
だが、今はそんな感情は湧かない。
冬月アキナを恋愛対象として見る事ができない。
一人の、一個の女性としてみることができない。
今あるのは畏怖の念、憧憬の心、服従心。
主人ではない。
だが、対等な存在でもない。
彼女は、冬月アキナはそんな簡単な言葉で言い表せる存在ではない。
そんなに近しい存在ではない。
言葉の上では夫婦で、これから共に生活をする者かもしれないが彼女はテレビの中のアイドルと本質的な違いは無いのだ。
絶対に汚してはならない。
そんな強迫観念にも似た思いがある。
たとえアキナが自分のことをどう思っていたとしても。
そこを曲げればシンジの中では道理がとおらなくなる。
それは異常で限りなく愚かしい道理。
わかっていても抗えない。
「おう、おまえ、今日は授業はないんかい。」
ガラスの欠片が残る窓の桟をなでていたとき、後ろから突然声をかけられた。
関西弁特有のイントネーションはシンジがはじめて聞くものだった。
不快感こそ感じないものの奇妙な感覚には襲われる。
振り返るべきかどうか、少し迷ったが結局シンジは振り返った。
「そうみたいだね。さっき先生がそういっていたから間違いないと思うよ。」
制服でもスーツでもない。
全身ジャージ姿の少年がこちらを見ていた。
「ほ〜、そうか。気張って家出たっちゅうのに無駄足やったかのぅ?」
「そうみたいだね。」
「さよか。・・・お〜い、ヌエ!今日学校無いらしいわ!!」
ジャージの少年は顎を撫でながら隣のクラスへと入っていった。
「どうしたの?」
声を聞きつけたのだろう。
入れ替わりにアキナが教室から顔を出した。
「何でもないよ。僕たちのほかにも登校してきた生徒がいただけだよ。」
「そう・・・。」
「見学はもういい?」
「うん。」
あどけなさが強く残っているその返答にシンジは苦笑した。
体は成長したのに言葉遣いやしぐさには大きな違いがない。
まるで七年前の少女が殻だけを取り替え目の前に立っているかのごとき錯覚すら覚える。
だが、そうではないこともまた十分に理解していた。
出会ってすぐのころ、彼女は普通の、シンジが知る人間とさほど変わらぬ喋り方しかしていなかった。
さらに言えば昨日の夕食前。
あの時見たアキナはシンジの知る彼女ではなかった。
あんなものが{冬月アキナ}であろう筈が無かった。
「じゃあ町のほうへ出てみようか。」
「うん。」
柔らかく頭を撫でてやるとアキナは心地よさそうに目を細めた。
愛玩動物を思わせるようないじらしい反応。
その姿に思わず嘆息する。
彼女は、冬月アキナは、本質的に何も変わっていない。
強く、幼く、儚く、脆い。
{冬月アキナ}は変化していないのだ。
「何か話があるの?」
頭を撫でているうちに何か気づくことがあったのだろう。
アキナは小さく顔を上げてシンジの顔を眺めた。
洞察力が良いだけであるはずなのに心の中をのぞかれているような錯覚にとらわれる。
「少しね。」
「何?」
「うん、昨日・・・。」
「やっぱり今日来てもあかんかったな。完全な無駄足やったわ。」
二人だけの時間に浸りかけた時、B組の中からさっきのジャージ姿の少年が現れた。
その後ろに不思議なたたずまいの少年が続いている。
急がねばならぬほどの用件でも無かったこともあり、シンジの言動は自然に封殺された。
かわりに二人の視線は新しく現れた少年に惜しみなく注がれる。
それだけその少年が異色の存在であったから。
アキナにとってはあまりにも見慣れた姿だったから。
シンジにとってはあまりにも聞きなれた姿だったから。
「レ・・・イ・・・?」
口からは良く知る少女の名が漏れる。
赤い目を持ち。
青みがかった銀髪を持つ人間。
そのような存在がそう多くいるとは思えない。
だが、少年はぴくりとも顔を動かさなかった。
まるで悟りきった修行僧(もしくは痴呆の老人)のようにじっとシンジ達を眺めている。
だが、その姿さえも本当にシンジたちを見ているかどうかは怪しいものだった。
もっと遠くの・・・空か何かを眺めているようにも見える。
「レイ?ああ、綾波の事か。ちゃうちゃう。こいつは長門ヌエっちゅうんや。よろしく頼むわ・・・。」
黙ったままの少年に代わり、ジャージ姿の少年が答えを返す。
ただ、その途中でふと考え込むような仕種を見せた。
「・・・おまえら誰や?よう考えたら全く知らん顔なんやけど・・・。」
シンジの顔をのぞき、頻りに首を傾げる。
どうやらそれがわからずに悩んでいたらしい。
根は単純なのだろう。
「彼女は冬月アキナ、僕は碇シンジ。今日から転入してきたんだから知らないのは当然だと思うよ?」
心底あきれたようにシンジは肩をすくめて見せた。
その後ろでアキナも首を縦に振る。
「何や、そうか。わしの名前は・・」
「鈴原、だろ。さっき先生がそう言ってた。」
シンジは途中でジャージの少年の言葉をさえぎった。
きょとん、と、ジャージの少年の目が見開かれる。
「槙原が?何やねんあの先公。わしにやってぷらいばしいってもんがやな・・。」
ぶつぶつと文句を言う。
「・・・。」
アキナは少し引き気味にそんな鈴原の姿を見つめていた。
どうやら彼女のこれまでの人生経験の中ではこのような男性に会ったことが無かったらしい。
シンジの服の裾を掴み、まるで珍獣でも見るように少年たちを観察している。
(そっか、女子校だっけ・・・。)
例え女子校であったとしても、普通の中学生の女の子ならこんなにも引くことは無かっただろう。
つまり、きっとそれは・・・彼女は普通ではなかったということ。
普通の中学生のように、いや、普通の人間として生きたことが無かったということ。
それは今のシンジとアキナの間にある最大の違いかもしれなかった。
「まあええわ。わしの名前は鈴原トウジ。おまえらと同じA組や。よろしゅう頼むで、転校生。」
無造作に突き出された右手。
シンジはそれをしっかりと握り返す。
少なくとも今、敵ではない人間ができたのは嬉しい誤算だった。
このジャージ姿の少年は、トウジは自分たちのことを微塵も恨んではいない。
もしかしたら頭が悪いだけかもしれないが今はそれでもいい。
根が単純そうだから少し話し込めば味方につけられるだろう。
そんな計算を頭の中で瞬時に立てる。
相手がアキナで無いのであれば卑屈になる必要は全く無い。
「アキナさんもよろしゅう。」
出された手を前にして一瞬アキナの目に怯えのようなものが浮かんだ。
困惑したかのようにシンジのほうを眺めてくる。
手を握り返してもいいか。
そのことを確認しているのだ。
(ただの握手なのに・・・。)
そうは思うものの少しだけ嬉しいという感情もあった。
シンジにとってアキナが一番であるのと同じく、アキナにとってもシンジは一番の存在である。
そのことがこんな些細なことで確認できる。
小さく頷く顔にも笑みが洩れた。
それを見たアキナはようやっと出されたままになっていたトウジの手を握り返した。
「おおきに。嫌われてしもたか思たで。」
冗句のつもりなのだろう。
トウジはそう言って豪快に笑った。
その顔をアキナは不思議そうに覗き込む。
「・・・・・・・・・・。」
「・・・・・・・・・・。」
「・・・・・・・・・・。」
奇妙な沈黙が流れた。
「あ〜、もしかしてほんまに嫌われてます?」
アキナは答えない。
シンジも何も言わない。
だが、この場で一番意外な人物が口を開いた。
「嫌われてはいない。」
簡潔な一言。
注意していなければ聞き逃してしまいそうな小声。
それが今までずっと案山子のように立ち尽くしていた少年の声だと理解するのに誰もが少量の時間を要した。
「そのリリンから嫌悪の感情は感じないよ・・・トウジ。」
静かで厳かな声。
トウジは目をぱちくりさせ、シンジは警戒心をあらわにした。
だが、その中でも全く物怖じすることなくヌエはアキナに近づいていく。
「何?」
アキナは握っていたトウジの手を解き、ヌエのほうへと向き直った。
彼女の中で小さな流転が起こる。
内部序列が小さく入れ替わる。
それは小さな変化。
それは大きな変貌。
そして、巻き起こるものは凶悪な衝動。
「私はあなたに好意を見せた覚えも無いのだけど。」
握手を交わしながらアキナはぼそりと囁いた。
握手を交わしている二人以外には聞きようも無い小さな声。
だが、それまでは無かった小さな炎がアキナの目の中で揺れていた。
幸いだったのはシンジに背を向けていたこと。
不幸だったのはアキナの異常性にヌエが気づいてしまったこと。
リリスの存在に・・・気づいてしまったこと。
「・・・・・・君は・・・。」
「え?何?」
ヌエが話し掛けようとしたとき、すでにアキナの中の序列は元に戻っていた。
その姿は無邪気な一人の少女でしかない。
その目に宿る炎はすでに消えている。
この状態でこれ以上の事態の進展はありえないだろう。
だが、ヌエの心の中では邪悪な思考が踊っている。
やっと見つけた少女をおめおめと放す気は無かった。
自然、握る手にも力が篭もる。
「ほなま、挨拶もすんだし行くで、ヌエ。」
トウジは何も知らぬままにヌエに声をかける。
「・・・わかった。」
抑揚された普段と何一つ変わらぬ声。
少なくともトウジにはそう聞こえた。
その声に不自然なところがあると、そう気づける少女は今ここにはいなかった。
「転校生たちはこれからどうするんや?」
「さあね。君達には関係のないことだろう?」
シンジはトウジの質問を完全に封殺した。
相手の目だけを見ることで返答すらも許さない。
「ほなわしらは帰らしてもらうわ。」
しばらく睨み合っていたトウジとシンジだったが、あきらめるのはトウジのほうが早かった。
ついと目をそらし踵を返す。
「ほら、いくで、ヌエ。」
後ろを向いたまま声をかけるとヌエはすぐさまトウジの後を追った。
ぺたん、ぱたん、という踵を引きずるような音に規則正しい靴音が重なる。
ゆっくりと遠ざかっていくその音を二人は黙って聞いていた。
シンジは壁にもたれかかり。
アキナは教室の扉の端にもたれかかり。
互いに互いを見詰め合う。
再び二人きりの空間が訪れた。
だが、静けさが空間の空気を押しつぶす瞬間がくるまで二人は何も言葉を発さずに押し黙っていた。
それがいつかなど知らない。
それでもシンジはアキナが話し掛けてくれるまで待つつもりだったし、実際そうした。
「昨日・・・何?」
静けさに重さが混じり、それが人を狂わせるほどの質量を持ち始めたころになってようやくアキナが口を開いた。
その間に一時間近くの時間が流れていたため、シンジは最初、彼女が何の話をしているのかわからなかった。
ゆっくりと記憶をたどり、自分が振った話だったことを思い出す。
それまでに少々の時間を要した。
現実時間で表せば十秒ほど。
だが、この静寂の支配する空間にあってそのような事実に何の意味があるだろうか?
アインシュタインの言葉を引用するまでもなく、その時間は酷く圧延された長々としたものだった。
一時間も待たされたのに待たせてしまうという意識が先行する。
「そうだね・・・昨日何で寝てたのかな、と思ったんだけなんだけど・・・。」
違う。
聞きたいことはそんなことではない。
「・・・命令・・・だったから。」
「・・・そう。」
誰からの命令だと言うのだろうか。
{冬月アキナ}に命令できるほどの人物が本当にいるのだろうか?
思い当たる人物はそう多くはない。
自らの父か。
それ以外のNERVの上級職員か。
そんなところだろう。
だが、自分と話をせずに眠ることに何の意味があると言うのだろうか。
それほど意味のあることだとは思えない。
「じゃあ・・・今日のお昼、どこで取る?」
言ってからこれはすばらしい質問だと思った。
今はまだ早すぎるがそれはさっきの質問よりもずっと重要性があることだと思われた。
持ってきた弁当は二つ。
もうここにいる意味はないのだからどこで食べても構わないのだができることならアキナの希望を聞きたかった。
「・・・・・・空が見えるところならどこでもいい・・・。」
「・・・・・・。」
アキナの希望は単調で、だからこそ非常に難しいものとなった。
空が見える場所などそれこそ掃いて捨てるほどある。
公園でもいいし、海辺でもいいし、人目を気にしないなら復興中の町の中でだって食べられる。
「だめ?」
「だめじゃないけどね・・・どこにしようかと思って・・・。」
沈黙を否定の意味に取ったのだろう。
アキナが不安そうにシンジの顔を覗き込んでくる。
シンジはそれを軽く受け流した。
だめなわけがない。
アキナが望むなら工場の排煙をかぶりながら食べる事だって厭わない。
ただ、この少女が何を望んでいるのか、それを考えていたのだ。
「・・・屋上にしようか。」
しばらく考えた後、シンジはそこに考えを落ち着けた。
以前通っていた学校では屋上で食事を取っていた。
それに倣ったに過ぎないが、これからもそこで食事をとるであろうことを考えると少し見ておきたい気もする。
「屋上?」
「空も見えると思うよ。」
昼食には少し早いが、早すぎると言うほど早くもない。
屋上の扉が閉まっている可能性もあるがまあどうにかなるだろうと踏んでいた。
「・・・行く?」
手に持っていた包みを振って見せるとアキナは首を縦に振った。
風が吹いている。
東から西へ暖かい風が吹き抜ける。
それは強すぎず、弱すぎず。
肌を心地よく撫でるだけで何もしない。
何もせず・・・何処へ?
もちろん今の風に意味を求めても仕方がないだろう。
風は風。
意思も意味も持たない。
高気圧から低気圧へ。
高いところから低いところへ。
坂道に置かれた球体のように転がり落ちるだけ。
だがこの風に意味があればそれはどんな事だろうと。
そう想像する事ぐらいは許して欲しい。
こんな事を言っていれば恋人はそういうところがロマンチストなのだとからかうだろう。
むろん自分で自分をロマンチストだとは思わない。
むしろ酷い現実主義者だと思っている。
今だって、この風の発生源は意外と近いのだろうな、とか。
そんな事を考えていたりする。
少なくともこの風が日本から吹いてくるものではありえない事ぐらいはすぐにわかる。
それでも。
想像してしまうのだ。
この風が微かにでも彼らの匂いを含んでいればいいと。
この風が地球を回って、私の心の一部でも、故国に送ってはくれないかと。
そんな冗句を。
そんな事を思ってしまうのは今日の空があまりにも蒼いから?
それとも年中偏西風の吹くこの国での東風が珍しかっただけ?
違うだろう。
心に浮かぶのは二人。
紫電の少女と。
無色の少年と。
生きていた。
まだ生きていた。
ならまた会えるではないか。
ならまた話せるではないか。
離れ離れになり。
連絡もつかぬまま。
ずっとずっと待ち続けて。
もう少し。
もう少しで会える。
だからだろう。
こんな冗句にもならぬ冗句を。
普段の私なら考えもしない冗句を。
考え付いてしまうのは。
まだ風は吹いている。
東から西へ暖かい風が吹き抜ける。
それは強すぎず、弱すぎず。
肌を心地よく撫でるだけで何もしない。
ドイツに東風が・・・吹く。
ずっと眺めていた。
自分でも自分の食事を取りながら。
ずっと眺めていた。
目線の先には一人の少女。
黙々と食事をとりつづけている少女。
その膝の上には自分の物の倍近くありそうな弁当箱が置かれている。
だが、その半分近くがもうなくなっていた。
美味しいかどうかは聞かない。
そんな事を聞いてみずとも自分の味に自信があった。
そしてそれを肯定するかのようにアキナは食べ続けている。
会話は・・・成立しない。
する事がないシンジはやっと四分の一ほどを食べ終わった弁当箱を膝の上に乗せたままアキナを眺めている。
それだけの事。
「全く・・・なんでこんな事になったのかしらね・・・。」
人払いをすませた病室でリツコはそっと自分の親友の頭を撫でていた。
葛城ミサトは目を覚まさない。
全身にチューブが刺しこまれ、壁に掛けられた心電図がむなしく生存を告げている。
ただでさえ痛々しい傷を持つ彼女の体なのに、これ以上傷が増えたらどうするのだ・・・。
漠然とそんな事を思った。
「今日梶君から連絡が入ったわ。」
聞こえているだろうか?
壁に掛けられた心電図は変化を見せない。
コン、コン、と規則的に緑の光を揺らすだけ。
「彼、こっちに帰ってくるそうよ。」
朝見たメールの内容を告げる。
それは彼女にとって嬉しい事だろう。
もっとも、もし起きていれば全身全霊でもって否定するだろうが・・・。
「新しくできた彼女は14歳だって。自分でも何を考えてるかわからないって。」
こんな事を聞かせたら余計起きてこないかもしれない。
自分でも嫌な事を言っていると思う。
「馬鹿げてると思わない?」
馬鹿げているのは・・・。
誰だろう?
「あの加持君が・・・レイやアキナちゃんと同年代の子と付き合っているのよ・・・?」
無駄だろう。
ミサトはアキナを知らない。
彼女が入ったのはアキナが抜けた後だ。
「本気で付き合ってるのかしらね・・・?」
本気ではないだろう。
彼が年下趣味だという話は聞いた事がない。
「早く起きてこないと・・・・・・。」
ピリリリリリ
言葉を遮るようにして電子音が響いた。
少しうんざりしながら通話のボタンを押す。
人払いしたのだから当然のことだがなんとタイミングの悪い部下だろう。
「赤城博士、時間です。研究塔のほうへ戻ってください。」
「分かったわ。すぐ戻る。」
最後に名残惜しげに彼女の頭を撫でる。
そのときまで彼女の顔にはまるで自愛に満ちた聖母のような優しげな笑みが浮かんでいた。
だが、直後には技術者の顔に戻り退室していった。
後には怪我人が一人だけ。
あとがき
そろそろ溜め込みすぎた疑問符を放出しないとな・・・と思いつつもさらに疑問符を増やしていますね。
とりあえず紛いなりにも主要キャラの名前は揃いつつあるのではないかと思うのです。
後は委員長とミリタリーオタクと使徒の坊ちゃんぐらいでしょうか・・・・・?
忘れてるのがいるぞ〜とかこいつは一押し、とかあったら教えてください。(どうせ返事なんてこないんでしょうけどね〜。)
では最後に・・・ここの中学ってプールは屋上にあるんでしたっけ?
なんだかうろ覚えにも程があるんですがどこかのSSでシンジが綾波の水泳(スクール水着姿?)を見上げていた・・・ような記憶があって・・・。(それもオールドだったかニューだったか・・・。)
だとしたらこいつらプールサイドで飯食ってたわけでして・・・別にいいんだけどやっぱり変な気もして・・・。
ああ〜、映像を見る事ができればそれが一番早いのに!!
・・・・・・{捩れた繰り人形}にでも聞けばわかるかな・・・?
蒼來の感想(?)
長門ヌエさんってもしかして・・・ダークパラサイトさん?!Σ(;゜◇゜)ノノ
鈴菜「なんで?」
いやね、作品のメールの氏名欄が「ヌエ」で来るんだよ。
観月「あらあら、そう言う蒼來こそ作品の中に出てきますわ。」
・・・大航海時代日誌のことか?確かに出てきてはいるが・・・
鈴菜「しかもメインでな!!」
・・・自分の視点じゃあないと、あれ書けませぬ。<(_ _)>
観月「やはり、へタレ作家ですわ。」
(/TДT)/あうぅ・・・・
鈴菜「まあ、へタレは置いといて・・・確か、プールは屋上じゃあないんじゃあないかなあ?」
観月「ネルフのプールは確か地下ですわね。」
うろ覚えだが、トウジ・シンジ・ケンスケでバスケだが何だが授業でプールを見てたような・・・
多分、普通の学校と同じく地上にあると思われます。
鈴菜「後、感想のメールを皆さんよろしくな!!」
観月「来ない場合は、集客力不足の蒼來のせいですわ。v」
・・・いや、その通りなんだが・・・何とか努力します。(´Д⊂)