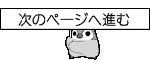僕は彼女のためになにができるのか?
彼女と生きてる限りつきまとう疑問。
答など・・・いらない。
自分で出す・・・。
姫君の寵愛 byダークパラサイト
第5話:父と子
「ん・・・・・。」
朝がきた。
部屋の中にいるので陽光の差し込むすがすがしい朝・・・とはいかないがそれでも自分の体がそのことに敏感に反応している。
「シンジ君・・・?」
シーツから顔を出し周囲を見回す。
だが、目に入る範囲に人はいなかった。
(どこ・・・?)
ならばとばかりに気配を探る。
目を閉じ、ゆっくりと呼吸を落ち着ける。
(いない・・・)
少なくともここの周囲には誰か人がいるようには思えなかった。
(・・・そう・・・。)
ゆっくりとベッドから抜け出す。
パジャマのような院内着が汗でべとついていた。
「マギ、着替えるから監視システムを解除してちょうだい。ネルフ所属、冬月アキナ。わかるわね。」
周囲の壁が少しずつ動いた。
カメラの前に遮蔽用の壁が現れ、物理的に監視不可の状態を作る。
「ありがとう、ナオコ先生。」
その当たり前の反応に対し彼女は謝辞を述べた。
スーパーコンピューターマギ、ではなく。
人間としての赤城ナオコ、に。
「どういたしまして。」
人工音声が部屋に埋め込まれたスピーカーから聞こえた。
その言葉にアキナの頬がゆるむ。
「それと・・・ただいま。」
少しだけ頬を朱に染めて。
7年ぶりの挨拶を交わす。
「お帰りなさい、ゼロ。・・・照れることないのに・・・。」
拗ねたような言葉が何の抑揚もない電子音によって紡がれる。
結構不気味な情景のはずなのだがアキナは何の関心も払わなかった。
というより別の場所に関心を持っていた。
「先生まだのぞいてる?」
部屋の中にきょろきょろと目を走らせる。
「なにを言ってるの?」
あきれたような言葉。
「だって・・・。」
アキナの頬がさらに染まる。
「先生そういうの好きだし・・・。」
沈黙。
ゲンドウと違いずっこけたりすることはないが部屋の明かりが少し暗くなった。
以外と芸が細かい。
「あはは・・・冗談。先生のことは信用してるから。ねえ、シンジ君はどこ?」
ぱちん、ぱちん、とボタンのはずされる音だけが響く。
「先生?」
しばらく待った後アキナは天井に顔を向けた。
「自分で探した方がいいんじゃない?私が探してあげるより・・・。」
「カスパーの意地悪。」
「・・・・・。」
部屋の中を静寂が包む。
「・・・・・・・・・・カメラ、開けてもいいかしら?」
かたん、と小さく壁が動く。
どうやら本気で切れているらしい。
「ああ〜、ちょっと待って!!それなし!!」
慌てて脱ぎかけた院内着を着込み直す。
なにを恥ずかしがる必要があるのか、と思う人もいるかもしれないが彼女にとっては文字通り死活問題だった。
ここで下手を打ったらネルフにいられなくなる可能性がある。
「お願い!謝るから。着替えたいんだって。・・・汗ばんでて気持ち悪いのよ!」
必死に体を動かし訴える。
怪我人としての自覚が全くない。
というよりも怪我がどこにあったのかすらわからない。
「相変わらず元気ね。怪我はどうしたの?」
アキナの声が途絶えた。
「・・・治っちゃった。」
しばらく逡巡したあとアキナはぼそっとつぶやいた。
全治一週間を一夜にして治す。
それが彼女の能力のひとつだった。
「相変わらず非常識ね。本当にATフィールドは使えないの?」
「使えないわよ・・・もし使えたとしても今のままじゃ無理。誰かが教えてくれないと・・・。」
生まれたその日に泳げる人間などいない。
アキナが言いたいのはそういうことだ。
「エヴァに乗ってたら使えるんでしょう?やっぱり勝手が違う?」
「全然。」
アキナはため息をついた。
もし使えたらもっと簡単にシンジを守ってあげられる。
そう思うと少し情けなくもある。
「ため息ばっかりついてるとふけるわよ。」
天井から聞こえる声。
「やっぱりのぞいてる。」
その声に苦情を返す。
端から見ていると一人芝居に見えなくもないだろう。
「何よ、文句ある?」
ナオコ(カスパー)は開き直ったらしかった。
「カスパーのせいでここにいられなくなりかけましたから・・・。」
「ろ、6歳の頃の話じゃない!まだ蒸し返すの?!」
アキナの言葉に反応して電気が極限まで明るくなった。
どうやら興奮しているらしい。
「三つ子の魂百までって言いますから。」
アキナの言葉に情け容赦はない。
「バーサンになったとは言っても百は越えてませんもんね、カスパー。」
「っ!!あなたね・・・まあいいわ。しばらく完全に落としてあげるからさっさと着替えなさい。」
今度こそ本当に落としたようだった。
・・・電気まで。
(先生怒ってるな・・・)
だが受け入れてくれた。
アキナは暗い部屋の中で上着を落とした。
それによって紫を基調にしたブラに包まれた胸があらわになる。
だが暗い部屋の中でありながらアキナの周囲だけが光に包まれていた。
胸の間にある小さな光球から放たれている赤いぼうっとした光。
それを慈しむように撫でた後彼女はすべての着衣を体から落とした。
院内着の下に隠れていた中学生離れした身体が露わになる。
遺伝子を操作された身体。
なによりもそれを証明しているのが背中に刻印された文字。
『BX000S』
赤い字で刻まれた刻印。
人工進化研究所第二分室、特殊成功例第零号。
アキナに与えられたもう一つの名がその記号だった。
アキナはその光に周囲をてらさせながらベッドの横に置かれたタンスから一枚の服を取り出した。
彼女の好みに合わせられたのだろう。
紫がかった服ばかりが並べられていた。
「私ってそんなに紫色の服ばっかりきてるかな・・?」
言葉ではいやそうにしていながらも顔は笑っていた。
7年前から好みは変わっていない。
中から薄い紫のタンクトップを取り出し、首まで羽織る
ズボンには黒に近い紫のハーフパンツを選んだ。
そのまま鏡の前にたち、胸をはだけさせたまま自分の光でぼさぼさになった髪をとかしていく。
半分ほどとかし終えたところで突然部屋の中に電気が戻った。
「いやああぁぁぁ!!」
悲鳴が響く。
「何をしているの?着替えは終わった?」
姿が見えないだけにたちが悪いのかもしれない。
鏡の前には慌てて服をおろしぜえぜえと荒い息を吐くアキナの姿があった。
「ふんふんふん・・・・」
20分後、ネルフの廊下には鼻歌を歌いながら歩くアキナの姿があった。
特に向かう先があるわけではない。
ふらふらと歩く。
だがつい先日大けがを負った人間が歩いていると普通の人間はどんな対応をするだろうか?
アキナはそのことを完全に失念していた。
「ち、ちょっと、アキナちゃん?!こんなところで何してるのよ!」
伊吹マヤ。
ネルフ本部技術局1課所属オペレーター。
エヴァ操縦者のモニターを担当している彼女は当然彼女の怪我がどの程度のものであったかを知っている。
「あ、マヤさん。昨日はご迷惑をおかけしました。」
そんな女性に対しアキナは何ら物怖じすることなくぺこり、と頭を下げた。
「あ、いいのよ。そんなこと・・・じゃなくて、身体の方は大丈夫なの?」
「肋骨にひびが入っただけなら大丈夫です。もう治ったので。」
「治った?病院の許可がでたの?」
「いいえ。許可なんていりませんから。」
さらりと答える。
そんなアキナの答にマヤは絶句した。
「許可がいらないってあなた・・・。」
「職員ランク特S。軍内ランクに直せば三将。・・・調べてみればどうですか?」
アキナは平然と自分の階級を告げた。
本当だとしたら少女の階級は冬月に次ぐ位置にいることになる。
二尉である自分よりも遙かな高み。
そして何よりも愛する先輩より上の存在。
目の前に立つ少女にそれほどの権限が与えられていると言われて信じられるものがいったいどれほどいるだろうか?
少なくともマヤは信じなかった。
「そんな嘘ついたってだめなんだからね。先輩だってランクは特Aよ。いくらエヴァのパイロットだからって、そんなに高いはずが無いじゃない。」
胸ぐらをつかみ、アキナを揺さぶる。
決して責めるような口調ではないが先輩を侮辱されたととらえたらしく、普段の彼女らしくない凶行に及んでいた。
「だから調べてみればいいじゃないですか。すぐそこに館内用端末もあるんですから。」
それに対しいい気分だったところを害されたアキナは少し怒っていた。
引きつった笑みを浮かべるマヤに対し顎で壁につけられた端末を指し示す。
「それとも、確認せずに今すぐここを追い出されて路頭に迷う道の方がいいですか?」
普段と同じ冬月アキナとして、だが、先日シンジに見せたものとは明らかに違う少女。
見つめる目には無意識のうちに殺気がこもっていた。
黒い瞳の奥に妖しい光がちらほらと見え始める。
「ひっ・・・なに・・・これ・・・。」
その光、いや、炎を間近で見てしまったマヤは思わず手を離し後ずさった。
「選んでください。マヤさん。」
手が離れたのをいいことにアキナはマヤの顔に後数センチと言うところまで近づいた。
ほんの少し顔を動かせば唇が触れ合ってしまいそうな距離で相対する。
「私があなたを追放することなどできないとお思いですか?」
その距離まで近寄ってもなお彼女の動きは滑らかだった。
猫をあやすようにマヤの顎の下を撫でる。
「ごめんなさい・・・ゆるして・・・。」
マヤはすでに涙目になっていた。
おびえからかかちかちと歯がなっている。
「そうね・・・私は何を許してあげればいいの?・・・首はいや?」
ふるふると首が横に振られる。
「殺さないで・・・殺さないで・・・。」
よく聞けば蚊の鳴くような声で訴える声が聞こえた。
その声にアキナの表情がゆるむ。
「マヤさんは私があなたを殺すと思っているの?」
そこまでいったところでアキナの顔は豹変した。
目の端がつり上がり怒りが露わになる。
「・・・こんなふうに・・・。」
突然撫でていたアキナの指がぐっとねじられた。
それだけでマヤの気道と動脈がつぶれ息が詰まる。
悲鳴を上げる暇もなかった。
「かっ・・・はっ。」
苦しいと思う間ことすら許されない。
爪を突き立てられたところが急速に熱を持ち痛みを与える。
その痛みに耐えられなければ彼女の死は確実だろう。
マヤが両手両足をばたつかせ必死にもがく。
だがアキナの力は意外にも強く、それで彼女が解放されるということはなかった。
指先に触れるマヤの皮膚が異常なほどの熱を持っているのはアキナにもわかっていた。
それでも彼女が指先に込める力を緩めることはない。
むしろその締め付けをさらに強くする。
「教えてよ、マヤさん。」
マヤにしてみたらそんなものに答えている場合ではないといったところだろう。
顔は真っ赤になり、もがいていた手にも力はなくなりつつあった。
人間は脳へとつながっている動脈をつぶされると抵抗する力すら奪われてしまう。
つぶされてからまだ30秒ぐらいしかたっていなかったがすでにマヤの脳は酸素を求める細胞でいっぱいになっていた。
魂が浮かび上がるような浮遊間におそわれる。
(な・・・に・・・?)
無重力の空間にでもいるかのように全身から体重という概念が消えていく。
(私・・・死ぬの?)
マヤは自分の考えたことに愕然となった。
『死』
今まで考えたこともないことだった。
昨日の使徒の襲撃の時でさえ、そんなことを考えはしなかった。
だが今この瞬間彼女は間違いなく死に面していた。
(いやよ、そんなの)
少しだけ意識が戻ってきた。
持てる力のすべてを振り絞り首にかけられた手をつかみ引き剥がしにかかる。
意外にも手は簡単にはずれた。
だがさっきまではずそうとしていた手だったがはずしたらはずしたで新たな苦しみが待っていた。
急に開かれた血管から大量の血が流れ込んでくる。
「あ・・が・・はぁ・・・。」
周囲の目をはばかることなく廊下をのたうち回る。
突然の環境の変化に身体がついてきていなかった。
のどの奥に血の味が残る。
無意識のうちに自分の身体をかき抱いていた。
ふるえる手で必死に自分の身体をつつみこむ。
「何をしているの?マヤさん。」
アキナの手がそんなマヤの身体を無理矢理引き起こした。
「こんなところで寝てると風邪を引くわよ。」
ぱんぱん、という乾いた音を立て、マヤの両の頬を打つ。
その痛みがマヤを完全に覚醒させた。
「怖い思いをさせちゃったわね。けど・・・信じてくれた?」
「う・・・あ・・・・・・。」
瞳に映る少女の瞳にはもう炎は燃えていない。
それでも悪魔のような少女の笑み。
絶対的な力で人を支配する。
彼女はこれまでずっとそうすることで生きてきていた。
身近な人物とはごく親しく。
それ以外の人物には冷酷な仕打ちで恐怖心を植え付ける。
それが通用しなかったのはおじの家族だけだ。
「はい。」
マヤは目に涙をいっぱいにたたえたままうなずいた。
そのひょうしに目から大粒の涙がこぼれ落ちる。
「いい子ね、もう泣かないで。」
頬を伝い落ちるマヤの涙をアキナは自分の舌でゆっくりとなめとった。
ざらついた肉のかたまりがマヤの肌の上ではねる。
その異常な状況の中でマヤは目を閉じ首をすくめていることしかできなかった。
まるで死刑宣告を受けた虜囚のように口を閉ざし、
やがて、アキナがマヤから体を離す。
「これからもよろしくね、二尉。」
そう言い残してアキナは去っていった。
必然的に後には顔を唾液でべたべたにしたマヤだけが取り残される。
(・・・顔・・・洗わなくちゃ・・・。)
彼女の頭の中ではそんな考えだけが渦巻いていた。
時は少し前後する。
アキナが起きる少し前にシンジは総司令室に呼び出されていた。
他ならぬアキナの提案についての件はすぐにシンジにも受理された。
もう少し抵抗があると考えていたゲンドウにとってはうれしい誤算だったといえる。
「アキナちゃんがそれを望んでいるのなら。」
彼は自分の意志をそう表現した。
そこにシンジ自身の意志はない。
まるでそれが当然のことであるかのようにシンジはアキナの提案を受け入れる。
「それで・・・アキナちゃんの様子はどうなんですか?起きているのなら迎えに行ってあげたいのですが・・・。」
父のことを父と思っていないような発言。
少年の関心はここにきてからは常にアキナのことに対し注がれていた。
「ああ、先ほど医務室に連絡を取ったのだがどうやらまだ眠っているらしい。それで、ものは頼みなのだが彼女の荷物をまとめてこちらに持ってきてはくれないか?場所は誰かに案内させる。」
「わかりました。ですがその前に父さん、その前にあなたに二つだけ聞きたいことがあります。」
今度の提案も受理されたゲンドウはほっとため息をついた。
「エヴァは最重要機密だ。それについて話せることはいくらおまえが相手でもそう多くはないぞ。」
「わかっています。そんなことを聞こうとしているんじゃありません。一つ目は・・・昨日僕のことを迎えにくるはずだったミサトさんのことです。来る気配もなかったんですがどうなってたんですか?」
詰め寄る、というのが正しいだろう。
彼女が間に合っていればこんな惨事にならなかった可能性は十分にある。
もしそれによって自分があの鬼に乗らねばならなかったとしても・・・だ。
「彼女は昨日の戦闘に巻き込まれてな、一命はとりとめたものの重体だそうだ。」
押し黙るゲンドウの代わりに冬月が答えた。
「そうですか。ではもう一つ、七年前、なぜ僕たちを引き離したのですか?アスカや・・・アキナちゃんと。」
少年の目が細められる。
過去の記憶は未だに鮮明で目を閉じれば空気の温度まで思い出せそうなほどだった。
「あのとき僕たちは何も知らされることなく引き離された。あのときいったい何が起こったのですか?」
シンジにはアキナの持つような威圧感は備わっていない。
だが、彼には自分でも知らない武器が備わっていた。
アキナの夫であるという事実。
その一点だけでゲンドウたちに与える影響としては十分であるはずだった。
もしシンジが止めればエヴァのパイロットを同時に二人失ってしまうのだ。
それほどに両者の信頼関係は厚い。
「おまえはどう思う?シンジ。私たちの判断が間違いだったと思うか?」
ゲンドウは質問に答えなかった。
かわりにシンジに結果を聞いた。
今大事なのは結果なのだ。
「そうは思いませんよ。父さんのおかげで僕は外の世界を知った。・・・皮肉なことですがね。」
「ならそれでよいだろう。」
ゲンドウはそこで話を打ち切った。
「そう・・ですね。」
奇妙な沈黙があたりを包んだ。
互いにいいたいことが言い出せない。
そんな沈黙。
「あの・・・ただいま、父さん。」
先に切り出したのはシンジの方だった。
照れくさいのか鼻をかきながらそっぽを向いている。
「ああ、お帰り、シンジ。」
ゲンドウも顔を赤らめながら答えた。
もっとも隠れている顔を推し量ることなどできはしないのだが・・・。
「・・・もういいだろうそろそろ行って来い。」
ゲンドウの声と同時にシンジも総司令室から消えた。
「・・・もういないぞ。」
「・・・も、問題ない。」
「そうか・・・?」
「うむ。」
「・・・・・・・・・・・・。」
「・・・・・・・・・・・・。」
「・・・・・で?用とは何だったのだ?冬月。」
「ああ、老人たちからの緊急会議への出頭要請だ。どうする?」
冬月の言葉でやっとゲンドウの顔にも普段の緊張感が戻ってきた。
「そんなもの、適当にあしらっておけばいい。どうせまたつらつらと嫌みを言われるだけだろう。」
一方冬月の額にはしわが寄せられている。
「本当にそれでいいのか?計画への遅れはでていないのだろうな?」
「ふっ、問題ない。多少の誤差はでているが修正範囲内だ。」
「ならそのように伝えておこう。だが忘れるなよ、碇。我らの最終目標が人類補完計画であることを・・。」
「問題ない。」
「そうか、それならよいのだがな。」
「しかし、まさかあなたが案内役だとは思いませんでしたよ、姉さん。」
ゲンドウの前から退室した一時間後、シンジはリツコの車で新東京市の東にあるアキナの養父の家へと向かっていた。
その横では金髪の女性が自分の部下が今生命の危機に瀕しているとも知らずにハンドルを握っている。
急遽設置された工事用の信号がちょうど赤にかわり、車は道路で釘付けになっていた。
「私だってまさかこんな仕事を言いつけられるとは思わなかったわよ。いくらあなた達がエヴァのパイロットで最重要機密に値する人物だからって、私に押しつけること無いのに・・・。まだ仕事だって山のように残っているのよ?!昨日壊れたエヴァの修理やらなにやら・・・私が持ち場を離れていいわけがないのに・・・そんなに私の仕事を増やしたいのかしら?総司令は。結局全部の負担は部下に回るんですからね・・・。」
シンジへの返事のつもりなのだろう。
なにやらぶつぶつとつぶやいている。
繰り返すことになるがその部下がすでに一人毒牙にかかっていることを知らなかったのは幸いかもしれない。
もし知っていたらシンジの命は危機的状態に陥ることになっていたであろう。
(姉さん、相変わらずなんだ・・・。)
徹夜からきているのであろうくまを目のはしにとどめながらシンジは外の様子に目をやった。
まだ中央部に近いせいか戦闘の被害が大きかった。
そこここに大穴が空き、民家のほとんどが何かしらの形で被害を受けている。
そんな中必死に汗を流す住民たち。
一大ドキュメントが十本は作れそうな光景だった。
なぎ倒された木や、家の塀が昨日の爆発の衝撃を物語っている。
そして町中からあがる白い煙。
シンジにはその光景が教科書にセカンドインパクト直後の写真と全く同じに思われた。
(こんなに死んだのか・・・。)
教科書では写真の横に死体を燃やす煙、と説明書きがつけられていた。
窓の外に広がる景色にもその写真に匹敵するほどの煙が立ちこめている。
風がないせいか上がった煙はまっすぐに上に上りそのままかすれて消えて言っていた。
そんな中でも人は生きようと努力している。
(いったい何のために・・・ん?)
ふと一人の少年と目があったような気がした。
気のせいではなかった。
自分と同い年ぐらいの少年。
そんな少年が小学生ぐらいの女の子を抱きかかえたままこちらをじっと見つめていた。
(何だろう?気味が悪いな・・・。)
少年の緋のような瞳が印象的だった。
「見ない方がいいわ。誰のせいでもないもの。」
リツコがそういった瞬間、信号が赤から青に変わり、車が動き出した。
見る見るうちに少年の姿も遠ざかっていく。
それを見てシンジも外を見るのをやめた。
目線を車内に戻し、ため息をつく。
「あれだけの戦闘があったんだもの、死者だって出るわよ。」
「そう・・・ですね。」
努めて平静を装う。
だがシンジのそれは明らかに失敗していた。
疲れていることぐらい一目でわかってしまうだろう。
「あなたが気に病む必要はないわ。あの子にだってわかっていたはずですもの・・・こうなることぐらい。」
リツコのその言葉を皮切りに会話は完全にストップした。
砕け散ったビルの破片を器用にかわしながら車が町の中を疾走していく。
朝日がすでに高く昇ったころ、ようやく二人はアキナの養父の家へとたどり着いていた。
家は庶民階級のものとは比べものにならないほどに巨大だった。
自分が預かってもらっていた「先生」の家と比べても倍以上の広さがあるであろうその敷地にシンジは目をむいた。
リツコはといえばそんな光景に物怖じすることもなく門に取り付けられたインターホンを押す。
「こんにちは、連絡がきていたかと思いますが・・・特務機関ネルフ本部技術開発部技術局1課所属、赤城リツコです。こちらで引き取っていただいていた冬月アキナは本日付けで特務機関ネルフの保護下に戻ることになりました。よって彼女の生活備品その他を引き取らせていただきます。」
しばらくどたどたという音が聞こえていた。
だが、すぐにそれも途絶え、元の落ち着いた空気が取り戻される。
同時に邸宅のドアが開いた。
「IDカードを提示いただけますか?」
中から現れたのは人の良さそうな婦人と対照的に怠惰感すらただよう大学生ぐらいの青年だった。
「はっ・・・これでよろしいでしょうか?」
リツコが胸元のポケットから一枚のカードを取り出す。
婦人はしばらくカードを眺めていたがやがて、
「どうぞこちらへ。」
といって二人を中へ入れた。
青年と婦人の二人に挟まれるようにしてシンジたちは奥の部屋へと通されていく。
(なんだ?こいつ・・・)
途中、シンジは後ろからついてくる青年が異常な殺気を放っていることに気づいた。
姉の方も気づいているのだろう。
しきりに後ろを気にしていた。
「あなた、赤城さんと碇君が到着なさいました。」
「ああ、通してくれ。」
言葉が返ってくるのと同時にふすまが開けられる。
見事な和室がそこに広がっていた。
12畳はあろうかという部屋の中央に大きな机が一つだけ置かれている。
その対面に当たる位置に初老の男が一人座っていた。
「やあ、よくきてくれましたね。リツコさん、シンジ君。あなた達に会えるのを楽しみにしていましたよ。」
にこりともせずに二人に話しかける。
「こちらこそ、ご高名はかねがね伺っておりますわ、冬月コウシロウ先生。」
対するリツコの顔の筋肉も全く動かされることはなかった。
しばらくの間にらみ合いが続く。
「おまえたちは下がれ。後は受け渡し手続きをすれば終わりだ。」
根負けしたのかコウシロウがシンジたちの後ろで控えていた二人に退室するよう指示を出した。
「いやだ。」
そのときになって初めて青年が口を開いた。
「彼女は俺のものだ。こんなやつにやってたまるか。」
シンジを指さしながらつぶやく。
「やっと俺のものになりかけたんだ・・・それをこんなやつになんか・・・。」
(なにを言っているんだ?)
シンジは首を傾げた。
言っていることが頭の中でつながらなかったのだ。
「やめろ、これ以上まだ恥をさらすつもりか?」
コウシロウの厳かな声は一声で青年を黙らせた。
婦人の方はずっと黙ったままだったが、青年をけしかけるようにして部屋から出ていってしまう。
だが青年はその瞬間までじっとシンジだけを見続けていた。
その顔をよく見れば左の頬に大きなひっかき傷がある。
「いやはや、お見苦しいところをお見せしてしまいました。荷物はすでにまとめてあります。お茶も出せず申し訳ない。」
ひとまずはなし・・・というより挨拶は終わり、ということだろう。
コウシロウは立ち上がり、部屋の隅に置かれている荷物の方へと歩み寄っていく。
「教科書やら過去に買い与えたおもちゃやらもすべて入っています。車に乗せ切れないかもしれませんな・・・。」
「ここへは判を押してもらいにきただけです。荷物は後で保安部のものにでも運ばせましょう。」
山のような荷物に苦笑する。
それだけ大事にされていた、ということだろう、とシンジは解釈していた。
そのどれもがほこりをかぶっていたことには気づけなかった。
その後はシンジの出る幕はなかった。
リツコが書類を取り出し、それにコウシロウが判を押すのを見ているだけである。
(何をしにきたんだ・・・僕は?)
疑問だけが残る遠征だった。
--------------------------------------------------------------------------------
あとがき
だいぶ一気に仕事進めてる・・・。
現時点ではなんとも言えないんだけどやっぱりこの作品はアキナXシンジにはしづらいかな・・・・。
となるとアスカXシンジの線が濃厚かな・・・。
う〜ん、そろそろ自分で続きを書かなきゃいけないと思うと気が重いな〜。
蒼來の感想(?)は第6話にて<(_ _)>
一挙掲載なものですから・・・(⌒▽⌒;ゞ