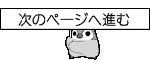世界は、主人公だけでは語れない。
世界は、ヒロインだけでは語れない。
世界とは、数多くの人の集合体。
その結末。
これは、数多の人々の物語。
そのほんの断片。
ガラクタの、ガラクタ。
姫君の寵愛byダークパラサイト
第十七話:「ガラクタのガラクタ」
カール・アンダルシア空軍曹長にとって、その日は朝から厄日だった。
まず、目覚し時計の電池がちょうど切れていて鳴らなかった。
それでも寝坊せずに何とかおきだしたというのに、強くついた寝癖のせいでなかなか髪がセットできなかった。
結局遅刻して上司に怒られ、同僚には笑われた。
彼女に電話しても繋がらず、その上朝から退屈な哨戒任務が入っていた。
せっかく禁煙を始めたのに同僚はそんな事お構い無しに煙草を勧めてくる。
どいつもこいつも、ろくでもないことばかりだ。
ここ数日、いいことがあったためしがない。
「・・・糞ッ!」
自分の愛機、64式VTOL”フリュンベルグ”のコクピットで、思いっきり毒づく。
だが、独り言のつもりだったその声も隣でコ・パイロットを務めるフィリップ・アール軍曹の耳には入ってしまったらしかった。
レーダーに集中しているため顔をあげるような事はさすがにしないが、彼の特徴とでも言うべき大きな耳がぴくぴくと動いた。
それと同時に加えていた煙草から口を離し、盛大に紫煙を吐き出してくる。
「どうしたんすか、曹長殿。朝から機嫌悪いっすね。」
「五月蝿え。コクピットの中は禁煙だと、何度言ったら分かるんだ。」
訳も無くむしゃくしゃする気持ちをフィリップの煙草にぶつける。
ちなみに禁煙の理由は計器に対して支障があるからだったり、換気能力に支障が出るからだったり、自分の精神に対しての悪影響だったり、まあそんな理由からだ。
実際整備部の連中に言わせればこの機体の排気口の色は相当凄い事になっているらしい。
「固いことは言いっこ無しっすよ。曹長殿だって、去年の今ごろはじゃんじゃん吸ってたらしいじゃないっすか。」
「あれは無煙煙草だ。」
「あれ嫌いなんすよ。吸ってる気になれないし、味も悪い。」
「贅沢言うな。仮にも任務中だぞ。」
「へいへい・・・っと、レーダーに反応確認。十三時の方向、高度六百四十。相対距離、120km。」
くしゃ、っと、丸めた煙草が携帯灰皿に押し付けられ、小さな煙を一筋残して消えた。
「またか・・・。」
カールも自分のレーダーを覗き、さらに憂鬱になってしまった。
そこにはパターンオレンジのサインと同時に、前方やや右の方向に浮かぶ小型飛行物体が捉えられている。
確認できる敵の数は三体。
どれもこれも身長は2mに満たない小型のもので、UNKNOUWNとされてこそいるものの何者であるかは一目瞭然といっていい。
「またっすね。全く、どうなってるんだか・・・。」
知るか。
そう口に出しそうになるのを、カールは何とか飲み込んだ。
このところ立て続けに現れる人型の飛行物体。
それが何であるかなど、理解できよう筈も無い。
分かるのはこれらが明確に敵であるというその一点だけだ。
「あ〜、司令部、例のUNKNOWNを確認した。数は3、これより交戦に入る。」
『了解、速やかな撃破を願います。』
「了解。」
通信は速やかに終わった。
後はもう、こちらの世界だ。
その速さに身を任せ、命の削りあいを演じればいい。
「ALTミサイルセット。機関砲の火気管制も外しておけよ。」
「サー、既にやってます。相対距離、残り50km。」
時速1000を出す事も可能とするVTOLにとって、100kmなどはあっという間の距離だった。
つまり、用意を怠れば、それだけで死ねる。
「標的、ロック。誘導波、出ます。」
「了解、戦闘軌道に入る。」
機体が加速し、正体不明の敵へ向かって突進していく。
悪魔と人の戦場。
その最前線へ向かって飛んでいく。
「・・・・・・。」
だが、ここ数日いいことがなかったと言うのなら、何故それほどに早急な行動を取ろうとするのか。
何をもって今日こそはいいことがある、などと考え得るのか。
四時の方角からその交戦を眺める黒い影があった事でさえ知りようもなかったというのに。
「・・・・・・愚かな。」
『世界の何処にでもいて何処にもいないもの』が、哄笑する。
七十二の兵を抱える七十二の兵長。
それを束ねた七十二の騎士団
そしてそれを統べる七十二の将軍。
擁するは七十二の王。
そして、ただ一人、すべてを知り、すべてを学んだ『王の中の王』
総勢億を超える兵を操る権利を持つダビデの王――ソロモン。
顕現せしむるは雑兵。
されどその力、侮る者は死に至る。
「えっと、相田に碇、冬月に菊花・・・か。他は揃ってるな?」
出席簿に欠席の印をつけながら、ゴロウは内心で溜め息を吐いていた。
――――ドイツに行ってきます――――
そんなふざけた言葉を残して彼らが休むようになってから、はや一週間。
この一週間の間、この四人は一度も学校に姿を見せていない。
否、アキナとシンジだけを見るのであれば、その休みはさらに一週間、つまり二週間前にまでさかのぼる。
NERV本社から長期休暇の認定が出ているため公欠扱いとなってはいるものの、元がそれほど頭の良くなかった二人と、最近転入してきたばかりの転入生が二人。
心配するなというほうが無理があった。
――――あいつ等・・・ドイツ語なんて出来ねえ癖に・・・
疎らになっている教室を見回し、もう一度、今度はそれとわかるようなため息をつく。
たかが四人休んだだけと侮ってはならない。
たかが四人、されど四人。
クラス全体の一割を超える人間が休んでいるのだから、必然的に席の空きが目立つようになる。
そして、それ以上にゴロウはあの転入生たちの事をよく思っていなかった。
いや、はっきりと嫌悪していたと言っても良い。
今もB組で授業を受けている(筈の)ヌエなどというふざけた名を持つ少年を含めた三人の転入生は、その登場のタイミングといい言行といい、不審な点が多すぎる。
そのような事は口にこそしないが、ゴロウは彼らこそが今回のいくつかの事件の首謀者なのではないかというようなことまで考えていた。(それは限りなく本質に近くもあったのだが。)
――――帰ってきたら補修の山、だな・・・。
今日の日直に日誌を渡しながら、そんな事を思う。
その程度では足りないが、教師である彼にはその程度しかできる事が無い。
教師という殻を捨て去れるほどには、転入生を嫌ってはいない。
――――どうしようもないよなあ。
西の窓へと向き合い、ドイツにいるはずの彼らのことを思う。
外は、見事に晴れ渡っていた。
「ここ・・・どこ?」
葛城・ミサトは、目を覚ますなり傍らにいた女性看護士にそう訊ねた。
白い天井は、彼女の知る自分の家の光景とは大きく食い違いがあったから。
自分が何故こんなところで寝ているのか、その記憶が全く無かったから。
なのに、看護士はすぐさまどこかへと走っていってしまい、返事はくれなかった。
後には、自分ひとりだけが残される。
ぱたぱた・・・という看護士のスリッパの音が、やけに虚しい。
「なにびょぅ。ここがどごがぐらい、おじえでぐれだって良いじゃない・・・って、あぐっ!」
仕方なく一人ごちながら、なぜか痛む体をゆっくりと起こそうとする。
が、身体は全く彼女の思うように動いてはくれなかった。
普段のようにベッドから足を下ろしただけなのに、全く足腰に力が入らない。
咄嗟にベッドに身体を投げ出すようにして無様な転倒こそ避けたものの、硬いベッドに打ち付けるような形になってしまった腹部が必要以上に痛み、息をする事もままならないような状態だった。
――――な、何が・・・。
焼け付くような痛みの中、意識を保つべく必死に頭を回す。
目に入るものの全てを情報として処理していく。
それで、ようやく自分が病室にいる事までは理解できた。
見慣れているわけではないが、全く知らないわけでもない。
NERV本社ビルの中にある、従業員用としてはありふれた個人用の病室だ。
これまで自分で使用した事は数えるほどしかないが、レイ絡みの件で何度か見る機会があった。
わからないのは、自分が何故このようなところにいるのか。
――――過労で倒れた・・・わけないか。
それだけ働いた記憶は無いし、だとすれば、今の自分の状況はあまりに異常だ。
よく見れば、全身が包帯のようなもので巻かれている。
――――確か、総司令の息子さんを迎えに行って・・・。
なぜか途切れそうに成っている記憶を、必死につなぎ合わせていく。
その途中、思い出したのは轟音と、熱。
閃光と、衝撃。
――――何・・・?
愛車であるアルピーノ・ルノーA310を駆って、町の中を必死に飛ばしていた。
遅れた事は悪いと思っていたし、的確な連絡を入れなかった事も、悪いとは思っていた。
そもそも、体裁だけを言うなら碇シンジのような子供に頼らなければならないという状況そのものに、嫌悪感に似たものを抱いてもいた。
だが、何故その中に。
――――こんな。
有り得ない。
――――こんな、景色が。
それは、焦土と化した山間の村。
もしかしたら、今はもうその存在自体を失ってしまったかもしれない小さな村。
それを見ていた自分は。
――――いったい、何処に・・・。
ゆっくりと、記憶は戻る。
山間の国道を走っている途中に爆発したN2。
その衝撃と爆風にあおられ、車は何度もひっくり返った。
そしてその末に自分は。
――――自分は。
偶々突き出る形になっていた鉄骨に身体を叩きつけられ、そこで、全身を焼かれた。
ガラスの破片が全身に刺さり、熱によって皮膚は糜爛した。
今もし生きているのであれば、それこそが奇跡とでも呼ばれるべき景色だった。
「あ・・・あぁ・・・。」
恐怖とも、後悔ともつかぬ声が、ミサトの口から洩れる。
必至になって自分の顔に、腹に、熱き焔に焼かれたはずの全ての場所に手をやり、擦り。
そして、その全てが包帯を掴む。
白い布の感触を、掴み取る。
否、その指先とて、包帯でがんじがらめに巻かれているのだ。
既に一部は治癒しているようだが、全身に及ぶ傷の殆どはまだ醜い爛れを残していた。
そして、治癒している所でさえ、幾重にも残る痛々しい傷跡が見える。
「い・・・や・・・。」
なきたくても、涙が出ない。
叫びたくとも、上手く口が動かせない。
全ての動作を、痛みが阻害する。
邪魔をする。
「やだ・・・。ごんなの・・・。」
咄嗟に浮かんだのは、一人の青年の顔だった。
昔の、恋人。
今も恋人であって欲しいと、願ってしまう人。
こんな姿を、彼に見られたくない。
もし見られたとしても、分かってもらえない。
「がじ・・・君・・・。」
言葉にすれば、思いが零れる。
覆水は、盆には帰らない。
――――こんなの、やだよ・・・。
まるで幼子のように怯え、震え、たった一人の人を、想う。
醜いという意味において、これ以上に醜い姿があるだろうか?
以前学校の授業の一環としてみた事のある、裸足のげんというアニメ映画のことを思い出した。
その中で、全身を焼かれて、爛れさせて、それでも生き続けている人がいた。
あの、吐き気を催しそうな醜い「ヒト」の姿。
今の自分は、それと同じなのだ。
この姿では、誰も自分の事がわからない。
彼だって、分かってくれない。
涙は涸れ、美しい声も失われた。
畜生と、変わらない。
いつしか、慟哭の呻きだけが病室を満たしていった。
「ちょっと兄ちゃん、つまみ食いしたらあかんって言よるやろ?」
鈴原ナオはキッチンから飛び出してくるなり、大皿に盛られたおかずへと伸びた兄の手を慌ててはたいた。
先ほどまで野菜炒めをかき混ぜていたアツアツのへらが正確に兄の手甲を捉え、小さなキャベツの切れ端を飛ばす。
「熱ッ!!何すんねん!ナオ!」
「何よ、兄ちゃんが悪いんやないか。それはヌエ兄ちゃんの分。」
「なッ!お前まだ怨んでるのかよ!」
突然の暴挙に抗議の叫び声をあげるジャージ姿の中学二年生と、それが当然のことであるといわんばかりに腰に手を当てる割烹着姿の小学二年生。
服装では一体いつの時代かと思わせるようなかなりの時代錯誤っぷりを見せているこの兄弟だが、普段は然程仲は悪くない。
兄思いの妹――妹思いの兄。
そのような言葉で表してもいいはずのこの二人はここ数日、食事時だけこのような臨戦状態に突入する。
「人がわざわざ作ってやった料理を全部残して帰ってくるような兄ちゃんに作ってやるような料理なんか無いわ!悔しかったらだれぞ自分の為に作ってくれる彼女さんでも見つけてきい。」
「う、うるさいわこのマセガキ!はん、どうせお前の作る弁当なんぞよりもマルサのパンのほうがよっぽど上手かったんじゃ!別に無くなった所でどうって事はないわい!」
「なら外で食ってきたらええやないの!何でわざわざ家で食うねんや!」
売り言葉に、買い言葉。
共にそんなつもりは無いのに、小さな齟齬が大きなぶれとなっている。
分かっているのに、戻せない。
戻せないのにわざわざ接触しようとするから、またぶれは大きくなる。
ある意味では、最悪の負の連鎖。
断ち切ることができるのは、これまた負の剣。
「・・・どうしたの?・・・何かあった?」
この家にあって、ただ一人標準語の少年。
黒衣の真性悪魔。
ただし、今は薄手の紺色のパジャマに身を包み、とてもそうとは見えないが。
「あ、おはよう!ヌエ兄ちゃん。」
「おう、おきたか、寝ぼすけ。」
ただの居候でしかないはずの少年の登場で、兄妹の争いはいったん水入りとなった。
驚くのは、先ほどまで「食いたあないんやったら食わんでええわ!今すぐ出て行け!」とでも言いたげにしていた妹の変わり身の早さ。
嬉しそうにヌエの胸に抱きついていく今の彼女はただの幼い少女でしかなく、先ほどまでの怒りの欠片も見せていない。
――――理不尽や・・・。
何かに打ちひしがれたように崩れ落ちる実の兄。
「女心と秋の空」などというが、何もこんなに幼いうちからその片鱗を見せつけなくともよいと思う。
ましてや相手は人間ですらないというのに、明らかに自分よりも優遇されているのだ。
その身に降りかかるショックは大きかった。
綺麗にフローリングの施された床に『の』の字を描くが、生憎とそのような古典的な表現方法に真面目に反応してくれるような心優しき住人はこの舘には誰一人として存在しなかった。
ナオは少年の手を取り、先ほど出来たばかりの朝食の前に座らせる。
現在の鈴原家内の序列が如実に現れた結果だった。
――――わし、なんか悪いことしたか・・・?
ほんのお情け程度に与えられた朝食が、余計哀れみを誘った。
第一印象は、闇。
それほどに暗い部屋だった。
一寸先は闇、というほどではないが、採光用の窓が一つも無い部屋に何の電気もつけていないのだから、可視光に至るほどの光など到底期待できない。
ブレーカーさえ落としているのか、部屋の明かりをつけようとスイッチを弄っても一向につく気配は無かった。
部屋の中では、自分の持つ懐中電灯の明かりだけがゆらゆら揺れている。
――――遅かった・・・か・・・。
そんな部屋を見回して、女――赤木リツコは溜め息をついた。
――――誰かに見られているような気がする――――
いつだったか、彼女はそう言っていた。
電化製品が怖いのだ、とも。
視線恐怖症。
それが彼女の病状だ。
――――せめて、後一週間早く気付いていたら・・・ね。
潔癖症だった以前の彼女では考えられないほどに汚れた部屋を見回し、悩む。
スナックの袋やインスタント食品の残骸が散乱した部屋は、一見した所足の踏み場すらないように思えた。
「マヤ、いるんでしょう?上がるわよ?」
暗がりに向かって声をかける。
だが、返事は無かった。
シーン、という静寂音だけが感じられる。
「マヤ、いるんでしょう?!」
もう一度大声をあげる。
それでも返答は無い。
何処かへ出かけているのかとも考えたが、だとすれば鍵が開けっ放しだった点やお気に入りだといっていた靴が残されている点が気にかかる。
――――まさか・・・・・・。
一瞬、頭の中を最悪のイメージが掠めた。
高々二週間程度でそれほどに病状が深刻なものになるとは思いたくなかったが一週間でその状態に至ってしまったという例も無かったわけではない。
「マヤ?!」
自ず、声は緊張を帯びたものとなる。
だがちょうどそのとき、揺れていた懐中電灯の光が暗がりの奥でうごめく何かを補らえた。
確かな事は分からないが、風や偶然で動いたものではない。
少なくとも、そこに生きている何かがいるのだ。
「い、いるならいるで返事ぐらいしなさいよ・・・。」
少しおっかなびっくり、魔窟と化した部屋の中へと足を踏み入れる。
流石に靴を脱ぐ気にはなれなかったのだがどうやら正解だったらしく、ヒールが踏んだ発泡スチロール製の容器がピシ、という音を立てた。
嫌悪感を押し殺しつつ、一歩、また一歩と蠢く何かへと近づいていく。
だが、後ほんの二歩という距離まで来た所でその歩みは強制的に止められた。
「・・・・・・?」
初め、それが何かわからなかった。
生き物であろう事は、分かる。
だが、人、としてみるのであれば何かがおかしい。
「マヤ・・・?」
それには、眼も、耳も、口も、何も無かった。
加えて言うならば手も、足も、人として認識するに足るだけのものは、何もなかった。
「何を、しているの?」
「それ」に向かって恐る恐る声をかける。
だが、何事かぶつぶつと呟く声のほかには何の返事も帰ってこない。
「マヤ?」
泣なきそうになりながら声をかけても、やはり返事はなかった。
幾重にも重なるバスタオルの山は時折震えて見せるものの、最早その中に潜んでいるマヤに自我と呼べるものは残されていなかった。
試しに一番外側に捲かれている一枚を剥ぎ取ろうとすると、女性のそれとは思えない強い力で引き戻される。
――――駄目・・・なのね・・・。
彼女の身に何が起こったのかは、分からない。
このところ調子が悪そうだと思っていたが、二週間前から音信不通となっていた。
このところずっとミサトにかかりっきりになっていたこともあり、殆ど構ってやる事ができていなかったのだが、それが拙かったらしい。
疑心暗鬼も、ここまでくれば病気の域に達している。
部下の中でも彼女の事は可愛がっていただけに、ショックだった。
「病院へ、行きましょう。」
ごわついたバスタオルの殻をなでてやりながら、そっと話し掛ける。
呟く声は、途切れなかった。
「本当に驚いたのよ。まさかあなたが一番に死ぬなんて、ね。」
殆ど全てを放出しきり、元よりもはるかに小さくなった神は笑う。
「あれはもう私の手を離れているのだけれど・・・人一人で歴史はこうも変わるものなのね・・・。」
感慨深げに地上を見下ろす巨大な碧眼。
その隣を、一匹の蝶が舞う。
「私とて、不死身ではない。人並みに心は痛むし、銃に撃たれれば死ぬ。」
「そうだったわね。けれど、面白かったでしょう?」
「悪くは無い。完全ではないが、娯楽として眺めるだけならばこれで十分だ。」
蝶の眼下には赤い地球。
死んでしまったはずの星に、ふわりふわりと幻想が飛び回る。
「『あれ』は私が作って『私』に任せたものだったのだけれど、少しは情も移ったんじゃないの?」
「まさか。やはり私は慎ましい女性のほうが好きだ。」
「例えば、私のような?」
神の手が、蝶の身体を包み込む。
「それを言ってしまえば台無しだよ、ユイ。・・・しかし、ここに残っている君こそがユイであるとするならば、私と出会ったあの女性は誰だったのだ?」
「さあ、ね。私だけれど、私ではないもの。最後に残っていたものを適当に押し込んだから。私も覚えていないわ。」
蝶は舞い、神は語る。
これは幻想か、はたまたこれこそが真実なのか。
夢と現は何処で交わり、何処で剥がされたのか。
知る者がただ一人神のみであるとするならば、登場人物たちにとってはこれ以上ない不幸だろう。
如何なる道をたどろうと彼らに未来は無く、全てが死へ繋がる道でしかないのだから。
あとがき
・・・・・・・・・・とりあえず、トウジのエピソードは気に入らないな〜、と。
書き直さなきゃならないほどじゃないけど他に比べると物語として重要なエピソードじゃないし文章も色々と変だし、何よりまず浮いてるし・・・。
う〜ん。
いっそ冬月辺りのエピソードと差し替えようかな・・・。
入れたいエピソードはまだ結構あるし・・・。
・・・・・・とかなんとか。
今考えてるのはそんな事なんですが、蒼來様はどう思われますか?
蒼來の感想(?)
えーと・・・ネルフぼろぼろなんですが(−−;
つうか一番ショックだったのは、マヤちゃん壊れちゃった!!だな。(−−;
映画版での一つになる時に見たのがリツコつうのも引いたが(−−;
結構好きなキャラなんですよ?>伊吹マヤ
昔、試案でオリキャラ軍人主人公ネルフ派遣で、オペレーターズ(日向・青葉は除く女性陣)が取り合いなんて試案書いたし。(−−;
学校関係者はそれぞれの不在の日常とのギャップありすぎです。
しかしゲンドウ・・・お前さん願いがかなってるじゃん>TV版の願い。