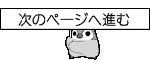きのうの焔はどこへ行った、
きのうの町はどこへ消えた、
夜あけと一しょにあらわれた
このまったく違った風景!
川路 柳虹 『燃える本』
姫君の寵愛byダークパラサイト
第十六話:「女帝の国」
「ただいま、シンジ!!」
広い病室の中に、少女の明るい声が響く。
勿論病室は彼女の家ではないのだが、ここ数日、彼女はずっと同じ挨拶を続けてきた。
「お帰り、アスカ。・・・相変わらず元気だね。」
病室は広いが、ベッドは一つしか設置されていない。
シンジはそのベッドの上で本を読んでいたのだが、少女の声で軽く面を上げ、病室の入り口を見る。
どれほどのスピードで駈けてきたものか、アスカの特徴的な赤毛は風で脹らみ、普段とは違った形で波打っていた。
それを見て笑うと、アスカは少し膨れっ面になった。
「そう?普通だと思うんだけど・・・。」
「うん、アスカが元気が無い所は、僕も想像しにくい。」
「なら良いじゃない。」
片手に下げた書類鞄と羽織っていたコートをベッドの横の机に放り出し、アスカはシンジの伸ばした足の袂に座る。
ここ数日、アスカのホームポジションはそこと、相場が決まっていた。
午前中の会議が終わったばかりだったので、今日はまだかなりの時間がある。
「姉さんは・・・やっぱりまだ来てないんだ。」
「うん、アキナちゃんはまだだね。・・・でも、アスカはこっちにいて大丈夫なの? EVA――アスカも乗るんじゃなかったっけ?」
「え?・・・うん、確かに・・・そうなんだけど・・・。」
シンジの素直な問いに、アスカの表情が僅かに曇る。
「二号機の調整、こっちのスタッフがいい加減にやってたみたいで、凄く大変な事になってたから・・・。」
正直に言えば、アスカとて一度は手伝おうとしたのだ。
自分の搭乗する機体であるということもあったし、本人も栄養失調でやつれていたアキナにしわ寄せが行くというのは、納得がいかない面もあった。
ただ、マギ・システム(S型)によって示された演算の閾値を確認した瞬間、自分の手伝いなど邪魔以外の何者でもない事を悟ってしまったのだ。
仮にも工科系の大学を卒業しているというのに、全くといって良いほどに歯が立たなかった。
結果として、本来の予定なら今日が一時接触予定日だったのだのに、それが必要以上にずれ込んでいるのだが、やむをえない事だったと思っている。
何しろプログラムの半分が膨大な数字によって埋められていたのだから、理解どころの騒ぎではない。
あれはCコード云々ではなく、それ以上の領域、ほとんど人知の域を超えたレベルでの話だ。
自らの母でさえ気付けなかったような間違いを、彼女はものの数分で見つけ出してしまった。
そのことの凄さは、シンジには伝わらない。
「あれじゃ、私では手伝えなくて・・・。」
「ふ〜ん、そうなんだ。」
どこか悔しそうなアスカとは違い、シンジのほうは飄々としていた。
少なからぬプライドを持ち合わせているアスカと何の教育も受けていないシンジとでは、感じ方があまりに違う。
彼としては、アキナがそれほどのプログラムを動かしていると知ったところで、そのような事もあるだろう、と感じる程度の事でしかない。
あの鬼に乗れるという事自体がプライドを作り上げるものであるだなんて、知らない。
理解――出来ない。
「じゃあ、今日はアキナちゃんは来ないかな?」
「さあ? 昨日は絶対に行く、みたいなこといってたから、何とかして時間を作ってきそうでもあるけど・・・。」
何しろ、到着の挨拶もそこそこに母――キョウコと共にラボに篭もってしまったのだ。
来欧の理由が「シンジへの面会」だったのだから、一応の目的は果たしているのだが、それでもそれほど長い時間彼女が待ちつづけられるとも思いにくい。
「一週間も経ったわけだし、シンジが近くにいるとは言え、夜帰ってきて顔を見るだけじゃあそろそろ限界でしょ。案外もうその辺りにまで来てるかも。」
実感を込めて、過去のアキナと重ね合わせて、アスカは言葉を紡ぐ。
アスカと別れてからシンジの身に何が起こり、アキナの身に何が起こったのか、彼女は知らなかった。
「あ、でもその場合は後ろに大量の追っ手がついてるかしら?」
「う・・・それはちょっと。・・・出来ればじっくりと会話できる環境のほうがいい・・・かな?」
言いながら、二人ともついつい窓の外や入り口のほうに目が行ってしまう。
そこにいない事が分かっているとは言え、ほんの一瞬彼女なら・・・と考えさせてしまう所がアキナのアキナたる所以なのだろう。
幸い、通りにも廊下にも、それらしき気配は無かった。
「ハハ・・・さすがに、ね。」
「そ、そうよね、さすがに・・・ね。」
二人揃って顔を見合わせ、一頻り笑った。
その上で、互いの目線を互いに向ける。
シンジが目を覚ましてから、5日。
話しておくべき事も、話したいことも、それこそ山ほどある――筈だった。
――――けど、聞いちゃ駄目なんだろうな――――
それは彼女がシンジと話す上で、気付いた事だった。
彼は7年前に別れてからアキナと再会するまでに起こったことを、アキナのことも含めて絶対に話そうとはしない。
まるでその時間が忌々しいものでしかなかったかのように――事実そうだったのだろうが――拒絶している。
――――私は、何をしていたんだろう?――――
こんなことになるぐらいなら。
加持や、この地においての出来事など、互いに秘密にしなければならないようなことが出来てしまうぐらいなら。
――――私はドイツに来た事を後悔する事しか出来ない――――
「・・・・・・で、あの二人の様子は?」
結局、暫く待っても口を開かないアスカに代わって、シンジが口を開いた。
それでようやく、アスカも現実へと帰ってくる。
「ああ、それなら完璧よ。勝手についてきただけなんだから本当ならどうでもいいんだけど、・・・本当に、どうでも良いんだけど・・・ずっと付きっきりでいるわけにもいかないから、一応こっちにいる日本人の知り合いに紹介しておいたわ。母さんの知り合いで、私の・・・じゃ無かった。・・・でも、彼なら別段問題はないと思う。」
「そう。」
「ええ、それにしてもあの二人の知識レベルときたら・・・。来週からあんなのと一緒に勉強しなきゃならないとなるとちょっとげんなりするわね。」
勿論シンジは別だけど、などといい、殊更明るく振舞いながら、アスカは自らの鞄から分厚い書類を取り出してきた。
その表紙に書かれた文字はこちらでは公用語であるドイツ語だが、シンジには全く理解できないのだろう。
首を傾げる姿がどこか可愛らしい。
「ちょっとごめんね。明日は私もNERVに行かなきゃならないから・・・。」
「ん、分かった。大変だね。」
断りを入れ、書類に目を落とす。
「・・・・あ、けどさ、アスカ、そういう考えは、その・・・よくないと思うよ?」
だが、一枚目を読み終わるころになってシンジが再度話し掛けてきた。
とは言え、速読を行っているため然程時間はたっていない。
「あら、シンジにそんな事を言われるとは思わなかったわ。」
意外意外、などと言いながら一枚目をめくる。
その応えに、シンジは僅かに顔をしかめて見せた。
思い当たる事が、多すぎる。
「うっ・・・そりゃ、自分が人付き合いが上手いというつもりは無いけど・・・。」
「分かってるわよ。利用できるかもしれないものを自ら放棄するのは衆愚の極み、そう言いたいんでしょ?シンジは。」
次のページは分かりきった注意事項ばかりだった。
また、一枚めくられる。
「それにしてもシンジ、本っ当に変わってないのね。昔っからのその性格、一体誰からの影響やら・・・。」
「な、何だよ、それ・・・。」
「人付き合いなんてもんじゃ無い。あんたの性格は根っこの所が捻じ曲がってる。そう言いたいのよ。・・・私も姉さんもいなくなってるって分かってから、一番心配だったのはその性格なんだからね・・・。」
「あ・・・うん、ごめん。」
「プラグマティズム(道具主義)だっけ?昔は知らなかったけど、今ならよく分かるわ。あんたの異常性。」
異常かなあ・・・というシンジの呟きは、当然のこととして無視された。
「人間は役に立つかどうかだけで判断されるべきじゃないのよ。そりゃその見方で言えば私や姉さんは役に立つ人間の筆頭なのでしょうけど、だからと言って何の役にも立たない、つまらない惰性で付き合っているだけみたいな友人関係だって、あってしかるべきものだと思わない?」
まあ私が言えたことじゃないかも知れないけど・・・などと言いながら、また一枚めくられる。
当然のことのように自分を有用の側に置くことが出来るのは、まあ、彼女の強さでもあるのだろう。
「あれらと友達付きあいをしたいかといわれたら、そりゃ微妙かもしれないけど、少なくとも姉さんの友達であるという一念だけでも、私たちにとっては十分なんじゃない?」
「うん、まあ、そうだろうね。」
「何を思って姉さんがあの二人を選んだのかは分からないけど・・・もしかしたら理由なんて無かったのかもしれないけど・・・だから、あの二人には可能な限り協力してあげるつもりよ。」
「僕も、そのつもりだよ。」
「そう?」
また一枚めくり、少しアスカの顔が険しくなった。
どうやら何らかの壁にぶつかったらしい。
口の中でぶつぶつと呟きながら、紙を数枚飛ばしてめくり、また戻す。
そんな動作が数度繰り返された。
その間、シンジはじっと待つ。
「けど、人はあれだけじゃあないんでしょう?」
結局理解できなかったらしく、アスカはそのページに折り目をつけて次のページに入った。
一瞬横目でシンジを見るが、すぐにまた資料の束へと視線が戻される。
それを見計らって、シンジもまた口を開く。
「そうだね・・・人はたくさんいるよ。」
「あんたの言うような意味じゃなくて・・・そうね、友達と呼ばなければならない人間は、たくさんいるんでしょう?」
「・・・・・・・うん。」
「友達百人と言うつもりは無いけど・・・シンジは姉さんにとって有用であるか、もしくは姉さんの選んだ友人としか付き合わないつもり?」
「う〜ん、どうだろう?」
首を傾げるシンジに、今度はアスカが顔をしかめる番だった。
この少年は、狂っている。
「・・・それがどれだけ無茶苦茶なことか、理解できてるわけ?」
「うん・・・。」
答えには迷いがある。
それはつまり、本質的には何もわかっていないという事。
「あ、でも、アキナちゃんは何人か友達作ってるみたいだよ?」
「あの二人を含めて・・・ね。けど、私が心配してるのはあんたの・・・。」
事だ。
そう続くはずだった言葉は、唐突に途切れた。
顔を上げたアスカの口が、そのまま笑みに変わる。
病室の入り口には一週間前のやつれ方が嘘のように回復している黒髪の少女が立っていた。
そして、その後ろには呆れ顔で立つ自らの母の姿も見える。
「ああ、お帰り、姉さん。母さん。」
軽く手を上げて、その二人を迎え入れる。
「シンジ君はだいぶ回復したみたいね。・・・娘が迷惑をかけなかったかしら?」
「ええ、大丈夫ですよ、キョウコさん。それと・・・お帰り、アキナちゃん。」
「うん、ただいま。シンジ君。」
遠いドイツの地にあって、幾年もの時を経て、それでも彼等の挨拶は何ら変わっていなかった。
彼に会うというそれだけのことのためにこの地までやってきたはずのアキナでさえ、アスカに応え軽く手を上げただけだった。
「どうしてもこっちへ来るんだって聞かないのよ。・・・別にシンジ君が逃げてしまうわけでもないのにねぇ・・・。」
「私は父さんの手伝いに来たんじゃないもの。」
まだ全部終わっているわけじゃないのよ・・・などと言いながら、それでも満足そうにキョウコが笑う。
そのことに少しむくれるアキナだったが、それでもまあ、一段落はつけてきたのだろう。
キョウコにアキナを咎める様子は見受けられなかった。
この分なら、午後は久しぶりに皆で過ごせるだろう。
「ふ〜ん、相変わらずシンジラブなのね、姉さん。」
「アスカちゃんまでそんなこと言う〜。」
七年前と同じように、病室に笑い声が満ちる。
七年前から全てが変わり。
七年前に全てを壊されてしまったのに。
その笑みだけは、違えても、壊されても、いなかった。
キシ、キシ、と窓枠が軋む音だけが部屋の中を包み込んでいた。
日本が常夏に近い気候となった分ドイツの冬は長く、まだ9月だというのに吐く息は白いし、そこここに見える水溜りは全て氷が張っている。
窓から見える往来には木枯らしが吹き、道行く人はみなコートの襟元を抑え、少しでも暖を取ろうと必死になっていた。
ケンスケとヤエの泊まる民間の小さなホテルの一室でも暖炉の火が赤々と燃え、部屋の温度が一定以下に下がり過ぎないように調節されている。
「・・・・・・暇。」
そんな中、ポつり、とヤエが口を開いた。
寝転がり天井を向いたままなので顔は見えないのだが、見たくも無い顔をしているであろう事は容易に想像がつく。
彼女からおおよそ3〜4mほど離れた部屋の隅でカメラをいじっていたケンスケは顔を上げるが、殊更立ち上がったりすることはしなかった。
「まあ、そりゃ、な。」
返答も、短く止める。
ドイツに来てからおおよそ一週間にもなるのにアスカと名乗った赤毛の少女か、その恋人を名乗る男――加持 リョウジがいないと外出さえままならないというのだから、暇な事は当然の帰結でしかないのだ。
「何で私はこんな所でいるんだと思う?」
「・・・・・・さあ?」
ここに到着してから既に何度繰り返されたかもわからないような質問を、ケンスケは身じろぎ一つせず一言で一蹴する。
アスカが用意した部屋は人間が二人いるだけということを考えれば広さも十分にあるし、古典的な煉瓦造りの部屋ながら必要なものは全て揃っていた。
にもかかわらず二人の行動半径が極度に狭く、せいぜいが自分のベッドの周辺域を抜け出ていないのは、ひとえにヤエが剥き身のままに抱えた木刀がそこに甘美な空気が入り込むような余地が生じる事を執拗に拒んでいるからに他ならない。
夜眠る前は勿論の事、まるでそれこそが一番の友達だとでも言わんばかりに昼でもずっと抱えたままの木刀がぎすぎすした空気を盛大なファンファーレと共に送り出している状況の上では必然的に口数を減らさざるを得ないのだ。
・・・口が裂けてもそんな事は言わないが。
「アキナがドイツ語話せるなんて聞いてないし、話せるなら話せるでつれってってくれても良い気がするし・・・。」
「碇の所に行ってるんだから、仕方ないだろ。俺たちが行っても邪魔になるだけだよ。」
「そんな事分かってるわよ。」
バすっという音を立て、ヤエは分厚い毛布の上でうつぶせになるように転がった。
「けど、アキナ、私には何も教えてくれてなかった。」
「またそのことかよ・・・。」
「だって!」
沈めていた毛布の山の中から顔を出す。
顔の半分以上が隠れて見えないが、泣いているように見えて、少し戸惑った。
「相田は知ってたんでしょ? アキナがNERVに所属してることも、それなりに敬意を払われるべき存在である事も。」
「・・・まあ、ね。知らなかったって言ったら・・・嘘になると思う。」
何なら、その上の事だって知っている。
彼女が現時点におけるNERVの第三位(現実には総司令の死亡の為第二位)に当たる事も、EVAのパイロットである事も、彼女の内に巣食う神と悪魔の事も。
ともすれば、彼女自身以上に彼女の事を理解している。
「けど、だからどうって訳じゃないだろう。彼女が隠したがっていたんなら、吹聴して回るような事じゃない。」
例え彼女が人であるかどうかすら怪しい存在であったとしても、向けられた信頼を無碍には出来なかったのだ。
そして、心のどこかでヤエを出し抜いた事に対しての優越感も、あった。
「うん・・・。」
納得はしているようだが、ヤエの歯切れは悪い。
自分が間違っているという自覚と、それでも知りたかったというどこか裏切られてしまったかのような感慨の間で板ばさみになっているのが手にとるように分かった。
「俺だってつい最近になって知ったことだし・・・。」
「知ってるわよ、そんな事。・・・けど、やっぱり一番に知りたかった。」
声尾の調子は低く、いつもの120%元気の塊のようなヤエではない。
そのことが気になって少し近づく素振りを見せるが、ヤエはどこか危うさや脆さを感じさせる笑みを一瞬浮かべて見せた後、毛布を口に押し当てただけだった。
抱えた木刀の切っ先は、上がらない。
「・・・どうかした?」
「なんでもない。」
そうは言うものの、よくよく注意してみれば心なしか顔が赤い。
体調がおかしいのは明らかだった。
「ちょっと近寄るけど、攻撃してくるなよ。」
「よるな、変態。」
「・・・・・・。」
何故心配して貶されなければならないのか。
どこか理不尽なものを感じるものの放っておくわけにもいかず、木刀の切っ先に怯えながら神域同然であったベッドに近づいていく。
「ッ!・・・寄るなって・・・」
残り1mほどの距離まで詰めたところで、ヤエが気だるそうに体を起こした。
それまでは転がっているだけだった木刀の切っ先が上がり、ぴたりとケンスケの心中線を捉える。
これ以上ないというぐらい明確な拒絶の意思が、そこここに見え隠れする。
「それ以上近寄ったら、本気で打ち込むからね。」
「・・・けど・・・。」
「心配なら無用よ。ただの風邪。」
軽く頭を振り、自らを恥じるかのように顔を背ける。
ただ、余計な力が抜けているためかその姿も何処か艶っぽさがあった。
「不覚だったわ。授業で習ったはずなのに、ヨーロッパが亜寒帯だって事、すっかり忘れちゃってた・・・。」
「こっちに来る前は半袖だったもんな・・・。」
「アキナはちゃっかり長袖を用意してたけどね。そんな事まで隠しておくんだもん・・・。」
空港についた直後の事を思い出す。
タラップへ向けて伸ばした足に容赦なく吹き込んだ刺すように冷たい空気と、いつのまにか毛皮のコートを着込んでいたアキナ。
「あれは・・・酷かったな。」
「まったくよ・・・とっとと。」
膨れっ面のまま、ヤエが一度木刀を下ろす。
「・・・・・どうした?」
「ちょっと・・・さすがにずっと持ち上げてるってのは疲れるわ。」
本当に体調が悪いのか、木刀を手元に置いたまま、包まっていた毛布を抱き寄せる。
「おいおい・・・。」
「それに、相田なら何かあってからでも十分に間に合うでしょ。」
「なんだよ、それ。・・・なんなら薬でも買ってこようか?」
「あんたが?どうやって?」
猫背になったまま、それでもヤエは鼻先でせせら笑う。
この地では彼らの言葉が通じる人間など殆ど存在しない事を身に沁みて知っているだけに、ケンスケの言葉が現実味を持たないものとしてしか聞こえなかったのだろう。
「どうやって、って言われても困るけど・・・。」
だが、少なくともケンスケは本気だった。
未だにヤエには内緒にしているのだが、彼はアキナの携帯の番号を既に手に入れている。
アキナの長期休暇の間は気恥ずかしさも手伝ってかけることはしなかったが、こんな時ならばかけても悪い事は無いと思われた。
「詳しくはいえないけど・・・何とかなると思う。」
「それじゃやってみれば?」
そう言われても、彼の携帯電話は国際仕様ではない。
どこかで電話を探さなければ、どうしようもない。
「えっと、じゃあ悪い、ちょっと出てくる。」
「二度と帰ってこなくてもいいからね。」
「いちいちむかつく奴だな・・・。」
ドアを開け、公衆電話を探す。
幸いにも、電話はすぐに見つかった。
ホテル備え付けらしき電話機が、廊下の突き当たりに見える。
「助かった・・・。」
ポケットの中に詰め込んでいた財布の中から加持に両替してもらった小銭を探しながら、足早に歩を進めていく。
そのせいで、少し前方不注意に陥っていた。
廊下の途中にあった階段に気付くことなく歩を進め、それゆえにそこから出てきた人物にも当然気付くことなく、正面から衝突してしまう。
「あ、ごめんな・・・さ・・・い・・・。」
言葉は、途中で飛んでしまった。
外国人だから言葉が通じないだろう、などと殊勝な事を考えたわけではない。
ぶつかった相手の大きさに圧倒されていた。
(で・・・でけぇ・・・。)
見上げて、口をぱくつかせる。
身長は、2mにも及ぶだろうか?
相撲取りもかくやというほどの脂肪質の身体は白人の体格に合わせてそれなりに大きく設計されているはずの通路の半分を一人で塞ぎ、ケンスケの視界の半分を奪ってしまっている。
さらにその周囲を取り巻きらしき黒服の男が取り囲んでいるため、街角の小さなホテルの一角は突如としてチャイニーズマフィアの宴会場のごとき空間と化していた。
「気をつけろ、坊主。」
「え?あ、はい。」
男の横に連れ添っていた黒服の男が凄みを利かせるが、ぶつかられた当の男はちらりとケンスケを見ただけで、興味を示したようには見えなかった。
「あ、その・・・。」
言葉に、詰まる。
加持に簡単なドイツ語の挨拶ぐらいならば教わったはずなのに、いざとなると全く出てこなかった。
謝ろうとしても続けるべき言葉が見つからず、立ち往生してしまう。
「えっと・・・その・・・。」
「気にすることはない。突然出てきたこちらも悪かった。」
「は、はい、ごめんなさい。」
仕方なく日本語で返答し、男の集団が行ってしまうのをじっと待つ。
彼らが使っていたのが日本語だったと気付いたのは、ちょうど最後の黒服が角を曲がり、見えなくなった瞬間だった。
あとがき
結局殆ど訂正はされませんでした。
語尾を少し治して、どちらの主観なのかをはっきりさせた程度です。
なので、代わりにこれまでのあらすじ表のようなものとキャラクター表を作ってみました。
友人曰く読んでいて誰が何だったのか分からなくなる・・・との事でしたので・・・。
ではでは、今回はこのぐらいで・・・再見!
蒼來の感想(?)
まずは・・・・ヤエさん行動力ありすぎ!!w
まあ、それに捲き込まれてドイツまで来てるケンスケもすごいがw
ふむ、シンジは対人恐怖症のケがあるのかな?
アキナは何しにきたのかわからん状態に・・・・シンジに会いにきたのでは?
で、一番謎なのが陸奥ですね。
いいもんなのか、わるもんなのか・・・?
では17話の感想で。<(_ _)>