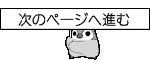昔からずっと彼女がいたから、絶対に一番になれない事ぐらいあたりまえの事のように知っていた。
けれど、どうしても諦められない事と、どうしても負けられない事が、三つだけあった。
姫君の寵愛byダークパラサイト
第十五話:「冷たい夜」
夕焼けの砂浜に、疾駆する影が見える。
少し近寄れば、それが一人の少女であることは、すぐにわかる。
色素が抜け赤みがかった髪を振り乱しながら、少女――惣流 アスカ ラングレーは砂浜を一心不乱に駆け抜けていた。
「はあ・・・はあ・・・。」
額には玉の汗が浮かび、目には西風で舞い上げられた砂が入り込んでくる。
疲れてへとへとになっているのに、ほんの少し足を緩めれば強靭な身体が彼女を支えてくれるのに、それでもアスカは全力疾走をやめようとはしなかった。
辺りを見回すことすらせず、砂を巻き上げながら一心不乱に走っていく。
その先の岩陰に、黒山の・・・と言うには若干数の少ない人だかりが、見える。
「お母さん!!」
アスカはその人山に飛び込むなり、そう叫んだ。
その声でようやく娘の到着を知ったのか、白衣姿の女性が一瞬顔を持ち上げる。
「シンジは?・・・大丈夫なの?」
半ば押しのけるようにして、人の中心、母のいる所まで足早に近寄っていく。
だが、その母の足元におそらく学校のものであろうと思われる制服を着込んだ少年の姿が見えた瞬間、その顔から見る間に血の気が引いていった。
「シン・・・ジ・・・?」
現実を信じられず、直視する事が出来ない。
それでも現実を振り払おうとかけた声にも、足元に転がる少年は反応を示さなかった。
普段は活動的な少女の顔が、恐怖と失望で、露骨に歪んでいく。
「だめ、ね。極度の栄養失調で意識が混濁してる。・・・この様子だと、何も食べなくなってから一週間ぐらいが経過しているんじゃないかしら・・・。」
勿論水ぐらいは貰ってたみたいだけど、と、母親は何の足しにもならぬ事を平然と呟き、少年のお腹に当てていた聴診器を外した。
「あの人が殺害されてからちょうど一週間、その間ずっと何も食べてないとしたら、発見はギリギリのタイミングね。・・・絶対に手を触れちゃ駄目よ!救急車を手配したから、それまでは安静にしておかないと・・・。」
びくっと震え、アスカは伸ばしかけていた手を胸元に戻した。
その目に、見る見るうちに涙が浮かんでいく。
「シンジは?・・・助かる?」
「・・・微妙ね。まだ何とも言えない。」
母の声は、こんなときでさえ冷静だった。
そのことが煩わしく思え、涙を浮かべたまま、まるで親の敵でも見るように実の親を凝視する。
ぎりっという歯軋りの音と共に、アスカの手が強く握られるその様子に、母――惣流 キョウコ ツェペリンは、ほんの一瞬の苦笑をもらした。
――――本当に、何も変わっていない。
「勿論出来る限りのことはするわ。日本のゼロにとってもあなたにとっても、この子は重要な意味を持っているのだから。」
先ほど見つけた両手の縄の後を隠すようにしながら、キョウコは娘に語りかける。
自分の娘がどれほどに少年の事を思っていたか――想っていたかを知っているだけに、それは見せてはならないものだった。
「ほん・・・とに?」
「ええ。」
自分でも確証の無いままに頷き、娘を安心させる。
嘘を吐くわけにはいかないが、ここで娘に不安を感じさせるわけにはいかなかった。
一週間後には、セカンドチルドレンとしての彼女の実力が試される時が来るのだ。
――――それまでに回復・・・いえ、その前に死なせない事が先ね。
暗澹とした思いのまま、遠くに響く救急車のサイレンの音に耳を傾ける。
――――死んじゃ駄目よ、シンジ君。
シンジの顔を見つめるキョウコの顔に、夕闇が、ゆっくりと迫っていた。
ドイツの空に、日が――落ちる。
黒い影が、何処までも伸びていた。
広い家の中に、一人ぼっち。
どうしても思い出してしまう過去が、あった。
意図的に思い出さなかった、家を出た途端に忘れていたと思っていた、忌まわしい記憶。
「シンジ・・・君。」
だが、名を呼んでも、帰る声が無い今、最悪のタイミングで、記憶は再来する。
「何で・・・。」
理由は、わかっていた。
ここ数日、食事が全く喉をとおらないのだ。
それゆえに、餓えている。
体力が、枯渇している。
まるで、七年前の自分のように。
七年前の自分よりも酷く。
「何で・・・。」
うわ言のように、口走る。
食卓の上に乗る冷めた夕食は、美味しくなかった。
記憶は、無限に、夢幻に、再生を続ける。
「いやああぁぁぁぁ!!!!」
泣き喚く声が、冬月家の食卓に響く。
七歳であったころのアキナが、自分の席から逃れようと、もがく。
「こら、やめろ!!」
制止しようとするコウシロウの声は、届いていなかった。
アキナの手が、熱いご飯の入ったお碗を放り投げ、あたり一帯に白い米粒が飛び散る。
「私は!!」
投げ捨てられたお皿が数枚、周囲の壁にぶつかって、砕け散る。
「シンジ君の作ったご飯意外食べない!! シンジ君の作ったものじゃないと!!」
両目を精一杯に見開き、幼女は叫んだ。
愛するものの名を、生涯の伴侶の名を。
だがその様を、冬月家の人間はまるで奇異なる獣を眺めでもするかのように柱の外から眺めるばかりだった。
コウシロウを除く人間は決して近寄ろうとせず、遠巻きに、狂える幼女を見つめる。
「落ち着きたまえ、君は愚か者ではないはずだ。」
その中でただ一人、コウシロウだけは幼女を羽交い絞めにして立っていた。
幼女の力、その齢を考えれば驚くほどに強いが、それでも大の大人が止められぬほどでも、無い。
そして、男は叫ぶ。
「ここは君の家だろう!!シンジなどと言う少年は!金輪際!何処にも存在しない!」
その言葉は、咄嗟に出た体のいい嘘でしかなかった。
だが、男は狡猾だった。
「君には、親など存在しない。家族も、友達も、いない。」
暗い部屋の中で、男は鎖に繋がれた幼女に何度も同じ事を吹き込みつづけた。
何度も。
何度も。
何度も。
勿論初めは少女とてその言葉をシンジはしなかっただろう。
それでも、繰り返されるうち、衰弱していく幼女の中で、言葉は意味を持ち始める。
心の中で小さな芽をつけ、ゆっくりと少女の心を壊し始める。
それを数える事すら無意味と思えるほどに何度も記憶を塗り重ね、魂の記憶さえをも塗りつぶしていく。
元の色が赤であろうと青であろうと、かさぶたのようにこびり付いた記憶がその色の発露を妨害するように、全ての記憶を作り変えた。
「君は、一人だった。だから我々が引き取ったのだ。」
いつしか、男の言葉は空を見つめる幼女の心を掌握し、少女は虚ろな瞳でその言葉に頷いてみせる。
記憶を作り変えられた事に気付きながら、何を作り変えられたのかに気付かず、生涯の伴侶であるべきものの名を、一時少女は忘れた。
そして、そうなると今度は肉体が。
人としての極みを詰め込まれた肉体が、幼女が衰弱したままである事を、許さなかった。
監獄のような部屋の中であるというのに幼女は少女となり、匂いたつような美人へと、幼いつぼみを膨らませていく。
その内に秘めた言葉の鍵は、碇シンジと言う少年の名。
絶対に触れてはならない、かさぶたをはがす鍵。
だが、自覚があればそのような言葉、洩れるようなものではない、
誰もその言葉に触れないまま、少女は学校に通い、下卑た男の息子の慰み者としての人形の如き生活を、それでも恙無く送る。
あの日、その息子が、小さなミスを犯してしまうまでは、ずっとそうだった。
「何で・・・。」
記憶は全て、失っていたものだった。
あまりに悲惨であったが故に自ら記憶を改ざんしてしまっていた、間違った記憶。
それらがすべて、まるで走馬灯のように蘇ってくる。
「何で、今・・・。」
あの日。
写真をたくさんとってもらい、上機嫌で彼を送り届けたあの日。
彼の父が、死んだと聞いた。
殺されたと、聞いた。
彼がいなくなったと、聞いた。
何処に行ったのかてんで見当もつかないのだと、聞かされた。
「何で・・・。」
もう昔のように、取り乱して暴れるような事はしない。
かといって、平静でいられるわけでも、ない。
ただ、自分の心がほんの少し大人になって、狂う事を自分に許さないと言うだけの事。
その証拠に、あの日から学校に行っていない。
たくさん撮ってもらった写真も、まだ貰っていない。
「なんで・・・。」
何度も何度も、同じ言葉を繰り返しつづける。
頬が扱けてきているのは、自分でもわかっていた。
もう、叫ぶための気力も、残されてはいない。
毎日機械的にトレインに乗ってNERV本部まで出向き、少々の治療を受け、何の成果も無いままに家に帰り着く。
そんな毎日が、健康的であろう筈も無かった。
「なんで・・・。」
時として、思う。
思い出してはならなかったのは、どちらの記憶だったのだろうか、と。
シンジの記憶を封じていれば、自分はこれほどの痛苦を味わわなかった。
だが、コウシロウの家の記憶を忘れたままにいれば、そちらを頼る事も出来た。
今ではもう、どちらも出来はしない。
記憶は全て、返ってきた。
「・・・・・・。」
否。
少なくとも先ほどの問いは、問いの形を成してはいない。
他者にとってどうであれ、少なくともアキナにとって、シンジの記憶は思い出されなければならないものだった。
彼を忘れていた事こそが無類の罪であるのに、これ以上の忘却など許されようはずも無い。
「・・・・・・。」
ポタリ、と、涙の雫がビニールで覆われた惣菜の上に落ち、広がり、水溜りとなる。
喪失の、痛み。
心が傷つくから、涙が出る。
心が泣くから、世界の全てが暗く見える。
だが、次の雫が落ちるより早く、涙は眼前から伸ばされた手によって拭われた。
「シンジ・・・君?」
何度も幻を見、何度も空耳に惑わされ、それでも僅かな希望を胸に、その手の先を見る。
だが、希望は、失望に。
夢は現実に、取って代わった。
「お前・・・。」
眼前にいたのは、銀髪の少年。
黒衣を纏い、闇をつれて歩く、異形のもの。
「何故・・・泣くの?」
その少年の口が開き、哀しげな声が洩れた。
「守るべき力を人から与えられて、もとより全てを壊す力を持って、それでなぜ泣くの?リリス・・・何を泣く事があるの?」
少年は、迷うそぶりすら見せずにアキナの身体を抱きしめた。
だが、それは間違いでしかない。
どれほど流動しようとも冬月アキナは冬月アキナでしかなく、リリスなどと言う異形では、無い。
それでも、少女は否定しようとするそぶりさえ見せず、少年にされるがままになっていた。
今はもう、碇シンジ以外のものの声は彼女の心には届かない。
「これほどに衰弱してまで、何を待ちつづけているんだい?」
「シンジ・・・君を。」
「・・・・・・。」
「シンジ君を・・・待ってるの・・・。」
止まりかけていた涙が吹き零れ、少年の肩口を濡らす。
その様を、少年は悲しそうに見つめていた。
だが、アキナはそんな少年の心を知ってかしらずか、しがみつくようにして泣き崩れてしまう。
「もう、やだよ・・・別れるのも・・・待っているのも・・・。」
「・・・・・・そう・・・。」
少女の言葉は自分に向いていない。
それを悟ったほんの一瞬の後、少年の赤い瞳が、黄金色に変わった。
第一位天使としての力、世界の全てを見通す目が、開かれる。
罪を見通し全てを裁くための力が、たった一人の人間のために使われる。
「・・・・・・大丈夫。」
程なくして、少年は再度口を開いた。
その言葉にアキナが耳を傾ける事も、リリスが目を覚ます事も、どちらも起こらなかったが、聞いているものとして、言葉を紡ぐ。
「碇シンジと言う名のリリンは・・・生きている。今はゲルムにいるし、危険な状態である事に替わりは無いけど・・・大丈夫、この様子なら、死ぬ事はないよ。」
ほんの一瞬、アキナの目に生気が戻った。
そして、次の瞬間、静かな部屋には不似合いな巨大な呼び出し音を鳴らしながら、少女の電話が震え、力の限りに少女を呼ぶ。
「・・・・・・。」
緩慢な動作で携帯を取り出そうとする少女の横をすり抜けるようにして、少年は部屋の闇へと消えていく。
何の要件を告げる電話か。
その「目」で見たが故に、少年は知っていた。
「まだ時ではないと言うのであれば、僕はいくらでも待とう。」
カーテンの陰、比喩でも何でもなく夜闇に溶け込みながら、少年は涙を拭った手を握り締めた。
未だ、その手には小さな雫が残る。
「・・・作られた歴史とは言え、二千もの年月を待ったんだ。今更どうと言う事はないよ。」
部屋の中には一人の少女。
その目にはもう、涙は無い。
「ちょっと相田、どうなってるの?あんた、本っ・・・当に何も知らないの?」
トウジと新しく入ったヌエという名の少年と、三人で机を突き合わせて昼食を取っていたところに、ヤエが割って入ってきた。
トウジは無視するようにパンを貪り、ヌエはトウジの妹お手製の弁当を、美味しいのか不味いのかよく分からない顔で黙々と食べ進めている。
少なくとも二人とも助け舟を入れるつもりは無いようであった。
「あんたの言うシャムシ何たらいうのの襲来からもう八日も経ってるのに、何でアキナも碇君も姿を見せないのよ?」
「俺がそんな事知るわけ無いだろ・・・。第一、知ってたらお前より先に先生に報告するよ。」
自分も持ってきた弁当を掻き込みながら、ケンスケはそちらを見もせずに告げる。
昼休みになるたびにヤエからの質問攻めにあっていたせいで、もうなれてしまっていた。
「そもそもまだ来てない生徒だっていっぱいいるのに、何で毎日毎日俺にばっか当たるんだよ・・・。他にもいろいろ当たれるのいっぱいいるだろ・・・委員長とかさ・・・。」
「委員長が知ってるわけ無いでしょ?ちょっと考えれば分かる事じゃない。」
「なら俺も知ってるわけ無いだろ!!」
叫ぶ。
だが、ケンスケもまた内心では心配していた。
あの日、シャムシエルとの戦闘の後、彼女はケンスケに約束していた。
必ず明日学校に来る、と。
学校に来て、出来上がった写真を受け取る、と。
だから彼の学生鞄の中には、未だに写真店の封筒が入れられているのだ。
―――大丈夫だって言ってたのに・・・。
身体に異常は無かったはずだった。
だから、彼が心配しているのは別の事。
彼女が組織の中で拙い位置に立たされることになったのではないかという事。
「・・・まさかあんたが監禁してるんじゃないでしょうね。」
暫くの黙考の後、ヤエはそんな答えを頭の中で導き出してきた。
「んな訳あるか!それと自分の分を食え!!」
その問いに崩れそうになりながら、伸びてくるヤエの魔の手から自分の弁当を死守する。
「良いじゃない、減るもんじゃないんだし・・・。」
ちっと舌打ちして、ヤエはその手をヌエの弁当へと伸ばした。
見る見るうちに、ヌエの弁当箱の中身が減っていく。
倍速、いや、三倍速といった所だろうか?
「それと、さっきのだってわからないわよ。アキナ可愛いし・・・あんた童貞だし。」
喋っている最中であっても、ヤエの口が止まる事は無かった。
行儀としては最低だが、それはまた別の話。
「とりあえずそこで童貞は関係ないだろ!と言うか勝手に他人を童貞と決め付けるな、この腐女子!」
「んふふ〜、むきになっちゃって、お子様〜。」
当初の目的が忘れられ、いつのまにかケンスケをからかう事が主体になっていた。
その様子を眺めるものたちは、何も言わない。
言えば自分に火の粉が降りかかる事を知っているから、絶対に首を突っ込まない。
「あと、私は腐女子じゃなくてスポーツ美少女の分類なの、いっしょにしないでくれる?」
大仰に胸を逸らし、ヤエは言い放つ。
それを見た健介は、げんなりした様子で肩を落とした。
「自分で言ってりゃ世話無いよ。・・・まあ、可愛い事は認めるけどさ。」
俯いたままぼそっと呟く声は、ヤエの耳には届いていない。
それは菊花ヤエにとってどうだったかはともかく、少なくともケンスケにとっては僥倖だった。
「でも、本当にどうしたんだろう・・・。お弁当持ちも最近ぜんぜん学校にこないし・・・。」
変わりに、不意に真剣になったヤエは、顔を窓の外に向ける。
シンジがいつのまにか弁当持ちに降格していた事については、悲しいかな、誰も突っ込むものはいない。
皆自分たちの会話に夢中で、こちらを見る余裕など無かった。
だからこそ、馬鹿な会話が成り立つ。
だが、不意に何かを見つけたらしく、トウジの手の動きが早まった。
それまでは味わうように食べていたパンが、見る見るうちに胃の中へと消えていく。
「・・・・・・。」
「・・・・・・。」
その様子に驚き、ついつい二人揃って凝視してしまう。
少し気を回せば教室がざわめきたっている事ぐらい気付けたろうに、二人は結局気付く事が出来なかった。
「・・・・・・なあ、お二人さん。」
そして、数秒のときを経て、パンが全て彼の胃の中に納まった時、ようやくトウジが口を開いた。
「どうでもええんやけど、その冬月さん、そこにおるで。」
指差す先は、教室の入り口。
そこに、一人の少女が立つ。
ようやく気付いたケンスケとヤエに向かい、弱々しく手をふってみせる。
転校してきた当初に比べると幾分頬がこけ、痩せてはいるものの、その特徴的な容姿を、少なくともヤエやケンスケが見紛うべくも無かった。
「アキナ?!大丈夫なの?」
「冬月さん?」
両者ほぼ同時に立ち上がり、アキナへと近寄っていく。
ただ、その際ケンスケが置いた弁当箱を拾ってから向かった分、ヤエのほうが数歩遅れた。
その差は会話の主導権というカタチにおいて、絶対的な差となって現れる。
「何があったのさ。ずっと学校にこないから何かあったのかと・・・。」
「・・・ごめん、なさい。」
――思った。
そう続けようと思った言葉は、泣きそうなアキナの顔を見た瞬間に忘れてしまった。
普段からどこか愁いを帯びた顔はしていたが・・・これは。
なんと、なんと哀しげなのだろう。
「シンジ君が・・・ドイツにいるって・・・だから・・・。」
切れ切れに言葉を放ちながら、アキナは身体をケンスケの胸に預けてくる。
そう厚くもないケンスケの胸板に、アキナの頭がトンと乗った。
その距離と、突然繰り広げられた情景に、教室中にざわめきが起こる。
「私、心配して・・・。」
言葉は、つながりを欠いている。
そして、それ以上に、この状況は異常だった。
学校でこのような状況は、あまり目立たないオタクな生徒でしかなかったケンスケがこの状況に陥るというのは――。
あまりに、異常。
そのような事、許されようはずも無い。
(おい、ちょっと・・・)
ケンスケの両手が、手持ち無沙汰に揺れる。
このような時抱きしめればよいのか、突き放せばよいのか。
経験が薄い、いや、無いといっても過言ではないケンスケに分かるはずも無かった。
それゆえに、まるでさまようように両手が宙を舞う。
「何これ。大して美味しくもないじゃない・・・って・・・・・・。」
そこに、タイミング悪くヤエがやって来てしまった。
これまで弁当箱(とその中身)に注目していたせいか、他のクラスメイトたちよりもさらに情景に気付くのが遅れた。
――――げ・・・――――
一瞬、ケンスケの顔が強張った。
背筋を悪寒が走り抜け、禍々しい記憶が次々とフラッシュバックしてくる。
他のクラスメイトならば少々からかわれる程度で済むだろうが、彼女に限ってはその限りではない。
いざとなれば実力行使も辞さないであろう事は、これまでの人生において何度も経験しているために周知の事実だった。
「あの、これは・・・。」
「・・・・・・・・・。」
だが、それでもヤエは自棄になったようにケンスケの弁当をお腹の中に掻き込みながら見ているだけだった。
この状況を回避する代金がそう美味くも無い弁当一つで済むというなら、それは安いものだと言わざるを得ない。
「・・・・・・?」
「さっさと済ませてよ。私もアキナと話したいこと、いっぱいあるんだから。」
ふてくされたように、そっぽを向く。
それでようやく、彼女が気を使っているのだと分かった。
これまでの成り行きを見ていなくとも、成った結果から口を挿んでいい状況に無い事ぐらいは分かったらしいと気付き、心底ほっとする。
「えっと、じゃあ・・・。」
振り返ったところで、気付く。
――だがいったい、いったい何を話す?
一週間前の出来事についてこの場で話すことは憚られる。
何処までが話してもいいことであるのか分からない以上、迂闊に話を切り出すわけにはいかなかった。
「・・・冬月さん、とりあえず、離れない?」
「え・・・?」
それでようやく、アキナは自分の状況に気付いたらしかった。
シンジとの再会のときもそうだったあたり、パニックに陥ると自分が何をしているのか分からなくなるらしい。
顔を真っ赤にして離れるアキナを見て自分も頬を赤らめながら、それでも彼は一頻り乾いた笑い声を上げた。
どうしようもない自己だったのだと、判断を下した。
「・・・で、何があったの?」
「あ、その・・・。」
まるでラブコメを演じているかのように、二人は目線をあわさぬままに会話する。
ケンスケの顔は赤いまま。
アキナの顔はほんの一瞬赤くなっていたが、今はまた青い色。
それでもまあ、声さえ通れば会話は成立する。
「えっと、写真・・・。」
弱った口から放たれた言葉は、聞くという一点に神経を集中させていたケンスケにとって拍子抜けするほど簡単なものだった。
勿論持ってきてはいるが、先ほどの深刻そうな状況から考えて、それほど優先されるべき事象だとも思えない。
「あれ、まだ・・・?」
「え?・・・ああ、ちょっと待って。」
言葉を遮って、机のほうへと戻る。
その途中、すれ違うヤエに睨まれたが、肩をすくめるだけに止めた。
本当に、何があったのかの見当もつかないのだ。
――――碇が・・・ドイツにいる?――――
かばんの中の封筒を探しながら、思考する。
だが、それがどうしたと言うのだろう?
彼がドイツにいるというのは確かに驚きだが、それによって何故ああもアキナが衰弱してしまうのかが分からない。
――――あの痩せ方・・・尋常じゃなかった――――
ようやく出てきた封筒を、少し開く。
一枚目は、あの病室で撮った写真だった。
痩せてはいるが血色の良い少女が、画面いっぱいに躍動している。
その写真と、ヤエの質問攻めにあっている今のアキナを見比べ、そして、確信した。
今のアキナと一週間前のアキナは、最早別人といっていい。
今の彼女では、この写真は撮れない。
――――何が・・・あった?――――
この一週間。
いや、この写真を撮ってから、その日が終わるまでの間にあったことを、写真と今とをつなぐ時間を、想像する。
記憶の糸を、じっくりと手繰り寄せていく。
――――この時も、碇はいなかった・・・。
だが、彼女は溌剌とした笑みを見せていた。
だとすれば、碇がいなくなったのは、少なくともその時点においては予定調和のうちだったのだろう。
それが、ドイツに行った事に関しては、取り乱した。
想像することしかできないが、おそらくは殆ど食事も喉を通らなくなるほどにまで。
――――いや、待て。
急遽思考を停止させ、巻き戻した。
条件が、おかしい。
今彼女がその事実――碇シンジがドイツに滞在しているというその事実を知っているところで、その時彼女が知っていたという事にはならない。
むしろ、最悪の状況を想定したほうが、いい。
――――そう、例えば・・・。
例えば――何があるだろうか?
ドイツというのは、家出で行くにはあまりに遠い。
もちろんあの天使の言葉を信じるのであれば彼もそれなりの人物ではあるのだから、不可能ではないのかもしれないが、それにした所でアキナが本気になればすぐに見つけることは可能だっただろう。
少なくとも、一週間もの間何も手を打たずにいたとは考えにくい。
だとすれば、アキナが探そうと思っても、探す事が出来ないような状況におかれていたのなら・・・。
――――誘拐?
思い浮かんだ単語に、戦慄する。
通常ならば思いつかなかったような答えではあったが、彼女たちの境遇を考えると十分にありえる考えだった。
――――もし、どこかへ向かう途中、予想外のアクシデントが起こったのならば・・・。
アキナが知るのは、ずっと先のことになる。
事が起こったのが夕方頃だったとすれば、早くとも報告が入るのは深夜になる。
それまでの間に戦闘が起こり、写真が撮影されたのであれば。
そして、その数分後、もしくは数時間後に、彼女にそれが知らされたのだとすれば。
――――少なくとも時間軸は、一致する――――
「なに写真覗き込んで深刻な顔してるの?」
「うわああぁぁぁぁっ!!!」
突然、座り込んでいたケンスケの上に黒い影が落ちた。
慌てて写真の封筒を閉じながら、背後を振り返る。
「アキナがお待ちかね。何があったのかは知らないけど、止めてよね、ぼうっとするの。」
「あ、ああ、分かってる・・・。」
写真を覗かれた恐れは無いらしい事に安堵しながら、よっこいしょ、とジジくさい科白を吐きながら立ち上がる。
それはブラフでありポーズだったのだが、果たしてそれほどの行動を必要とする場面だったのか、それは定かではない。
ヤエからはそれ以上の追求は無く、アキナがそのことを気にするかどうかも、分からない。
あるいは、どうでもいいと思っているのかもしれない。
この写真の事は会話に入るためのきっかけでしかないのかも・・・。
――――ん?――――
その時、ふと入り口付近に立つアキナの事が気になった。
まるでお預けを喰らった犬のような顔でこちらを見ている、若干十四歳にして女帝となった存在の不安と、期待に満ちた目。
――――やめよう――――
それを見て、思考は強制的に停止させた。
――――下種の勘繰りをしても、意味なんか無い――――
意味も無いし――自分が馬鹿を見るだけだ。
そんな事で初めて写真やビデオに純粋な理解を示してくれた友人を失うのは、あまりに惜しい。
「えっと、じゃあ、これ。」
「・・・・・・。」
表情を取り繕うようにしながら近づき、ドアにもたれかかるようにして立つ少女に表紙に会社名の記された封筒を手渡す。
無言のままだったが、渡された瞬間、ほんの一瞬だけ笑いを失っていたアキナの顔が綻んだ。
受け取った封筒を無造作に開き、四十枚近くある写真を、いとおしそうに取り出してくる。
「・・・・・・全く、写真なんかいつの間に・・・。」
その様子を、苦虫を噛み潰したような顔のヤエが後ろから覗き込むようにして眺めていた。
隠した意味が無いとも感じたが、アキナがそれを許すのであればケンスケが口を挿む道理は無い。
そんな事よりも、ヤエの顔が一枚、また一枚とめくるにつれ驚愕の表情に変わっていくのを眺めているほうが、数倍面白かった。
「相田・・・これ、全部あんたが撮ったの?」
「ん?ああ、そうだよ。悪くないできだろ?」
「・・・・・・。」
少し得意になって、答える。
パソコンの画面で適当な写真をピックアップする作業を行うときは、自分でも驚いたのだ。
これまでにも何度も人を題材にした写真は撮っていたが、これほど綺麗に撮る事が出来たためしは無かった。
プリンタ印刷で終わらせるのがもったいなく、専門の業者に頼んだのもそのせいだ。
集めて編集すれば、一つの写真集として出す事さえ出来てしまいそうだと思っていた。
「・・・・・・。」
アキナからの感想は、得られなかった。
だが、その顔を見る限り、少なくとも嫌がっていないであろう事は、分かる。
「・・・・・・ん、ありがとう。」
そして、全てが一巡したとき、ようやく小さな感謝の声が聞こえた。
写真を戻した封筒を胸に抱き、まるで宝物のように抱きしめている。
その姿を見ているうちに、不意に恥ずかしさがこみ上げてきた。
「えっと、それで・・・。」
鼻を掻きながら、周囲をきょろきょろと見回す。
「・・・結局、何で学校にこなかったの?やっぱり写真は拙かった・・・とか? データごとって言うなら・・・。」
「・・・・・・。」
無言のまま、首が左右に振られた。
それはつまり、否定という事なのだろう。
「なら、やっぱりシンジの事・・・?」
「うん、一週間行方不明で・・・昨日の夜、連絡が入って・・・。」
声を潜め、話す。
が、それは意図したことではなかった。
声を潜めて見せた所でその内容はヤエには聞こえているだろうし、そのことを気にする必要も無い。
彼女が興味を持っているのは冬月アキナであって碇シンジではないのだ。
極端な話、もしシンジの命に別状があったとしても、彼女にとっては「その程度」の事でしかない。
そしてケンスケにしても、シンジはアキナの付属品程度にしか思っていない。
転校してきた初日から、シンジはずっとその地位を貫き通していた。
それがこれほどに少女にとって重要な存在であろうなどと、誰が思い知ろうか。
如何なる友人よりも、如何なる家族よりも、深い関係であるなどと、誰が思い知ろうか。
「だから・・・。」
ただ、少し逡巡した後にアキナの放った一言は、それでも十二分にヤエの耳にも届いた。
届かざるを、得なかった。
それがあまりにも唐突であったから。
それがあまりにも非現実的であったから。
即ち――
「私も、ドイツに行ってくる・・・。」
――と。
あとがき
ひゃっほ〜い!やっぱり超えたね、百キロバイト!(Windows2000ワードパッド・リッチテキスト形式換算)
いや、もう、なんて言いますか・・・シンジは主人公じゃないんです!(今更)
主人公はケンスケなんです!!(エ?
ヒロインはきっとヤエなんです!!(オイ
・・・と、まあそんなこんなでなんだかいろいろあった第四使徒編もいったんここで幕切れ。
次回からは――サブキャラ一号と隠れヒロインの根城にオリキャラが突入、蜜月の館をぶち壊し、金銀財宝を根こそぎ奪い取り、記憶を失った一号を手篭めにする――そんな感じのドイツ編が始まります(まあ殆ど全部嘘ですが。)
というか、いろいろなサイトを見てもなんだか無茶苦茶に破茶滅茶に滅茶苦茶に強いみたいな――第五使徒――は、大丈夫なのでしょうか?(人に聞くな)
現存戦力結構減っている気が・・・というか・・・レイと初号機だけですね。
ミサト無し、ゲンドウ無し、シンジとの友情もレイの根性も一切無し・・・・・・日本滅びるかな・・・?
・・・・・・で、では、なんだか治まりつかなくなっている気配がありますが、ひとまず再見!・・・ということで。
蒼來の感想(?)
急展開〜急展開〜急旋回に急降下に〜もうこうなったらトリプルアクセルきめちゃる!!(大いに錯乱)
鈴菜「・・・壊れた?」
観月「トリプルアクセルは完全に無理ですわ。スケートをまともに滑れない蒼來には。」
受験生気にするなよーーーー!!大学入試を26連続落ちた俺でも最後には入れたからなあ!!(まだ錯乱)
鈴菜「ええと・・・コメントが難しいな・・・つうかまともに戻って感想言えよ!!」
ふう(深呼吸)、すまん錯乱してた。というか受験ネタは実話だからね。(´Д⊂)
観月「では感想にもどりましょう。シンジ君とアスカちゃん、お知り合いみたいですわね。」
うむ、もしかしてアスカはアキナも知り合いか?つうかキョウコさん生きてるし。
鈴菜「キョウコさんが居るアスカはまともなはずだよな?」
多分。殆どのSSではそうだな。但し、ツンデレアスカも存在するがね?
ところでレイは無事なんですか?13話の最後以来見てないんですが・・・
観月「それもそうですが、本部ボロボロですわ。」
う〜ん、アキナはドイツに行こうとしてるし、シンジ・アスカもドイツ。・・・戦自頼みかなあ・・・あるSSだと戦艦:大和で殲滅したけどね。
鈴菜「日本が滅びる前に、アスカVSアキナでドイツが更地になるようにも思えるが」
ん?なるだろ確実に。
観月「エヴァで対決してですか・・・」
うんにゃ、生身でできるだろ。あの2人なら。
二人「できません(るか)!!」