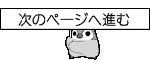「変えられない運命など存在しないのだよ。そうなったという結果を変えることはできないかもしれないが・・・まだなっていない結果に変更を加える事など、今ここで君にコイントスで勝つ事よりもはるかに容易い事だ。」
姫君の寵愛byダークパラサイト
第十四話:「鼠一匹」
「こういう・・・ことか。」
全ての登場人物が姿を消し誰もいなくなった真っ暗なロビーの片隅で、ゲンドウはそう言って僅かに口の端を吊り上げた。
その笑みは普段の覇気に満ち溢れたそれと寸分違わず同じで、だがその足元には普段ならば、絶対とは言わないまでもまず有り得ない赤い水溜りがある。
ここに至るまでの道のりに、赤い線が引かれている。
誰の血か?
そんなものは、一人しかいない。
ゲンドウ本人の血だ。
その証拠に、彼の腹には穴が、
ちょうど心中線の真上に大きな、背中まで貫通した穴があいている。
先ほど旧友につけられた穴は、見る見るうちに鮮血を噴出させる。
「これも酬いだと、そういうことか?キール・ローレンツ。」
もう動く事もままならないのだろう。
体を壁に預け虚空を睨んだまま、ゲンドウはゆっくりと、まるで言い聞かせるように虚空に向かって話し掛けた。
惜しむらくはその視線の先に記録装置が存在しない事。
これより先、彼が死に至るまでの思考も、言語も、何者にも記録されていない事。
ここには、これほどに明らかな答えがあるというのに。
紅き世界の鬼だけが、彼の終わりを眺めている。
「間違いを正そうとするものは、悪に見える。神を裁こうとした者は、例外なく裁かれる。・・・そういうこと、なのだろう?旧き友を使ってまで・・・私を・・・ぐぅっ・・・。」
肋が大きく動き、地獄の底から絞り出したような声が洩れた。
意識があることが不思議なほどの出血の前に、残された時間はあまりに少ない。
なのに、それがあたりまえの事であるかのように返事は無かった。
暗闇の中、彼の言葉を聞く者は、何もない。
「だが、キール。・・・それは間違い・・・。私を殺しても・・・何も・・・。」
変わらない。
そう告げようとした言葉は、吐血によって途切れた。
しかし怪我の功名とでも言うべきか、喉元に溜まっていた血を吐き出した結果、男の息は少し楽なものになった。
「狂いは治らない・・・もう止まらんよ。・・・貴様等がどう足掻こうとも・・・。」
そこにいない自分の上司、いや、元上司に向かって嘲りの嘲笑を浮かべながら、語りかける。
「間違いは彼女だよ、キール。私ではない。私などであろう筈が無い・・・。」
もう体はぼろぼろのはずなのに。
後数秒のはずの命だというのに。
ゲンドウは覇気の無い顔で、それでも必死になって豪胆に、笑った。
「は・・・はは・・・そうだろう?ユイ。」
その笑いの意味は何か。
知り得る者は傍におらず。
本来傍に仕えるべき少年も、姿を見せず。
それでも最後のひと時を前に、ゲンドウの言葉は衰弱からの一時的な立ち直りを見せた。
「君は、・・・君はゼーレの終わりも私の終わりも受け入れようとはしなかった。・・・愚かだと思っていたのだがね・・・やっと分かったよ。彼女に諭されてもなお分かっていなかったが、やっと分かった。」
語りかける言葉の先。
満面の笑みの先に、今は戦場にいるはずの妻が映る。
それが網膜の見せる幻想であろうと、最早構いはしなかった。
「君は知っていたのだな・・・。彼女が、狂いの張本人だという事を、本能的に理解していた・・・全てが無駄だと知っていた。」
妻へと差し伸べた手が、虚しく空を切り、笑いを収めたゲンドウの頬に、大粒の涙が伝う。
「・・・愚か者は私だったという事か・・・。」
その涙が痛みによるものか、それとも悲しみによるものか、それは定かではない。
もしかすると、まったくの別種の感情だったのかもしれない。
例えば、歓喜や憤怒といった激情。
それらが沸き起こっていたとしても、不思議は無い。
「だが、これは・・・。」
そして、それが如何なる感情であろうと彼の命が尽きる事には何の変わりも無い。
「少しばかり・・・早過ぎるかな・・・。」
ずるり、ずるりと、ゲンドウの体は崩れていく。
両の瞼が閉じていく。
「もう少しだけ・・・世界を・・・見て・・・」
それを最後の言葉とし、彼の口は二度と言の葉を紡がなかった。
暗闇の中、息づくものは消え、既に物言わぬ骸と化した身体の上を一羽の鴉揚羽がひらりひらりと飛んでいく。
兄妹たちは、まだ眠っている。
だが、少年は未だ、起きていた。
そして、少女はもう、起きていた。
そして厄介な事に、目を覚ますなりその少女は泣き出していた。
怖かったのだと。
恐ろしかったのだと。
声にならぬ声の中、嗚咽の狭間で、まるで熱に魘されながらのうわ言のように、その言葉を繰り返した。
巻き込んだ少女を責めるでもなく。
暴れた鬼を詰るでもなく。
体中に出来た傷への痛みでも、少年と言う異形に対しての恐怖でもなく。
ただ一つの感情のために、恐怖と言う感情のためだけに、泣く。
その様を、少年は不思議なものでも見るかのように、眺めていた。
少年から見れば、その泣き声には理由がなく、理由無き悲しみをどうすれば良いか、彼には対処するべき術がない。
だから仕方なく、少年は先ほど自分が隣で眠る少女のためにさせられた行動を、その意味すらわからぬままに再度実行した。
理由すらわからぬままに、もう一度。
今度は別の少女の身体を掻き抱き、頭を優しく撫でた。
図らずも、その様は親が子供をあやす仕種に、似る。
「・・・ん・・・。」
泣き声の狭間に、小さく甘えるような声が混じった。
そのことをいいことに、少年は少女の顔を自分の胸に埋めてみせる。
少年の行ったそれは優しさとは無縁の事務的な作業でしかなかったが、それだけでも恐慌に陥りかけていた少女を救うには、十分だった。
少女の泣き声はやがて啜り泣きに変わり、穏やかな息に戻る。
それでも少年が頭を撫でつづけていると、少女は擽ったそうにしながらも少し嬉しそうに、目を閉じたままその愛撫を受け止めていた。
そして長い時間がたち、涙が乾いてくるころになるとようやく、硬い表情ながらも笑って見せる事さえできるようになる。
それでも少年はその終わりが分からず、少女の頭をなでつづける。
「あの・・・ヌエさん、もう、大丈夫です。」
それ以上甘える事を悪いと思ったのか、それとも別の理由からか。
少女はさらに撫で続けようとする少年の腕をすり抜け、その前に立った。
そうしておいて、座ったまま見上げる少年の前でぺこりと頭を下げる。
「その・・・ごめんなさい。」
「?」
声が少年の脳髄に浸透するまでに、少し時間がかかった。
頭に疑問符を浮かべるヌエを、だが、少女はどう勘違いしたものか、責められていると感じたらしかった。
「本当なら、私が、止めないといけなかったのに・・・。」
頭を上げず、言葉を詰まらせながら、本当に申し訳なさそうに、少女は謝った。
それでようやく、少女が先ほど外に出た事を、図らずも神々の、いや、神の子達の戦いに介入してしまった事を謝っているのだと、気付く。
「私が、止めなかったから、ナオちゃんも・・・ヌエさんも・・・。」
擦り傷や痣は、少なくともこの少女にとって勲章ではなかった。
少女にとっての冒険や危険とは、常に避けられるべきものだった。
だからだろうか?
その姿が、似ても似つかぬと思われた少女の姉と、少なからず被る。
あの煩わしくも一途な少女と、本質的に一致する。
それは、過ちですらないと言うのに。
過ちを犯したのは、咎人ただ一人であると言うのに。
この少女はきっと、世界の全ての罪さえも、攻められればその身に背負う。
「気にするようなことじゃない。」
だから、必然的に少年の声はそのトーンを落とした。
罪を負わせる者である以上、罪を負う者は嫌いでは無いが、さりとて限界はある。
世界の罪さえも、他人の罪さえも背負おうとするものは、必ず自滅する。
それがかつての自分であっただけに、少年の悲しみは増していく。
「おいで。・・・そんな事は気にするようなことじゃないよ、リリン。今命があることを喜ぶのならともかく、他者への罪の意識など、持ち合わせないほうがいい。」
「リ・・・リン?」
少女には、言葉の意味はわからない。
だから、招かれるままに少年の下へと戻りながらも、少女は首を傾げてみせる。
「僕は、人をそう呼んでいる。全ての者がたった一人の母から生まれたのだから・・・。」
少女の身体を抱きしめ、少年は彼女の耳元で全ての理を囁いた。
「お母さん・・・ですか?」
少女は、まるで噛み締めるかのように母と言う言葉を復唱する。
そして、顔を綻ばせ、少年の胸に、より深く、まるでそこに穴でも求めるかのように顔をこすりつけてくる。
何もせずとも満ちていく喜びの波動が、少女の身体を満たしていく。
「私も・・・そのお母さんから?」
「そう。君も、リリスから。」
顔をあげ尋ねる少女に、頷く少年は少女の家庭環境を知らない。
少女の幼さを、理解していない。
「リリス・・・私のお母さん・・・。」
「その人は、何処にいるんですか?」
「さっきまで戦っていたよ。紫の鬼のパイロットとして・・・。」
少年の放った一言が少女の幻想を、世界を、根底から変えてしまった事を少年は知らず、そして何よりも、少年は嘘を突くということを知らなかった。
目を輝かせながら呟く少女に母がいない事など知りようもないことだが、さりとてそれは言い訳にならない。
「お母・・・さん。」
少女はもう一度呟き、クフフ、と小さな笑みを漏らした。
――ウオオォォォン――
叫び声は、近く、遠く、何処からとも無く地鳴りのように響いてくる。
人とも、獣ともつかぬ不思議な叫びは、だが、不思議と耳から離れない。
(あ・・・・・・)
そして、気がつけばあたりには何も無かった。
あるものは廃墟と化した都市と真っ赤に染まった空、そして天にも届こうかという巨大な瓦礫の山脈だけ。
――――――オン―――――――
その瓦礫の山のふもとで、まるで示し合わせたかのように片翼の鬼が哭いた。
片翼を夕闇に赤く染め、飛ぶことのできぬままに。
たった一人。
一人ぼっち。
その寂しさを嘆くように、哭いた。
そして少年は、叫びは鬼の咆哮だったのだと、思い出す。
自分が何だったのかを、思い出す。
(なんだ・・・これ・・・・・・。)
現実ではない。
だが、夢で片付けるにはあまりにリアルすぎる世界。
―――ガアアァァァァァッッッ!!!―――
瓦礫の中、時折鬼は咆哮を上げる。
それが誰かを呼ぶ呼び声なのだと理解するのに、それほどの時間はかからなかった。
だが、誰を?
――――自分ではない
どこから?
――――ここではないが、ここにはここしかない
そんなとりとめの無い疑問が浮かんでは消える。
そして、如何なる結果を持ち出してみたところで、鬼は一人だというその事実は変わらない。
周囲一体に、瓦礫以外のものを認める事はできない。
(・・・・・・・ん?)
そこまで考えて、気付く。
瓦礫とは、それがなる前にそこに何かがあったという事だ。
そこに何かがあり、それが壊れたという事だ。
(どういうことだ・・・?)
このような建造物は。
半径数キロにわたり聳え立つ人工的建造物などは、如何なる場所を探しても存在しないだろう。
あるとすれば、それは神話と呼ばれる世界の産物だ。
―――ガアアァァァァァッッッ!!!―――
また、哭き声が聞こえた。
高く。
低く。
まるで謡うような、節のついた哭き声。
だが、それが正常なのだと思い知らされた。
何もかもが異常で、これ以上ないぐらい正常なのだ。
自分がここにいることも、この世界を知っている事も。
全てが異常だったのに、この世界が正常で、自分の記憶にある世界であるのだと教えられる。
こんな世界は、勿論彼の世界ではない。
周囲の瓦礫を見ても、そこに自分のすむ世界の痕跡は認められない。
そこにあるのはただ無用の長物と化した数え切れないほどの塵芥。
そう表現するしかないものだけだ。
待てど暮らせど、四方八方それしか存在しない。
この世界においてはそれが現実、それが全て。
なら作り出すものは?
ただ一つ、それはある。
少女が、この世界に堕ちてきたものであったなら。
この、世界でも例を見ないほどの巨大な建造物の上に少女が落ちてきたのであれば、十分にありうる事ではないか。
知っているが故に、鬼は慟哭する。
鬼の姿をした少女は、天に向かい叫ぶ。
だが、このような世界は現実において存在し得ないのだ。
外とのつながりの無い究極の閉鎖空間において、あるのは瓦礫の山と己が身体のみ。
どれほど哭いても、怨念を込めても、この地の果ての牢獄から出る術は無い。
何処にも出口は、無い。
――――なら、ここで暮らせばいい。
ふと。
有り得ないはずの空間で、有り得ないはずの声を聞いた気がした。
(な・・・。)
つい最近聞いた声のはずなのに、それが誰の声なのか思い出せない。
それどころか、酷く眠い。
(・・・誰・・・だっけ・・・?)
記憶に探りを入れようとするが、それはすぐに無駄な作業となった。
眠気が、脳細胞を殺してゆく。
思考能力の全てが、殺されていく。
そして。
ゆっくりと。
覚醒する。
「あ、起きた?」
「うわっ!!」
目を開けた途端、女性の顔が視界いっぱいに大写しにされた。
そのショックで、見ていた夢の殆どを忘れてしまう。
女性は長い黒髪を後ろで一つに纏め上げた、同い年の少女だった。
その長い髪が頬を撫でているのが、どこかくすぐったい。
だが、少年――ケンスケにとって見れば、その顔はもうかなり見慣れたものであると言っていいものだ。
つい最近転校してきた少女。
紛れも無く自分のクラスメイトで、同時にエヴァと呼ばれるロボットのパイロット。
名は・・・
冬月・・・冬月 アキナ。
「おはよう、相田君。」
「・・・・・・ああ、そうか。おはよう。」
言葉を交わしあい、苦笑する。
「良く寝てたみたいだけど、目立った外傷は無いから身体のほうは大丈夫だって。・・・けどごめんね、変な事に巻き込んじゃって。」
「別に良いよ。・・・そりゃちょっとは驚いたけど、冬月さんがパイロットだって言うのなら心配も無いだろうし。」
彼女は、彼女自身ですら知らぬ秘密を自分が知っている事を、知らない。
そのことを思うと、ケンスケの心は少し痛んだ。
何か、覗き見でもしてしまったような気分だった。
「・・・・・・そんな事より、ここ、何処?」
「NERV直属の医療センターよ。」
言いながら、少女が身体を起こす。
その向こうに白い壁と天井が見え、それでようやくここが病院かどこかの施設なのだと確信をもてた。
右手に注射針が刺さり、その先では点滴が繋がっていたのだが、どこか現実感を伴っていなかったのだ。
「医療センターって・・・そうか、気絶・・・?」
「うん・・・。」
そして、唐突に思い出す。
思い浮かんだのは、自らの秘密を告げた天使の顔と、その握りこまれた拳。
恐怖を覚えるに値する。
いや、恐怖しか与えないであろう赤い瞳と、白き光翼。
今の目はどうやら黒いようだが、天使の言葉を借りるなら、いつ赤くなっても不思議は無いのだろう。
「私は何も覚えていないんだけど・・・何があったの?」
「う〜ん、何があったと言うか・・・。」
聞かれても、知らないとしか答えようが無い。
知っているのは戦いが始まるまでの数分と、戦いが終わった後の天使の言葉。
自らを、神と名乗った天使の言葉。
「ごめん、俺にもよく分からないんだ・・・。」
「そう・・・なんだ。」
少年の言葉に、目に見えてアキナは落胆する。
戦闘中の記憶が無い事を気にしているのだと思われたが、それをどうこうする力はケンスケには無かった。
「それより、冬月さんこんな所にいていいの?いろいろしなくちゃならない事とか・・・。」
「別に、いい。」
触れてほしくない話題だったのか、アキナはそっぽを向いてしまう。
それは、しなくてはならない事の全てを放棄したのと、同義だった。
彼女が動かない分は誰かに、どこかに、しわ寄せが行くのだろう。
そのことを思うと少し心が痛んだが、かといって彼女を遮るのはケンスケの仕事ではない。
「約束したから・・・そっちが先。」
「約束・・・?」
だが、続く言葉は、予想を越えていた。
それが何の事なのか、分からない。
「カメラ・・・。写真撮ってくれるって。」
「え?・・・ああ、そうか。けど、カメラは・・・。」
「・・・・・・。」
壊れている、と言うよりも早く目の前に新品のカメラが突き出された。
以前使っていたものと同じビデオもカメラも兼用できるタイプのものだが、記憶が正しければ値段の桁が一つ違う。
中学生のなけなしの小遣いでは、到底手が出ない代物だ。
「これで、いい?」
「え?あ、ああ・・・。」
突き出されたカメラを手にとり、しげしげと眺める。
その前で、少女が不安げに眺めていた。
「十分だけど・・・これ、何処で手に入れたの?」
「私の写真を撮るって言ったら、カスパーが用意してくれた。」
「そう・・・。」
カスパーという耳慣れない言葉が気になったが、ケンスケはそれ以上に目の前のカメラに執心していた。
「起きられる?写真、撮れる?」
「ん・・・。」
正直に言えば、まだ身体はだるかった。
だが、それを言ってしまえば全てが駄目になってしまいそうで、ケンスケは無理やり自らの身体を引き起こした。
「大丈夫・・・。これが邪魔だけど。」
精一杯おどけて、少女に点滴の針を見せる。
「あ、ちょっと待って。」
アキナは慣れた様子でその手を取り、すぐさま針を外してしまった。
「これで良い?」
「・・・・・・・うん。」
「じゃあ行こう!!」
少女の声は、弾んでいる。
その姿は、躍動する。
だから、ケンスケはほんの悪戯のつもりで少女にレンズを向け、少女が気付くよりも早くシャッターを切った。
カシャっという音と共に、冬月アキナと言う少女の表情が、その一欠片が、カメラという箱の中で固定される。
「え?」
その音に驚いたのか、アキナは目を見開いたままの表情で固まった。
そこで、もう一度シャッターを切る。
また一つ、少女の表情の欠片が箱の中に収められる。
「ここで、撮るの?」
「いや、ごめん、ちょうどシャッターチャンスだったから。」
「なにもポーズとってないよ?」
「何もポーズをとらなくても、シャッターチャンスはある。・・・ちょっと待ってね・・・。」
言いながら、ケンスケはいくつかのボタンを操作していた。
程なくして、先ほどとった写真が小さな画面の中に表示される。
「わぁ・・・!!」
そこに、躍動する少女がいた。
喜び。
期待。
安堵。
そういった感情の全てを秘めたまま、白の世界で少女は躍動する。
「勿論背景が綺麗ならもっとよかったんだろうけど、写真って結局はその被写体がどんな表情をしているか、だから・・・。」
無機物にせよ、有機物にせよ、その被写体が魅力的でありさえすれば写真は映えるものになる。
それがケンスケの持論であり、常に心がけている事だった。
「ポーズをとっていい写真になる事もあるけど、素の表情のほうがいい写真になりやすい。だから子供を撮るといい写真ができやすいんだ。彼らは心の底から笑うから。」
「へえ・・・。」
アキナは、上の空で小さな画面を眺めている。
彼女の心にケンスケの言葉が浸透しているかどうかをその姿から判断する事は出来なかったが、ケンスケはさらに言葉を続けた。
「だから、写真を撮るからと言ってわざわざ何かをする事は無いと思う。いつもどおりでいてくれさえすれば、それで。」
言いながら、食い入るように小さな画面を見つめるアキナの横から手を伸ばし、小さなボタンを操作する。
そこで写真が切り替えられ、画面いっぱいに驚きの表情を見せるアキナの顔がみえる。
「な・・・!!」
「じゃあ、そろそろ行かない?」
顔を赤らめる少女の肩を借り、何とかよろけることなく立ち上がる。
だるさを隠すように、部屋の出口を目指すと、アキナは慌てたように後を追いかけてきて、そのまま追い抜いていってしまう。
「何処か撮るところにあてでもあるの?」
「中庭で・・・と言うか先にこの写真消して!」
戦闘の直後だとは思えない温い空気。
(それでもまあ、昔の自分が受けていたものよりはいい・・・かな?)
押し付けられたカメラを操作しながら、ケンスケは少女の後を付いて歩いていく。
その、内に秘めたる記憶。
遠く離れた地にて失われたそれと、一致する。
その事実が持つ意味の巨大さ。
未だ少年たちは知らない。
あとがき
どうも、なにやら週一更新に治してくださるそうなので急いで仕上げました。
いやはやそれにしても前回の「神々の旋律」更新の折は真無礼な発言、お許しあれ。
自分のほうでもそんなスピード更新などできないくせに、無茶苦茶を申してしまいました。
・・・が、それでもまあ、時間は見つけるものではなく作るものだと思います。
自らの分の更新の時間を考えても一週間に一時間ぐらいあれば何とかなると思いますので、、ご健勝のもと頑張ってください。(無責任)
それと、BBSやお絵かきBBSのほうもご確認いただけると恐悦至極で御座います。
特に絵は趣味の産物とは言え感想がつかないとなるとなかなか(と言うか全く)描く気になれませんので感想は必須です。
KOTO様には遠く及ばないとは言え、そんなに下手糞な絵は書いてない・・・つもりですので。
・・・・・・そう言えば、話は少し飛ぶのですが蒼來様も絵をお描きになってみては如何でしょうか?
面白いし、私としても他者の絵を見ることはいろいろと参考になります。
下手糞だ、とかいう謙遜はいらないですから、一度試してみられては如何でしょう
・・・と言った所で今回はこの辺りにて時間切れ。
次回もこっち(姫君の寵愛)の更新に相成ると思われますが、よろしくお願いいたします。
では、アディオス!!
蒼來の感想(?)
珍しく、ゲンちゃん早期退場!!
第五使徒戦後、司令解任で退場は見たことありますが、死亡で退場は初めてだな。
鈴菜「と言う事は司令は・・・?」
冬月か陸奥だな・・・まあ新キャラの可能性もあるがね。
観月「そういえば、この回にも2人新キャラが出ていますわ。」
うむ。・・・でも片方カヲル君じゃあないかなあ?
少女(?)の方は新キャラか、使徒っ娘かw
鈴菜「皆、外見が綾波レイ?」
それ、市販フィギュアの方だろうが。普通の人解らんぞ?
観月「解る蒼來が異常ということですわ。」
グッ・・・・
鈴菜「まあそれはそれとして・・・ケンスケがいい目見てるのがなあ。」
ゲンちゃん曰く「彼女こそイレギュラー」のアキナと良い感じが・・・
委員長が叫びそうだw
で、シンジの心配をしてないアキナに「?」
観月「シンジ君は、どうなるんでしょうか?」
解らん、だがこの流れだと誰も救われない作品になるように思われてきた。
願わくは、子供達に幸あらんことを。