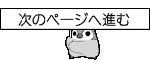「我々を怪物と呼ばずして、いったい何を怪物と呼ぶのだ? この美しくも醜い人間という種が怪物ではないというのなら、それ以上の怪物を知っているというのなら、どうか教えてくれたまえ。」
姫君の寵愛byダークパラサイト
第十三話:「大山鳴動」
「うわぁ!!」
それが、相田ケンスケが初めて乗ったエヴァの中で、初めて漏らした声だった。
悲鳴ではない。
明確な意味での感嘆符。
「冬月さん、こんなもの見ながら戦ってたのか!!」
少年の眼下には巨大なジオラマのような町が一面に広がっている。
見慣れた道路が、自分たちの住む町が、酷くちっぽけに見える程の高み。
巨人に乗っている、というよりも箱庭に入っていると言ったほうが正しいような感覚。
摩天楼並みの高さから眺める景色なのに、吸い込まれそうなあの違和感が無い。
ましてや高層ビル群の半分以上が消えた町を上空から俯瞰しているのだ。
それが不思議な感覚でないはずが無い。
「少しお黙りなさい、戦闘中よ。」
「うわっ!」
・・・が、そんな光景は見慣れているからか、それとも戦闘中に騒ぐ馬鹿を煩わしく感じたからか、リリスは必死にモニターを覗き込もうとするケンスケを酷くぞんざいに扱った。
具体的には・・・学生服の首根っこを引っつかんで自分のシートの後ろに放り込んだ。
然程力を入れたようにも見えなかったが、それだけで少年の身体は見事に後ろの内壁に叩きつけられた。
衝撃で内唇が切れ、少量の血がLCLの中に混じる。
赤い不純物がゆっくりと周囲のLCLに溶け込んでいくのが痛々しかったが、少女は既に正面の敵を見据えていた。
「戦闘中は激しく揺れるんだから、しっかり掴まってないと怪我するわよ。」
「ッ!!・・・り、了解。」
言葉に刺は無いが、少女の声には先ほどまでは感じられなかった気迫が混じる。
とてもではないが「既に怪我しています。それもあなたのせいで」・・・などといえる状況ではなく、ケンスケは出かけた言葉を飲み込みながら慌ててシートの横に突き出ている出っ張りに体を預けた。
「・・・?」
「ご、ごめんなさい!!」
その際、ほんの少し少女の胸に手が触れてしまった。
柔らかい感触に驚き、慌てて手を放す。
怒られるかと思い慌てて謝るが、その動作の何を気に入ったのか、振り向いたリリスは軽く笑みを浮かべている。
「謝ることは無い。つかまりやすいというなら胸でも局部でも、好きなところに触れているといいだろう。戦闘に支障は無いし、私も気にしない。」
からかっているような言葉とは裏腹に、その顔にはまるで子を持つ母のような笑みが浮かぶ。
否、正しく言うならば彼女とてケンスケの母である事に替わりは無いのだ。
ユダヤの民以外はリリスの子であり、当然ケンスケもリリスの子孫であるということになる。
彼女も母である以上、自らを頼る子には弱い。
悪戯っぽい言葉は、単に彼女の捩れた性格ゆえ。
「えっと・・・じゃあ・・・。」
結局、ケンスケは少し迷った後に彼女の腰に手を回した。
シートに身体を固定するための部位が無くやむを得ずとった行動だったが、出来るだけ意識しないようにしようとしても、筋肉の上に適度に乗った脂肪の柔らかさまでもがスーツ越しに感じられる。
胸を触ったときほどではないものの、罪悪感はある。
「それでいい。矮小であるものには矮小であるものの生き方がある。」
ただ、幸いだったのは本当にリリスが気にするそぶりを見せなかった事。
本当にどうでもいいと思っているらしく、ひとしきりケンスケの頭を撫で戦場に向き直るころにはすでに普段の戦闘狂の顔に戻っていた。
顔が見えなくなることで、ほんの少しだけ落ち着きが取り戻され、ケンスケも自らのいるべき位置を探り、少しだけ身体をずらす。
「じゃあ、いくわよ。」
少女の声は、遠い。
ここではないどこかを見つめ、その声は響く。
「へぇ・・・」
普段ならば何機もの大型旅客機や貨物機が出入りし騒音を撒き散らす西日本随一の国際空港も、人っ子一人いないとなればそれはそれでまた不気味だった。
勿論本当に人がいないわけではなく、巨大な待ち受けロビーやホールではサラリーマンや旅行客の変わりにいかにもといった風貌の黒服の男たちが大量に居並んでいる。
が、誰一人動かずまるで彫像のように固まっている人間を、果たして一人と数えていいものだろうか。
NERVの専用VTOLで空港に降り立ったシンジとゲンドウはそれら厳つい黒服の壁に押し出されるように、ゆっくりと空港の中央ロビーへと通されていった。
彼等の視線のどれもが、文字通り刺すようにゲストであるはずのゲンドウとシンジを睨みつけている。
(っぅ・・・)
NERVの保安部員が二人ボディーガードとしてついていたが、それだけではあまりに心もとなかった。
数も、武器の質も、地の利も、どれもこれもが圧倒的に不利な状況下にある。
この状況で行われる話し合いがあるとすれば、それは一方的な押し付けか・・・脅迫だ。
それでも言われる通りに歩かなければならないのが歯痒くてならない。
だが、ちょうど空港の中央にあたるロビーまで来た時、延々と続くかと思われた黒服の列が突然途切れた。
そのただ広いだけの空間の中央に、破れてしまうのではないかとこちらが心配してしまうほどにスーツを膨らませた中年の男が、二十人は座れるのではないかというような長椅子の中央に腰掛けている。
二百キロはあろうかという身体はぎっとりと脂ぎっており、首と顎の見分けすらつかなくなった顔は、息をする事さえ苦しそうにも見えた。
年のころは父と同じ程度なのだろうが、鋭く光る目を除けば似通った所は一つも認められない。
「久方ぶりの再会だというのに、中々の歓待だな。陸奥。暫く会わないうちにまた太ったとも見える・・・。」
その姿を確認したゲンドウが、ここにきてようやく口を開いた。
NERVでVTOLに搭乗してからここまで、錆付いて使い物にならなくなってしまったのではないかと疑いたくなるほどただの一度も口を開かなかったというのに、その口調は驚くほどに軽い。
いや、軽いというよりもこれは軽率と言ったほうが正しいのかもしれない。
この状況を、この異常な状況を、理解できているとは思いがたい。
「それだけ君たちの危険性が高まっているということさ、六文儀、いや、碇ゲンドウ。久しぶりだな、あえて嬉しいよ。」
怯えたようにあたりを見回すシンジと保安部員だったが、男は禄に気にする様子もなくゲンドウたちに笑みを向けた。
それに対し、ゲンドウもまた笑みを返す。
笑っていないのは保安部員とシンジ、そして黒服の男たち。
そして、運命の女神。
「高校の卒業式以来か・・・私が涙に咽ぶとでも思ったか?陸奥。」
「まさか。」
のっそりとした動きと共に、男の両肩がゆっくりと上がる。
まるで肉が少しずれただけのようにも見えるそれが首をすくめる動作であったのだと気付くまでに、シンジは数秒の時間を要した。
その動作で周囲の黒服たちがゆっくりと動き始めた事には、まだ気付いていない。
「今日は答えを聞きに来ただけだよ、ゲンドウ。同窓会に来たわけではない。」
醜悪な男は、自分が畏怖の対象となっている事に気付いている。
気づいていて、そうあるように演じている。
だからこそ余計性質が悪い。
「それは良かった。豚と二人っきりでの同窓会など、こちらも願い下げだ。」
「ははは・・・変わらないな、ゲンドウ。・・・だが、今日ばかりは君のほうが部が悪いよ。・・・そこにいる少年をつれてきてしまった事は、君にとって最大の間違いで、我々にとっては修正のチャンスとなる。」
「息子が、何か?」
突然話に上がり困惑するシンジをよそに、旧友たちの会話は続く。
何か重要な案件を切り出そうとする肥満男と、笑ってはぐらかそうとするゲンドウ。
だが、力の差が圧倒的であるのなら、強いものは自分の考えを押し付けてしまえばそれでいい。
「君はしくじったんだよ、ゲンドウ。・・・確かにゼロは強いかもしれないが、彼女は委員会からすれば異質すぎる。今回の戦闘では、無理にでも彼を、碇シンジを使うべきだったんだ。」
肥満男は薄ら笑いを浮かべながら立ち上がり、ゆっくりと右手を上げた。
それにあわせ、いつのまにか周囲を取り巻いていた黒服たちが距離を詰める。
ようやく気付いた保安部員たちも対抗するように銃を抜こうとしたが、狙撃銃まで配備されていたのだろう。
何処からとも無く飛来した弾丸に二人ともが胸を貫かれて一瞬の後に絶命した。
その二人には一瞥もくれず、陸奥と呼ばれている男は近付いてくる。
それに気圧されるように、シンジは一歩下がった。
「・・・おい。」
が、すぐさまその背中に詰めたい銃口が突きつけられた。
何も言葉は無かったが、それが動くなという意思の現れである事は明確だった。
「・・・逃げませんよ。」
小声で囁いてみるが、背後の男は端から信用する気など無いらしく銃口が逸れた気配は無い。
そうこうしているうちに陸奥はゲンドウの前まで来ている。
(でかい・・・。)
一瞬で、気圧された理由がわかった。
まるで肉団子のような身体は、父ゲンドウと比べても頭一つ分の差がある。
父の身長が小さいとは思わないが、陸奥に比べると中学生か何かのようにさえ思えた。
その身長、概算でも百九十近く―――
「また一段と太くなったな、陸奥。」
軽口を叩く。
「・・・そうだな。」
ふと、男の顔にやさしい顔が浮かんだように見えた。
だがそれも一瞬。
次の瞬間には、男の手が父の腹に押し付けられる。
(何・・・?)
初め、シンジにはそれが何かわからなかった。
それがあまりに小さく、男があまりに大きすぎたから、判断が一瞬遅れたのだ。
そして、理解したときには全てが遅かった。
「ゲームセットだよ、ゲンドウ。碇シンジの替わりはいないが、碇ゲンドウの替わりならばいくらでも用意できる。」
乾いた破裂音と共に、視界が暗転する。
男の手に在ったのはデリンジャータイプの小銃だった。
男が持つとまるで玩具のように見えたが、れっきとした本物であったらしい。
最後の瞬間くの字に折れる父の姿がはっきりと見えていた。
(父・・・さん・・・・・・)
意識が。
途絶える。
「ツアッッ!!」
肩が抉れ、フィードバックされた痛みがレイの全身を駆け抜けた。
また失敗した。
それを悟り、内心で舌打ちを繰り返す。
「・・・なんで」
間合いが計れないのか。
口に出してそれを語る事はしなかった。
より一層自分の弱さをかみ締める事になるだけと知っているから、代わりに背後の武装ビルに体を預け、体制の立て直しを図る。
シンクロしているが故に感じるビルの持つ熱気が、レイに生きていることを実感させた。
「とりあえず・・・落ち着かないと・・・。」
荒い息をつきながらも、まずは状況確認を急ぐ。
とは言え満身創痍の身体でこれ以上戦う事は最早不可能に近い。
咄嗟にATフィールドを張れた事が幸いしてついさっきやられた肩の痛みは殆ど残っていないが、戦闘が始まって未だ数分し語っていないというのに全身に数え切れないほどの傷を負っていた。
体力も限界に近い。
既にフルマラソンを走りきるのと同じ程度の体力を使っているのだろう。
LCLの含有酸素量では追いつかないのか、さっきからしきりに肺臓が稼動していた。
並みの運動ではびくともしない筈の心臓の鼓動が必要以上に五月蝿く、明らかに消耗している事が分かる。
「・・・何をしているのよ、化物。」
毒づき、背後の紫色の鬼に一瞬気配をやる。
だが、次の瞬間前方の敵が動いた。
言葉にする事が憚られるような不気味な身体から生えた二本の光鞭が無音のまま振りかぶられ、攻撃準備に入る。
「・・・ッ!」
咄嗟に前転してかわしはしたものの、凭れかかっていた背後のビルは真っ二つになっていた。
ここでもまだ、届く。
その事実にレイは愕然となった。
既にエヴァと使徒との距離は300m以上離れている。
それでも届くというのであれば、実質レイがこの化物の射程から逃れる術はないということだ。
これ以上下がれば・・・味方に殺される。
それが出撃の際に彼女と交わした約束であり、交わさせられた自白だ。
「赤木主任・・・。」
「何?レイ。」
「D-42区画にバズーカの弾頭だけを射出してください。」
「D-42?間違いじゃないの?あなたが今いるのは・・・」
「大丈夫です。D-42、よろしくお願いします。」
言い終えて、軽く息を吐く。
正直に言えば、少し破れかぶれになっていた感は否めない。
D-42区画とは今私のいる区画から見てちょうど敵を挿んだ対称区画の事だった。
取りに行こうと思えば、否応なしに奴の横をすり抜ける必要がある。
それも、武器が射出される一分後までに。
(できる・・・?)
自問する。
だが、答えは出なかった。
出来ない可能性のほうが圧倒的に高く、なまじそこまで到達できたとしても今度は未完成のバズーカ、それもその弾頭だけでやつを倒せるのかという疑問は残る。
N2でも倒せなかったのだから不可能だと考えたほうが正しいかもしれない。
それでも少しでも距離を詰めるべくクラウチングスタートの姿勢をとる。
なんという事は無いのだと、自分に言い聞かせる。
ここから射出予定地点まで600m。
その気になれば数秒で到達できる。
そのためのタイミングを、計る。
1・・・2・・・3・・・
頭の中でゆっくりと数を数え始める。
相手が動かないなら、それでいい。
このままここで時間をつぶし、化物の帰りを待つ。
だが、動くのであればレイとて動かないわけにはいかない。
史上最悪、いや、それは言いすぎかもしれないが、有史以来あまり例の無い短距離走となるはずだ。
そのときを、じっと待つ。
9・・・10・・・11・・・
敵は動かない。
レイは、動けない。
張り詰めた空気が重く、嘔吐感すら催してくる。
操作用レバーは長く握り緊めていたせいで体温と同じ温度になっていた。
15・・・16・・・17・・・
だんだんと、このまま敵が帰ってくれるのではないかという気になってくる。
だが、変な気は起こさないほうが身のためだ。
その一瞬の緩みが、死に直結する。
「まだ・・・まだ・・・。」
口にしながら、相手を睨みつける。
そして、脳内でのカウントがちょうど20を数えたとき、ようやく敵が動いた。
光に覆われた鞭が、大きく後ろに下がる。
その瞬間を見逃すことなく、レイは一気に前に向かって飛び出した。
引かれた鞭が相手を捕らえるまでの時差、およそ0.5秒の間隙を縫うように走る。
一撃目は、足元への一撃だった。
ただ、それ自体は予測がついていればかわす事はそう難くない。
案の定、レイも軽いジャンプだけでその一撃に対処して見せた。
その速度はいささかも揺るがない。
残り、150m。
振るわれた鞭が右であるというなら、抜けるのも右でいい。
そこにはもう鞭は無い。
戻すだけの、時間が無い。
そう見切りをつけ、走る。
だが、この期に及んでまだ彼女は思い違いをしていた。
この使徒の攻撃は変幻自在。
鞭が一度戻さねばならぬものであるなど、そのようなルールは存在しない。
「な!」
ゼロ号機の走りが、唐突に止まった。
その目線の先には、もう一本。
否、先ほど繰り出された鞭は消えているから正確にはやはり二本しか生えていなかったのだが、少なくともそう見えるという形でもう一本、これまでには無かった光鞭が生えていた。
それも、完全に引き絞られた状態のままで、だ。
「そんなの・・・。」
このようなタイミング、確認できたからといってよけられようはずも無かった。
引き絞られた鞭が放たれるのを、呆然と待つしかない。
その時間差、僅か0・3秒。
永遠にも思われる一瞬が、駆け抜けていく。
そして、
「!!$#!$!”!」
声にならない声が、レイの口から洩れた。
それは紛いも無い悲鳴。
胴体を生きたまま引き裂かれる痛みに対しての、恐怖と絶望の叫び。
司令部からの神経切断は、全く間に合っていなかった。
神経が焼けきれてしまえば、実際に無い痛みであったとしても身体はその痛みを記憶してしまう。
頭が理解するまで、痛みは残る。
表皮がその熱で破れ、その下にある真皮が蒸発し、さらには筋肉質までもが焼かれていくという、常人の想像をはるかに絶する痛みが、レイを襲っていた。
「がぁアアぁァああ!!!!」
プラグの中、腹を抑えのたうちまわるが、傷があるのはEVAだけなのだから抑えても痛みは引かない。
意識を飛ばしそうになりながら、それも思うようにいかないという無駄な時だけが過ぎる。
「・・・五月蝿いわよ、覚醒者。」
だが、絶対零度の言葉が急速にレイの意識を現実に引き戻した。
「勝手に出てきて、勝手に無謀な突撃して、勝手に戦線離脱して、何がしたいの?」
言葉は頭の中に直接聞こえてくる。
見えぬはずの王が、まるで目の前にいるかのように映る。
「!!&!%!*?!!」
そして、次の瞬間最早痛みとさえ呼べない、本当に全身の神経が妬き切れてしまうような痛みが再度レイに襲い掛かった。
言葉と同時に、強制的に神経接続が戻されたのだ。
途中の必要プロセスを全て省略し強制的に意識をEVAの中へと戻されたらしく、五感の内二感、すなわち触覚と味覚はその瞬間全ての細胞が完全に失われてしまい再起不能となっていた。
幸い先頭にはあまり影響が無い感覚であったものの、安全対策も何も在ったものではない。
こんな事をされたら。
これほどの痛みを与えられたら。
どのような人であっても狂ってしまう。
駄目になってしまう。
「そのままこいつを抑えてなさい。すぐに終わらせるから。」
なのに、狂王は更なる要求を繰り出してくる。
かろうじで残った視力で確認すると、自分のすぐ横に紫色の装束を纏った鬼が立っていた。
その姿、目の前の使徒よりもはるかに恐ろしい。
そして、その使徒の武器、光鞭はというとレイの、正確にはレイの搭乗しているEVAの腹の中ほどで止まっていた。
もともとが勢いをつけて相手を打ち据える性格の武器であったため、攻撃力が足りなかったらしい。
腹部から内蔵がはみ出している映像は正視に絶えるものではなかったが、不幸中の幸いとでも言うべきか、先ほどの無茶な神経接続のせいか痛みは全く感じなかった。
「ほら、ぼうっとしてるともう一本来る。」
リリスの言葉は痛いぐらいに正確だった。
その言葉と寸分違わず左の鞭がゼロ号機の胸に炸裂する。
痛みは無かったが、その光景はさらに凄惨なものになった。
血肉が散り、構成物質の一部としての肋骨が剥き出しにされる。
それでも、上官命令としてのリリスの命令を実行するべく両手を上げ、緩慢な動作ではあるが体の中に食い込んだ鞭を引きずり出した。
念のためATフィールドは張っていたが、無くとも痛みを感じる事は無かっただろう。
痛みを感じるための神経など、何処にも接続されていない。
自分のものとも思えぬ肌がじわりじわりと焼けていくのをただ眺めるだけだ。
「これで・・・いいの?」
「ええ、上出来。後で楽に殺してあげるわ。」
この戦闘が始まって初めて、本気で嬉しい言葉だった。
それ故に力が入る。
握る力が強くなる。
「けど・・・。」
このころになってようやく現れたバズーカ弾頭には目もくれず、両の武器を封じられ身動きが取れずにいる使徒の横をすり抜けるようにしてリリスは使徒の後ろに降り立った。
初号機の手の中で逆手に握られた二振りのプログレッシブナイフが戦場の空気に呼応し唸りを上げる。
その上で、まるで抱擁して見せるかのように、初号機は背後から使徒を羽交い絞めにした。
「とりあえず、今はこっち。」
暴れ、もがく使徒をものともせず、言葉と共にナイフが振るわれる。
刃渡りだけでも十メートルを越えるナイフが、しっかり二本。
背後から抱きかかえるようにして接近した初号機の手によって、シャムシエルという名の使徒はコアにそれらの深い爪あとを残す。
ギャギャッ!という金属を切り裂くような音が聞こえ、暫くの痙攣行動と一瞬の静寂の後、戦場は呆気なく沈黙した。
ほぼ、即死。
人間にしてみれば心臓にナイフをつきこまれ、その上三つに引き裂かれたような状態だ。
如何に使徒の生命力が強かろうと、こればかりはどうしようもなかった。
「シャローム、シャムシエル。」
初号機から発せられた別れの言葉は、聞こえていなかっただろう。
だが、そんな事は使徒にとってもリリスにとっても、そしてレイにとってもどうでもいいことだった。
今重要なのは、これで戦闘が終わったということ。
自分が死にかけ、ゼロ号機が大破したという事の他はこれといった被害も無く、そつなく戦闘が終わらせられたということ。
そのことに安堵し、普段の彼女であればあまりしない溜め息を吐き。
そこで、ありえないことが起こった。
「雑魚にしては良く持ったじゃない、覚醒者。」
このとき、今日という日が始まってから初めて、それどころかNERVの発足以来初めて、リリスの顔がモニタ上に映し出されたのだ。
真っ黒な長髪が水の中を漂い、その後ろには眠るように気絶している少年の姿も見える。
その映像は司令部にも届いていたらしく、ざわめきやどよめきが、レイの搭乗するEVAのコクピットの中で広がっていった。
戦闘中の冬月アキナ(リリス)が自らの映像を他者に送る。
その一点だけでも破格の出来事であるというのに、こともあろうに少女の姿をした王は自らの最も嫌う相手の前で少年の頭を優しくなでさすって見せたのだ。
誰もが皆、自分の目を信じられずにいた。
その映像を、ただただ凝視する事しか出来ず、その姿が本当のものであるのかと自分の目を疑ってしまう。
だが、その事をいったい誰に責められようか。
これほどに明確な映像になっていても、少女の性質を少しでも知るものなら困惑してしまう。
「・・・。」
それは、レイも同じだった、
しばし絶句した後、眉を顰めてみせる。
「何?」
「意外。あなたにそんな顔が出来るなんて。」
「覚醒者、お前私を何だと思っていたの?」
「別に・・・。ただ、珍しいと思っただけ。」
言いながら、内心でレイは首をかしげていた。
普段ならば激昂してすぐにでも襲い掛かってきそうな会話だが、不思議とその兆候がない。
この会話の間に成された反応は、せいぜいが軽く首をすくめてみる程度だ。
なんとなく、張り合いが無く、結局調子がおかしいのだと判断する。
理由は一つしか考えつかなかった。
かすかに見覚えのある気がしないでもない、眼鏡の少年。
彼が全ての原因だろう。
ただ、名前がわからなかった。
「・・・その子、誰?」
だから、訊ねた。
「これ?ケンスケよ。」
「ケン・・・スケ?」
なのに、言われてもなお、分からない。
首を傾げるしか出来ない。
NERVの職員は制服のはずだし、こんな時間に外に出ている理由がわからない。
となると外部の人間ということになるのだが、そうなるとレイにはお手上げだった。
何しろ今の内閣最高責任者が誰かすら分かっていないのだ。
名前だけでそれが重要人物であるのかそうでないのかを判断するのは不可能だった。
「相田 ケンスケ・・・お前の同級生なのでしょう?」
心底あきれたらしく、リリスはカメラを掲げながら溜め息を吐いて見せた。
それでようやく、レイはその少年が自分のはるか後ろに座るクラスメイトであった事に気付いた。
いつもいつも教室で馬鹿騒ぎを起こしている人間だ。
以前には写真の撮影許可を求められた事もある。
だが。
だが何故彼の頭をリリスが撫でているのか。
そこに明確な説明を与える事は出来なかった。
つながりが、なさ過ぎる。
「リリス・・。」
「何?」
「抱いたの?」
「な!!」
漠然とした思いのまま、訊ねる。
ただ、聞きながらレイは自分でその結論を消去していた。
リリスが抱くにしてはあまりに容姿が若々しく、まだ子供といってもいい容姿だ。
おそらくは他の理由。
ゲンドウか、はたまた他の彼女への命令権をもつものからの命令だと判断するのが妥当な所だろう。
そのような人間が多くいるとは思いにくいが、かといって全くの皆無というわけでもない。
リリスは無言のままだったが、無言が彼女の肯定となりえない事を、彼女は良く知っていた。
「まあ、良い。」
そして、思い出す。
つい先ほど交わした約束と。
先送りにされた結末の事。
言葉が頭の中で反響し、不思議な音となった。
だが、そのことに違和感を覚えながらも、ゆっくりと次の言葉を、許された要求を、紡ぐ。
「私を、殺して。」
突然の要求だったが、リリスはぴくりとも動かなかった。
リリスの劣化コピーとして生まれたレイの能力は、魂の転移。
時として復活と同義とされ、人の求めた極限に最も近い半永久的な生命を約束された能力。
だがそれほどの能力ですら、否、それほどの能力であるからこそそこには大きな制約が与えられる。
即ち、自死すべからず。
聖書の奇跡の顕現たる身のレイにとって、この制約は与えられて当然のものでありながら大きな枷となる。
能力の条件上どれほどの大怪我をおっても死に至るまでは復活が出来ないのだ。
故に、少女は他者に罪を背負わせる。
それを悪いと感じた事は無く、それは今回も同じだった。
共に戦った「仲間」であるならば、それは当然だと思っていた。
「そうね。でも、もうそれは終わっている。」
そのレイの姿に何を見たのか、少し寂しそうにリリスが笑い、そこで通信は切れた。
そしてそれっきりモニタは何も映さない。
通信用のモニタには、あちらが電源を落とした事を告げるシステムダウンの文字が明滅するばかりだった。
(どういうこと?)
最後の言葉の意味が理解出来ずに、黙考する。
が、答えはすぐに、思いもよらぬ方向から流れ出てきた。
LCLで満たされたプラグの中が、下から流れ出てくる真紅の血で見る見るうちに赤く染まっていく。
それでようやく、自分の首と身体が乖離していた事に気付いた。
副作用が残っていたために、それほどの痛みにすら気付く事が出来なかったのだ。
何しろ気付いた今となってもこれが現実であるのかどうかの判断が出来ない。
それでも意識は加速度的に飽和し、拡散していた。
(そういう・・・こと。)
その中で、レイは笑う。
なんとも彼女らしいやり口だと、自らの天敵を褒め称える。
出だされた罰は、魔女を狩る制裁の剣。
ATフィールドで形作られたギロチンだった。
あとがき
えっと・・・受験勉強が本格化し始める時期に今回の未履修問題によって超の六乗分の大打撃を受けたダークパラサイトです。
なんとその合計未履修時間たるや245時間! どちらかというと民主党を応援していたりした私ですが、今回ばかりは自民公明様々です。
・・・というわけで、 「あ〜、きっと将来私たちの世代は未履修世代とか言われるんだろうな〜。すっごく馬鹿っぽくって嫌だな〜。」 とかなんとか思いながらかきあげた第13話、如何だったでしょうか?
とりあえず今回の見所はレイの能力の解説とかなり地味〜に倒された第四使徒でしょうか?(なんだか使徒が通常の五割増ぐらいの強さになっている気がするのは気のせいですので触れないように。)
他にも伏線ともいえないような伏線を二つほど張ってはいるんですが・・・気付かないだろうと思われるので、別に探して頂かなくとも結構です。
では・・・・・・って、そうそうゲンドウとシンジ君が何故関西にいるのかは、気にしちゃ駄目です。
別に私が東京に言った事が無い事との関係なんてありませんから。
そういうわけで・・・再見!!
蒼來の感想(?)
はい、では改めて感想を・・・って、なんじゃこりゃあああああああ!!!
鈴菜「うるしゃい!!ミギストレート ☆(゚o゚(○=(−_−○」
うぉ!!(避けた)
観月「あらあら、御姉様はまだ、寝惚けていらっしぃますわ。(クスクス)」
す、すまん起こしたか。でもこれ見てみ。
鈴菜「なんだよ・・・(ヨミヨミ)・・・色んなことが同時に起こってるーーーー!!!」
観月「あら、ホントにですわ。」
・・・相変わらず冷静だな、観月。
まず、纏めてみよう。
シンジ攫われる・ゲンドウ撃たれる(死亡?)・レイ無残(希望通り?死亡)・アキナ暴走(?)・ケンスケ役得。
鈴菜「陸奥っておっさんが登場したな。しかもゼーレ関係者だし。」
観月「シンジ君はどうなるんでしょう?」
解らん。だが、当分はゼーレの駒扱いだろうな。
陸奥なのだが・・・どうも本部の司令になりそうだな。
鈴菜「へ?なんで?」
司令できるやつが他に居なそうだから。現在本部所属で、ゼーレの言う事聞くやついなそうだからな。
まあ、その陸奥も謎の爆発で・・・(´Д⊂)
観月「まあ、そんなに亡くなれる方が多いのですのね。」
鈴菜「・・・観月、蒼來が言ってる爆発ネタは、旧日本海軍の戦艦:陸奥のことだぞ。この陸奥とは関係ないから。(−−;」
・・・よく考えたら観月は天然娘だったな。ところで、あのヤエさんがまた暴走しそうなとこが・・・
観月「あらあら、次回は血の雨ですわね。」
・・・観月、ホントに天然か?