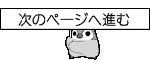「ハーモニクス誤差89%、殆ど完全に拒絶してますよ?」
高らかに、人はその目覚めを歌う。
「知らないわよ、彼女が大丈夫だというんだから大丈夫なんでしょう。シンクロ率はどうなの?」
「168%・・・前回戦闘中にたたき出した値からすれば低いですね・・・。」
それは悪魔の心の高ぶりを示すだけ。
そんな答えに、何の意味があるというのだろう?
「いいわ。後はパイロットが何とかするでしょう。さっさと発進準備に移って頂戴。」
「分かりました。ではこのまま引き続き発進準備に移ります。」
悪魔が戦場に立ったとき、人の世は混沌に落ちる。
それを知ってなお、人は彼等に縋ろうとする。
なぜか?
簡単だ。
彼等はただ単純に、強いのである。
姫君の寵愛byダークパラサイト
第十二話:「十人十色の恐怖心」
警報からちょうど二時間。
第334避難所では2−Aの面々を含む第3新東京市立第壱中学校の生徒たちがかなり退屈な時間を送っていた。
「おいお前たち!あまり騒ぐなよ!!」
引率教諭として一緒に避難所に入っているゴロウが声をあげるが、どこか疲れを感じさせる注意を聞いている生徒などいない。
それを知っていてなお、彼はおざなりな声をあげ続けた。
本人としてもこんな呼びかけに意味がないことぐらい察して入るのだが、一応の警告義務という奴である。
「は〜い。」
怒られない事を本能的に察しているのか、生徒たちの返事もおざなりだ。
言ったその先から忘れてしまっているらしく、避難所を満たす声のボリュームが落ちる事は無かった。
なにしろ緊急避難警報とは言え、セカンドインパクト後の空襲と違い攻めてくるのは非現実的な化物なのだ。
死ぬときは死ぬし、生きていられるときは何の影響もない。
いつ自分たちの上にN2や原子爆弾が振ってくるかといった心配とは無縁でいられるからか、はたまた極度の恐怖心を和らげるためか、殆どの人間は誰かが持ってきていたトランプ等のカードゲームで時間をつぶしていた。
一応避難所の中では静かにしなければならない規則があるのだが、そのようなものは学生しかいない避難所の中ではあってなきが如しものだ。
各個にいつものグループを作り、話に花を咲かせている様は普段の休み時間と大差は無い。
「まったく・・・。誰も聴いちゃいないな。」
分かってしていることでありながら、無視されていると思うといい気分はしない。
一頻り声を張り上げた後、ゴロウはいったん水を飲み、喉を潤した。
コップに並々と注がれた非常用飲料水が瞬く間に彼の胃の中へと消えていく。
「やっぱり私も注意しましょうか?時任先生。」
即座に空になったステンレス製のコップにもう一度水が注ぎ足された。
傍らに座った少女が配給所から持ってきたポットを片手に話し掛けてくる。
「ああ、ありがとう委員長。だがまあいいよ。私だってこいつ等が何を考えているかぐらいは分かってるつもりだ。」
いったん小休止とでも言ったところだろう。
彼は再度いっぱいになったコップをもう一度傾けた。
だが、今度は半分ほどまで減った所で飲むのをいったん止める。
「何だかんだ言いつつ不安なんだよ、やっぱり。幸いうちのクラスは犠牲者が少なかったが、それでも二人死んだ。高田も、陸奥も、死んだ。他のクラスじゃ、クラスの三分の一が死んだなんてところもある。」
「はあ・・・。」
目を閉じたまま上を向き、一言一言かみ締めるようなゴロウの言葉は重い。
「次は自分の番かもしれない。全員がそれを感じているんだ。連中、表面上こそ平気なふりを装ってはいるが、内心は穏やかじゃない・・・。」
ゴロウが目を閉じているのは死んでしまった二人を思い出すためなのだろう。
だが同じように目を閉じてみても、ヒカリには二人の面影を思い出す事ができなかった。
そんな記憶などどうでも良くなってしまうぐらい人が死んだのだ。
所詮ただのクラスメイトの一人でしかなかった男子の顔を覚えていろといわれても、それはどだい無理な話だった。
「セカンドインパクトのときも、大勢死んだ。そういえば・・・あの時もこうだったんだ。誰もがナチュラルハイになって騒ぎまわして、その後でとんでもない空虚に襲われて。・・・なあ、委員長、近くで人が死んだら、そいつの神経は麻痺しちまうのかな・・・。」
そうかもしれない。
泣き出しそうなゴロウを見ながら、ヒカリは軽く溜め息をついた。
現に自分も、悲しんでいない。
たった三週間しか経っていないというのに、死んでいった二人のために泣く気になれない。
運が悪かったのだろうという一言で全て片付けようとしている。
「辛いよな・・・老いたものより先に若い者が死んでいくなんてのは・・・。」
言われてみれば、ここ数日でこの担任もえらく老け込んだ気がする。
以前の彼は、こんな事を言うような人間ではなかった。
「もう、戻っても宜しいでしょうか?」
だが、そんな彼の言葉も今のヒカリの心を動かす事はない。
今気になっているのはもう絶対にここにもどることのない少年たちの事ではない。
それよりももっと早く解決しなければならないことが山のようにある。
「では失礼します。」
ゴロウの返事を聞くよりも早く、ヒカリはゴロウに背を向けて大股で歩き出した。
だが、その口には歪な歪みが生じている。
「何処行ったのよ、あの馬鹿・・・。」
三度目の点呼の時、教師には報告しなかった行方不明者が、実は数名いる。
相田ケンスケ
鈴原トウジ
この二人が、どれほど探してもいなかったのだ。
――――トウジ?ああ、あいつ達ならトイレだってさ・・・大方ケンスケにでも誘われて上に行ったんじゃねえの?とりあえずこっちにはいないよ――――
彼等の行方を仲のいい友人数人に聞いても、皆一様に同じような返事しか返さない。
皆、彼等二人は上に行ったという。
(そんなことって・・・。)
あり得るのだろうか?
以前のあの事件があって、あれほどの人が死んで。
それでも外に出ようとするほど、彼等は馬鹿なのだろうか?
「トウジ・・・。」
見回してみても、やはり影はない。
40mX50mという狭い避難所で、早々見失うとも思いにくい。
「馬鹿・・・。」
帰ってきてほしい。
五体満足なまま、いつものように、何もなかったかのように。
そう思うことは、贅沢が過ぎるのだろうか?
少女の眼前で、天使と悪魔が対峙していた。
天使は絵画に描かれるような美しい顔を持たず。
悪魔に空を飛ぶための羽はなく。
天使の頭の上に浮かべる光輪はなく。
悪魔の手に凶々しき武器はなく。
それでも毅然とした態度で、全てのものを見下すような暗い瞳とともにそれらはそこにいた。
「あ・・・ああ・・・。」
それはそれを知る者にとってもあまりにおぞましく、見上げる少女は戦慄のうめきを漏らす。
(助けて・・・。)
気絶し、動かなくなった友人を胸に抱いたまま、少女は震えていた。
何が怖いのか、何に怯えているのか。
何が正義で何が悪なのか、何もわからぬままに少女は動けなくなっていた。
少女と天使の間の距離は200m程。
だが、それは天使がその気になればすぐさまゼロとなる、あえて言えば限界値のようなもの。
逃げ出さなければ死あるのみだ。
(助けて・・・お兄ちゃん。)
それでも、少女は動く事ができない。
手元に抱いた友人のこともあるが、それ以上に恐怖に射竦められた身体が言う事を聞いてくれなかった。
(助けて・・・。)
戦場に不似合いな言の葉が、洩れる。
だが、誰に助けを求めようと言うのだ。
この戦場。
この禍々しき舞台。
踊る資格をもたぬものを、誰が・・・。
・・・・・・巨大な岩盤。
戦場からの流れ弾が、宙を舞う。
「ううぅぅぅ。」
菊花 ヤエは悩んでいた。
手札は残り四枚。
クラブのQ、ハートの8、ダイヤの6、スペードの3、
相手は残り三枚。
他のライバルたちは早々に勝ちぬけてしまい、残ったのは二人だけだ。
「どうしたの?早く出せば?」
気になるのは眼前の友人の不敵な笑みだ。
一体何を持っていればあれほどに自信満々な顔ができるのか、全く分からない。
セオリー通りに出すのであればスペードの3から出すべきだと思うのだが、それもどこか引っかかる。
「えっと・・・はい。」
結局ヤエは迷った挙句にダイヤの6を出した。
だが、その瞬間友人の相好が崩れた。
「ハイ、長考ご苦労様でした〜。」
言葉と共に出されたのはダイヤのエース。
さらに、それから間髪をおかずに4のダブルが提示される。
「あ・・・えあぁぁ??」
「あははは!! これでヤエの十二連敗〜♪ ヤエ弱すぎだよ〜。」
何が面白いのか、ヤエの友人たちは皆一様にどっと笑い崩れた。
その中央で、ヤエだけが目を白黒させている。
「えっと・・・つまり・・・。」
「勝ち目はなかったってこと。ごめんね、無駄に考えさせちゃって〜。」
「ええぇぇ!!そ・・・そんな〜!」
「あはははは!! いや、それにしてもほんっとヤエって勝負事弱いよね〜。剣道やってるくせに〜。」
パタン、と手札を捨てて崩れ落ちたヤエに、また周囲の皆が笑う。
手を変え品を変え、さまざまなゲームであそんでいるがヤエはことごとく負けつづけていた。
「剣道関係ないし、皆が強すぎるだけだし・・・。ユキなんてさっき5を出したときはパスって言ってたのに・・・。」
「ああ、あれ?あれはヤエが2を持ってる可能性があったからよ。でもほら、それはカエデが出して解決してくれたし?・・・何?ヤエってばそれを根拠に悩んでたの?」
「ううぅぅそんなの分かるわけ無いじゃない・・・。」
「カード覚えてないからそうなるのよ〜。・・・ねえ、今度は何する?ポーカーとかどう?」
「あ、いいね〜。あれならヤエでも毎回ビリって事は無いだろうし。」
「がああぁぁ!!毎回ビリじゃな〜い!!」
きゃっきゃっと、健康的な声が避難所の中で響く。
「はいはい。じゃあ次はポーカーってことで皆良い?」
「うん、いいよ〜。」
「まあ良いんじゃない? さすがにルール知らない人はいないよね。」
「あ、私正確な役とか知らないかも。」
「マジ?!えっとね、まず基本になるのがワンペアって言って・・・」
だが、その中に新しい転校生の顔はなかった。
そのことに少し。
ほんの少しだけ、ヤエの心が痛む。
(アキナもあんな呼び出し無視しちゃえば良かったのに・・・。)
あれ――冬月アキナが食事中に出て行ってしまったのは、本当に唐突に入った一本の電話のせいであり、彼女はそれが父からの呼び出しであったといっていた。
事実を全て話せばそういうことになるだろう。
だが、タイミングといい、その理由といい、あまりにも不自然な点が多い。
そもそも、学校に通っている娘をまだ学校が終わっていないにもかかわらず呼び出すような父親が本当にいるのだろうか?
もしいたとして、それが特別非常事態宣言の直前である確率は、一体どれほどなのだろう?
考えても答えは出ない。
ただ、彼女はその呼び出しに凄く嫌なものを感じていた。
あえて言う言葉もないけれど、出て行くアキナの顔が、シンジの前で見せる無邪気な表情とも、普段自分の前で見せるどこか頼りない表情とも、どこか微妙に違っていたように思えたのだ。
そう、それは、試合前の自分と同じどこか覚悟を決めたような・・・。
戦いに臨む戦士の顔・・・そう見えた。
それは、つまり・・・・・・
「どうしたの? ヤエちん。」
「え?・・・ああ、なんでもない。ごめんね、ちょっとぼうっとしてた。」
「もう、しっかりしてよ。チェンジ、するの?」
気がつけば、カードは既に配り終えられ、ゲームは始まっていた。
そのことだけでも、相当時間自分がぼうっとしていた事がわかる。
「あったり前じゃん!・・・ちょっと待ってね・・・。」
一瞬頭に浮かんだ考えを急ぎ頭の中で取り消し、ヤエは自分の手札に向かい合った。
そもそも、根拠があまりに脆弱すぎる。
今はまだ、何処も大変なのだ。
引っ越してきてすぐにE事件に遭遇したという事実だけを鑑みても、大変な状況は変わりなかっただろう。
(・・・帰ってくるよね・・・、アキナ・・・。)
手札の中から三枚を捨て、新しいカードを引く。
彼女には、祈る事しかできない。
カードの出も。
新しい友人の帰りも。
(せっかく友達になったのに、お別れなんて嫌だからね・・・。)
揃った役は道化師を含むスリーカード。
・・・悪くない。
状況は、必要以上に混乱していた。
突然地上に現れた二匹の鬼。
彼は、その二匹がそのまま戦場に臨むものだとばかり思っていた。
だというのに・・・
(どうなってるんだよ・・・・・・。)
前を、睨む。
「おまえ! 相田とかいったわね!!」
「え?・・・あ、うん。」
鎮座したNERVのものと思しきロボットから出てきた少女の口からケンスケが今まで聞いた事もないような声が、言葉が、洩れ出てくる。
「さっさと乗りなさい!お前が死んだらアキナが悲しむでしょう!?」
もはや日本語にすらなっていない言葉は、天からの啓示ではない。
甚く煽情的なスーツに身を包んだクラスメイト、新しい転校生の口から発されたれっきとした言葉だ。
だがそれは直訳すれば彼女は冬月アキナではない、ということになる。
そこにいるのはいつのまにかクローン技術が公に認められるなどの歴史的快挙が行われない限りは彼の知る冬月アキナと同じだというのに、だ。
「あの、君は・・・冬月さん・・・だよね?」
「あら、それ以外の誰かに見えるの?」
「あ・・・いえ・・・。」
―――少なくとも話し方だけは別人です―――
そう突っ込みそうになる言葉を危うく飲み込みながら、ケンスケは一瞬思案した。
そもそも、この少女は本当に「冬月アキナ」なのだろうか?
まずはそこ。
これがあの少女、明るくて、物腰も柔らかな、あの少女なのだろうか?
本質的に何かが。
何かが違う気がしてならない。
「早くこっちへ来なさい!! それとも何?自殺するためにそこにいるの?」
「違うよ!!」
だが、彼女の言っている事はどうしようもないぐらいに事実だった。
少なくとも、ここにいれば自分は死ぬだろう。
想像以上に戦闘は激しく、敵はすぐそこまで迫っている。
今は目の前の鬼に少し遅れる形で現れた青い機体が敵を押し留めているが、攻撃がここに到達するまで然程時間がかかるとは思いにくい。
だからこそ、次点はそこにあるのだ。
(どうする・・・?)
このままお言葉に甘える形で乗せてもらうか。
申し出を断ってシェルターまで戻るか。
どちらにも欠点はある。
どちらにも、特に前者には抗いがたい誘惑がある。
「早くなさい!!シャムシエルが来る前に!!」
差し出された手はあまりにも遠く、高く、到底届くとは思えない。
同様に、背後のシェルターまでの距離もあまりに遠く、そこへ到達できるとも思えない。
「いいの?!その・・・乗っても・・・。」
「そう言っているのだけれど・・・それとも何? 私と一緒だと欲情しちゃいそうで怖い?」
―――冗談でも一緒に乗るのは嫌? とか聞いてほしかったです―――
がっくりと頭を落としながら、それでもケンスケは一歩を踏み出した。
それは陳腐な英雄願望だったかもしれないし、ただ少女の色香に釣られただけだったのかもしれない。
が、それでも彼は選択したのだ。
後ろへではなく、前へ。
知らずに安穏と過ごす道ではなく、知って激動に身を焦がす道を。
「やれやれ・・・間に合ったみたいだね。」
優しげな声がする。
この戦場にはあまりに不似合いな、どこか愁いを帯びた声。
「この阿呆! 何考えとるねん! こんな所まで出てくるなんて・・・。」
聞き慣れた声がする。
自分のよく知る・・・泣きそうなときの兄の声。
もう駄目だと思ったのに。
今度こそ死んでしまうと思ったのに。
自分は、まだ生きている。
生きてここにいる。
「兄ちゃん・・・私・・・兄ちゃんたちのところへ・・・。」
少女は、手元に抱いた友人に身を隠すようにしながら恐々と上を見上げた。
その硝子のような瞳に真っ赤なドーム状の壁と、二人の少年の姿が映る。
怒られると思っていた。
お世辞にも誉められる行動でない事は知っていた。
覚悟はしていた。
持ち上げられた掌はそのまま自分の頬を打ち据えるだろう。
そう思っていた。
なのに・・・
「うん。頑張ったね、ナオちゃん。」
掌は頭の上に乗せられ、ゆっくりと数回・・・撫でる。
少女は眼を見張った。
そして、その大きく見開かれた目からは、そのまま涙が吹き零れた。
理解されるだなんて、思ってもみなかったのだ。
「兄ちゃん・・・。」
「ん・・・。」
助けに来てくれた。
助けが来てくれた。
そのことが、こんなにも嬉しいだなんて、知らなかった。
「ごめん・・・なさい・・・。」
「ん・・・。」
謝罪の言葉は、自然に洩れた。
溢れる涙は止まらず、声が震えて自分でも何を言っているのかわからなかったけれど。
この二人には、それでも通じる。
堕ちた天使の少年と。
実の・・・兄と。
「阿呆、謝るぐらいなら出てくるなや、ほんま・・・。」
兄は愚痴りながらも友人の身体を抱きかかえ、肩に担ぎ上げる。
それを見た少女もまた、ゆっくりと立ち上がった。
真っ赤なドームの中では時の流れも変わるのだろうか。
これだけ話しているのに、外の音が何も聞こえない。
それでも帰らなければならないのだ。
ここではなく。
自分たちのいるべき場所・・・家へ。
あとがき
えっと・・・まずは一周年おめでとう!!(誰も言ってくれないので自分で言っている&自分でも忘れていた)
紆余曲折、驚天動地、五里霧中・・・まあいろいろありましたが面白い一年でした。
さて、時期的には高校生は夏休みが終わり、社会人は盆休みなんてとっくの昔に終わり・・・まあ、楽しい事には必ず終わりがあるっていういい例のような時期ですね。
一年経って大きく成長する人、全く成長しなかった人、いつのまにか退化しちゃってた人・・・いろいろいると思いますがまた新しい労働の季節なのですよ・・・。
・・・というわけで私も自分の労働があるのでこのあたりで失礼します。
P.S.確か三話以上の同時更新なら感想はまとめて・・・でしたよね?これなら二話同時更新で済んでますよね?
蒼來の感想(?)
ひゅう〜〜〜〜〜〜〜〜〜、ドカッッ!!(着地?)
鈴菜「うわっ!!蒼來が飛んできた?!」
観月「あらあら、どうしたのでしょう?」
・・・ここの主人公にバイクで轢き飛ばされた・・・(−−;
鈴菜「・・・で、よく生きてるな。」
まあ、戦闘機だからな・・・代わりは幾らでもあるものw
観月「と言うか・・・姿が大型ジェット戦闘機の用ですが・・・?」
はい、レシプロ機からジェット機になりました。外見、能力は「F-15C」を参照してくださいw
鈴菜「何気に無駄なパワーアップのような・・・しかもそれレイの台詞・・・」
まあ、言いたかっただけだ。(−−;
で本編だが・・・
観月「外に出た組が対称的な扱いですわ。」
ケンスケは原作どおりか・・・シンジ&トウジ組がなんかカッコいいぞw
鈴菜「やはりシェルターのような閉鎖的空間では、考え方も暗い方向だね。」
だな。しかし委員長、あんたどうでもいいはないだろうがw
観月「・・・このお話だと潔癖症の方が居ないようですわ。」
まあ、戦争だからしょうもないな・・・
・・・でやっぱり原作通り飛ばされるのね、初号機。
鈴菜「その前にハーモニクスが滅茶苦茶なんだが・・・・」
観月「よく動きますわね。」
ああ、さて次回の反撃を期待して待ちますね!!