相模良哉 視点

玄関で抱き上げたハルカを、キスをしながら寝室に連れて行って
ベットに座らせる。
そしてお互い唇を貪り合いながら服を脱ぎ捨てた。
舎弟と仲良く話す姿はいつもの事なのに、酒の勢いか何となく
苛立たしくなった。
ハルカの気持ちを疑ったわけではない。
ただ、少しでもハルカの気を俺から他に移させるのではないかと
思うだけで、気が狂いそうになる。
ハルカは俺を見ていればいい。
俺だけを……
****************
生まれてすぐ親に捨てられた俺は、似たような子供が沢山いる
孤児院で育った。
一番古い記憶は『お父さんかお母さんの絵を描いて下さい』と
幼稚園で言われ、他の孤児院の奴らが院長の顔を描くのを横目で
見ながら、親などいないとその紙を破り捨てた事だ。
当時院長が嫌いだったわけではない。感謝もしていた。
だが、小学校4年生の時、院長が金を持ち逃げして孤児院が潰れた。
いきなり放り出された俺達は他の孤児院に移されたが、
その時からもう二度と誰も信じないと決めて生きてきた。
一日も早く誰の手も借りずに生きようと、考え付く限り何でもやった。
小学生の分際で盗みでも詐欺でも恐喝でも。
当然痛い目を見る事も多く、孤児院の隣にあった空手道場を窓から
覗きながら独学で体を鍛えた。
その上数知れない喧嘩を繰り返す事で、どんどん強くなっていった。
そして中学に入り、体が成長期をむかえると同時に孤児院を
飛び出し、夜の街をうろつくようになる。
中坊が独りで生きていく為にはそこしかなかったから。
相手が暴走族だろうがチンピラだろうが関係なかった。
とにかく買える限りの喧嘩は買って、勝てば金を巻き上げる。
何度も族に入らないかと誘われたが、元々集団で群れるのは
嫌いだった。
人数がいればいるほど裏切り者も増える。
そんな面倒に巻き込まれるのはごめんだ。
連日その日の分の食べ物を買える金さえあればいいと思っていた。
寝る場所は公園のベンチで充分だ。
だがそんな時、今の会長と出会う。
普通に夜の街を歩いているオッサンだと思い、
恐喝を仕掛けた俺の腕をあっという間に捻じ伏せる。
それなりに腕に自信があった俺は、周りにバラバラと音を立てて
近付いてきた連中を見て、相手を間違えた事を悟った。
すると即座に俺を連れて行こうとする奴らを、そのオッサンが
まぁ待てや、と言って止めた。
「お前が最近うちのシマを荒らしとった中坊か。」
殺されると覚悟した。
それ程心底凍りつくような目だった。
だが、それならそれでいい、とそいつの目を見返した時
「……良い目をしてる。まぁまずはうちに来て飯でも食え。」
と優しく笑いながら俺を立ち上がらせ、
そのままその後の全ての面倒を見てくれた。
誰も信じた事の無い俺が、唯一命を懸けて信じようと思ったのが
当時組長だった会長だった。
これから先はヤクザも頭が良くなくちゃいかん、と俺を大学まで
行かせてくれ、それなりの下積みをさせた後、
自分が会長になると同時にいきなり若頭まで引っ張り上げてくれた。
俺が背中に昇り龍を背負ったのもその時だ。
下界を見下ろし雲を呼んで雨を降らせながら、一気に天を駆け昇る。
その生き様を、人に見せる為ではなく自分の為に刻み込みたいと
思った。
組長は自分が若頭の時代から俺を可愛がってくれていたので、
俺が後を継ぐ事を難なく受け入れた。
当然面白くないと思う奴らもいたが、会長が本格的に習わせてくれた
様々な武道や、大学卒業後に散々見せ付けてきた株などの業績に
正面切って文句を言える奴はいなかった。
忙しく充実した日々だったが、何かが物足りないと思い始めたのも
その頃だ。
一見順風満帆に見えるのに、家で独りになると何故か溜息しか
出ない。
その頃には女を買っても、前戯の最中にどんどん興醒めするだけで
抱く事が出来ず、自分が男しか抱けないのだと理解するようになる。
だが、散々男を買って性欲の発散をさせていても、
心のどこかに空しさが残っていた。
そんな時会長が他の組の抗争に巻き込まれ、危ない!と思って
会長の前に飛び出した瞬間、日本刀で背中を斬られた。
そしてそのまま俺は意識不明に陥る。
次に目が覚めた時、一番最初に見えたのがハルカの顔だった……
うつ伏せに寝かされていた俺がふと目を開けると
そこには白衣を着た医者が俺の顔をじっと覗き込んでいて
俺が目を開けた瞬間花が綻ぶように笑った。
良かった、目が覚めたんですね、と。
その瞬間からハルカの笑顔が離れなかった。
そこに何を求めているのか自分でもわからないまま、
いつの間にか毎日飄々として回診に訪れるハルカを待つように
なっていた。
そのうち看護師達を連れず、独りで回診に来るようになったハルカを
迎え入れるようになり、背中を消毒する度に俺に触れるその指にも
自分のモノが反応するようになっていく。
それなのに俺の反応に全く気付かないまま、遊びに来ました〜、と
笑っては何だかんだと俺に構ってくる。
ハルカも俺と同種、男としか交われない奴だという事にはその頃
気が付いた。
ハルカの話を聞くのは楽しい。
こいつが何を楽しんでいるのか、何を嫌だと思うのか、
少しずつ俺に心を開いて見せてくれる事がだんだん嬉しくなってきた。
そしてそう思った時、初めて俺は自分がハルカを欲しているのだと
気が付いた。
俺はこいつに、今まで自分に与えられなかった全ての物を
求めているのかもしれない、と。
そう思い出したら止まらなかった。
渇き切っていた俺の心に、どんどんハルカの存在が染みて来る。
ハルカを俺のモノにしたくて、ハルカの存在で俺を満たして欲しくて、
俺はこんなに誰かから愛される事に飢えていたのだと感じる。
好きだとか愛してるとか、そんな生易しい感情ではなく
ハルカの存在自体を渇望している自分がいた。

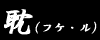
|

