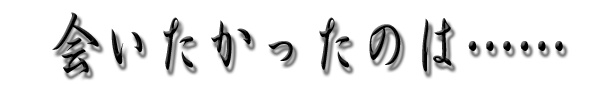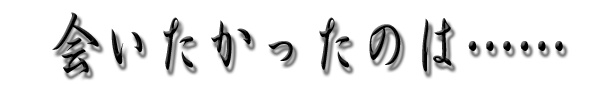|
<2>
ベッドの中で甘い声をあげながらも、怜の心はどこか空虚だった。自分の上にいる相手が誰だか分からないなんて言うのは、いつものことだ。ここずっと一人だけを相手にしていたからひさしぶりと言えばひさしぶりではあったが、怜はもともとそうして夜の相手を適当に選んでいた。だからそれで空しくなるなんてことはあり得なかった。今までなら。
なのに体は快楽を追っていても、心はどこか冷めている。相手はそんな怜の内心になど頓着せずに欲望のままに怜をむさぼる。以前はその相手の動きに伴って怜も熱くなることができていた。それなのに……。
「良かったよ。また、いいだろ?」
「……ん」
くしゃりと髪をなでてからシャワーを浴びに行く男に適当な返事を返しながら、怜は重い体をなんとか引きずり起こす。まるで鉛がつまっているようだった。
たばこをくわえて男がシャワーを浴びる音を聞きながら、自分に何がおこっているのかを考えてみた。今まで楽しかったはずの時間が、まるで楽しいと思えなくなった訳を。
夜、適当な相手を見つけて一夜を過ごすのは今までの怜にとっては当たり前のことだった。むしろ不可欠なことだったと言っていい。それが、まるで楽しくないどころか面倒で、疲れを伴うのはどういうことか。すっきりと欲望を吐き出したはずなのに、逆になにかが体の中につまって、凝っているような気にすらなる。それが一度だけではない、ここずっと続いているのだ。
だが考えたところでまともな答えは出てこない。ただ一つ言えるのは、シャワーを浴びているあの男ともう一度コトに及ぶ気にならないということだろうか。ここは早々に退散した方が無難かと怜はだるい体を引きずって服を着込む。男がシャワーから出てくる前に聞こえていないと知りながら帰るねと一言だけ言いおいて、逃げるようにホテルを出た。
「なー怜。お前その不景気な顔(ツラ)、なんとかならない?」
珍しく講議を寝倒した怜に高校の時からのもち上がりの友人が声をかける。返事代わりにくれられた怜の冷たい視線も何のその、がたりと音をたてて隣に座り、さらに言葉を続ける。
「ここ数カ月浮き沈みが激しかったけど、こんどは沈みっぱなしか? 例の年上の相手とうまくいってたんじゃないのかよ?」
怜が以前は多くの相手を渡り歩いていたことも、ここ数カ月は相手を一人に絞っていたことも知っている彼は、あらかたの事情を知っている。その年上の相手が昔つきあっていた相手であることも。
「うっせーよ、木谷。もうふった」
机に突っ伏してそっぽを向けば、木谷は嘘だろうとぐるりと机を回り反対側にやってきて顔を覗き込む。
「だってお前、あんだけ楽しそうに……」
「ふったっつったらふったの。お前には関係ない」
ばんっと大きな音が出る程の勢いで机を叩き、怜は立ち上がるとまくら代わりにしていた鞄をひったくるようにして席を立つ。
あきれ顔の木谷に見送られながらずんずんと歩いていって。
どれだけいらついているかなんて自分で分かっていた。沈み込んでいる理由も、何もかも。だけど怜にはそれをどうにかする手立てなどなく、またどうにかする気もない。どうにもならないことが分かっているからだ。
「……これじゃ、どっちがふられたんだか……」
認めたくないのに、そんな声がもれる。それでも心が、体があの男を求めているのを自覚するのにはこの数日で十分だった。どんな行きずりの相手も、その穴をうめてはくれなかった。
好きだと言われた。告白まがいのことを言われたのに、逃げてきたのは怜の方だ。だけど、恐かった。どうしようもなく恐かったのだ。何がかは分からないけど、そのままあの言葉を信じることは出来なかった。信じたいと思ってはいたけれど。
それでも、未練とでもいうように携帯の電源はずっと入れたままになっていた。だが、一度もあの男からの着信はない。それはつまるところ、相手にはもう連絡する意志がないと言うこと。
「もういい……どのみち、縁がなかったんだ」
一つ息を吐くと、怜は携帯を取り出して履歴と、裕一の電話番号を消去した。
ひさしぶりに訪れたあの店は、それでもいつもと同じ心地よいざわめきに満ちていた。帽子を目深にかぶっていったせいか、誰も怜に気付かない。姿を隠したかったわけではなかったけど、良く考えてみればつきあっていたはずの相手と別れたことになるのだ。下手をすると、質問攻めになる。いつまでつき合っているかと賭けの対象にすらなっていたと言う話を聞いたこともあったことだし。いや、だが良く考えれば、別れたなどということは二人の間のことなのだから、だれも知らない能性の方が高い。
「レイ、裕一をふったって?」
カウンターでざわめきに背を向けて飲んでいたら後ろから明るく声をかけられた。だが、かけられた言葉に少し目をむく。ふった? そういう話になっているのか。確かに、一方的にふったことになるのだろうが、それは怜と裕一しか知らないことだ。裕一がいったというのか? あの格好つけが? 怜には信じられなかった。
「この間来た時すっごいしおれてて。俺、聞き出しちゃったよ」
しおれてた? とまるで信じられないという顔をする怜に、確か以前裕一と関係があったその少年は真面目くさって頷く。
彼によると、数日前にふらりとあらわれた裕一は、無口に、不機嫌に一杯だけ飲んで帰ったという。怜のことを聞いてきた相手に、ふられたとだけ漏らして。
相手がそんな状態になっているとは思ってもみなかった怜は、心中複雑だった。確かにあれは、相手にダメージを与えるために起こした行動。もちろん、嘘偽りはどこにもない。すべて本当のこと。だが、しおれていたというその言葉にこんなにも心揺すぶられる。落ち着かない気持ちにさせられる。そして、どうにかしたいとまで瞬時に思ってしまう。もちろんそんな考えは理性に支配された感情がすぐに引っ込めてしまうけど。
「なんでふったの? けっこういい感じだったと思ったけど」
いい感じはいい感じだったのだろう。俺のこだわりを捨ててしまえば、と怜はひとりごちる。だがそのために近付いた。そのためにそばにいた。昔のあの思いを捨ててしまうことは出来ない。
「一時の熱病みたいなモンじゃない? もともと適当な付き合い繰り替えしてるような人なんだしさ。すぐ元気になるよ。のどもと過ぎればってヤツ」
きっと今までもそうだっただろう裕一の態度を言い当ててやれば、相手もそうかもしれないとうなずきはする。だが、やはり納得しきれないのだろう、なにか言いた気な顔だ。
「何?」
問いかければなんでもないとこぼし、少年はまたねと去っていく。怜はそこでまた小さく息をついた。
皆が皆、怜と裕一が一緒にいないのを不思議そうに見つめる。ほんの数カ月一緒にいただけで、まるでそれが当然のように思っている。今までだって気に入って数カ月一緒にいたことの有る相手はいる。だけどその時だってこんなふうには見られなかった。やっぱり別れたの? それが誰かと終わった時の周りの視線。こんなふうになぜ、と問われることはなかった。それこそ怜のほうこそ、なぜと問いたい。
それほどまでに濃密な雰囲気をただよわせていたというのだろうか。自覚はまるでないが。
思いを振り切るかのようにグラスをあけ、ふと気付くと携帯にメールが入っていた。登録した人以外からのメール。迷惑メールの類いかと眉を寄せて消去しようとして、ふと気付いてしまった。
「………………裕一さん」
機械に忘れさせても、人間の方が覚えていてはどうしようもない。それでもほぼ毎日、何ヶ月にも渡ってくり返されてきた裕一との電話やメールのやり取りで、相手のアドレスや電話番号は空で言えるようになってしまっている。つまり、せっかく機械に忘れさせ、名前が表示されないようにしていても無駄だった。意味のない数字や文字の羅列で相手を知ってしまうとなると、どうしようもない。
怜はしばらく着信を受けた状態の画面をじっと睨んでいた。そうしていればメッセージが消えるわけでも、望みのものにかわるわけでもないことは分かっていたけど。今さら何を言ってきたというのか。それが分からなくて、そこに書かれている文字がなんだか分からないのが恐くてメッセージを開くことが出来ない。
どれぐらいそうしていただろうか。意を決して開いたメッセージはとても簡単なものだった。
『15日。17時』
だが、それはそれだけで用を足すのだ。つきあっていた頃、二人の待ち合わせのメールはそれだけのものだった。待ち合わせる場所も決まっているから、いつもと違う所というのでなければ得に文字にならない。日にちと、時間。その日に待ち合わせるなら日にちすら入らないこともあった。
15日。それは三日後だった。今までならすぐに行けるか行けないか、メールで返事をしていた。だけど今日はそのままそのメールを削除してしまう。そうして気分直しにもう一杯飲んで、怜は店を後にした。
そのメールがちゃんと相手に届いているのかどうか、裕一に判断することは出来なかった。どうやって連絡を取ろうかと悩みに悩み、結局はずっと送っていたのと同じ形でメールを送った。電話をすることも考えないではなかったが、声をきいたとたんにきられそうな気がして、結局はメールにした。
会って何を話そうと言うのか、今の裕一には分かっていない。実のところ突き付けられた事実をどう処理していいかすら分かっていなかった。ただ、怜がそばにいないことがたまらなくつまらなかったのだ。退屈で物足りなくて。それをうめようと思えば、怜と連絡をとるしかないではないか。その後どうしていいのか分かっていなかったとしても。
待ち合わせ場所はチェーンのコーヒーショップ。裕一の会社に程近いところ。いつもそこでコーヒーを飲みながら待つのが好きだと
怜は言っていた。今もそうかどうかは分からないし、果たして待っているかどうかも分からない。
待ち合わせの時間は終業の時間よりも少し早い。出先からの直帰ということにしていて、電話一本入れるだけで会社に戻る必要もなかったから、得に問題はない。
約束の時間にはまだ少しあったが、裕一はコーヒーショップのトビラを開いた。ぐるりと中を見回す。怜はまだいない。
いつも座っていたあたりに腰をおろし、ただ怜がくるのを待つ。それはとんでもなく長い時間だった。コーヒーを飲む。腕時計に目を落とす。コーヒーを飲む。腕時計に目を落とす。コーヒーを飲む、腕時計に……。その作業をいったい何度繰り返したか裕一も分からない。ただ、その一回一回の間は、とてつもなく短くて。何度くり返そうとも時間が過ぎない。
「何してんの? まだ仕事中のはずじゃなかった?」
懐かしい、だが固い声に裕一が振り向くと、そこにはやはり懐かしい顔があった。来るかどうかが半信半疑だったせいで、いざ目の前にその顔があらわれるとなぜか慌ててしまう。
「……時間、決めたのは俺だろ。来れない時間は指定しない。それにさぼったわけじゃないからな。今日の仕事は終わった」
あっそ。と短く答えて、怜は裕一の前に座った。だが、コーヒーも何も頼んでいないらしくテーブルには何も乗っていない。そのうえ長引かせるつもりはないとでも言うように鞄は肩にかけたまま。コートも着たままだ。
「で? 何のはなし? 今さら俺になんの用?」
切り捨てるような口調でも、裕一は嬉しかった。ここに怜があらわれなかったら話が続かなかったのだ。怜がどんなつもりで出てきてくれたのか彼には分からなかったが、この状況は十分に活用しなければならなかった。
もう一度怜を手に入れたければ。
「好きだ」
どう伝えるか。悩んでいたはずなのに答えを出す前に勝手に言葉が出てきた。相手が面喰らっているのはもちろん見えているが、それすら気にしていられない程、裕一はただ自分の言葉と心を伝えようと必死だった。
自分を凝視したまま、声もなく面喰らっている少年がいる。呆れたのか、腹をたてたのか、そのまま何の返答も帰ってこない少年に裕一は再度「好きだ」と言を重ねた。少年のからだの前に所在な気にテーブルに置かれている手をとり、さらに言葉を重ねる。それだけのことで、少年の顔が見る間に赤くなっていった。
「なに寝ぼけてるんだよ。あんたが好きなのは俺の体だろう」
その怜の声は少し大きすぎた。一斉に視線が集まり、彼自身も自分の失敗を知る。そのまま口元に手をやってうつむいたかと思えば、今だ手首を捕らえたままの裕一の腕を振払おうとぶんと手をひとふりする。そうして逃れていこうとする少年を捕まえなおし、裕一は席を立ち上がった。そのまま彼の手を引いて店を出る。
「…っ、はなせよっ」
まっかになって、必死で振払おうとしているように周囲には見えたかも知れない。また、本人さえ振払おうとしていると思っていただろう。だけど裕一にはその行為がそこまでの拒絶を示していないということは、断固とした態度で振払われなかったその事実で明らかだった。もし本当に怜が裕一を振払おうとしていたのなら、それはすでに果たされていたはずだからだ。
「話を聞いてくれるなら、放す。……どうする?」
腕をぐいと引き寄せ顔を近付けて囁く男に、怜は頷くしかなかった。
「それで、なんでこんなところ?」
そうして手を引っ張られたまま連れて来られたのは裕一の部屋で、怜はひとしきり文句を言ってから出された紅茶に手を付けた。文句を言い過ぎてのどが乾いたのだ。
「別にホテルでもどこでも良かったんだけど。あの場所であのままだと思いきり文句も言えないだろう?」
それは確かにその通りなので、怜は仕方なく口を閉じる。最前、大声を出して注目を浴びてしまったし、それは別に怜の本意ではない。
「それで、話ってなに?」
まるで少し前、通うようにここに来ていた時のように空気が和みかけて怜は慌てて話題を戻した。彼自身も、自分がどれだけ強がっているか分かっていた。このところずっとつまらなかったのも、イライラし続けていたのも何が原因か嫌と言う程分かっている。それでも。
それでもこの男だけはダメだと思っていた。今までのことを考えれば当然だ。なのに、先程言われたあの言葉が例え用もない程に嬉しい。懲りると言うことを知らない自分に、怜はため息もでない。
「好きだ。……どうしたら俺の言葉を信じてくれる?」
無理、とすっぱり言い切ることが出来なかったのは、自分の中に目の前の男に対する気持ちが残っていたからだ。それを理解しているだけに怜はたまらなかった。だけど、それは絶対に認めたくはない感情。でなければ、先日の告白は無意味になってしまうような気がするのだ。正確には無意味ではなかったかも知れない。言わなければ彼の目の前にいる男はそのことに気付きもしなかっただろうし、下手をするとあの時の少年が彼を恨んでいたことにすら気付きもしなかっただろう。それに実際、まるで信じていないわけでもない。少なくともあの時、そして今裕一が怜に思いを寄せていることは疑っていない。ただそれがいつまで続くのか、明日さえも信じることが出来ないのだ。
「俺がずっと怜のことを見ていたら信じることができる? それとも、他に何か必要か?」
尚も言いつのる男に、怜ののどはつまって言葉が出てこない。別にずっと自分を見ていると言う約束が欲しいわけではない。そんなものは誰にだって出来ないことだ。
「答えろよ、怜」
言いながら、裕一は少年をベッドの際にまで追い込み、気付いた時には少年はベッドに押し倒されていた。上から顔を覗き込み、伺うようにされては返事も限られてくる。それに目の前の相手は、肯定の返事しか望んでいない。それ以外のいらえをきく気もない。
あんなことがあってなぜそこまで大きく出れるのかと考えてみて、結局自分が悪いんだろうと怜は息をつく。自分が、目の前のこのどうしようもない男のことが好きだから……。そしてそのことが相手の男にも分かっているから……。
「お前が好きだよ、怜……」
丸め込まれている、そう思いながらも、迫りくる唇をさけることが出来なかった。怜と名前で呼ばれる度になんとも言いがたい感情が少年の胸につもる。それは嬉しさではなく、悲しさでも腹立たしさですらない、何か。虚勢を張って、必死に保っていたのもが壊れる音だったのかも知れない。
「おまえさぁ、前の人とより戻したっつってたろ? らぶらぶしてるはずなのに、なんでそんな機嫌悪ぃんだよ?」
怜が友人にそんなふうに言われたのは裕一に呼び出された日から三ヶ月程たった頃だった。一応心配してくれていたから、と経過報告をしたのが間違いだったのかも知れないと思いながらも、やはり以前と同じく景気の悪い顔を相手に向ける。
「面白くないんだから仕方ないだろ。丸め込まれたような気分なんだよ」
吐き捨てるように言って、怜はコーヒーをやけで一気飲みする。目の前の友人がどれだけ自分のことを気にしてくれていたかを知っているから、席を立って帰ってしまうことも出来ない。砂糖もミルクもいれ忘れたインスタントのコーヒーは、胸焼けを起こさせる不味さだった。
そう、実際丸め込まれたのだ。あれから三月たった今現在の状況を冷静に分析すればそれ以外の答えは出ないだろうと怜は思う。何しろ裕一はすでに何度も別の人間とベッドを共にしている。怜にはばれていないつもりだろうが、おそらく彼は相手を全て並べることが出来た。
口先で、体で丸め込まれたと怜が思っても無理はない。しかも、それが分かっていてもなお、少年には裕一を思い切ることが出来ないのだ。昔、ひどいふられ方をしたのに忘れることが出来なかったように。考えるとだんだん嫌な気分になってくるので、ふだんの怜はなるだけ思考をそこに向けないようにしている。それが、友人の言葉で裕一の所業が蘇ってくる。いや、繕っても仕方ない。どうしたっていつもあのろくでなしのことが頭にあるのだ。
あれだけ大騒ぎをして好きだと言った癖に、すでに二股三股。それが面白いはずがない。面白くないのに、別れを切り出せない。それだけの気力も体力も、根性もなくなっている。好きなのだ、あの男が。そんなどうしようもない相手だと分かっていながら。
これなら気になって仕方ない状況で、再び出会っていない方がましだったかも知れない。あるいは、あんな言葉にほだされないか……。
だが、他でもない怜が、それは無理だと知っていた。
あの男にずっと会いたかった。
それは、好きだったから……。
たとえどんなにひどい男だと知っていても、忘れることが出来なかったのだから……。
END
|