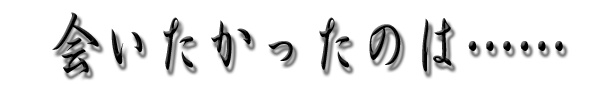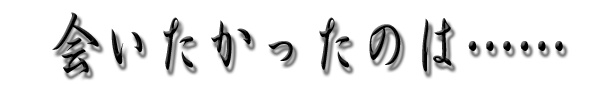|
<1>
「俺の名前? レイだよ。そう呼ばれてる。あんたは名前、教えてくれないの?」
青木怜(あおき・さとし)がそのバーに通うようになったのは、ほんの些細な理由からだった。
今だ成年を迎える前であったというのに、彼の夜遊びはすでに習慣と化していて、酒もたばこもすでに日常だった。だがその店は今だ二十歳に手が届かない怜には敷き居が高いような気がして一人で入ることを躊躇っていた。一度、人につれられて入ったことがあったが、それっきりになっている。そんな店に入ったのは、ふと見た知った顔の後ろ姿を思わず追ってしまったから。店に入るとか入らないとか。そんなことを考える前にトビラを押してしまっていた。
知り合いと言って、とても仲がいいとか、追い掛けて声を駆けるとかそう言った関係ではない。随分昔に、半年程関係があっただけの相手。それでも怜には忘れられない相手だった。
声をかけるつもりがあったわけではない。もともとひどいふられ方をした相手だから、そんな勇気は持ち合わせていなかった。それでも結局、入りにくそうだと思っていたその店は意外と雰囲気が良く、気に入って通うようになっていた。週に一度、金曜日か土曜日。カウンター席で一、二杯の酒を飲むだけだが、それは怜にとって欠かすことのできない、楽しい時間になっていた。
店にくる客の八割が男で、似た者同士があつまるのだろう、そのほとんどはゲイだった。それ以外の客も、そう言った物事に偏見を持たない者がほとんどだ。偏見があっては、この店にはリピーターとして来れない。そんな雰囲気があった。それも怜が気に入って通うようになった理由の一つだ。
高校に入る頃には彼は自分の性癖に気付いていた。本気に慣れる相手を探してとっかえひっかえ、何人もとつきあってはみたけれど、それらは全て長続きしなかった。ならばと今はステディな相手を作ることを諦め、幾人かのセックスフレンドがいるだけだ。ほとんどが学校の上級生だったそのセックスフレンド達も、この店にくるようになってあらかたメンバーがかわった。この店の常連になるような、大人の男に。
そんなふうにしてその店に通うようになって、数カ月過ぎた頃だろうか。相手のことを、怜はいつも気にはしていた。だけど自分から声をかけようとは思えなかった。いつも一緒にいる相手が違うその彼に自分から声をかけることが、勝ち負けの問題ではないと分かっているとは言え、自らの負けを認めることのような気がしたのだ。だからこうして時々眺めることが出来る状況と言うのに、怜は十分満足していたのだ。別に何をするでもなく、見ているだけ。それでいいはずだった。そうすれば傷付かずにすむと自衛していたのかもしれないと怜は後になって思う。
それなのに、だ。
声をかけてきたのは相手の方からだった。完璧なナンパの口調で名前を聞かれたのだ。驚いて一瞬返事がおくれたが、それでもなんとか不振に思われない程度に笑みを浮かべて名前を答える。通り名を教えただけで納得する相手に軽く失望しながらも聞くまでもなく知っている相手の名前を聞いてみる。かえってきたのはやはり知った名で、目の前で笑みを浮かべる相手を怜はにらみ殺したくなった。
そのまま適当に初対面らしい話をして、二人はそれなりに楽しい時間を過ごした。また会えればいいねと別れ際に携帯の番号を交換し、じゃあねとにこやかに別れる。
怜は相手からもらった名刺をその場でさも大切そうにポケットにしまい、一瞥もくれなかった。見なくてもそこに書いてある名前は分かっていたし、自分から連絡を入れる気はさらさらなかったから。
青木怜の初恋は中学三年の時だった。相手は受験対策で親が雇ってくれていた家庭教師の大学生。幼い時に母親が病気で他界し、仕事に忙しい父親をもっていた怜は、それでも別段ぐれたりひねくれたりすることなくまっすぐに成長していた。父親に愛されていることも、かつて母親に愛されていたことも分かってはいたけれど、常日頃の愛情にはやはりうえていたのだろう。その家庭教師がちょっとした関心を示すと、飛びつくようにそれにしがみついた。
勉強をおろそかにしたりしたわけではない。むしろ人一倍勉強はしたのではないかとその頃を振り返った怜はいつも思う。そうしないと、家庭教師がかわってしまうかも知れないという危機感はずっと彼に付きまとっていた。そうしてその、本来勉強をするために作られた時間は、彼等が互いを知るための時間に使われた。手をとり、息を触れあわせ、肌を重ねる。
そんな行為に溺れながらも、怜はそれをなくしたくはなかったからこそ必死で勉強もした。希望の高校にも合格し、これからが楽しい時間なのだと思っていた。期待していた。それなのに。
「お前はがんばったよ。ごくろうさん。じゃぁな、怜」
「なんでっ? なんでじゃぁ、なんて言うのさ? 俺のこと好きだって言ったじゃんか」
いったよ? 相手は簡単にうなずく、じゃぁと縋る思いで見上げる怜を見下ろしていたのは、それでも冷たい瞳だった。怜が今まで見たことがない程に冷たく、暗い。
「言ったよ。そりゃ、ベッドの中では礼儀みたいなもんだろ?」
何を今さらと言うようなその言葉に、怜はただ首をふる。自分はそんな礼儀、知らない。ベッド以外の場所でもずっと好きだと相手に伝えてきていた。それは伝わっていると思っていた。だけど……。
「じゃぁな、怜。元気で。高校入っても頑張れよ」
なんの感慨も見せずに金を受け取ってそう言い手をふる相手を見て、怜は初めて自分の気持ちが一方通行だったことに気付いた。この数カ月甘やかされ続けてきたから、今の今まで気付くことができずにいた。呆然と見送る怜を、相手は振り返ることすらしなかったのだ。
「……………やな夢」
一人暮らしのワンルームのベッドで目をさまして、掛布団から腕だけをだして目覚ましを止めてしばらくみの虫のように丸まっていた怜は、それでも息をつくとひょっこりと頭を布団から出す。自分がじっとりと汗をかいていることに気付いて、仕方なく起き上がった。
そのまま前日使って椅子にかけっぱなしになっていたタオルをひっさげ、バスルームに向かう。行儀が悪いと思いつつも移動する道すがらぽいぽいと着衣を脱ぎ散らかし、バスルームに入る頃には一糸まとわぬ姿になっていた。
熱い湯と冷たい水を交互にかぶって、体からは張り付いた汗を、頭からは嫌な記憶を洗い流す。水しぶきの中に一瞬蘇った記憶は妙に鮮明で、あの時まだ大学生であったはずの男が、先日声をかけてきた時の、スーツにネクタイの社会人とかぶる。それらすべてを振払うように冷水を頭からかぶり、怜はやっとバスルームを出た。髪から滴る雫を肩にかけたタオルで拭い、ふとテーブルの上に置いたままになっているくしゃくしゃの名刺に目をとめる。
昨日の夜、もらってきたものだ。名刺にあるのは男の名前と、携帯の番号とメールアドレス。ナンパ用に用意した名刺だということに気付いたのは、一度その名刺を握りつぶした後だ。結局捨てることができなくて持ち帰ってきて、テーブルの上で広げた時に気付いた。
野村裕一(のむらゆういち)。それが男の名前だった。以前と同じ笑み、同じ声、会話のテンポ……。
思い出すにつけて怜はどんどん混乱していった。あの男のことは恨んでいたはずなのだ。側にいてほしいと泣き叫ぶ怜を捨て置いていったから。だがその男を前にして、不思議と以前の感情はうかんでこなかった。ただ、自分が覚えているのに相手が覚えていないというのが不愉快ではある。正直、面白くない。でもそれだけだった。
「………あの人は、俺を覚えてるんだろうか? ほんの少しでも……」
そのつぶやきを、気付くと本気で考えていた。
あの男は、昔戯れに手を出した子供のことを、いったい覚えているのだろうかと。
その夜、野村裕一は珍しく一人だった。いつもなら男なり女なり、気に入った人間を侍らせている男が、だ。隣に腰掛けようとした人間がいなかったわけではない。何かいらだった雰囲気をただよわせるその肩に手を置き、声をかけて罵声や冷たい視線を浴びる勇気のある者はまるでおらず、結果彼の周りに人はいない。新しいグラスを持ったマスターが、時折前に立つのみだ。
それでも今日はまるで相手にする気になれなくてすべて そんな飲み方をしていて楽しいわけなどないのだが、本人も何が原因でこれほどまでにいらついているのかもわからない。仕事をしていても集中力に欠ける。遊びにでもくればなおるかと思ったのがうまく行かず、さらにイライラは募る。
「こんばんは、野村……サン? また会ったね」
相手のそんなイライラが分かっていて、怜はあえて声をかけることを選んだ。幾人もの男女をとっかえひっかえしているような男だ。普通に声をかけても何の印象にも残らない。だから、ずっと記憶に焼き付きそうな声のかけ方をした。前回、飲むだけでベッドまで持ち込ませなかったのも、全てそのためだ。
「ああ、レイ、だったかな。ひさしぶり」
振り向きざま、男は笑みを浮かべる。その反射はいっそ見事だと怜は喝采をあげたくなった。名前を覚えられていたことに満足げな笑みを浮かべ、怜はわざとらしいぐらいの仕種で裕一の周囲に人がいないことを確認する。それは遠巻きに様子を伺っている周りに、よってくるなと言う牽制にもなった。
笑みを浮かべた裕一が、怜の顔を見てやっと名前を思い出したことぐらい分かっている。その笑みの下に先日確かめることのできなかった風評を確かめてやろうという意図があることも。
「ずっと連絡、待ってたんだけどね。そんな気にはならなかった?」
自分から連絡をする気など欠片とてなかったはずの男は、少し恨みを込めた口調でそんなふうに相手を見上げる。返事をしたことで許可ととったのか、少年はするりと裕一の隣に腰掛けた。これだけのやり取りをしていれば、もう追い払う気もないだろうとい計算は実に正しく、裕一はただ怜が腰を落とすのを待つ。
「野村サンだって連絡くれなかったよ。俺だって連絡先、渡してたのにね」
にっこりと微笑んでお互い様だと牽制し、何くわぬ顔で飲み物を注文する。そんな態度が相手の気を引けばいいと思った。裕一が今どんな相手を好んでいるのかを怜は知らない。より興味を引くためにどうすればいいのか分からないから、自然いつもの自分が出る。
「一人なんて珍しいよね。いつも誰かと一緒にいるのに。それとも待ち合わせしてるところだった? 俺、邪魔しちゃってる?」
グラスを軽くかかげ、乾杯をねだるような態度を見せながらもそんな殊勝なことを口にしてみる。それでも邪気のない笑みを浮かべ、懐くようにするのは、結局いつもセフレに媚びを売る時とかわらない。それで落ちてくれるなら安いものだ。そうして返事が帰ってくる前にだめ押しをする。
「でもね、声、かけたかったんだ。だから謝らないよ? どうしてもっていう約束じゃなかったら、俺のこと選んでよ」
「別に約束があったわけじゃない。暇を持て余してたんだ。こっちこそお相手をお願いしたいね」
自分のあまったるい物言いに吐き気を催しながらも、相手から色好い返事をえたことで怜はひとまず満足した。新しい酒をもらい、グラスをあげて軽く相手のそれに触れあわせる。乾いた音が二人の間で響き、それはまるで試合開始のゴングのようだと怜はひとり息を吐く。
「本当はね、電話しようとしたんだ、何度か。でも、誰だ? なんて言われたらって思ったらかけれなかったよ」
普段ならこんなこと、気にもしないのにねと自嘲気味に笑い、新しいグラスをもらう。自分で自分の姿が見えないことを怜はこの時程感謝したことはない。万が一見えていれば、爆笑していたことだろう。こんな殊勝なやつ知らない、と。
「俺が君みたいな美人、忘れるとでも? ひどい言い掛かりだ」
さも心外だと言うように裕一は肩を竦める。そんなやりかた一つ一つがいちいち芝居がかっているとは思ったが、怜は取りあえず何の感想も告げずにやり過ごす。相手がその笑顔の下で何か計算をするのを感じたから。それでも取りあえず、次の一歩には進んでおくべきか。
「そう? じゃあ、今日はお詫びにずっとつき合うよ。……って、僕がそうしたいからだから、お詫びにはならないんだけどね」
クスクスと笑う怜を。裕一もまた楽しそうに見ている。
それが、二人の事実上の二度目出会い。
「ねぇ裕一さん。コーヒー入れてよ」
怜はソファに寝そべるように座っている裕一のひざに乗り上げるようにしてねだった。自分で入れろと追い払おうとするのを、必死でとり縋る。
「紅茶だったら自分で入れるけど。コーヒーは裕一さんの方が上手じゃん。ねぇ、入れてってば。ひまでしょ」
暇かと問われれば暇と答えるしかなかった裕一は、仕方ないなと立ち上がって台所に立つ。こんなつき合方をしたのは随分ひさしぶりだなと思い返してため息がもれた。
こんな、どころか、家に他人をあげた事自体が年単位で久しぶりだった。最後にここに誰かを入れたのはいつだっただろうと思いを巡らせ、結局思い出すことができなかったというくらいに。ずっと誰かとマトモにつきあっていなかったのは怜だけでなく裕一もだった。幾人かのセックスフレンドとの、気侭なセックスライフ。とうぜんその場限りでのことが多いから家に呼ぼうなんてことにはならない。怜は、ほんとうに久しぶりに家にまであげた相手だったのだ。なぜそんな気持ちになったのか分からないのだけど。
「レイ、座ってないでこっち来て手伝え。俺にカップ二つ持って行けっていうのか?」
ドリップに慎重にお湯を落としながら、背後の怜を怒鳴り付け、呼ぶ。そのままカップを出せ、砂糖とミルクを用意しろと次々に用事を言い付ける。まるで同居中の恋人同士であるかのような会話に、今までの自分とは違うと裕一は何やら反吐が出そうな嫌悪を感じた。だが、止めることはできない。
人使いが荒いとぼやく怜に、どっちがだとかえしながらも裕一はなにか楽しいものを感じる。こんな気持ちは初めて……もしかしたら昔に知っていたのかも知れないが、ずっと忘れていたものだった。
「俺たちってさ、つきあってるんだって。この間一人で飲んでたら、あんたの行方聞かれたよ」
「そりゃ、この状況知ってるヤツならそう言うだろ。で、なんて答えたよ?」
さすがにカギを渡すところまでは行っていないが、ふだんドライなその場限りの付き合いをしている者同士が、何度も逢瀬をくり重ねていれば、そんな噂も出ようというものだ。
「別にどうもしないけど? 俺達つきあってますーってフリしといた。裕一さんも調子あわせておいてよね」
「フリ、ね」
何となく帰ってくる答えを予想していたとは言え、なにやら物悲しいものを感じて裕一は軽く息を吐く。状況から言えば、つきあっているといって問題はないだろうと思う。先ほどのように甘えてコーヒーをねだるかと思えば、この冷たさだ。もちろん裕一だとてなんらかの意思表示を今までにしたわけではない。それでも他の誰よりも気に入っていることは分かってもらえていると思っていたし、怜にしても自分とは特別なつき合方をしているという自負はあった。
それなのに、だ。
怜はいつもどこかさめている。甘く喘ぎ、甘えてきている時でさえ心のどこか奥の方を閉じている。そんなふうに思うから、フリと言われても意外には思わなかった。寂しいとは思ったが。
「フリ、じゃ不満? でも裕一さん、俺のこと別に特別好きなわけじゃないでしょ?」
他の今までのセフレ達にくらべれば遥かに好きで本気だったのだが。
「俺は、俺のことちゃんと好きになってくれる人じゃないと嫌なの。裕一さんみたいなのじゃダメ。俺は一番お気に入りのセフレってところでしょ?」
ものの見事に言い当てられて、結局裕一はぐうの音も出ない。だが、怜と寝るようになって、他のセフレに手を触れていないのも事実だ。今までならつきあっているわけではないのだからといろいろな相手を一時に渡り歩いていた。それが、ここずっと怜ひとりしか相手にしていない。そのことを怜自身は分かってくれていないと裕一は密かにため息をつく。
「それに。俺、昔かなりひどいふられ方してるんだよね。だからよっぽどじゃないとのめり込めないんだ。がーってあつくなって、痛い目見ちゃったから」
大きなあくび混じりに眠そうに呟く怜を裕一は思わず揺すって起こしてまで話の続きを促してしまう。それは何故か気になることだった。聞かなければいけない。そして、聞いてはいけない何か。
「ん、だめ。また今度。眠いよ……。裕一さん、ほんと無茶するんだから……」
確かに夜通し無茶をさせたの裕一だったが……。つい今し方までハッキリ起きていて、コーヒーまでねだっていた癖に。
ころりと様子をかえ、気になる言葉だけを残して怜が眠ってしまっても、裕一の眠気はどこか遠くに行ったままになってしまった。
その後裕一が怜の話をきけたかと言うとそんなことはない。相変わらずの付かず離れずの付き合いの中で、体の交流だけが増えていく。終いには相手が何を考えているか分からなくても、どこをどうしたら一番気持ちいいかだけは分かるようになった。それを寂しいと思いはじめたのは裕一。
彼はある時ふと気付いたのだ。怜のことを何も知らないと。知っているのは携帯の番号と、レイという呼び名。どこが一番感じやすいか、どんなキスが好きか、そんなことだけ。本名も、年も、どこに住んでいるかも。そんな根本的なことすら何も知らない。自分は全て明かしていると言うのに。だけどこうして体だけの関係を重ねていて、今さらどうやって聞けば言いのかが裕一には分からなかった。
そして怜も、自分で何をどうしたいのか分からないでいた。今すでに彼は裕一に自分を十分印象づけているはずだ。名を明かせば思い出してもらえるだろうかと思ったことは一度や二度ではない。フラれたあの時の状況を話せば思い出してもらえるだろうかと言いかけたことも、やはり一度や二度ではない。それでも、覚えていないと言われるのが恐くて結局その言葉は口にのぼらせることができなかった。
「レイ。お前今いくつだった?」
昨夜も怜は泊まっていった。気持ち悪いからシャワーを浴びるのだとなんとか起き上がり、浴室に消えたのを見送って裕一はベッドでたばこをふかしていたところだ。ふいに戻ってきた少年に、思っていたことをふと訪ねる。
「……二十歳……ってことにしてるけど?」
ほんの少しの間があって、怜はいつもと同じ声音で不思議そうに首をかしげる。今まで俺のことなど何も気にしなかったのに、その目はそう語っていた。
「そんな目するなよ。恋人ってことになってんだろ? 年ぐらい知ってるだろうが、普通は」
「あ……そっか。そうだよね。えっと、本当は十九だよ」
まるで不意をつかれた、というのがぴったりの表情で、怜は髪から滴り落ちる水滴を拭う。その唇が自嘲的な笑みを浮かべるのに、裕一はうっかり気付かなかった。
「名字は?」
さらに続けられる質問に、怜はぎゅっと眉を寄せる。不快もあらわに、と言う程ではないが、なぜ今さらそんなことを、と言うのがありありと分かる表情だった。
「青木。……なに、ほんとに急に。何かあった?」
素直に答えながらも、怜は心配そうに顔を覗き込む。
「何かって……俺がお前に興味持っちゃ不味いのか?」
そんな仕種が不服で、裕一は顔を背けたばこのフィルターを噛み締める。自分の感情がどこを向いているのか分からなかった。急に、そう、本当に急に怜のことをなんにも知らないと言うことが不安になった。こんなにたびたび泊まりに来て、裕一に完全に体を任せてしまっているのに、どうしてそんな不安を覚えなければいけないのか。いや、それよりも何よりも、ただのセックスフレンドだ。なぜそんなことをいちいち考える必要があるのか。
「別に不味くはないけど、急だから。……もしかして、俺に本気になっちゃった?」
「………かもな」
ちゃかすような言い方が気にくわなかったが、そうかも知れないと裕一は思う。そう自覚するだけの材料が足りてきてしまっているのだ。
「冗談よしてよ」
鎖に繋がれるような決死の覚悟で口にした言葉であったと言うのに、思いの他かたい声がそれを遮る。それこそ冗談でもそんな声で否定してくれるなと言いたくなるような声だ。
「……そんなこと言われたら、俺もちゃんとこたえなきゃいけないじゃないか」
答えは決まっているけど。心の中で小さく付け加えながら、怜は視線を落とす。どう言う意味だと相手が問い返すのにも、小さく肩を竦めただけだった。
「レイ」
「だから。ひどいふられ方したって言っただろ。おれ一人熱あげて、相手はなんともなくて。そんなのもう耐えれないから、絶対に自分からは熱あげないようにしてるんだ」
相手の気持ちがはっきりするまで。恋愛などそんなふうに計算でできるものではないと怜自身が一番よく知っている。だけどそれが今の怜の信条で、告げるつもりもなかったそんなことを口走ってしまったのは、あるいは相手の言葉に余りにも意表をつかれてしまい面喰らっていたからかも知れない。
そんな言葉が免罪符になどならないことは、怜自身分かっている。自分がどれだけ都合のいいことを言っているかの自覚もある。だけど、それだけはどうしようもなかった。もう、自分からは熱をあげられない。自己保身のために身につけた方法。あんなふうに傷つけられては、もう二度と立ちあがることができないだろうから。
「俺ね、凄くすきだったんだよ、その人のこと。家庭教師だったんだけど。でもその人はそうでもなかったみたいで、多分何人もいる遊び相手のひとりだったんだと思う」
裕一からたばこを奪い取って怜はとうとうと話し出した。説明したところでどうなると言うのか。状況を説明したところで、その時の怜の気持ちなど目の前の男には分からないだろう。それにもし万が一、この男の今の言葉が嘘偽りないものであるのなら、ここでさよならを告げるのが一番の復讐方だ。それなのに気付くとせんのない言い訳をしている。
「十四、五のガキにピロートークなんて分かるわけないと思わない? ベッドで好きだって言われて、俺はずっとそれが相手の本心だと思ってたんだ。口先だけでそんなことを言うことがあるなんて、考えもしなかった。当たり前の礼儀だって言われたけどね」
淡々と言葉を続ける怜。その少年を前にして、裕一はなんとも言いがたい居心地の悪さを感じていた。微かな既視感。目の前でこんなふうに真剣な顔をしている怜を、裕一は知っているような気がした。バーであって以来、そんな顔を見たことなどないと言うのに。
「……ひどい男だと思わない? そんな仕打ちをしてくれたのに、未だに俺はそれを忘れられないんだよ」
ふぅっと煙りを吐き出し、たばこを灰皿に押し付ける。
「……俺だけじゃダメなのかよ」
「うん。だめ」
プレイボーイを自他共に認めるその価値観を覆すようなその決死の発言も、怜にかかれば一言で切られてしまう。余りの素早い返事に鼻白む裕一に、怜は裕一さんだけはダメだよ、と続ける。ここまで言ってもまだ分からない男の反応の鈍さはいっそ見事だと怜はひとりごちる。
「俺の名字は?」
「青木」
「じゃぁ、俺がふられた状況は分かった?」
「……? ああ、それが?」
きちんと返答は帰ってくるが、なぜそんなことを聞かれるのか分からない。そんな裕一の対応を、怜はさもありなんと見下ろすように眺める。そう、忘れている。気付きもしないのだ、この男は。
「まだ分かんない? 野村先生、案外物覚え悪いね」
心底呆れたと言わんばかりの怜の言葉にも、マトモな反応が帰らない。何を言われているのかまるで分かっていないと言う感じだ。男のあまりの反応に、怜の理性がぶちりと音をたてる。
「俺は、あんたの言葉だけは信じないって言ってるんだよ。だって、あんたはベッドでは平気で嘘をつくじゃないか」
今まさにそのベッドの上にいる男に肩にかけていたタオルを放り、怜は言い放つ。それで、裕一はやっと気付いた。目の前にいるのが誰だか。
「さとし? まさか……なんで」
「全然気付いてなかったみたいだね。俺は一目で分かったよ」
放り出したままの下着を手にし、シャツにそでを通しながら怜はたんたんと続ける。
「別にあんたを恨んでるとか、そんなじゃないよ。ただ、本当にただの遊び相手だったのか、それとも多少は本気が混じってたのか。それが知りたかっただけ。……遊びだったね」
いっそ華やかな程の笑みを浮かべて、ジーンズのボタンをとめる。怜のそんな様を裕一はただ見ているしかない。何かを言いたいのに、それが何か分からないのだ。
じゃぁね。そう言って出ていく怜を、裕一は止めることが出来なかった。とめたいのかどうかすら分からなかった。
|