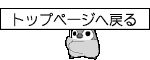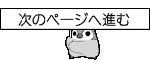傅く世界は儚く脆く:巻の壱
銀太が畑仕事を終えたとき、辺りはもう暗くなっていた。
通常であれば畑仕事は日が落ちると共に終わりとなり、後は最早眠りにつくだけとなる。
しかし、村の男たちは畑仕事を終えるなり村の中央に位置するお堂へ向かって歩いていた。
勿論銀太も彼らと目的地は同じである。
だが、仕事を終えるのに手間取ったためだろう。
銀太がそこにつくころには、お堂の中は一杯に埋まっていた。
男衆だけではなく、女や子供までが集まったお堂の中は人々の熱気で噎せ返りそうな匂いが立ち込めている。
凡そ六十人はいるであろうか。
平素であれば、これほどに人が集まればおしゃべりの一つや二つは始まろうかというもの。
だが、村のものは皆、まるで世闇に溶け込もうとするかのように息を殺している。
誰一人としてその中に音を放り込むものはおらず、音といえる音はこの堂の主たる老尼が茶を啜る音だけであった。
本堂の最奥で座る老尼はゆっくりと茶を啜り、老婆とは思えないほどに凛々しい眼で一同集いしものどもを眺め回していく。
誰もが時が満ちるのを待っていた。
ようやくの事で円座の中に空きを見つけた銀太も極力音を立てぬように注意しつつ座る。
「さて、皆さん」
一杯の茶を全て飲み終える頃になって、ようやく老尼は口を開いた。
女としてはかなり低い声だったが、その声は不思議とよく通った。
集まっていた村の周の姿勢が、自然と良くなり、全員の視線がその老尼に注がれる。
「今宵はこの様なる老婆の昔語りにこれほどの人に集まっていただけました事、真恐縮で御座います」
三つ指を突き、老婆が腰を折る。
と同時に、何処からとも無く取り出された桧扇がふわり、と一陣の風を起こした。
扇はふわりふわりと宙を待った後、老婆の前にぽとりと落ちる。
老婆はそれを手にとると、さらに口上を続けた。
「これまでお話いたしてまいりましたる童話、民謡など数知れず。されど、今宵よりお話いたしまするはある男の物語にて御座います」
何処か哀しそうに、老婆は閉じられた扇を振るう。
「恐らくは、このお話が私の語る最後のお話となりましょう。されど、いえ、さればこそ、少々長いお話にはなりましょうがお付き合い頂きとう存知まする」
何処までが本気なのか、老尼はゆったりとした動作で自らの扇を手繰り寄せると、ぱっとそれを開く。
顔の前で開かれた扇には、馬に乗る騎馬武者が見事な蒔絵張りで描かれていた。
「では、お聞きいただきます。こは旭将軍とまでに呼ばれし豪の男の物語。まずはその生まれ、久寿元年(千百五十四年)、大蔵舘より話を起こしてまいります・・・・・・
「小枝様、後一息にてございまする。はい、息を吸って、吐いて・・・」
助産婦の声が、遠く聞こえる。
最早、自分が息を吸っているのか、それとも吐いているのか、それすらもわからなくなりつつあった小枝は、ただただいきむばかりであった。
朝より始まったお産は中々の難産で、もう何度も気が遠くなりかけている。
今が何の刻なのかはわからないが、小枝は最早三日三晩ばかりは経ったのではないかとさえ考えていた。
「吸って、吐いて・・・」
声が遠い。
後一息というからには、もう頭は出たであろうか?
もう足を残すぐらいであれば良い。
切にそう願いながら、歯を食いしばる。
「・・・・・・あ!」
ちょうどそのとき、体にかかる負担が突如として軽くなった。
「生まれましたぞ!」
助産婦の叫ぶ声が、やけにはっきりと耳に入る。
「うま・・・れた・・・?」
掴んでいた棒を手放し、土間へ向かって崩れ落ちる。
本当に、疲れていた。
「小枝様!小枝様!」
助産婦の叫びが、遠い。
もしかすればこのままに死んでしまうのではないだろうか?
小枝は、本気でそのような事を考えていた。
《ふぎゃぁ!!》
だが、次の瞬間に聞こえたややの叫び声が小枝を現実に引き戻した。
絹を裂くような、元気な産声だった。
「小枝様、お手柄で御座いまする。見事な男の子で御座います!」
助産婦の手には一尺ばかりの赤ん坊が高々と掲げられている。
なるほど、その股間部には小さいなりに女子には無いものがしっかりとついていた。
和子であったか・・・・・・。
ほうと息を吐き、我が子の顔を眺める。
真っ赤な顔をくしゃくしゃにしてなく赤子は人とは思えぬ酷い顔つきであったが、今の小枝にはこの世に並ぶものの無いとても美しいもののように感ぜられた。
さて、この赤子こそ駒王丸。
後の世の木曾冠者、源次郎義仲その人である。
だが、今はまだ名前すら決まり定まらぬ一人の赤子でしかない。
それでも助産婦が喜び叫んだのは、この子供が源氏の嫡流、源義賢の長男であるからに他ならなかった。
「それでは、御身体御清め致します」
暫くじっと我が子を眺めていた小枝だったが、助産婦はその手の中から割と強引に子供を引き剥がした。
源氏の後継ぎとなるべき子供をいつまでも羊水に汚れたままにしておくのは忍びないという配慮からであったが、この出産がはじめてである小枝にとっては奪われたように感ぜられてもいた仕方ない。
少し恨みがましげな瞳が、子供を洗う助産婦へと向けられる。
だが、我が子が湯の中で綺麗にされているのを見ているうちにその目も少しずつ優しげなものへと変わっていった。
「上手く、育てられるであろうか?」
「大丈夫で御座いますよ。女子は皆生まれたその日より子供を扱う術を心得ておるものです。子供をいとおしく思う心さえあれば、然程難しい事でもありますまい」
優しい手つきで子供を洗う助産婦は、何を根拠にしてかそのようなことを言った。
その言葉に、頬が緩む。
「義賢殿は、いつごろこちらへ参られるかのう?」
「はて、そこまでは何とも・・・・・・。されど、重俊様が京への早馬を飛ばされたとか。いずれこちらにまで知らせが参るのではないでしょうか」
「父上が・・・そうか」
「京のお方様も御懐妊なさっておられるとか。まこと羨ましき・・・・・・いえ、これは失言で御座いました」
お忘れくださいませ、といいながら助産婦は笑う。
「構わぬ。女子の務めが子を産むことにあると申すのであれば、男の仕事は女子を守り子胤を作ること。・・・・・・・それに義賢様が京に参ったのは帯刀先生(皇太子の護衛長官)としての任の延長に過ぎぬ。本拠地はこの武蔵。いずれ帰ると分かったものを相手に嫉妬に狂うような醜態は見せられぬ」
「それはよう御座います・・・・・・さて、これで終わりで御座います」
言って助産婦が差し出した子は、既にしてふわふわの産着に身を包まれていた。
先ほどは真っ赤に見えた子供の肌も、よく見れば色白で見目形も良い。
おっかなびっくり抱き上げる小枝を見て、助産婦はまた笑った。
「あれ。お父上よりは小枝様に似られましたか。なんとまあ綺麗な肌で御座いましょう」
横合いから見比べながら、助産婦が軽く赤子の頬をつつく。
「どうやら重俊様も参られたご様子で御座いますね・・・」
言われて耳を済ませると、確かに、バタバタという足音が聞こえてきた。
「あれだけ急がずとも、和子は逃げはせぬというに・・・」
「ほほほ。それでもお孫様の顔を早く見たいので御座いましょう。では私めはこれにて。後々ご健勝でいられますよう」
助産婦はそう言い残すと、道具を片付けて去っていった。
それと入れ替わりに、小枝の父、重俊が入ってくる。
「小枝、でかしたぞ。和子だそうではないか」
普段は武骨な重俊の顔は、入ってくるその瞬間からだらしなく緩みっぱなしであった。
それもそのはずで、重俊の兄である重隆の娘、千雪は、同じ男の胤を受けながら、産み落とした和子を生まれてすぐに失っている。
関係のない事は知りつつも、もしやと考えるのは当然の成り行きとも言えた。
「これが和子か・・・いや、綺麗な子じゃ。義賢殿には毛ほども似ておらぬようだがな」
がはははと一頻り笑い、ようやく重俊は腰をおろした。
そのまま、両の手を小枝へ向けて突き出してくる。
「どうじゃ?わしにも抱かせてくれぬか?」
「よう御座いますよ。」
言って、重俊のほうへとややを差し出そうとする。
だが、母の胸から離れたのを敏感に感じとったのだろう。
赤子は火がついたように泣き出してしまった。
「あれ、そなたの御祖父様で御座いますよ。それほどに泣き出さずとも・・・」
重俊は慌てて両手を戻し、小枝は必死にあやそうとする。
だが、一度泣き出した赤子はそう簡単に泣き止みそうには無かった。
「ふ〜む。嫌われてしもうたかのう・・・?」
自分の顔に何か感じるものでもあったのか、重俊は右手で顎を撫でながら肩を落とした。
その様に、小枝が申し訳なさそうに笑う。
「遠路はるばるおいでいただきましたところ、申し訳ありません、父上」
「ああ、よいよい。いずれわしにも懐いてくれるだろうよ。・・・・・・そのような事よりも、ほれ、乳は出るようになったのか?」
「え?・・・・・・そ、それは・・・」
赤い風呂敷包みを広げながらの重俊の言葉に対し、先ほどまで幸せの絶頂にいるように思えた小枝の顔が露骨に曇った。
自らの胸は、子供を産んだ直後とは思えないほどにのっぺりとしている。
元より危惧されていた事であり、初産の女ではそう珍しからぬ事ではあるとは言え、現実として乳がまったくでないというのはこの幼子を育て上げる上で大きな不安要素となる。
「やはり・・・出ぬか」
娘の顔色から事態を悟ったのか、重俊もまた顔を曇らせる。
「乳母は、どうじゃ?」
「それも、中々・・・」
通常であればこのような時、同じ頃に子供を産んだがそれに死なれたような女に乳母を頼み込む。
だが、何の因果か武蔵の国を方々駆けずり回ってもそのような女は見つけられなかった。
今でこそ一人二人乳母を抱えているものの、その誰もが子供を産んだのが一年近く前であるとあって乳の道は殆ど閉じかかっている。
「・・・・・・」
「・・・・・・」
双方、無言。
小枝は母としての務めが果たせない不甲斐なさから。
そして、重俊は思いの端を今告げるべきかどうか迷ったから。
喜ばしき場であるはずの産屋に重苦しい沈黙が落ちた。
だが、一瞬の逡巡の後、重俊は再度口を開く。
「実はな・・・千雪にこの屋敷に上がってもらおうかと思っておるのじゃ」
重俊の言葉は父として、源氏の嫡流を孫にもつ身として、考え抜いた末の結論だったのだろう。
だが、重俊の言葉を聞いた途端、小枝の眉間には深い縦皺が刻まれた。
「・・・・・・何を申しておられるのか、判断がつきかねます」
未だ飲む乳のあてもつかぬ幼子を抱いたまま。
そうあるならば、父が言いたい事など一つしかありえない。
だが、それでも小枝は訊ね返した。
「千雪に、和子の乳母を努めてもらおうか、と。そう思うておる」
また、沈黙が降りた。
小枝はじっと天井を見上げ、何かを思案している風であった。
だがやがて考えもまとまったらしく、そっと顔が戻される。
その顔に、笑みは無かった。
泣き疲れて眠りについた子供を寝床に下ろし、自らはしっかりと重俊のほうへと向き直る。
「父上。その言葉、戯れで申したのであらばお取り消しくださいませ」
開口一番、小枝はそう切り出した。
その顔からは母としての優しい表情が失われ、瞳には普段の彼女と同じ強い輝きが戻っている。
その顔を見た瞬間、重俊はことの切り出しを間違えた事を悟った。
「勿論それがかなうならばそれに増した僥倖は御座いますまい。ですが、お考え直しくださいませ。千雪は和子を失のうてこの方以前にも増して塞ぎこんでいるそうで御座います。他の女子であるならばともかく、あの千雪です。何故同じ父の胤を受けて産まれた子に乳など与えられましょう。傷を広げてしまうのがおちで御座います」
小枝の言葉には澱みが無かった。
自らの父が相手であろうと言いたいことは言い、例え我が子の命がかかっていようとも間違いは間違いであると指摘する。
平素と全く変わらないその様に、嘆息する。
やはり、千雪を連れてきてから話し掛ければよかったのだ。
暗い思考の底に、思った。
千雪は小枝にとって従妹にあたる存在であるが、性格は丸っきり正反対である。
強気な小枝と、内気な千雪。
周囲のものは愚か、彼女たちは自分たちでもそのように自らを評価していた。
義賢との結婚についても小枝が自らの意思で選び取ったのに対し、千雪は小枝に促されるようにして奥に入っただけに過ぎない。
それでも彼女たちの中は概ね良好であり、嫁いで一年もしないうちに常ならざる仲へと発展していた。
自分の懐妊が知れるよりも早く千雪の懐妊が伝わったときでさえ、最も喜んだのは間違いなく小枝だっただろう。
彼女は生まれ出る和子のためにと産着から何から全てを千雪と共に準備していた。
結果的にそれらは全て今現在小枝が使用しているわけであるが、元はといえばここにあるすべてのものが千雪のものとして小枝に用意されたものであった。
それを知っていたが故に、重俊も繰り出すのを躊躇したのだ。
「そもそも乳母の件につきましてはすべてこちらで都合するゆえ父上の手はお借りいたさぬと、先月申し上げたばかりであったかと存じ上げまする。それを何故・・・・・・」
《ふええぇぇ》
まだ言葉を続けようとしたのだろうが、小枝が声を荒げる寸前になって寝かせられていた和子がむずかった。
必然的に小枝の声は小さくなり、替わりに外で控えていた乳母が呼ばれる。
すぐさま顔を出したのは、明らかに三十路も後半に入ろうとしている高齢な女性だった。
男の目を気にすることなく胸をさらけ出し和子に乳を与えようとするが、上手く出ないためかむずかる赤子が泣き止む事は無い。
その姿に、重俊の懸念はますます大きくなった。
「と、ともかく、他の女であるならば考えに入れることは御座いませぬが、千雪に乳母を頼むなど言語道断で御座います。父上のお言葉とは言え、ここは・・・・・・」
部屋を出る直前、背後から叫ぶ小枝の声が聞こえたが、重俊は俯いたまま何も言葉を返す事は無かった。
「・・・・・・重隆兄さん・・・」
襖をぴしゃりと閉め、ようやくぼそりと呟く。
―――明後日、千雪が大蔵館に参上した。
あとがき
怒涛の責めでかきあげた巻の壱、如何だったでしょうか?
真面目に書くのは自身初となる歴史小説なので色々と至らない所などあるかとは思いますが、今はこの程度が限界です。(逆にいれば私が本気で書いたはじめての小説、でもあります)
全体的に古風な雰囲気を鏤めようとした結果敬語表現の多様や関係図の無駄な複雑化など普段書くSSではあまり起こらない現象が発生してしまっている事については自身でも認知しています。・・・が、何分不慣れな作業ですのでお許しあれ。
自分でもまだまだ暗中模索の状態なので。
で、です。
今回名前が出てきたキャラは銀太を除いて七人いるのですが、明らかに作中に標記しきれない点などについて少々解説を入れたいと思います。
「小枝」 源義仲(駒王丸)の実の母。源義賢の妾の一人であり、大蔵舘の主でもある。千雪に比べると幾分年上。
「和子(駒王丸)」 後の源義仲その人。和子とは男の子供の意味であり、正確に言うのであれば彼は名前のあるキャラクターではない。
「源義賢」 源義仲の実の父。清和源氏の貴種であり、源頼朝の父、源義朝の弟。現時点で妻が三人(小枝、京のお方様、千雪)判明している。このとき既に帯刀先生としての任は解かれていたが、天皇に気に入られたびたび京へ上っていた。
「河越重俊」 小枝の父で、秩父氏族高山党の頭領。既にかなりの高齢。
「京のお方様」 源義賢の妾(正妻?)。藤原氏の血を引いているらしいが詳細は不明。
「河越重隆」 千雪の父で、武蔵の国留守居所惣検校職(要するにいまで言う知事)を努める。大蔵舘から彼の住む多胡庄までは、目と鼻の先とでも言う距離にある。
「千雪」 源の義賢の妾の一人。京で和子を産むが、死産。現在は武蔵の国に帰ってきている。
蒼來の感想(?)
時間がないので、来週にUPします<(_ _)>