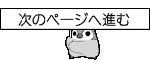朝は来た。
世界は再び動き出した。
なんら変わることなく、変えることなく。
ただ一人、ただ一人を抱えまわる。
姫君の寵愛 byダークパラサイト
第一話:イレギュラー
丘の上はあまりに静かだった。小鳥と風だけが集うのどかな墓場。
セカンドインパクトによって死んだ多くの人間へとささげられた集合墓地。
少女の言葉を借りるなら『魂を持たぬ墓の集まり』。
呼び方などどうでもいい。
人のいない墓など普通の少女なら近づくことさえ嫌がるであろう。
どれほどに開放的に作られていようともそこは 人の魂を祀るお墓なのだ。
だが多くの墓石と、巨大な碑によって構成されるそこは、少女のお気に入りの地でもあった。
辛気臭い場所であることは間違いない。
間違いはないがその少女にかかればそのような地でさえも少し華やいだ地へと変わる。
慰霊碑前の広場に設けられた広場で空を見上げる少女。
朝露と月の光を混ぜ、神に祝福させればこのような少女が誕生するだろうか?
黒真珠のような大きな瞳。
すらりと通った鼻。
後ろでまとめられていてなお腰まで届くほどの鮮やかな長い黒髪。
雪のように白い肌の上でそこだけが薄い桜色に染められた唇。
10人の男とすれ違えば10人が振り返ってしまいそうな人間離れした美を携え、少女はそこにいた。
妖艶。
そう形容するのがふさわしいほどの肢体を薄く紫がかったワンピースで包み、少女は空を見続けていた。
ここにきた理由など忘れ、青く澄んだ空を眺め続けていた。
何をするでもなく、何かを待っているわけでもない。
あえて待つものがあるとすればそれは顔も知らぬ両親のことであろう。
物心ついたときにはもう両親はいなかった。
子供のいなかった今の養父の家族が少女にとっての家族であり、養父の家が自分の家だった。
何も疑問を抱いてはいなかった。
だからこそ彼女はそこに存在していた。
少女自身、何かがおかしいということはうすうすわかっていた。
いや、そんな漠然としたものではなく、問題は確かにそこにあった。
ただ彼女にはそれに抗う力がなかっただけ。
そして彼女がその力を手に入れたとき、彼女にとっての日常は脆くも崩れ落ちる。
彼女が悪かったわけではない。
養父たちが悪かったわけでもない。
ただ、運命が彼女たちを引き裂いた。それだけのこと。
「どうしようか・・・これから」
家出したことなどなかった。それどころかずっと優等生で通して来ていた。
いまさら戻れない。
戻ることなどできよう筈もない。
「・・・まずは眠ろう。」
言いながら少女は広場の芝生に体を横たえた。
たまっていた朝露が少女の服を濡うらすが彼女は気にしていなかった。
若干14歳。
だが、その体に、頭に、刻み込まれた経験や記憶は並の大人を超えていた。
いざとなればどんな風にでも生きられる。
そのことには自信がある。
そして、だからこそ、今をいとおしく思うことができる。
ゆっくりと眠りの世界へと落ちていく少女を祝福するかのように朝の日差しが少女の体に降り注いでいった。
この物語の主人公が完全に物語に組み込まれるのはまだもう少し先の話だった。
2時間後、少女はけたたましく鳴り響くサイレンの中を急ぐ様子などかけらも見せずに、のんびりと歩いていた。
方向など決めてはいない。あえて言うなら養父の家から遠ざかる方向へ。
だから行き先などない。
この付近にあるシェルターに逃げ込む気も・・・ない。
その必要性を彼女は見つけられなかった。
だからしない。
さらに言えば少女はこの警報がN2使用に関するものであろうと考えている。
N2に対してあのシェルターでは何の役にも立たない
ならば開放的な空の下で死にたいではないか。
その思いだけが少女を丘から今歩いている町まで引き摺り下ろしてきたのだ。
(私の勘違い?)
警報が発令してから数時間がたとうとしているが、いまだに何かが起こるようなそぶりはない。
ならば細菌兵器か何かに対しての警報だったのか。
不安感は募る。
取り乱さなかったことは感嘆に値したが少女はこれからの行動の指標を探りかねていた。
せめて何か動きがあれば何が起こっているのかわかるだろう。
だが、何も起こっていないのでは何もできないではないか。
(本当に人っ子一人いない・・・って、え?)
あきらめて最寄のシェルターにでも入ろうか、と考え始めたころになってやっと少女は自分の前の駅に一人の少年を見つけることができた。
色白な顔といい、細身なからだと言い、見るからに弱々しいからだつきの少年だったが、少なくとも少女にそれは関係なかった。
問題となるのはその少年がこれだけの警報が鳴り響く中でぼおっと突っ立っているということ。
そして彼が彼女の知る少年に似ていたということ。
並外れた神経の持ち主か、ただの馬鹿か、いずれにせよ状況は動く。
近づくにつれ少年の耳から出ているケーブルから彼が後者、すなわちただの馬鹿であることは確信できた。
S-DAT。
少年の持つそれには少女も見覚えがあったのだ。
たしかクラスメイトのうち数人が持っていた音楽プレイヤー。
それでも少女は彼に声をかけていた。
暇でたまらない。それだけの理由だったのかもしれない。
あるいは何かを期待してのことだったのかもしれない。
「何してるの?警報なってるよ」
少女は彼の顔を覗き込むようにしながら問うた。
同時に少年の耳からケーブルを引っこ抜いてしまう。
りゆうはかんたん。
そうしなければ少女の声が聞こえないから。
ただそれだけ。
「うわっ、な、何するんですか、いった・・い・・・」
だが、やられたほうにしてみればたまったものではなかった。
気持ちよく音楽を聴いていたところを妨害されたのだ。
とりあえず文句のひとつでも言ってやろうと口上を切り出した少年だったが、その声は尻すぼみに小さくなっていった。
「警報なってるよ。逃げなくていいの?」
無邪気な天使のような少女がそこにいた。
「え?・・・あ・・・うん、知ってる」
瞬間的に少年のほほに朱がさした。
無理もないといえる。
ただでさえ魅力的な少女が自分の前、ほんの30センチほどしか離れていないところにたっていたのだ。
「けど、・・・その・・・待ってるんだ。人を・・・。」
しどろもどろになりながら少年は弁解の言葉を口にした。
理解してもらえるとは思っていなかった。
「ふ〜ん、なら私も一緒に待ってあげる。」
だが、少女は理解した。
頭で理解したのではない。
ほとんど直感に近かった。
すなわち、この少年はうそをついていない、と。
そういうことを理解するということには長けていた。
「けど、ずっと立ったままじゃなくて座って待たない?」
少女が指差した先には小さな木製ベンチがちょこんと置かれていた。
だが、それが二人がけの、本当に小さな木製ベンチであったことがさらに少年の顔を赤く染めていく。
「いや、僕は立ったままでも大丈夫だから。」
少年は反射的に少女の申し出を断った。
これまで積極的に女性と会話したことがなかった少年にとっては現在の距離ですら十分に自分を狂わせるにことたりているのだ。
彼を覗き込む顔は彼が知るどの女性よりも美しかった。
内気で、人を疑うことしか知らなかった少年をも狂わせてしまうほどに。
「私では不満?」
「いや、そういうわけじゃなくて」
少年は赤くなった顔を冷ますことすらできぬままに少女の手のひらの上で踊らされていた。
だが、それすらも心地よい。
天使のようなこの少女が自分を見てくれている。
それだけでもうれしかった。
なら良いでしょう。
少女の瞳がそういっているように感じた。
「君こそ僕なんかでいいの?」
「ええ。・・・あなた十分魅力的よ。」
「魅力的?」
少年は少女の言葉を鸚鵡返しに返した。
これまでそんなことを言われたことはなかった。
「ぼくが?」
信じられない。
そんな思いが先にたった。
目の前の少女が自分をからかっているのだと感じた。
しかし、少女は首を縦に振ることで否定した。
「君は十分かっこいいよ。だから自分に自信を持って、ね。」
そういわれても少年にはどうしたらいいのかわからなかった。
少女が椅子に座れと言っているのはわかる。
だがなぜ自分なのかがわからない。
本気でかっこいいといってくれているのだろうか?
そんなことがほんとにありえるのだろうか?
「ほら、早く座って。」
少女が笑う。
結局少年は考えることをやめた。
ただ素直に少女の好意に答えることにした。
どうせ誰も見てはいない。
とくん、とくん、とくん、・・・
それでも少女の笑顔にシンジの心臓が早鐘を打った。
(くそ、静まれよ・・・)
まだ少女は気づいていない。
シンジのほほが赤く染まっていること。
シンジの手が彼自身気づいていないうちに何度も開閉されていること。
もしそれに彼女が気づいてしまえば?
シンジはそれを思い苦悩した。
嫌われるだろうか?
(いやだ・・・)
(嫌われたくない・・・)
それはシンジにとっては本当にまれな感情だった。
シンジ自身そのことには気付いていないが・・・。
とく、とく、とく、とく、・・・・
意識すればするほどにシンジの心臓は早鐘を打つ
(やめろ・・・)
(鳴るな・・・)
どくん、どくん、どくん、・・・・
心臓の音は止まらない。
だがこのときシンジが顔をそらさずに少女のことをもっとよく観察していれば彼も気づいただろう。
このとき少女の頬にも少し朱がさしていた。
当然かもしれない。
ずっと女子高に通っていた少女にとって一人の男性と二人きりになることなど初めての経験であるといっても過言ではなかった。
ましてやシンジの容姿も人並みのはるか上を行く。
シンジのように明確に相手を意識していたわけではなかったが、それでもほほは赤くなる。
会話が続かないことも気まずさに拍車をかけていた。
このまま時間がとまればいいと、本気でシンジはそんなことを考え始めていた。
だが忘れてはならない。
特別非常事態宣言が発令されているにしてはあまりにも穏やかで甘美な時間。
シンジが一度も経験したことのなかった和やかな時間。
そんなものが許されるはずがないのだ。
ゴウ――――――
それはあまりに突然の出来事だった。
目のくらむような閃光。
それに少し遅れるように響く轟音。
「うあああぁぁぁぁぁぁ!!!!!!」
少女の体が大きく跳ねた。
そして、強力な爆風が彼らのいる駅舎に襲い掛かる。
すべてのガラスが砕け、彼らへと襲い掛かった。
駅そのものがきしみ、屋根が悲鳴を上げていた。
シンジににできることはない。
ただ少女と身を寄せあい、神の加護を祈るのみ。
互いに互いをその腕に抱き、互いの無事を祈るのみ。
条件は少女もそう大差ないはずだった。
・・・・・本当に?
「ふう・・・。」
すべてが過ぎ去ってから30秒後、少女はようやくシンジの体を開放した。
「大丈夫?シンジ君。」
「・・・大丈夫・・・です。」
少年は気付いていない。
この少女はまだ自分の名を知らぬはずだということに。
少女の中で何かが交じり合って大きく形を変え続けていることに。
体に異常のないことを確認した二人は周囲を見回し、自分たちの無事を神に感謝した。
そこここにガラス片が散らばり、歩くことすらままならないような状態。
ひとつのかけらも当たらなかったというのだからまさしく奇跡。
「ねえ、君の待ってる人って今どこにいるかわかる?」
しばらく呆けたようになっていた少女だったが、少なくともシンジよりは回復が早かった。
「送っていくわ。・・・この爆発じゃむこうから迎えに来るのは無理だろうから・・・。」
少女の言葉にシンジはただうなずくだけだった。
あとがき
何でだろう?
気に入らないところに修正を加えていったら文章の意味まで微妙に変わってしまった・・・。
もしかしてこのままずるずるとこの先の文章全てに加筆を加えていかなきゃならないのだろうか・・・・。
・・・変な想像はやめよう。
そんな地獄絵図の想像は・・・・。
蒼來の感想(?)
あた〜らしい朝が来た、きぼう〜のあ〜さ〜by某ラジオ番組(違
やはり感想は書きにくいなあ・・・・(−−;;;
大抵そういうものです>加筆
・・・ところで二人とも、NERVまで歩いていくの?(勘違