Frozen time &Hot heart 前編
11月の半ばともなれば日が暮れるのが随分と早くなるが、年末に向けて商店街は活気付く。
迫り来る冬の寒さを吹き飛ばすかのように明るく暖かな照明に彩られた大通りを、
はゲンマと連れ立って歩いていた。
いや、正確には任務直後に連れ出されたのだが。
「ねえ、どうして?」
が何度尋ねても、ゲンマは、
「黙ってついて来い」
と言うばかりで。
諦めてゲンマに従い歩く。
結構な人混みの中、ふと視界の端に入ったあるものに、の目は
吸い込まれるように釘付けになった。
遠くからでもすぐにそれとわかる長身と銀の髪。
それが、大通りの向こう側からこちらの方へと歩いて来る。
今、隣りにゲンマがいるのに、わざわざ横道へ避けるのも変に思われるだろう。
は、努めて平静にそのまま歩き通した。
後、3メートル、2メートル……。
何事もなくすれ違うかと思われたその時。
「や、さん」
カカシが立ち止まって、半ば振り返るようにの方を向いた。
その顔は大半が覆われて、ただでさえわかりにくい彼の表情を一層読み取りにくくする。
は、カカシに向かって軽く頭を下げた。
「こんにちは。・・・・・・はたけさん」
「最近、上忍に上がったんだって?おめでとう」
「ありがとうございます」
ごく普通に、当たり障りの無い会話をしているのが、不思議な気分だった。
こうして彼と言葉を交わすのは一体何年ぶりだろう。
そう考えながら短く礼を述べたは、顔を上げると同時にすぐさま歩き出した。
カカシの姿を視界から追い出すように、決して振り返らずに。
まるで逃げるかのように足早に歩くに、ゲンマはその長い脚ですぐに追いついた。
「お前等、知り合いか?」
訝しそうに尋ねるゲンマに、平気を装って明るく答える。
「うん、昔近所に住んでたから」
「成る程な」
察しのいい彼は、それ以上深く突っ込んではこなかった。
カカシも達とは反対の方向へ再び歩き始める気配がして。
その距離がどんどん離れていくことに、心のどこかで安堵を含んだ寂しさを覚えた。
ことを、他人行儀に苗字の方で呼んだカカシ。
昔はもっと気軽に名前を……と思いかけて自分を叱咤する。
そうだった。
私はもう、カカシとお隣さんでもないし、親しくもないんだ。
今更ながらに、彼との間に横たわる遥かな距離を、空白の時間のもたらす遠さを感じた。
カカシとは家が隣同士で、親も忍で親しくしていたからよく行き来した。
小さな頃はまるで兄弟のように朝から晩まで一緒だった。
長じて、カカシが父を、左眼を、親友を、更には師匠を失ったときも、側にいた。
の前では決して泣かないカカシの代わりのように、大粒の涙を流して泣いていたら、
逆に慰められてしまった。
距離が出来始めたのは、カカシが暗部に入った頃からだろうか。
元から愛想のいい性格ではなかったが、更に口数が少なくなり、あまり表情を出さなくなった。
それでも、向かいの部屋を眺めては、帰っている気配があると押しかけた。
その日も、数週間家を空けていたカカシが久しぶりに帰宅しているのを察して。
いつものようにノックもなしに上がりこんで、張り付くようにお喋りのシャワーを浴びせた。
ところが、忍具の装備を点検中のカカシは、の方を振り向きもしない。
時折、ああ、とか、うん、とか相槌を打ってはくれるけれど、ただそれだけ。
それがおもしろくなくて、口火を切ったのはの方。
単なる興味本位から発生した質問だった。
友達と、彼がいるとかいないとか、どこまで進んだとか、そんなことが度々話題に
上るようになっていた年頃だったし。
「ねえ、セックスって気持ちいいってほんと?」
唐突な質問にも、カカシはクナイに刃こぼれがないか目を細めてチェックしながら、
事も無げに答えた。
「いいよ。試してみる?」
照れもしない整った横顔が、ひどく大人びて見えた。
「・・・うん」
クナイを片付けたカカシに、手招きされるままに近づいて。
初めて唇が触れ合ったときには、心臓が飛びはねているのかと思うくらいドキドキした。
けれど、口内に舌が滑り込んできたときには、驚いて悲鳴を上げそうになった。
声が出なかったのは、単に唇が隙間ないほどにぴたりと重ね合わされていたから。
脇腹に触れられたときには、くすぐったさの方がまだ勝っていた。
服越しに胸に触れてくるカカシは、ゆっくりとボタンをひとつひとつ外していく。
ベッドに転がされて、それから何度か続いたキスは、半分夢見心地で受け止めた。
が、脚の間を撫で上げるカカシの手の感触に、急に不安になった。
いつの間に、こんな、男の子じゃなく男らしい手になったんだろう?
小さい時から知っているはずの彼が、急に見知らぬ人になってしまったかのような気がして
はそれ以上の行為を拒んだ。
「もうやだ……」
カカシの腕をつかんで止めようとしたけれど、逆に押さえつけられた。
濡れることを知らないそこへ容赦なく入り込んでくる指に、その痛みに、心底怯えた。
「ごめん。ごめんなさい、やめて」
切羽詰った懇願は無視されて、カカシは無言で行為を続けた。
一向に反応を示さないそこに、唾液と言う代わりの潤いを与えられ。
指よりもずっと太いものを押し込まれて、は泣き叫んだ。
全然気持ちよくなんか、ない。
何よりも、いつもと違うカカシがただ怖かった。
それから、どんな顔をしてカカシと会えばいいのかわからなくなってしまい、二度と
隣りの家には遊びに行かなくなった。
元々、任務で忙しい彼の方から会いに来ることもなかったので、の方から
出向かなければ顔を合わせることもないまま。
そして、両親のいない家に一人で住んでいたカカシは、ほどなくそこを売り払ったらしい。
ある日突然、知らない家族が引っ越しの挨拶に来て、それを知った。
もうずっと昔の古い記憶だ。
時の流れと一緒に忘れてしまえればいいのに、どうしても忘れ去ることができない。
噛み締めた唇が、苦々しいものを含んだかのように小さく震えた。
「おい、。ここだ、入るぞ」
ある居酒屋の前で立ち止まり、そう声をかけるゲンマに、唐突に現実に引き戻された。
が、ゲンマにここに連れてこられたのだって、元はと言えばカカシ絡みだったのだ。
今日の任務は大名家の姫の警護だった。
くノ一ばかりで編成された小隊は偶然皆親しい友人で、緊張する場面すら一度も無いような
のんびりとした仕事を終えて里に帰還した。
「私、報告書を出してくるね」
「皆でご飯食べに行かない?」
「わかった。すぐ戻るから待ってて」
隊長を務めたは友人達とそんな会話を交わすと、報告のために受付へ走った。
滞りなく報告書を提出した帰りに、近道しようと人通りの少ない小路を曲がりかけた
その時だった。
忍服をまとった男の背中がちらりと見えると同時には脊髄反射のように足を止めた。
後姿だけでも、それが誰であるか、わかってしまったから。
多分彼は――カカシは、に気づいていないだろう。
そのまま踵を返そうとしたが、彼と話す女性の声に思わず固まった。
「カカシさんが好きなんです。つきあってください」
広い背中越しに、垣間見える彼女の顔は思いつめたように真剣で。
どこかで見覚えがあると思ったら、二、三度任務を一緒にこなしたことのある
中忍のくノ一だった。
同性の目から見ても、気立てが良くて可愛らしい印象の子だ。
カカシが、手にしていたオレンジ色の本をパタンと閉じて、食い入るように自分を見つめて
返事を待つ彼女を眺め降ろす。
(盗み聞きなんかいけない。ここから離れなくちゃ)
まるで極秘任務のように気配を殺してその場から抜け出そうとしたの耳に届いたのは。
「君みたいなイイ子にはもったいないけど、本当にオレなんかでいーの?」
気安く申し入れを受けるカカシの姿を、それ以上目に留めておくのがやるせなくて、
まるで逃げるように駆け出した。
「お待たせ。ねえ、お腹空いたねー。どこに食べに行く?」
は、友人のところに戻ると、何事もなかったかのように話を先ほどの話題に戻した。
最近、開店したばかりの創作料理屋か、それとも美味しいと評判のラーメン屋か。
あれこれと情報を交換し合っていると、ゲンマとすれ違った。
はゲンマに手を振った。
「そっちも仕事帰り?」
「まぁな」
ゲンマのこちらを見る視線が、何故かいつもより強いような気がした。
「お疲れ様でした。じゃあね」
そのまま別れようとしたら、不意に腕をつかまれた。
「待てよ」
「何?」
不審そうに眉を寄せるの前で、千本がゆらゆら揺れた。
まるで、主の迷いを代弁するかのように。
じっとを見ていたゲンマが、千本をキリッと噛むとおもむろに口を開いた。
「えらく沈んでるなぁ。メシでもおごってやろうか」
随分と的外れな言葉に、は笑い転げた。
「やだ、ゲンマったら。どうして沈んでるなんて言うの。私が元気ないように見える?」
友人達も、不思議そうに顔を見合わせる。
はたった今まで、自分達と楽しそうにお喋りしていたのにねえ、と。
「らしくねーんだよ。お前には作り笑いなんか、似合わないぞ」
そう言うゲンマの顔は真剣で、ふざけている様子は微塵もない。
は首を傾げた。
「変なゲンマ。私はいつもと何も変わらないよ」
「そう思いたいなら思っとけ。ほら、行くぞ」
強引に腕をつかまれ、その場から引っ張り出される。
「ちょっと待って。痛いって。それに、私は友達と……ねえ、聞いてる!?」
ずるずると引っ張られて行くを、友人達は呆然と見送ったのだった。
「もー。ゲンマって強引すぎ!」
ぶすったれた顔で、がビールを喉に流し込む。
「おごってもらって文句を言うな」
口調はぞんざいだが、グラスを口に運ぶゲンマの、その口元が笑っている。
不覚にも一瞬見惚れた。
やっぱり、女の子に人気あるのもわかるよね。
おしぼりで手を拭くだけでも様になる男って、ゲンマくらいしかいない。
もう一人、―――以外は。
胸がつきんと痛んで、その人物の名前を思い出すことを拒んだ。
それを誤魔化すかのように、わざと強気な態度を取る。
「自分の分くらい払いますって。第一、ゲンマに借りなんか作ったら、利息が高そう」
「何なら体で払ってもらってもいいんだぞ」
「きゃー、セクハラおじさーん」
わざとらしく椅子をずらして距離を離すに、
「誰がおじさんだ、コラァ!」
丸めたおしぼりが飛んできた。
「で、どうしてあんなに無理矢理誘った訳?私、友達とご飯食べに行くとこだったんだけど」
道々何度も繰り返した問いを、もう一度ぶつければ。
「ちょっとばかりお前の変な顔が気になっただけだ」
「変って、何それ。失礼な!」
半分本気で怒りかけたに、ゲンマはさらりと言った。
「失恋でもしたのか」
「……ぐ……ごほっ!」
真実を知るはずのないゲンマにいきなり核心をつかれて、飲みかけのビールにむせた。
「おい、大丈夫か」
「ん、平気……。やだなぁ、私ってそんなにわかりやすいのかな……」
寂しげに言うに、ゲンマは視線を軽く逸らして、
「気にするな。当てずっぽうで言ってみただけだ」
とだけ答えると、勢いよく串かつにかじりついた。
それ以上、この話題を引きずる事もなかったので、はほっとしながら運ばれてくる
料理を堪能することに専念した。
居酒屋のドアを開けると、まだ11月だというのに、そこはすっかりクリスマスの準備で
盛り上がる街の真っ只中で。
一歩踏み出して外に出れば、ほどよく酔いの回った頬に当たる初冬の冷たい風が心地よい。
「あー、美味しかった」
「よく食うなぁ、お前」
ゲンマがわざとらしく軽くなった財布を振って見せる。
「だから、自分で払うって言ったのに」
ちょっぴり口を尖らせると。
「おごってやるって言ったのはオレだからな」
「えへへ〜、ご馳走様でした」
それからしばらくは、自然と肩を寄せ合うように、明るいショーウインドウの続く大通りを歩いた。
気の早い店は、もうクリスマスツリーを店頭に飾り付けてある。
洒落た雑貨店では、白い実のついた深緑色の葉の枝が、赤いリボンでくくられて
ドアに吊るされていた。
「あ、リースじゃなくて、やどりぎが飾ってある」
は立ち止まって隣りのゲンマを見上げた。
「ね、知ってる?これ、魔除けの意味があるんだって」
「それくらい、オレでも知ってる。そう言えば、こいつにはもう一つ、美味しい話があったな。
やどりぎの下では、まだ恋人じゃない女でも、キスすることを許される――だったっけ」
口元から千本を外した手が、真っ直ぐにの頤に当てられる。
「ゲンマ?やだ、冗談はやめて」
「冗談でこんなことするかよ」
「だって、まだクリスマスじゃないし……」
「オレじゃ駄目か?お前を支えてやれないのか?」
肩に回された腕が、逞しい胸にをぐいと抱き込む。
「何を言って……」
「男として見ろって言ってんだよ。オレなら、好きな女を泣かせたりはしない。絶対にだ」
琥珀色の瞳が戸惑うように瞬きして、すぐ目の前に迫る男の口元に釘付けになった。
何をされるのかわかっていながら、それでも信じられなくて、動けなかった。
動かなかった、のかもしれない。
痛いほど強く抱きしめてくれる人を振り払うには、今のは弱くなりすぎている。
抱擁に溺れる自分と、それを客観的に眺めるもう一人の自分と。
どちらが本当なのかわからなくなる。
いっそ、流されてしまえば楽になる?
何年も抱えてきた痛みをもたらすだけの思い出を、この人のおかげで振り切ることができる?
塞がれた唇の奥にからみつくのはゲンマの舌か、それとも古いばかりの記憶か。
ぼんやりとしたの脳裏に、不意にあのくノ一と話すカカシの姿が浮かび上がる。
知らず知らず、ゲンマの忍服を、頼るように握り締めていた。
「今夜はお前を返さない」
静かな囁きの中に潜む決意に、の迷いは飲み込まれるように消えた。
カカシはアパートに帰り着くと、寒さにかじかんだ指で玄関の鍵を開けた。
誰一人待つ者もいない部屋の中は外気と同じ温度に冷え切っていて、
独り暮らしの寂しさを際立たせる。
暖房をつけ、やかんを火にかけてお湯を沸かしながら、腰のポーチから小さな箱を
取り出すとダイニングテーブルの上に置いた。
コーヒーを淹れ、椅子に腰を降ろすと邪魔な口布を顎下まで引き下げた。
湯気の立つマグカップに唇を寄せながら、カカシの口元がふっと思い出し笑いの
ような形に歪んだ。
昔は、よくがふざけて口布を引き降ろしたものだ。
そんな行為を許したのは、後にも先にも彼女一人だった。
あの日、間違いを犯すまでは、確かにはカカシのものだった。
稀有な才能と写輪眼を有するカカシが10代半ばで暗部に抜擢されるのは、
当然の流れと言えよう。
だが、少年が責任と重圧に揉まれたからと言って、全ての面において一足飛びに
大人になれるはずもなく。
入隊して間もなくで昂ぶる感情をまだ御しきれない時期に、彼女が頻繁に
訪れていたのもまずかった。
ある時、事もあろうに自分から、セックスに興味があると示してくれて。
未知への期待に満ちた眼を見てしまっては、後には退けなくなった。
途中から嫌がったけれど、悲鳴や涙は、むしろ欲情を煽り立てた。
頭の片隅に、もうやめろという理性の叱咤の声が響きながら、その忠告を無視して
最後まで貪った。
当然のことながら、その日以降、はカカシの家に来なくなった。
そのとき以来、溶けない氷の棘のような痛みを胸に抱え、ただ流されるように
任務に明け暮れた。
鈍い痛みは、決して消えることなく、忘れることもできずに突き刺さったまま。
行き場の無い苦しさに回答を見つけたのは、それからしばらく後のことだ。
書店で忍術指導書を物色していたときに、自来也が著者だったから何気なく
手に取ったオレンジ色の表紙の本。
それは、意外な事に、少し描写の濃い恋愛小説だった。
目的の書物のついでにレジにもって行き、帰宅してページを繰り始めてからは
夢中で一晩で一気に読破した。
カカシの求めていた答えが、その本の行間に詰め込まれていた。
心が乾ききって見失いかけていた何か。
どんなに目を凝らしても、不鮮明な輪郭でしかなかったもの。
人を愛する、その意味、その行動、その結果。
何のために人を殺す?
―――木の葉の里のため。
何故、里のために尽くす?
―――そこにいる大切な人を護るため。
では、大切な人とは誰だ?
―――だ。彼女以外考えられない。
物心ついたときには、既に側にいた。
何度辛い目に遭っても、心配そうにカカシを見上げる大きな瞳を見ると、
自分を奮い立たせることができた。
なのに、いつの頃からか、を正面から見ることが苦しくなった。
最初は曖昧として、自分の中にありながら意味のわからない情動だった。
けれど、たまたまが遊びに来て、背中合わせにもたれかかりながら、
友達がどうしたとか当たり前すぎる日常のお喋りをしていたときだった。
その背に接する体温が、狂おしいほど熱く感じた。
抱きしめたい。いや、を抱きたい。
自分の中にある衝動をはっきりと自覚したときに、ポ-カーフェースという仮面を
被ることを選んだ。
の自分を見る目は、「仲のいい幼馴染」でしかなかったから。
なのに、何も知らず無邪気にすり寄ってくる彼女に心を度々かき乱された。
挙句の果てに、些細なきっかけに暴発した欲望に負けた。
を泣かせた。
世界で一番大切な人を。
何があっても護ってやるはずの自分が、彼女を傷つけた。
オレンジ色の本を閉じたとき、カカシは二度との目に触れないようにする
決意を固めていた。
自分を見れば、泣き虫のはまた泣いてしまうだろうから。
隣の家には何も言わず生家を売り払い、できるだけ遠いアパートへと引越した。
「それなのに、ねえ……」
苦い思い出と共に吐き出した溜息に憂いがこもる。
皮肉なことに、今になってが上忍になり、待機所などで出会ってしまう機会が増えた。
彼女の昇格を喜ぶべきなのだろうけれど。
カカシが視界に入ったとき、はいつも目を伏せる。
それは、瞬きするように短いほんの一瞬。
長い睫毛の下の瞳がどんな色を湛えているのか、垣間見ることは許されない。
けれど、容易に想像はつく。
自分はあの日以来、見るのも汚らわしい存在に成り下がってしまったのだから。
流石に、カカシの姿を見たら隠れるほど、あからさまに避けられたりはしていないが、
かと言って昔のように打ち解けるようなことがあるはずもなく。
遠くから見かける度に、言葉どころか視線すら絡むことのない距離に、何度も
もどかしさを噛み締めた。
そして、今日、繁華街に出かける途中で、ゲンマと肩を並べて歩くを見かけた。
己の入ることの許されない領域に容易に進入できるゲンマに、怒りを感じるほど嫉妬した。
二人の間に割り込みたい欲求に駆られると同時に、過ぎ去った年月の重みが少しでも
罪を軽くして くれたのではと、そんなわずかな希望を胸に抱えて十年ぶりに話しかけた。
結果は、言わずと知れたものだった。
は、最低限の会話でカカシの相手を済ませると、ゲンマと去って行った。
「我ながら、未練がましいとわかってはいるんだけど、ね……」
テーブルの上に片肘をついたカカシは、目の前にある小箱を、長い指でぴんとはじいた。
NEXT →
by ゆえ
2007/11/25 サイトアップ
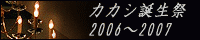
![]()