| Suburbia Suite |
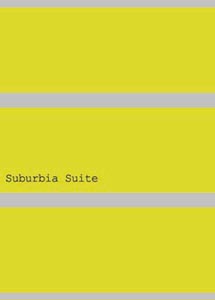
陽の落ちたクラブハウスは常夜灯も少なく、椿の眠る保健室は予備灯ひとつがぼんやりとオレンジ色を落としている。しかしカーテンを閉めたベッドで眠ったままの椿には届かず、その横で達海が丸椅子に腰掛けて椿を見下ろしていた。 目を覚まさない椿に、俺が見ておくよ話もしたいからと達海が保健医を帰らせたのだ。 椿は寝息もおだやかで、どこが悪いというところは感じさせない。ただもう、かなり眠り過ぎの感はあるが、寝不足だとしたらこういうものだろう。 寝不足、ねえ。 達海は背を丸めて薄暗いなか椿の顔色を見る。すうすうと洩れる寝息はゆったりとしており、子供のようだ。ふんわりと砂埃と汗の混じった匂いがまたその印象を強調する。 椿という選手の類まれなスピードとスタミナは、フットボールという競技には天性の才能ともいえる、のに、寝不足で倒れるというバランスの悪さが達海にはいまひとつ納得がいかない。 なんか変なやつなんだよなあ、ここでの様子とか。 達海の視線がくすぐったいのか、椿がんん、と眉根を寄せた。連鎖か乾いた唇がつと開いたように見える。ん、と達海は反射的に顔を近づけると、どうやって出てきたのか、掛け布団の中から椿の手が達海の首筋に添えられていた。 「あ?」 まばらな髪を指が梳って除けられて、大きな手のひらが達海の首にはりつく。達海は体温を感じない接触と妙に心得た力の入り方に避けるタイミングを失った。砂埃と汗の残り香はより密になって、達海は近過ぎるな、と今更のように思う。 「情熱的だな?」 からかいの言葉は椿にこぼしたのかそれとも自分にか。すると椿はその声にもぴくと唇を震わせて応じる。 「……いただきます……」 昨今の若者はそういう作法なんかね? 達海は顔色を変えることもなく、椿の力の入った手にまかせたまま顔を寄せられる。ぬるい肌の匂いは寝汗のせいかより濃く、達海のそれと混じりあう。 「おまえ、俺を食うの?」 届いた耳元にそう呟くと、椿はぱち、と音が鳴るほどに大きな目蓋を開いた。 「いいえ、ほんのひとくち、献血ほどもいらないんす!!」 「うわ」 がばと身を起こすと至近距離にいた達海はまともに椿の胸のなかへ収まってしまう。うわ、わ、か、監督。 椿は自分の手が達海を捉えたままなのを慌てて剥がした。じわんと滲む手のひらの熱は、体がなにより欲望する他人の体温であり、その源流だ。 「か、かかかかかんと、……!」 「血、なの?」 達海はベッドにもたれこんだまま椿へ顔を上げて問う。椿のそれはもう真っ青だ。唇を真一文字に引き結び、目を大きく見開いた顔はなんの申し開きもできない。 「ああ、でもそれだったらセンセイとできてるより納得だな」 先生よく居眠りしてるもんな、と達海はひとしきり得心する。 「ええっ!!」 自分の行いが知られていたとは、更に追い討ちだ。椿の驚きに開いた口は閉じることも忘れてぱくぱくと達海を見返している。しかしどう考えても事実はシンプルだ。監督に、ばれた。 言葉の出ないままの椿に達海はあら、と目を合わせた。まずかったかな。達海はショック状態で硬直する鳩を思い出す。あれってどうやって我に返るんだっけ? しかし事実関係の確認だって大切だ。達海は自分の興味を優先してゆっくりと椿に質問を投げた。 「倒れたのって、血を吸ってないから、とかなの?」 すると案外あっさりと椿は目を閉じて、観念した、とでもいうように頭を垂れた。 「……はい、そうです」 「……それは定期的に必要なんだよな? 今までもこんな風に倒れることってあったか」 達海の質問は監督としてもっともなことだが、椿は真正面から問われたことがないのであの、その、とインタビューよりも更にたどたどしく応じる。なにしろ自分というものを語る言葉を持っていないのだ。 「定期的、ていうか、なんとなくそろそろだな、っていう時があって、そうなったら気をつけてるって感じで……。こんなふうに倒れたのは、初めてっす」 ふうん。達海はもう布団から身を起こして、掛け布団を握り締める椿を見ながら話を聞いている。緊張で筋の立った手の甲。 「足りないな、てときは寝てればましになるんであんまり気にしてなかったんス、迷惑かけてすみませんっした」 すっかりしおれてしまった椿に、達海はいまはこれまで、と追求の手を止めた。だって、なに、この家出でもしかねない様相。 そりゃそうか、吸血鬼だってんだから。 しかし鬼、ねえ。まあ鬼でもいただきますくらい言うだろうけど。達海は目の前の椿と吸血鬼のイメージがそぐわなくて、未だ半信半疑の気持ちだった。 達海はさっき椿の手が触れた首筋に手をやる。自身の体温とかんたんに親和するそれは、椿のものを思い出さずにはおれなかった。 「あのさあ、吸われたとして、どうにかなっちゃうもんなの?」 太い杭でないと閉じられない不死の体、不滅の魂。十字架と太陽に弱くて、にんにくがどうたら。 「いいえ、いいえ。あの、ほんとあくまでも栄養の摂取、なんで……」 献血ほどもいらない、と叫んだ椿の言葉を達海は思い出した。ふうん。 「じゃあいいよ、俺の吸っても」 「え、あ、……か、……」 「だって、吸わないと、結局これがおまえの食事で栄養なんだろ? だったらどっかで供給先を確保しなきゃなんないんじゃないの?」 達海は意図してかそうでないのか、物事の本質をずばりと突いててらいがない。 すると椿は達海の言葉に青くなった顔を今度は真っ赤にした。え、え、と言葉にならない驚きを吐き出しながら、掛け布団を掴んだ手を震わせている。 「ほら、ここでもどこでも」 達海は首筋の髪を除けて示す。しかし椿は達海の首の白さを見ることができたのかどうか、気を失ってまたも枕に埋まってしまったからである。 |