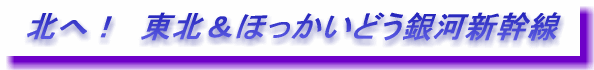 | ||
 | ||
 | ||
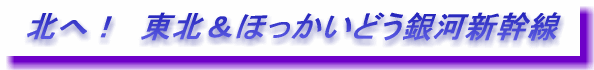 | ||
 | ||
 | ||
都心を貫く痛み ~苦心のルート選定~
1971(昭46)年10月14日、東北新幹線 東京~盛岡間の工事実施計画が運輸大臣により認可され、翌11月には着工されました。
しかし決定したルートは、戦前から東京市の中心として栄えてきた中央区・千代田区のど真ん中。過密都市を貫く鉄道建設には幾多の困難が予想されたのでした。工期は東海道新幹線とほぼ同じ5年が予想され、開業予定は昭和52年度とされました。当時、よもやそれが20年にもわたる苦闘の始まりになろうと一体誰が考えたでしょうか。
もちろん計画当初から、困難を最小限にするルート選定が行われました。最大のコンセプトは「用地取得をできる限り避ける」ことでした。東京-上野間を結ぶ回送線をできる限り転用した、苦心のルート選定を現地にたどってみましょう。
東京駅を出た東北新幹線は、東京-上野間回送線の一部を活用した東海道線の引上線の脇を北へ向かいます。この付近は、回送線の東側に張り出して新設された区間です。とはいえ、都心の一等地に鉄道用地を新規に確保することなど現実には不可能。そこで新幹線は都道407号線の直上を、2階=新幹線/1階=道路の重層構造で通過します。公道の直上を進むため、都から「上空占用」という特別の許可を得てのルート選定でした。千代田区のビル街を貫くことから、景観との調和にも配慮されており、コンクリート桁はアルミ製ルーバーで覆われ、防音壁には明るいイラストが描かれています。
| ↑ 都道の直上をゆく東北新幹線の高架橋。 アルミ製の飾り覆いや、カラー防音壁の採用など 都心部の景観に調和させるための配慮がみられる。 |
東京駅中心から700mすぎの地点で、東北新幹線は日本橋川を渡ります。ここは川の真上に首都高速道路
都心環状線が通っており、新幹線は川を渡りながら、道路とも直角交差します。ここで東北新幹線は、上下線がそれぞれ単線に分かれて首都高速をくぐっています。
道路を計画する際には、交差する道路や鉄道の管理者と協議して、将来の立体交差を見越した構造にするのがふつうです。ところが、ここでは新幹線が急なカーブ(制限70km/h)で上下線を分け、首都高速の橋脚を交わしています。しかし、これは致し方ないこと。ここに首都高速道路ができたのは東京オリンピック直前の1964(昭39)年7月、東海道新幹線の工事が最後の追い込みに入った頃です。この構造は、首都高速が建設された時点で、東北新幹線が計画すらなかったことの証左です。
| ↑ 東京駅を発車して1分後、下り「はやて」は首都高速道路都心環状線をくぐるが、この時右窓に 寄り添う上り線との間に割り込むように首都高速道路の橋脚が建っているのが確認できる。 新幹線で上下線がバラバラに道路等をくぐり抜ける例は極めて稀で、既に稠密な都心に 新幹線を通す困難さを象徴する構造である。 3007B「はやて・こまち7号」車窓(新幹線竜閑橋Bv)より |
日本橋川を渡ってから約100mは、都道を東側に付け替えて得た敷地を高架橋で進みます。
神田駅の手前で東海道線の引上線(旧回送線)は終わり、高架橋は京浜東北線(南行)に吸い付くようにSカーブを描きます。続いて回送線の高架橋を取り壊して得た敷地に、高架橋を再構築した区間が約900m連なります。この区間の構造物は、将来、東京-上野間を結ぶ通勤新線、いわゆる「縦貫線」に対応できるようにつくられています。3階=「縦貫線」/2階=新幹線の重層高架となるよう、橋脚は将来できる3階の構造物の重量を支えられるよう設計されています(別記)。
ここでは回送線の敷地を転用しているため、一見用地取得はないように見えます。しかし新幹線の線路敷のほうが回送線より幅が広いため約2m東へ出っ張り、区道もそのぶん東にずれたため、区道に面した建物は全てセットバックを余儀なくされました。これに伴う用地買収面積は計5,225.62㎡に及びます。もちろんこの用地買収も新幹線の工事費で行われました。
| ↑ 神田駅付近、山手・京浜東北線と並走する新幹線。 東京-上野間の回送線の敷地を転用したため、在来線に沿って走る。 (左)E1系12連 回送列車 (右)200系10連 回送列車 |
在来線並みの急カーブ(制限70km/h)で神田駅の横をすり抜け、中央通り(神田大通橋Bv)を越えます。秋葉原までカーブが連続していますが、最高90km/hの山手・京浜東北線にはなんでもないカーブでも、新幹線にとっては天敵です。とはいえ、当初計画では70~80km/hの運転を余儀なくされていたところ、開業直前の検討の結果、曲線の出入口でレールを滑らかにカーブさせる(*2)ことで、平永橋Bv付近から北側では90~100km/h運転が可能になりました。
また神田付近は、区道移転と新幹線高架下商店街の整備で生まれ変わった「神田一番街通り」の景観とマッチするよう、カラー防音壁が採用されています。これも地元の要望を受けてのことです。
その新幹線高架下商店街が終わる頃、新幹線は右にカーブして山手・京浜東北線と離れていきます。ここで「縦貫線」との重層高架区間が終わります。
地下に都営新宿線が走る靖国通りを平永橋Bvで越え、新幹線は25‰の急勾配で高架を下り始めます。続いてわたる神田川には、工事費の大半が新幹線建設費で賄われた歩行者専用の橋「神田ふれあい橋」が右手に架かっています。もっとも橋自体は、これも地元からの強い要請を受けてできた高い防音壁に遮られ、新幹線からはよく見えません。
 |
| ↑ 神田からビル群をすり抜けて進んできた下り新幹線は、靖国通りを越えると急勾配で地下へ向かって下る。 画面上、先頭車が渡っているのが神田川橋りょうである。 2425C列車たにがわ425号(200系10連) |
 |
|
歩行者専用橋「神田ふれあい橋」から新幹線の神田川橋りょうを見上げたところ。
2004/12/27(Tue) 16:46 神田川Bv新幹線通過に対する地元対策として架けられたもので、工事費の大半は新幹線建設費により支弁された。 歩行者からは高い防音壁に遮られて新幹線がほとんど見えないが、東京へ向かう200系新幹線が静かに通り過ぎる。 |
かつて東京の台所を支えた秋葉原貨物駅の跡地を右(東)に、「縦貫線」になる予定の引上線を左(西)に見ながら総武線高架をくぐります。貨物駅の一部を活用した秋葉原引上線の高架の真下に潜り込み、そのまま上野地下駅へと続く地下トンネル「第一上野トンネル」に入ります。
 |
| ↑ 秋葉原駅の脇を急勾配で下り、地下(第一上野トンネル)へ向かう下り新幹線。 1991年の新幹線開業時、この一帯には秋葉原貨物駅の廃墟が広がっていたが、2005年8月の つくばエクスプレス開業を前に、区画整理事業による駅前広場整備が実現した。 ITセンター(左、中央)や超高層マンション(右奥)の建設など、「萌え」タウン・アキハバラは 確実に変化を遂げている。 |
トンネルに入ってもゆるやかな右曲線を描きながら、上野駅の手前350mの地点まで25‰の急勾配で一気に下り続けます。御徒町駅付近までは、かつての回送線を活用した引上線の地下を進みます。
御徒町駅北側の春日通りを地下で交差する辺りは工事中陥没事故のあったところですが、この付近から右に急カーブしてビル群の地下を抜け、上野駅に至ります。
東京から上野までは新幹線でわずか4~5分ですが、工事費はこの区間だけで1,282億円にのぼります。東京駅の部分を除いてもキロ当たり約302億円で(*2)、まさに
地下鉄並みの工事費です。なかでも用地費は313億円と全体の24.4%を占めています。大部分を鉄道用地内に納めた路線選定にも係らず、都心の一等地・神田付近の僅か700mの用地補償費が大きく響いた結果でした。
そして計画着手から完成までに要した歳月は、実に20年。あまりにも長すぎる時間でした。
(*1) 曲線の出入口のレールをなめらかにカーブさせることを、鉄道の世界では「緩和曲線をとる」という。いきなり曲線に入るのではなく、徐々にレールを曲げていくことで、高速で曲線区間に入っても安定した乗り心地を保つことができ、同じ曲線区間でもスピードアップが可能になる。
(*2) 但し東京駅だけの工事費は公表されていないため、推定値である。推定の方法は以下の通り。
1990(平2)年3月15日付で新幹線鉄道保有機構が運輸省に申請した「東北新幹線東京・上野間の工事実施計画の変更(その12)」には、その工事費予算書が添付されており、東日本旅客鉄道東京工事事務所「東北新幹線東京・上野間工事誌」p.708に引用されている。それによると、合計予算1,317.00億円に占める停車場費は約297.42億円である。一方、軌道(工事延長3,803m全体で22.54億円)、電燈・電力線路費(同5.24億円)、通信線路費(同8.55億円)、運転保安設備費(同39.05億円)、電車線路費(同9.68億円)、発電所・変電所費(同12.41億円)、工事用建物費(同1.1億円)、工事附帯費(同155.74億円)の合計254.31億円を、実質的な東京駅構内(550m)の工事線路長で按分すると36.78億円となる。
但し1991(平3)年9月30日付で新幹線鉄道保有機構から運輸省に提出の「実施状況報告」(前掲「工事誌」p.23)によると、東海道・東北両新幹線の相互直通に係る工事費として35億円が計上されていることから、これを差し引く必要がある。
以上から、東北新幹線東京駅の工事費は、(停車場費)+(諸費按分)-(相互直通関係工事費)=約299.2億円と推定される。
なお別記の通り、上記予算は、1990(平2)年3月時点の予算編成上の計画値であり、開業までに費目毎の変化が若干あった(前掲の「実施状況報告」によると、全体は同額である)。またこの工事費には、現在東海道新幹線に使われている第7ホームの建設費、京葉線コンコースに転用された成田新幹線構造物の建設費の一部、東海道線の発着容量を確保するための東京駅・品川駅の改良工事費なども含まれているため、公開資料のみによる厳密な算定は困難である。