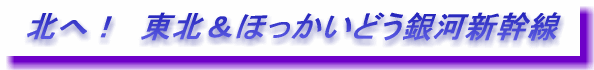 | ||
 | ||
 | ||
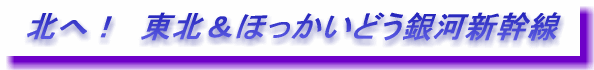 | ||
 | ||
 | ||
 |
|
東京開業をこのホームで祝った東北新幹線のシンボル「2階建車両」が停車中。 創生期のJR東日本を象徴するこの組み合わせも今は見られない。 2003年11月 8日(土) 8:12 (左)45B「やまびこ45号」200系H2編成 |
1.東北新幹線 第6ホームの建設 〜国鉄改革の荒波の中で〜
前述の通り、東北新幹線のために建設された第7ホームは、東北・上越新幹線の工事が遅々として進まぬ中で、東海道新幹線の増発・輸送安定に捧げられることになりました。このため、実質的な東北・上越新幹線用ホームとして計画されたのが第6ホームです。
1981(昭56)年8月、東京都は東北新幹線 東京−秋葉原付近の基本協議の開始に同意すると発表しました。長年にわたり東北新幹線の建設に反対してきた東京都が、東京以北の全線で新幹線建設に協力することを表明した瞬間でした。
これを受けて国鉄でも、東北新幹線東京−上野間の工事について着工を前提とした準備をはじめます。このうち東京駅については、1983(昭58)年より第6ホームの建設に着手しました。はじめは、当時東海道線の発着に使用していた旧第6ホームの発着線を一部移設するなどして、旧ホームの撤去と新ホームの建設が円滑に進められる準備が整えられました。
しかし東京駅の工事はここで足踏みしてしまいます。1983(昭58)年8月、当時の国鉄再建監理委員会が首相に「国鉄再建のための緊急措置について」を提出。その中でうたわれた設備投資抑制の方針を受けて、東京−上野間新幹線の工事も凍結されてしまったからです。
国鉄改革の中で幾多の議論を経て、国鉄は分割・民営化されることになりました。激動の時代の中で、東京−上野間の新幹線建設は不死鳥のようによみがえり、1987(昭62)年3月13日、東京−上野間の工事凍結解除を告げる「東北新幹線工事実施計画変更(その11)」が運輸省に認可されます。そして国鉄が分割民営化を果たした1987(昭62)年4月1日、特殊法人新幹線鉄道保有機構を建設主体として、東京−上野間の新幹線工事は再開されたのです。これによって東京駅第6ホームの整備が本格的にスタートしました。
1−1.第6ホームを支える構造物
第6ホームは、大きくいって(1)南部高架橋、(2)ホーム部、(3)北部高架橋の3つの構造物から成り立っています。
工事再開後、東京駅ではじめに着手されたのは、(2)ホーム部の工事でした。なかでも、工事凍結前に準備が整っていた旧第6ホームの撤去が優先して進められました。撤去工事は1987(昭62)年11月にスタートしましたが、はじめの3ヶ月は営業線に関係ないコンコース部分などで行われました。
一方、在来線(東海道線)の構内配線も、1988(昭63)年2月より使用頻度の著しく低い「西部群線」を使用廃止するとともに、現在使用していない分岐器を鎖錠・撤去する線路切替工事を行いました。「西部群線」はかつて荷物車や折り返し用の機関車の引き上げに使った側線群のことですが、当時既に東京駅に発着する列車の大半が電車となっており、一部残った客車列車(ブルートレイン)も固定編成で入換を行う必要がなくなっていました。続く翌3月のダイヤ改正では、旧第6ホーム(11番線・12番線)の使用が停止され、ホーム桁の解体・撤去が本格的に開始されました。
旧ホームの撤去に続き、1988(昭63)年12月からはホームを撤去した跡に新第6ホームを新設する工事を開始しました。この工事は、1階の改札階において、当初東北・東海道の各新幹線で改札を共用する計画だったものが、JR東日本とJR東海の協議の中で、完全に分離した改札とすることが決まり、その具体的計画策定のため一時施工の中止を余儀なくされ、工事が再開されたのは1989(平元)年9月のことでした。なお第7ホームは、完成後のホームとなる「ホーム桁」に鋼桁を採用しましたが、第6ホームはPC(コンクリート)桁を採用しているのが特徴です。また新第6ホームを挟む東北新幹線の12番線/13番線(現在の22番線・23番線)については、軌道のレベルが在来線より1.9m高くなっているため、線路を支える高架橋の上に、さらに「軌道桁」を載せてレベルを調節しています。
 |
|
元々在来線の軌道の高さは、東海道新幹線より1.9m低く、そのままでは東北・東海道の直通は出来ない。 そこで在来線用高架橋の上に「軌道桁」を載せ、その桁に東北新幹線の軌道を敷いて、東海道と高さを統一した。 2004年11月21日(日) 18:23 |
一方、(1) 南部高架橋 は、前述の通り、第7ホームの建設時に1期工事を完了しています。この時、この高架橋は成田新幹線と東北新幹線の共有設備と考えられていました。計画によると、当時の南部高架橋のフロア構成は下表の通りで、軌道敷以外は成田新幹線関係の施設として使用する計画でした。このうち鍛冶橋地下駅とは当時計画されていた成田新幹線の東京ターミナルのことで、東京駅と有楽町駅のあいだの地下に建設される予定でした。当然、その工事費も東北・成田の各新幹線に面積比按分で負担させることとなり、その負担割合は東北21%、成田79%とされました。これとは別に、地平階には成田新幹線の工事費で駅前広場を造成する計画もありました。
| 1973(昭48)年当時の計画 | 1991(平3)年 東北新幹線開業時の状況 | ||
| 軌道階 | 東北新幹線軌道敷 | → | 東北新幹線軌道敷 |
| 中2階 | 成田新幹線運転所、 同車掌所、業務施設 |
現業設備 | |
| 地平階 | 成田新幹線出札室 業務施設 |
未 定 (後に駅前広場化) | |
| 地下1階 | 機械室 成田新幹線業務施設 |
連絡通路 機械室 | |
| 地下2階 | 鍛冶橋地下駅への ラッチ内連絡通路 |
京葉線東京駅への ラッチ内連絡通路 |
1978(昭53)年2月、根強い反対運動に伴う成田新幹線計画の凍結により南部高架橋も地平・地下部分の工事が凍結されます。これにより、新幹線第6ホームの工事は一旦ストップしました。
国鉄は分割民営化を迎えた1987(昭62)年4月、成田新幹線の鍛冶橋地下駅等は京葉線東京駅として生まれ変わることが決まります。これを受け、日本鉄道建設公団(現
鉄道建設・運輸施設支援機構)から受託を受けたJR東日本が、京葉線東京駅と既存の東京駅を連絡するため、南部高架橋の地平階及び地下1/2階を整備することになったのです。これが南部高架橋(2期)です(写真)。
 |
|
(画面右側)白い業務施設との二層式高架橋が2期部分。 (画面中央)グレイの高架橋が3期部分。 1期部分は2期部分の奥にある。 東海道直通を考慮した歴史が、コンクリートの断面を晒す姿に残る。 2003/11/08(Sat) 用地管理者の許可を得て撮影 |
続いて東北新幹線第6ホームの線路敷を確保するため南部高架橋の継ぎ足し工事(南部三期工事)も1989(平元)年9月着工、1990(平2)年8月に完成。これで第6ホームに係る南側の土木構造物は全て完成を見ました。成田新幹線と同時着工した日から、実に19年の時が経過していました。
南部高架橋とは対照的に、(3)北部高架橋は比較的順調に工事が進められていました。
第7ホーム(14/15番線)の工事にあわせて進められた北部高架橋は、ホームと軌道に直接係る1期(1979(昭54)年6月竣工)、盛土を高架につくり変えて設備スペース等を捻出した2期(1983(昭58)年3月竣工)と整備が進められていましたが、き電区分所設備を確保するための3期工事も国鉄財政が最悪の状態の中、継続して進められ、1984(昭59)年3月に竣工しました。北部高架橋(3期)は、3階が将来新幹線線路敷となり、高架下に電気設備(新東京き電区分所)とJR東日本東京工事事務所が入居する複層構造が採られています。
 |
| 晩秋の夕陽を受け、北へ翔ぶE2系新幹線。 車両のいる場所を含め、右側2線ぶんが北部高架橋(3期)。 車両より手前の右側2線ぶんが北部高架橋(4期)。 3期高架橋の線路右側にスペースが空いているのは、14番線(画面右側の車止め)への連絡線用。 |
続く4期工事も、他の工事が凍結されていた1985(昭60)年9月に着工、順調に工事が進みました。
1−2.第6ホームのグレードアップ化 〜JR東日本の「顔」となるプラットホームに〜
さて第6ホームで特筆すべきは、今までの新幹線ホームにない高級感を醸し出すホームの建築です(写真)。
 |
|
ホーム自体は白いテラタイルで覆われ、独特のスリット照明と相まって高級感が漂う。 JR東日本のシンボルとして整備されたホームに、秋田・盛岡からの列車が到着する。 2004年11月21日(日) 18:41 |
まずホームのタイルは「テラタイル」と呼ばれる白い石が使われています。アクセントにJR東日本のコーポレートカラー(緑色)を意識した濃緑のタイルが随所にはめ込まれているのが特徴です。天井は新幹線ホームでは例を見ない円形のドームとなり、これも新幹線では初となる間接照明が採用されました。
階段部分の天井は、多数のパネルでドームを構成しています(冒頭写真)。
これらの相乗効果により、ホーム上はこれまでにない高級感が漂っています。
グレードアップに要した費用は、整備主体である新幹線鉄道保有機構ではなく、運行を行うJR東日本が自ら負担しました。同社の力の入れようが伺えます。
1−3. 「分割」されたコンコース
第6ホームの工事で難航したことの一つが、コンコースの配置でした。前述の通り、そもそも新幹線東京駅は、東海道・東北の両新幹線を直結する中間駅の位置づけで整備に着手されました。1977(昭52)年には「東海道と東北・上越新幹線の相互直通運転はダイヤの乱れが相互に波及し、運転管理面に多くの問題が予想されることなどから、団体用臨時列車等特殊列車の直通運転の可能性は残す必要があるにしても、東京駅着発線容量の向上を期待しうるほど多くの直通運転は考えられない。」(*1)との決定がなされますが、同じ国鉄の新幹線どうし、「東京駅は一つのターミナル」との考えが整備計画にも色濃く残されていました。
たとえば新幹線南乗換口と新幹線中央乗換口は、現在東海道新幹線に使われている第7ホーム(14/15番線)を建設した時、既に第6ホームの新設に伴う階段の新設等も織り込んでコンコースが整備されています(写真)。
 |
|
第7ホーム(14/15番線)直下のコンコースから在来線への乗換改札を望む。 このホームは東海道新幹線で一番西側に位置するはずなのに、 改札がはるか西に‥。そこで改札のほうに進んでみると‥(下へ続く)。 2004/11/21(Sun) 11:50 |
|
国鉄時代の設計では、ここに第6ホームへの階段ができる予定で、 改札を通ることなく、東海道・東北両新幹線相互の乗換が可能なはずだった。 2003/11/08(Sat) 8:15 |
ところが、1987(昭62)年4月1日、国鉄は分割民営化を迎えます。東京駅の新幹線は、既営業の東海道新幹線がJR東海、分割民営化を前提に工事が再開されていた東北新幹線はJR東日本と、2つの営業主体が経営することになったのです。このため、改札等の地上設備配置を見直す必要が出てきました。
先に記したとおり、1988(昭63)年12月からホーム工事を開始するにあたり、JR東日本とJR東海の両者で地上設備をめぐる協議が行われました。もとは同じ国鉄とはいえ、両者は今や独立した民営鉄道どうし。協議の結果、敷地も接客設備も完全に分離することが決まりました。当初計画にあった、第6ホームから東海道新幹線コンコース内へ降りる階段は建設されないことになり、その場所には不自然な空間だけが残りました。
結局、東北・上越新幹線用第6ホームへは、中央乗換口及び南乗換口付近に新設された専用コンコースを経てアクセスすることになりました。この専用コンコースは、JR東海の東海道新幹線コンコースとJR東日本の在来線コンコースにはさまれ、あたかも2つの「島」のような形でした。このコンコースには在来線側からはもとより、東海道新幹線側からも連絡改札を介して連絡されています。両新幹線を結ぶ連絡改札は、東京駅の新幹線を担う二社で受け持つことになり、新幹線中央乗換口をJR東海が、同南乗換口をJR東日本が、それぞれ担当することになりました(写真=中央乗換口)。計画の詳細が決まり、工事が再開されたのは1989(平元)年9月のことでした。
 |
|
東海道新幹線(JR東海)側から、東北・上越新幹線(JR東日本)側のコンコースを望む。 JR東海の改集札機・駅員と北へ向かう新幹線の案内表示は、なんとも妙な雰囲気。 2004/11/21(Sun) 11:36 |
(*1)東日本旅客鉄道東京工事事務所「東北新幹線工事誌
東京・上野間」p.516より。なお国鉄東京第三工事局「東北新幹線工事誌 上野・大宮間」p.26によると、1977(昭52)年7月18日に開かれた第247回常務会で東北・上越新幹線用量産先行試作車の基本仕様の考え方を審議決定した際、「東海道・山陽と東北・上越は定常的には直通運転を行わない方向で細部の検討を行う、但し団体臨時列車等については直通運転可能な50/60Hz両用車等で対処する」方針が決定されている。
1−4.日本橋口駅前広場と北側自由通路の新設
今回の東北新幹線東京乗り入れにあわせて整備されたのが、日本橋口の駅前広場です。
東北新幹線東京乗り入れにあたっては、東京駅〜日本橋川で都道407号線の上空を高架で抜ける必要がありました(「苦心のルート選定」参照)。この計画を東京都が認めるかわりに出された幾つかの条件のひとつが、この駅前広場の造成でした。
しかしこの駅前広場計画、実は東海道新幹線が計画段階にあった1960(昭35)年に端を発する、東京都にとってはまさに因縁の計画だったのです。
東海道新幹線計画当時、東京のターミナルをどこにおくかは随分議論になりました(「北の始発駅はなぜ東京か?(1)」参照)。東京を推す国鉄に対し、政府の首都圏整備委員会や東京都は品川や新宿など、当時の都心である東京周辺を避けるべきだと主張しました。結局、この論争は国鉄総裁・十河信二が各界を説得して東京駅案に一本化したのですが、決定後の1960(昭35)年11月9日付の公文書で、東京都は国鉄に対し、次のように求めています。
|
35首計監修第375号
日本国有鉄道総裁 殿
昭和35年11月9日
東京都知事 東龍太郎
(前略)新幹線の東京旅客ターミナルを東京駅とすることは、都市計画上種々問題が あるが、なお諸般の事情から始発駅を東京駅とする場合は、東京駅付近の道路交通事情 にかんがみ、現在の丸の内、八重洲両駅前広場並びに東京鉄道管理局敷地等を包含し、 総合的な駅舎計画、駅前広場計画、交通処理計画を樹立する必要があると考える。した がって、本計画の立案にあたっては、事前に本部と充分協議のうえ、これを都市計画 として決定し、新幹線建設工事と並行して事業を実施するほか、現施設以外の商業施設 を導入されないよう強く要請する。
以 上
|
|
35首計二企発第95号
昭和37年9月6日
日本国有鉄道総裁 殿
東京都知事 東龍太郎
東京駅付近の道路交通事情にかんがみ、東海道新幹線ターミナルを東京駅とすること に関連し、昭和35年11月9日付35首計監修第375号で総合的駅舎計画、駅前広場 計画、交通処理計画を樹立するよう協議を貴職に要請したが、いまだ協議がないので、 とりあえず、首都高速道路、前面取付道路、地下鉄等の接続を考慮し、本部において 立体的な東京駅北口広場計画を別紙図面及び次のとおり立案したので、貴職の御意見を 至急お伺いします。(後略)
以 上
|
|
56首計二企発第87号
日本国有鉄道昭和56年8月18日 東京第一工事局長 柳田 真司 殿
東京都都市計画局長 田神 一
昭和47年2月4日付東一工契第2920号、昭和52年12月13日付東一工契 第2135号及び昭和56年3月31日付東一工契第3644号で協議のあったこの ことのうち、東京起点新大阪方0.41km付近から、盛岡方2.38km付近まで について、下記条件を付して同意します。(中略) 1 事業施行にあたっては、千代田区及び中央区の意向を尊重すること。 2 新幹線による騒音・振動等の公害を防止し、沿線環境の保全を図ること。 3 新幹線の東京乗り入れに併せて、東京駅の北側に東西を連絡する自由通路及び 八重洲側北口付近に必要な広場を整備すること。 4 工事の実施に当たっては、別紙記載事項を遵守すること。 以 上 |

5 誘導障害対策
誘導障害とは、架線電源や無線など新設する路線に関係する電気系統が、既存の営業路線に引き起こす干渉のことです。都心の過密地帯に建設された新幹線東京−上野間でも、誘導障害対策は重要なテーマでした。これらの対策の検討・工事は、JR東日本の東京電気工事事務所(東電工)があたりました。
まず行われたのは、並行する在来線の対策です。
山手・京浜東北の各線は問題なかったのですが、中央線で当時使用されていた自動列車停止装置(ATS−B)が共振を起こすことがわかりました。そこで保安度の向上や輸送力の増強も兼ね、1988(昭63)年度から1989(平成元)年度にかけて、自動列車停止装置を新型のATS−Pに交換すると共に(*6)、東京−御茶ノ水間の軌道回路を50Hzタイプから80Hzタイプに変更、新幹線との共振を避けました。また在来各線の通信ケーブルはすべて電波遮蔽性の高いアルミ製被覆ケーブルに交換されました。
続いて帝都高速度交通営団(営団地下鉄、現東京地下鉄)、東京都(都営地下鉄)、さらには在来線に並行して通信ケーブルを所有するNTT、第二電電(現KDDI)との協議を行いました。
一番の問題は、東海道新幹線(JR東海)との干渉でした。無線系統だけでも、以下の4系統の周波数がすべて東海道(JR東海)・東北(JR東日本)の両新幹線で同一となっていました。
(1) 列車無線(公衆電話、輸送指令と列車との間の通信)
(2) 防護無線(異常時など緊急時の列車停止用)
(3) 構内無線(駅と列車、保守作業員との通信)
(4) 保守用車接近警報無線(保守用車の接近警報用)
このほか、新幹線の安全を支えるATC(自動列車制御装置)の干渉も予想されました。
元々は東海道と東北を一体で運用する計画であったために問題視されていなかった保安装置・通信系統。しかし、今や両者は別々の新幹線として営業をしようというのですから、当然両者の干渉は避けなければなりません。
まず(1)列車無線は、地上側のアンテナが沿線に張り巡らされたLCX(漏洩同軸ケーブル)というケーブルによっているため、東海道・東北の両新幹線のLCX敷設間隔を極力広げると共に、LCXを線路際ギリギリに敷設して車上アンテナが電波を拾いやすいよう努めました。それでも両新幹線の干渉が懸念される第6ホーム(東北)と第7ホーム(東海道)のあいだには、車上アンテナを持つ先頭車の停止位置付近に電波遮蔽板(下写真)を建てました。これらの対策により、ようやく干渉を避けることができたのです。
 |
一方、(2)防護無線は空間波を使用していました。元々緊急信号を発信した列車の周辺数キロにいる列車を一斉に緊急停止させるのが防護路線の機能ですから、同じ周波数を使う限り、両線の列車を同時に緊急停止させることは避けられません。やむを得ず、東北・上越新幹線の防護無線のために新たな周波数を割り振ることになり、東北・上越新幹線に関連する全ての現業機関と、JR東日本の所有する全ての新幹線車両の防護無線機を新しい周波数に対応するよう改修して解決しました。
(3)構内無線は、列車や保守作業者が駅を呼び出す方式なので、たとえば東北新幹線の列車がJR東日本とJR東海の両方を同時に呼び出すことになります。このため、このケースであれば、JR東海側が呼び出しを無視することで対応しました。
(4)保守用車接近警報無線は電波が弱いので、同じ東京駅ながら、東北(JR東日本)は上野方、東海道(JR東海)は品川方にそれぞれ地上側送信アンテナを建て、お互いの干渉を防ぎました。
最後はATCです。
東海道・東北の両新幹線は、列車のモーターを回す電源周波数が東海道60Hz・東北50Hzと異なっていますが、この電源周波数の整数倍の周波数をもった「高調波」と呼ばれる電波が車両の電気回路から漏れ出ています。これが他方の路線の軌道回路に入り込み、ATC、つまり信号表示(現示という)に誤動作を引き起こすことが懸念されたのです。
特に従来の東海道新幹線の1周波型ATCでは、停電時に軌道回路が無電流となり、これを停止信号とみなして受信するシステムが採用されていました。停電時に列車が必ずとまるという思想は、一見フェイルセーフに優れたシステムに思えます。しかし1974(昭49)年3月、品川付近で起きたATC異常現示事故では、この思想自体が仇になりました。停電で無電流のはずの軌道回路に、近くの車両基地(東京運転所)の車両自動洗浄機に使われていたモーターのコンデンサから漏れ出た高周波が紛れ込んだのです。この高調波の周波数が、たまたま70km/hで進んでよいことを示す信号(以下70km/h信号)の周波数に酷似していたことから、本来無電流=停止信号であるはずの軌道回路上にあたかも70km/h信号が流れているかのような状態が引き起こされたのです。当然、付近を走行中の列車の運転台には70km/h信号が現示され、運転士が肉眼で先行列車の存在を確認していなければ、追突事故を招くところでした。
仮に東海道新幹線のみが停電した場合、東北新幹線から漏れ出た電流が軌道回路に紛れ込み、危険な信号を出すかもしれません。理由はともかく、誤った信号が現示されるかもしれない‥新幹線の安全の根幹にかかわる問題だけに、慎重な対策が求められたのは言うまでもありません。
対策としては、東海道新幹線のATCを、より保安度の高い2周波ATCに改良することになりました。2周波ATCは、停電時も予備電源で停止信号に対応する電流を流し続ける(02E信号)ほか、従来の1つの電流周波数で信号を読み取る方式から、2つの電流周波数の組み合わせで信号を読み取る方式に変えることで、信号読み取りの信頼性を飛躍的に高めています。当時、東海道新幹線では新しい270km/h列車「スーパーひかり」、後の「のぞみ」の導入を控え、信号現示の種類を8種類(うち3種は理由の異なる停止信号)から10種類に増やすことを予定していました。1周波ATCでは8種類の信号が限界であったことから、組み合わせによって30種類以上の信号を作り出すことの出来る2周波ATCへの交換が必要で、東京駅部分についてこれを先行的に導入したことになります。
なお東北・上越新幹線は、先に述べた品川ATC異常現示事故の対策として、開業当初から2周波ATCを使用していました。