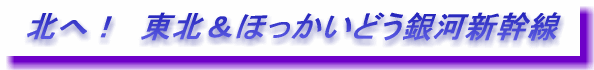 | ||
 | ||
 | ||
| ↑ 日本の鉄道の始発駅・東京駅。 西へ、そして北へ、我が国が世界に誇る新幹線のターミナルである。 2001/08/09 16:30 |
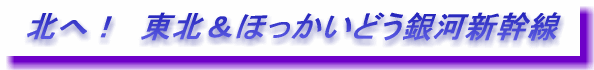 | ||
 | ||
 | ||
| ↑ 日本の鉄道の始発駅・東京駅。 西へ、そして北へ、我が国が世界に誇る新幹線のターミナルである。 2001/08/09 16:30 |
1.なぜ新幹線のターミナルは東京駅なのか?
東京駅‥ 日本の鉄道の中心。西へ、そして北へ延びる新幹線のターミナル。
それでは、新宿や上野をはじめ、東京に数あるターミナルのうちで、どうして東京駅が新幹線のターミナルなのでしょうか? 在来線の北の玄関口は上野なのに、なぜ新幹線では東京なのでしょうか?(*1)
この疑問を解くには、まず東海道新幹線のターミナルを東京に決定した理由を探らねばなりません。
‥1957(昭32)年、国鉄本社に「東海道幹線増強調査会」が設けられました。逼迫する東海道線の輸送力を大幅に増強する方策を検討するのが目的でした。
東海道線の輸送力増強の方法は大きくいって、(1) 現在の東海道線の複々線化、(2)
在来線と同じレール幅(=狭軌)の新線建設、(3) 在来線よりも広いレール幅(=標準軌)の新線建設、の3案が考えられていました。このうち(2)(3)の場合、大幅な輸送力増強が可能となる反面、現在線の東京駅では対応できないことから、東京ターミナルをどこに新設し、そのためのルートをどう確保するかという問題が生じました。1955(昭30)年に国鉄総裁に就任した十河信二は、この機に、世界に伍する標準軌の幹線鉄道を建設することが我が国の国益にかなうものと考え、特に(3)案の実現に邁進することになります。
 十河総裁は検討当初から標準軌の幹線鉄道を夢見ていた。 2001/08/09 13:30 |
ところで、新幹線の東京ターミナルの位置選定は、実は戦前にも一度検討されたにもかかわらず、結論の出せなかった大きな問題でした。
1957年の「東海道幹線増強調査会」は短期間で試案をまとめるため、大部分の検討は1939(昭14)年に当時の鉄道省に設置された「鉄道幹線調査会」の報告をもとにしていました。1939年の「鉄道幹線調査会」は、当時の東海道・山陽線の輸送力の逼迫を打開するために設立されたもので、関係者の血のにじむような努力により、わずか1年で「東京−下関間に標準軌の鉄道新線を建設する」という結論を出しています。この計画を鉄道省内では新しい幹線鉄道、すなわち「新幹線」と称しましたが、世間では「弾丸列車」と呼びました。当時の我が国は日中戦争の真っ最中で、報告が出た翌年には太平洋戦争に突入、軍事色が日に日に濃くなる情勢でした。
この戦前の「弾丸列車」計画では、建設に必要な建設基準の作成やルートの選定も行われています。あまり知られていませんが、現在の東海道新幹線の建設基準は「弾丸列車」計画の建設基準をもとに作成されており、大半の区間のルート選定や曲線半径等の各種諸元も「弾丸列車」計画を踏襲しています(*2)。
しかしこれだけ具体的な報告を行っている「弾丸列車計画」なのに、東京のターミナルだけは決定することができませんでした。それは「東京ターミナル」の位置選定が、純粋な輸送上の利便性だけでなく、都市計画や軍事上の要請、さらには皇居造営等との兼ね合いなど、鉄道省だけで決められない大きな問題だったからです。鉄道省では難工事が予想される長大トンネル3ヶ所(新丹那、日本坂、新東山)の掘削とルート確定区間の用地買収に着手する一方、この問題について関係省庁と協議をはじめました。しかし1941(昭16)年にはじまった太平洋戦争は戦局の悪化とともに国力の疲弊を招き、とても新幹線どころではなくなってしまったのです。鉄道省自身も1942(昭17)年度予算を最後に「新幹線」計画を中断せざるを得ませんでした。
こんな調子ですから、1957年の「東海道幹線鉄道調査会」のなかでも、東京ターミナルの立地を巡って、白熱した議論があったのは当然のことでした。当時、東京のターミナル候補地として実に14ヶ所もの場所がリストアップされました。
このうち十河総裁が推したのは、新宿案でした。羽間乙彦『「新幹線」物語』(毎日新聞1964年1月29日付、連載)によると、十河はその理由として「私はシビックセンターというものを、モノセンターでなく、ポリセンターにしたいと思っていた。したがって東京駅ではよくない。しかし、一つのセンターにおかねばらないので、新宿がよいと思った」と語っています。1957年当時の東京都は今と違い、ビジネスの中心は丸の内をはじめとする東京・新橋界隈がメインでした。新宿や渋谷など西部地区の商業発展は今ほどではなく、新幹線のターミナルを新宿に置くことで西部地区の発展を促し、東京の商業集積をモノセンター=1つのセンターではなく、ポリセンター=複数のセンターに拡げることを十河は考えたのでした。
十河総裁は新宿案実現のため、自ら淀橋浄水場跡地の利用を安井東京都知事(当時)に打診、都からも了承が得られたのですが、移転時期の関係で断念します。しかし国鉄は諦めませんでした。今度は大学の校庭など公有地を使い、多摩川から新宿までのボーリングも極秘裏に行いました。その結果、新宿付近の地下は水を含んだ砂れき層が多く、大規模な地下駅の建設が不可能であることが判明しました。こうして新宿案は幻に終わったのです(*3)。
新宿案以外も含めた候補地14ヶ所についての検討は下表の通りです(*4)。
(なお山手・中央部を起点とする場合のルートは代々木八幡・駒場東大前・池尻大橋・九品仏・武蔵中原等を経由、横浜付近の停車駅である小机に至り、その後西谷で現在線に接続するものでした。)
| 方面 | 場 所 | 整備困難な理由 |
| 山 手 |
ワシントンハイツ | 広さは十分だが、計画当時(1958年)米軍が未だ使用中であり、早急な返還は困難と考えられた。また他の交通機関との連絡もなかった。 現在は代々木公園として整備されている。 |
| 淀橋浄水場跡 | 交通機関との連絡は新宿駅から徒歩圏にあった。しかし計画当時は浄水場として稼動中であり、その移転完了後でないと着工できないため、工期の面で不安があった。 現在は新宿副都心として超高層ビル群が整備されている。 | |
| 新宿駅西口広場 | 西口広場に地下駅を構築する計画。地下鉄との交差や北方へ延伸する場合を考えると地下3階程度の駅となり、地質が悪く難工事が予想された。 現在は小田急及び京王の新宿ターミナル、それに付帯する地下街が整備されている。 | |
| 明治神宮外苑 | 所要面積(60,000平米を想定)が確保できなかった。 | |
| 新宿御苑 | 所要面積(60,000平米を想定)が確保できなかった。 | |
| 中 央 部 |
市ヶ谷付近 | 他の交通機関との連絡があまりよくない(中央線のみ)。計画当時、旧大本営跡を防衛庁が使用していたため、移転等を待たねば工事が出来なかった。 |
| 代官町付近 | 他の交通機関との連絡がよくない。旧大本営敷地をかすめるのも面倒。 | |
| 竹橋付近 | 所要面積(60,000平米を想定)が確保できなかった。 | |
| 飯田町貨物駅 | 所要面積(60,000平米を想定)が確保できなかった。 現在はJR貨物が再開発事業を行っている。 | |
| 東 海 道 |
品川駅(山側/海側) | 山側は地下で、海側は高架を想定。どうしても東京の中心部まで入れない場合は、せめて品川で在来線と連絡を取りたいという思いから出てきた発想。いずれも地形の面から、2線程度ならともかく、駅の施工は困難と思われた。 山側には品川プリンスホテルが建っている。 海側には、後に新幹線東京(第一)運転所が設けられたが、現在はこれも廃止され、跡地再開発は商業ビルや超高層マンションが建設中。さらに一部の用地は新幹線品川駅建設に充てられ、2003年10月に開業した。 |
| 汐留駅 | 高架を想定。品川案と同じく、どうしても東京の中心部まで入れない場合は、せめて在来線と連絡を取りたいという思いから出てきた発想。当時稼動中であった汐留貨物駅を移転するのに相当の日時を要するので、仮に着工しても、仮設でないと開業は出来ないと考えられた。 現在は、廃止となった汐留貨物駅の跡地再開発で商業ビルや超高層マンションなどが建設中。 | |
| 東京駅(八重洲) | 一重高架案(ふつうの高架)と二重高架(在来線と新幹線の二層)を想定。北方への延伸は、東京〜上野の回送線等を活用すれば比較的容易。 一重高架案は、都市計画(戦災復興計画)に盛り込まれた通勤輸送増強のための線路増設(4組め)用地(東京〜品川間)及び東京駅ホーム敷地を転用する想定。敷地をすべて新幹線に転用するので、通勤用の線路増設は東京ターミナルを含めて地下に建設せざるを得ない。 【最終決定案】。なお通勤用の線路増設は、新幹線計画から17年後の1976(昭51)年に横須賀〜総武快速線として実現、新幹線計画当時に考えられた通りの地下案で完成したことになる(*4)。 二重高架案は、上記の通勤新線と新幹線を二重高架で建設する想定。駅間の二重高架は困難ながらも施工可能だが、新橋駅部分を二重高架にすると通勤線側のホームが建設できないと考えられた。また東京駅を二重高架とする場合、施工期間中に在来線を相当支障し、また使用するホーム数の調整等も必要なので、事実上困難と考えられた。 駅間の二重高架自体は品川以西の品鶴線(貨物線)で実現した。一方、駅ホームを二重高架で建設する発想も38年後の1997(平成9年)に東京駅中央快速線及び京浜東北/山手線ホームで実現したが、こちらは枕木方向に対して5mほどずれており完全な重層のホームではない。(一層目のみホームがある二重高架は、東北新幹線の赤羽で実現している) | |
| 東京駅(丸の内) | 地下で想定。北方への延伸は比較的容易。地下鉄丸の内線との関係から相当の深さになり、また丸の内駅舎の改築にも関連があって、早急に具体案を決めることは難しかったので除外した。 この案での東京駅の位置及び品川までのルートは、17年後に建設された横須賀〜総武快速線の地下ルートとほぼ同じである。 | |
| 皇居前広場 | 北方への延伸は容易。但し皇居造営上の問題から宮内庁との協議を要するほか、東京駅と500m離れていて交通機関との連絡がないため、困難と考えられた。 この案では、皇居前広場から現在の都営三田線ルートを地下で進み、三田からは都営浅草線ルートで高輪台に至り、そのまま大崎に出ていた。 |
注目すべきは、検討のなかで「北方への延伸」が要素に含まれていることです。十河総裁が夢見た新宿案(新宿西口)も、「北方への延伸」を考えた場合に大規模地下駅の建設が困難とされており、無条件に却下されたものではないのです(*5)。
戦後の計画では、地積的な検討に加え、利用者分布からの利便性が検討されました。
まず当時の東京都の人口重心は、南北方向では中央線付近に、東西方向では東京と新宿を中心とする二大グループの重心がほぼ市ヶ谷付近に相当しました。
さらに当時の東海道線利用者のデータでは、遠距離利用で都区内各駅発着の利用者を東京駅と新宿駅のいずれが便利かで分類すると、3:1で東京駅が便利な利用者のほうが多いという結論が得られました。さらに東京駅発着の東海道遠距離客の利用交通機関の内訳は下の通り、大半が国電を利用していました。このことから、国電の各系統に連絡できることが旅客にもっとも便利であると考えられました(*6)。
|
(1959(昭34)年3月調査)(*6)
| ||||||||
| 国電 | 地下鉄 | 都電 | バス | タクシー | 自家用車 | 徒歩 | 不明 | |
| 発(%) | 53.5 | 1.4 | 0.8 | 4.8 | 22.7 | 5.2 | 8.2 | 3.4 |
| 着(%) | 51.7 | 2.5 | 2.3 | 3.4 | 20.7 | 2.7 | 6.9 | 9.8 |
利用者の利便性を勘案して、絞られた4案を比較したのが以下です(*6)。
| 位 置 |
距離 | 利 便 |
乗換の便 | 用地取得 の難易 |
現在線 との関係 |
工費 | 工期 | 備考 | |||
| 国鉄 | 地下鉄 | 高速道路 | |||||||||
| 八 重 洲 |
+7.1km | ◎ | 東海道 京浜東北 山手 中央 |
3号線500m (銀座線) 4号線300m (丸の内線) 5号線200m (計画中,*6) |
4号線 | 建築限界を縮小 すれば現在交渉 中の通勤線用の 線路増設用地で 足りる。 |
現在線の線路増設を別ル ート(地下)で考える必要 がある。 東京駅使用ホーム数を調整 する必要がある。 |
約 260 億円 |
4.5年 | - | |
| 皇 居 前 |
+6.5km | ○ | 東海道 京浜東北 山手 中央 各 500m |
4号線400m (丸の内線) 5号線400m (計画中,*6) |
4号線 | 公有地が多いの で協議を要する。 |
|
約 230 億円 |
4.5年 | - | |
| 汐 留 |
+5.0km | ○ | 東海道 京浜東北 山手 各 250m |
3号線200m (銀座線) 1号線100m (計画中,*6) 仮設駅より 3号線600m 1号線400m |
1号線 8号線 |
新貨物駅用地 取得の必要が ある。 |
汐留貨物駅並の貨物ヤード を移転する必要がある。 東京市場線を残す必要があ る。 貨物荷扱所(現在線、新幹線 共用)の設置を要する(*8)。 |
約 240 億円 |
7年 | - | |
| 品 川 |
山 側 |
|
△ | 東海道 京浜東北 山手 比較的便 |
1号線100m (計画中,*6) 京急 300m |
− | 公有地が多い ので協議を要 する。 |
|
約 140 億円 |
4.5年 | - |
| 海 側 |
+0.4km | △ | 東海道 京浜東北 山手 比較的便 |
1号線100m (計画中,*6) 京急 300m |
1号線 | 停車場は大部分 国鉄用地で足りる。 |
現在の貨物駅並のヤード改良 が必要。 |
約 110 億円 |
4年 | 環境不良 (汚水処理場 及びと殺場に 隣接) | |
この検討の結果、利用者の利便性を最優先する形で、東海道新幹線のターミナルは、国電への乗り換えの便がもっとも良い東京駅とし、都市計画(戦災復興計画)で残されている東京〜品川間の線路増設用地を使って八重洲側に1重高架で乗り入れることが決まったのでした。
北方延伸を考えるとき、東京〜上野間はビルが密集しており、当時まだ開発の余地があった新宿の方がよりベターだったでしょう。しかし、東海道新幹線の早期開業を図るためにはターミナルの立地を一刻も早く決定する必要もあり、当時としてはやむを得ない決断でした。
2.八重洲案とその反響
ところで、戦前の「弾丸列車」計画では、東京ターミナルの位置は公式決定には至っていません、しかし、鉄道省内ではその位置を東京駅と想定、東京−品川間を在来線と並行させる現在の東海道新幹線と同じルートを構想していたふしがみられます。たとえば1965(昭40)年に刊行された国鉄東京幹線工事局「東海道新幹線工事誌
一般編」p.20には、次のようなくだりがあります。
「東京の八重洲案には1重高架案(普通の高架)と2重高架案(在来線が下)とがあり、前者は狭軌線増で計画したものを新幹線に振替える案である。しかし実際は東京駅の7番ホームを施工した時には新幹線を想定して計画したものが、その後の通勤客の激増により、狭軌線の増強が強くいわれたので幹線敷を狭軌線増に使用する計画をたてたものであって原案に戻したものである。」
7番ホームとは、1957年当時、東海道線の長距離列車に使用されていた14/15番線のこと。このホームと、それに続く東京〜品川間の敷地こそ、「弾丸列車」と呼ばれた戦前計画における新幹線の線路敷だというのです。
1958(昭33)年11月に運転を開始した電車特急「こだま」は車両技術面で「新幹線」の礎を築いたとされますが、そのテープカットが十河総裁の手によって行われたのは、この東京駅15番線でした。そのホームが戦前の新幹線のために計画され、一旦在来線として使われながら、戦後の計画の中で再度新幹線用地として使われるのは、単なる偶然でしょうか? ‥いいえ、決してそうではないでしょう。工事誌のこのくだりを書いた人物は、戦前の計画を熟知しているからこそこのように書けたのでしょう。
戦後の新幹線計画は、その素案も、そして人も、そっくり戦前の計画を引き継いでいたことが読み取れます(*9)。
 有楽町のビル群を縫うように東京駅へ向かう東海道新幹線。 約40年前、既に稠密だった都心に新幹線が乗り入れられたのは、 戦後の都市計画と、その基礎を成す戦前の「新幹線」計画の賜物。 2003/08/17 17:50 |
さて、非公式ながら戦前からの流れを引き継いだ八重洲案でしたが、東京都より、都市計画の観点から強い反対が述べられました。新幹線のターミナルを東京駅とすると、既に進んでいた都心部への過密を加速させる、業務機能分散のためには新宿など、当時の都心部(都心3区=千代田、中央、港)の外がよい(*3)、というものでした。
一方、政府の首都圏整備委員会は品川案を推していました。これも首都圏の都市機能の分散を前提に、国電との乗換の利便性を考えた案ですが、品川と都心の間の交通事情や、当時の業務集積が都心3区に集中していたことを考えると、ベストな案とはいえませんでした。
結局国鉄側が八重洲案で首都圏整備委員会を説得し、委員長の次田大三郎氏の尽力により東京都の了承も取り付けることができました(*10)。こうして国鉄の計画通り、八重洲案が決定をみたのでした。
3.品川サブターミナルの開業
東海道新幹線が開業して約40年を経た2003年10月、東海道新幹線にサブターミナル・品川駅が開業しました。本来は輸送力増強のための列車増発を目的とした新駅ですが、横バイの輸送需要を反映して、同駅発着の列車は当面設定されず、JR東海はもっぱら東京西部の業務集積へのアクセス性の向上をアピールしています。
 東海道新幹線の開業から約40年を経て誕生した新ターミナル・品川。 新都心3区や急発展を遂げる品川地区からの旅客が大勢乗車する。 |
東海道新幹線の東京ターミナルが、戦前からの計画を土台にしながら、乗客の利便性を第一に選定されたことは今まで述べた通りです。しかし、同時にそれは「当時の」最適解でもあります。
たとえば都内の就業者数を旧都心3区と新都心3区(=渋谷、新宿、豊島)で比較すると、1955年にはそれぞれ29.4%と10.9%(3:1)であるのに対し、1990年には32.9%と17.0%(2:1)であり、新都心3区の就業者が大幅に増えたことがわかります。現在では東京より新宿の方が利便性が高いという利用者も相当な数にのぼるでしょう。品川ターミナルは、東京の業務集積の西部へのシフトに応えた存在である、という見方もできるかもしれません。
逆に、現在の状況は、都心の過密緩和を考えて新宿案を推した人にとっては予想外の事態ではないでしょうか。
今に至るまで、新宿に新幹線のターミナルはありません。しかし新都心3区は大きな発展を遂げ、新宿駅の混雑は飽和状態に達しています。もし、これに新幹線のターミナルが加わっていたら、新宿駅周辺は人で溢れかえり、あるいはパンクしていたかもしれません。
こう眺めてくると、何十年も先を予測することがいかに難しいか、交通計画や都市計画の難しさを実感します。
(*1)別記の通り、当初の工事実施計画では、東北新幹線の東京駅の次の停車駅は大宮であり、上野に駅は設けられていなかった。上野駅の設置は、新幹線の建設に断固反対する東京都を説得するための切り札であり、公式にも東京側のサブターミナルとしての位置づけと説明された。つまり、東北新幹線のメインターミナルは、計画当初から現在まで一貫して、上野駅ではなく東京駅であったことになる。
(*2)角本良平「新幹線 軌跡と展望」p.10より。
縦曲線半径とは、勾配が変わる部分(峠の頂上など)で、急激な乗り心地の変化を緩和するために挿入する曲線の半径のこと(図参照)。高速で走行する鉄道では不可欠の存在である。1940年に報告された「弾丸列車」計画では縦曲線半径R=10,000mとされたが、戦後の「新幹線」計画でも同じ数値が採用された。山陽以降の新幹線はR=15,000mとしたが、超高速を想定する北海道新幹線(新青森−札幌間)はR=25,000mで計画中である。
曲線半径も、戦前・戦後とも同じ半径2,500mを採用している。ルートも東京〜横浜西部(未定)と名古屋〜京都(鈴鹿峠経由が検討されていたが、決定に至らず)を除き、ほとんど戦前の「弾丸列車」計画を踏襲しており、神奈川県や静岡県では戦前の既買収地をそのまま利用して路線が建設されている。
 |
大きく異なるのは許容軸重で、戦前計画では大型の電気機関車及び蒸気機関車を想定していたため、軸重が23t程度とされていたが、戦後の計画では動力分散式の電車列車専用で計画されたため軸重16tに抑えられ、土木構造物の簡素化、ひいては建設費低減に大きく貢献した。また戦前計画では小さな道との平面交差(踏切)を許容していたが、戦後計画ではすべての道と立体交差としたため、既買収地を利用した区間でも縦断構造(地平→盛土又は高架)は変更している(国鉄東京幹線工事局「東海道新幹線工事誌
一般編」p.37)。
(*3)羽間乙彦『「新幹線」物語』(毎日新聞1964年1月29日付、連載)
(*4)東京−品川間の地下線は、横須賀線電車を東海道線用の複線から分離運転させるために建設された。しかし1976(昭51)年に完成したため、とりあえず総武快速線の電車を品川に延長する形で暫定使用を始めた。横須賀線の分離運転&総武快速線との直通は、東海道貨物線(羽沢線)と武蔵野線が全線開業し、品鶴線を通る貨物列車の迂回ルートが確保され、同線がほぼ横須賀線専用になった1980(昭55)年のことである。
(*5)実際、新宿西口にはその後、小田急線の緩行用地下ホームと京王線のターミナルが建設されている。4線程度の地下駅であれば建設可能であったと考えられる。
(*6)表の出典とも、国鉄東京幹線工事局「東海道新幹線工事誌 一般編」P.21。
(*7)地下鉄1号線は当時一部区間で建設が進められていた都営浅草線、同5号線は当時中野−大手町間が計画中だった営団東西線のこと。
(*8)当時、東京市場に入る鮮魚・青果等の大半は国鉄貨物として運ばれていた。このように国鉄は物流における大きな使命を担っていたため、仮に汐留貨物駅が移転したとしても、これらの市場への輸送を継続する必要があった。貨物荷扱い所も同様で、貨物駅自体は郊外に移転したとしても、都内へ送られる多くの貨物の荷扱いを行う場所が不可欠と考えられた。新幹線も共用、とあるのは、新幹線の貨物輸送を想定してのものと考えられる。その後、トラックの普及と道路の整備等により、わが国の物流はトラック輸送中心へと大きな変化を遂げた。そしてこの計画から27年後の1986(昭61)年、汐留貨物駅は廃止された。
(*9)戦後の新幹線計画では、東京駅のホームは第8・第9の2面を新設して、4線を確保する計画であった。件の第7ホームは東北新幹線計画の際、いよいよ新幹線ホームとして転用されることになるが、これについては別記する。
(*10)角本良平「新幹線 軌跡と展望」PP.186-187より。