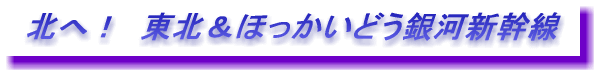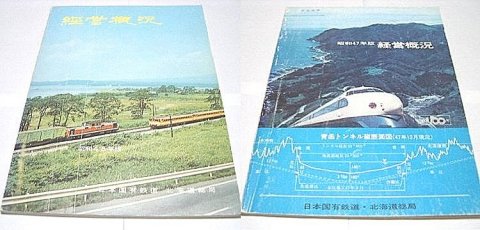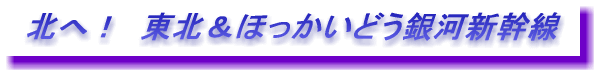

★ 御巣鷹山で思うこと
〜都市間交通の条件〜 ★
1. ためらい、そして
2003年夏、御巣鷹山に登りました。
1985年8月12日、東京羽田18時発大阪伊丹行のJAL123便(ボーイング747-100SR=ジャンボ機)が羽田を飛び立って12分後、後部垂直尾翼付近で機体破壊が発生、機体は操縦不能のまま迷走を続けますが、クルーの必死の奮闘も空しく、同日18:56、群馬県上野村の御巣鷹山の尾根近くに激突、墜落
しました。
夏休み中でほぼ満席の機体には乗員・乗客524名が搭乗、うち520名の命が天に召されました。単独機の事故による死者数は18年後の現在もなお世界最悪の大惨事、日航ジャンボ機墜落事故の現場が、この御巣鷹山です。
御巣鷹山にはずっと前から行ってみたいと思っていました。しかし、ためらいのほうが深くて、行けませんでした。乗客の、そして遺族たちの無念さを思うとき、部外者が立ち入ってはいけない場所だと思っていました。
しかし‥。あの夏から18年、事故はどんどん風化しています。私と同じ歳、あるいはそれより若い人に尋ねても、御巣鷹山を知る人は多くありません。
事故を深く心に刻む人が減ってきた今、あの事故の記憶を深くとどめる私のような者が現場に立ち、未来の幸せを創るため、無念の魂に祈ることも許される気がしてきました。
それに、単なる思い込みかもしれませんが、私が生きていくうえで御巣鷹山での祈りが是非とも必要に思えました。あの現場に立ち、高速交通の安全を願うことが、明日の幸せを創る礎として、ぜひとも必要だと思えたのです。
2.御巣鷹山へ
渋滞する週末の関越道を東京から2時間強で下仁田へ。さらに山道を1時間以上走ると、クルマはようやく上野村に入ります。村の中心から林道を20分ほど南下したところが、御巣鷹の登山口。ここから谷あいを流れる清流に沿って、険しい山道を歩いて登ります。
あの事故のとき、救助隊が麓から数時間を要した御巣鷹山。しかし現在は林道が整備され、登山口から1時間ほど山道を登ると、あの場所にたどり着くことができます。現在工事中のダムが完成すれば、山道は20分程度にまで縮まるそうです。
 |
↑ 御巣鷹山の尾根に向かう登山道。何事もなかったかのように、清水のせせらぎだけが辺りに響く。
2003/08/10 12:00ごろ 御巣鷹山(群馬県上野村)にて
|
深山の空気を吸いながら沢伝いに登ってゆくこと、約45分。斜面いっぱいに建つ、おびただしい数の墓標が目に入ります。ひとつひとつが、心ならず最期を迎えた無念さを訴える‥尋常でない光景を前に、私はただ黙して尾根を目指すしかできませんでした。
さらに登ること10分、急に視界が開けました。そこが御巣鷹の尾根でした。
南隣の尾根を見渡すと、木々の中にぽっかりと窪んだところが見えます(写真)。通称「U字溝」です。
 |
|
↑ 画面中央、山の木々がくぼんだところが通称「U字溝」。あのとき、山への激突を回避
しようと努めた事故機が、それでも避け切れずにぶつかった痕跡である。「U字溝」での
激突の衝撃で、機体は表裏・前後を反転、縦に真二つに裂けた状態で、足元の左右に
続く尾根に激突した。右側(ひっくり返る前は左側)の部位は右側の尾根に、左側(ひっくり
返る前は右側)の部位は左側の尾根に散乱したという。
2003/08/10 12:00 頃 御巣鷹山尾根(群馬県上野村)にて
|
‥操縦不能になりながら、それでも山への激突を必死に避けようとしたクルーたち。しかしその努力が実ることはなく、事故機は尾根に激突、大きな損傷を受けます。激突のショックで機体は表裏・前後共ひっくり返り、縦に真二つに裂かれ、御巣鷹山南麓の尾根に墜落しました。
はじめの激突の衝撃で山肌が剥げて出来た「U字溝」は事故の瞬間を今にとどめます。最期の瞬間、乗客たちは何を思ったのか、なぜ彼らはこんな目に遭わなければならなかったのか‥。その不条理さに、胸が詰まります。
墜落した尾根には、慰霊碑「昇魂の碑」が建立されています。脇には、祈りを記した鈴つきの札が括りつけられていました。「昇魂の鈴」というのだそうです。
「昇魂の鈴」には、空の安全に対する願い、そして航空関係者の事故を起こさぬ誓いも多数記されていました。山々をわたる風が、チリチリと鈴を鳴らしてゆきます。
 |
↑ 画面中央が慰霊碑「昇魂の碑」。
両脇には、祈りを記した鈴つきの札「昇魂の鈴」が多数寄せられている。
2003/08/10 12:20 頃 御巣鷹山尾根(群馬県上野村)にて
|
‥歴代の国土交通省(旧運輸省)航空局長は、新規参入の航空会社に事業認可を与える際、その交付を受けるため局長室を訪れた幹部たちに、必ず御巣鷹への慰霊登山を薦めています。それは競争が激化する航空業界のフロンティアたちに、空の安全に対する誓いを新たにしてもらうため。スカイマークエアラインズの初代社長も、Air
Do(北海道国際航空)の初代社長も、そしてスカイネットアジア航空の社長も、ここに登り、あの日あの時、無念の思いを遂げた御霊に手を合わせたのです。
3.航空事故が北海道新幹線に与えた影響
かつて「飛行機は危ない」と言われた時代がありました。戦後「東北・ほっかいどう銀河新幹線」沿線に関係する航空死傷事故は4件あり(下表)、その死者数は計364名にのぼります。特に1971年7月には2件の大事故が連続して発生、航空輸送に対する信頼感は大きく損なわれました。
| 「東北・ほっかいどう銀河新幹線」沿線に関係する航空死傷事故 |
| 1966年 2月 4日 |
千歳発羽田行ANA60便(ボーイング727)
着陸進入中に東京湾に墜落。
乗客・乗員133名全員死亡。
(我が国初の民間ジェット機の墜落事故。
当時、一機の事故では世界最大の死者数。) |
| 1971年 7月 3日 |
札幌丘珠発函館行TDA63便
(現JAS、YS−11「ばんだい号」)
着陸進入中に横津岳に激突。
乗客・乗員63名全員死亡。 |
| 1971年 7月30日 |
千歳発羽田行ANA58便(ボーイング727−200)
岩手県雫石上空で航空自衛隊F86Fと空中衝突。
ANA機の乗客・乗員162名全員死亡。航空自衛隊
のパイロットはパラシュートで脱出して無事。
(当時、航空事故では世界最大の死者数。) |
| 1999年 7月23日 |
羽田発新千歳行ANA63便(ボーイング747−400D)、
羽田離陸直後にハイジャック。
機長1名が殺害された後、異常降下に陥り、羽田空港に緊急着陸。 |
(※)なお東京−札幌間に関連する路線でのハイジャック事件は上記1件を含め8件起きている。
同日に2件発生(1977年3月17日、羽田→仙台及び千歳→仙台)したケースもある。 |
北海道新幹線(青森市〜札幌市)は、1972年5月に鉄道建設審議会による建設答申を受け、同6月に基本計画決定、1973年11月には整備計画が決定しています。当時から東北新幹線(東京都〜青森市)と一体となって、首都圏・東北・北海道の一体化を担う動脈としての活躍が期待されていました。
整備新幹線に対する批判の中に「航空機の利用が一般化していなかった時代につくられた計画を、30年後の今になって実現するのは馬鹿げている」という主張があります。しかし他の整備新幹線はともかく、北海道新幹線については、この批判が必ずしも正確とは言えません。なぜなら、首都圏−札幌圏間では、現代の我々が考えるよりはるかに早い段階で、鉄道旅客の航空シフトが進んでいたからです。
首都圏−札幌圏旅客の鉄道シェアがはじめて航空利用を下回ったのは1965(昭40)年度のこと。羽田−千歳間に国内線初のジェット機(JAL=コンベア880/ANA=ボーイング727)が導入されて1年、そして全日空羽田沖墜落事故が起きた時です。当時、上野−青森を結ぶ特急列車は、昼行「はつかり」(ディーゼルカー,1958年〜)、そして前年に運転を始めた夜行「はくつる」の2往復だけでした(*1)。
連続事故の起きた1971(昭46)年度、首都圏−札幌圏旅客に占める航空シェアは80%に達していました。当時の航空運賃は、鉄道の倍以上もしたのに、です(*2)。羽田−千歳間には一日30往復近いジェット機が就航していましたが、この便数は約25年を経た1995(平7)年と同じです(*3)。
こと札幌に関する限り、30年以上前の段階で航空利用は一般的なものとなっていました。むしろ飛行機が誰でも乗れるものだったからこそ、連続事故が人々に与えた影響が大きかったと考えるのが自然でしょう。
それなのに、東京−札幌間5時間50分(=当時の計画)もかかる新幹線を建設しようと考えたのは何故でしょう?
背景には、よく言われる「高度経済成長期の新幹線に対する万能の期待」もあったかもしれません。あるいは圧倒的な運賃差から考えて、新幹線の所要6時間でも航空に勝ち目があるという判断をしていたことも事実でしょう(*4)。しかし恐らくそれと同じくらいに、連続事故で航空に対する信頼感を大きく失っていた街の空気が、「安くて快適でいつでも乗れて、常に安全な交通機関」というコンセプトに強い自信を与えたのではないでしょうか。
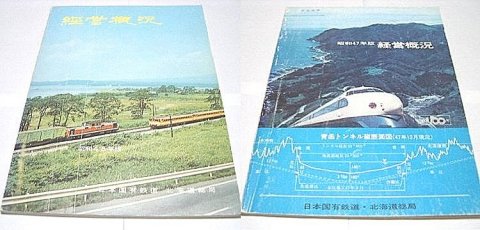 |
↑ (左)国鉄北海道総局「経営概況 昭和45年版」
(右)同「経営概況 昭和47年版」
国鉄の地方機関・北海道総局が毎年発行する経営概況。その表紙には、北海道
の大自然をゆく列車の写真が使われたが、昭和47年版だけは青函トンネルと新幹線
を前面に出した構成となっている。
連続航空事故から1年、基本計画が決まったばかりの北海道新幹線をを熱望する
当時の国鉄北海道総局の熱意が伝わってくるようである。内容でも、この年から「空
港と航空機輸送」という項目が加わり、航空輸送に対する危機感を強めていたことが
わかる。 |
計画段階でこれほど航空事故の影響を強く受けた整備新幹線は、もちろん北海道新幹線以外にありません(*5)。このこと自体、「安全・安心・確実な交通機関の確立」という北海道新幹線の特性を象徴しています。
4.より安全な高速交通体系を目指して
私は「飛行機は墜ちるから乗るな」というつもりはありません。私自身、年に数十回のペースで飛行機に乗っていますし、北海道にいた頃はほぼ毎週、飛行機で東京や大阪を往復していました。今でも東京−大阪を移動する約半分は飛行機を使っています。
幸いなことに、我が国の定期航空便は、御巣鷹山以来、乗客の死亡を伴う事故を起こしていません(*5)。御巣鷹山の頃と比較しても、航空輸送の安全性は飛躍的に高まっています。多くの航空関係者が御巣鷹の「昇魂の鈴」に誓っているように、これからも安全に対するたゆまぬ努力が続くことを願います。
しかし‥。尊い努力を重ねてもなお、社会を支えるシステムとしてみたときに感じる、航空輸送の持つ本質的な脆さから目を背けることはできません。
たしかに御巣鷹の頃と比べると、航空機の自動化は著しく進みました。衝突警報装置((TCAS)の設置も国内では義務化されています。事故率の低下は安全に対するこれらの努力の成果といえるかもしれません。
しかし自動化の影に生じた「人間系」の問題は、かつてない複雑な問題を私たちに提示しています。「機械の論理と人間の感性が異なる答えを導いたとき、人間(操縦士)はどう行動すべきか」‥この命題に答えなどあるのでしょうか?
たとえば数年に一度の割合で発生するニアミス事故。その最接近時の距離は焼津(2001年)や与論(2003年)の場合、わずかに20〜60mです。国内線航空機が秒速250mで飛んでいることを考えると、わずか0.1〜0.2秒の判断。人間である操縦士や管制官の能力を考えるとき、この時間内で判断を下すのは、もはや「努力」の領域を完全に超越しています(*7)。
あるいは最近でもしばしば起こる酷寒期のオーバーラン、気象条件の突発的な変化による離着陸の失敗。いずれも航空機を運航する上で不可避の事態です。これもまた「努力」では解決できない、航空というシステムの持つ本質的な弱さをさらけ出しているように思います。
もちろん新幹線の安全性だって完璧なものではありません。1966年の車軸折損事故、1973年の鳥飼事故に端を発するATC異常現示の連続発生、1976年と2003年に起きた無人(居眠り)運転、1990年頃から目立ってきた部品脱落、1999年のトンネルコンクリート崩落、さらに1995年には乗客1名が列車に引きずられて死亡する事故も起きています(*8)。
それでも、開業以来約40年、70億人以上を運んでなお「運転事故による死者ゼロ」の記録を守り続けていることは無視できない事実です。その列車の遅れは僅か平均0.4分(*9)。これらは、統計的に見て新幹線がきわめて安全で確実な乗り物であることをはっきり示しています。
 |
↑ 約40年にわたって走り続けてきた新幹線。その安全性・確実性は、設計時からの安全
思想に基づくシステム、そしてスタッフの努力の積み重ねによって支えられている。時代と
共に車両も人も替わってゆくが、その根幹を支えるものは変わらない。
2003/06/08(Sun) 9:48 新神戸駅にて
(左)「こだま608号」(0系R編成6連) (右)「ひかりRailstar365号」(700系E8編成8連)
|
ところで、この偉大な記録を「新幹線の安全神話」と表現することがあります。しかし新幹線だって人のつくったもの、決して「神話」などではありません。新幹線の安全性や確実性は、開業以来一貫した安全思想のもとにつくられたシステム、すなわち、目視に頼らない信号システム(ATC)や総合指令所で一元化している運行管理システム(CTC)を礎に、それを磨き上げるスタッフの努力の積み重ねで達成された賜物です。
2003年2月に起きた山陽新幹線の居眠り運転の例を考えてみましょう。運転士の居眠りにもかかわらず、列車は追突や暴走の危険もなく26kmを走り続け、ATCによる所定の自動減速で岡山駅に停車しています。これは安全思想に基づいて設計されたシステムが確実に動作したおかげです(*11)。しかしホームの停止位置の調整は運転士の手動操作に委ねられているため、所定より手前に大きくずれました。位置修正や指令所との打ち合わせのため、列車の定時運行は大きく妨げられたのです。定時性の確保は、オペレーターである人間の責任です。
5.犠牲の上に成り立つ交通計画
統計的に言えば、航空事故により死亡する確率は、自動車事故に巻き込まれて死亡する確率よりはるかに低いといわれています。しかし航空事故は、信じられない程多くの不慮の死を突然我々に突きつけます。そのインパクトの大きさは計り知れません。
事故死という極端な例をひくまでもなく、新幹線は、定時性の面でも環境負荷の面でも航空機より断然優れた特性を持っています。
もちろん、交通需要の少ない区間で航空・新幹線の双方を整備するのは無駄の多いことです。しかし我が国の人口100万人規模の大都市で、時間に正確で気軽に乗れる新幹線、移動中の拘束時間が短い航空機、その両者を場合に応じて使い分けることができないのは、今や札幌だけです。年間1,000万人近くが利用する東京−札幌間の交通需要は本当に少ないのでしょうか?
御巣鷹山の事故後、航空旅客需要は大きく減少しました。運輸省情報管理部の試算では、事故の影響で航空機の利用を取りやめた旅客は国内全体で440万人、当時の国内線航空旅客の10.7%に達しました。都市間の鉄道シェアも急伸、東京−大阪間は85%(事故前)→91%(事故後)、大阪−福岡間は62%→69%、東京−福岡間ですら26%→31%に増加しました(*10)。しかし東京−札幌間では目立った変化がありませんでした。15時間もかかる鉄道は、選択肢にもならなかったのです。事故の凄惨な記憶が消えぬ頃、我慢して飛行機に乗っていた人も少なからずいたのではないかと想像されるのですが‥。
* * * * * * *
御巣鷹山に登れば、二度とこのような事故があってはならないと願わずにはいられません。しかし、人の創りしものに「絶対安全」があり得ないことも冷徹な事実です。航空輸送の持つ本質的な脆弱性はその一つの現れでしょう。それならば、せめて人智を尽くして「できるだけ安全な交通体系」をつくる努力が求められます。
御巣鷹山から20年近く経ちました。悲しいけれど、人間は忘れやすい生き物です。冒頭に記した通り、御巣鷹山の記憶は年々風化しています。しかし、忘れてはいけないこともあるように思います。
 |
↑ 竜飛岬から北海道(画面中央)を望む。「内地」(=本州)と北海道を陸続きで結ぶ青函トンネル、
この突拍子もない発想を現実にしたのは、死者・不明者1,400名余を数えた洞爺丸台風の犠牲を
重く受け止め、「どんな時でも安全に行き来できる」交通路を整備しようとした国と国鉄の強い意志
であった。
2003/11/09(Sun) 12:55
青森県三厩村 竜飛岬にて
足元から対岸の北海道にかけての海面下を世界最長の青函トンネルが貫く。
画面右側のトンネル型の標石は、青函トンネル工事の犠牲者を弔う慰霊碑。
|
誰もがその実現を疑った青函トンネルの着工のきっかけが、1954(昭29)年9月に起きた青函連絡船「洞爺丸」他8隻の沈没事故にあったことはよく知られています。瀬戸大橋建設のきっかけも、1955(昭30)年に起きた紫雲丸等の衝突沈没事故でした。大変不幸なことですが、交通の進歩の歴史は犠牲の歴史でもあるのです。けれども‥我々は既に、あまりに多くの犠牲を負っています。
神は、人間に考える力と想像する力を与えました。私たちは、その力を尽くさなければなりません。もし私たちが、これ以上の犠牲を払わなければならないのなら、それは果たして「力を尽くした結果」といえるでしょうか?
これを書いている今も、一日に76万人が新幹線で駆け抜け、26万人が飛行機で国内の空を翔んでいます(*11)。その安全を心より願いながら‥。
2003年9月26日 2004年1月18日加筆
(*1)但しこの頃は、首都圏−札幌圏の鉄道旅客は微増を続けていた。国鉄北海道総局「経営概況
昭和45年版」によると、同区間の旅客数は、1964(昭39)年度の鉄道65.9万人/航空63.7万人に対し、1965(昭40)年度は鉄道69.6万人/航空72.4万人である。年度半ばの1965(昭40)年10月には、旅客の高速指向の高まりを受け、夜行急行格上げによる寝台特急「ゆうづる」(上野−青森間)が誕生している。
(*2)国鉄北海道総局「経営概況 昭和47年版」によると、首都圏−札幌圏の1971(昭46)年度の旅客数は、鉄道64.8万人/航空251.7万人であった。但し総輸送量が1965(昭40)年度と比べ、2.2倍(首都圏対札幌圏)と大幅に増加していたため、シェアの急激な低下にもかかわらず、国鉄の旅客輸送量自体は横バイであることに注意する必要がある。道内対本州輸送全体でみると、シェアの大幅な低下(1965年度83%→1971年度55%)にもかかわらず、国鉄の旅客輸送量は増加を続けていたのである(1965年度422.6万人→1971年度497.9万人)。このことが、本州対道内輸送の危機に対する状況判断を遅らせたことが想像される。
なお当時の運賃は、1969(昭44年)年当時、航空が12,900円に対し、鉄道は5,310円(2等、特急料金込)であった。また1971年度の首都圏−札幌圏旅客数は鉄道・航空合計して316.5万人(うち鉄道64.8万人)であるが、2000年度は936.9万人(うち鉄道17.5万人)と、実に約3倍に激増していることも特筆される。
(*3)1972年8月当時、羽田−千歳間には直行のジェット機が30往復、経由便のプロペラ機が1往復就航していた。その後、運輸省の指導により機材を大型化して26往復に減便したが、旅客数は一貫して増加し続けた。やむを得ず行われた増発により、1991年には再び30往復に達している。
(*4)この想定は、現在でこそ非現実的である。しかし1975(昭50)年の山陽新幹線博多延伸を分析すると、当時は妥当なものであったと考えられる。
新幹線と在来線特急を乗り継いで11時間を要した1974(昭49)年度の首都圏−福岡圏の旅客数は鉄道133.8万人/航空200.2万人(鉄道シェア36%)であったが、新幹線で7時間弱で結ばれた1975(昭50)年度には鉄道278.9万人/航空166.1万人(鉄道シェア63%)と鉄道利用者が倍増、シェアも大幅に増加した。全線260km/h運転で想定された東京−札幌間は、東京−博多間より所要時間が短く、シェアはさらに高くなると予想されたのである。
しかし新幹線の高いシェアは、大幅な運賃格差を前提に成立していたことが、すぐ明らかになる。赤字に悩む国鉄は、1975(昭50)年11月20日(平均32.2%)、1976(昭51)年11月6日(平均50.3%)と約1年のあいだに2度も大幅値上げを実施した。東京(羽田)−博多(福岡)間の運賃格差は2.0倍から1.3倍に縮小した。1976(昭51)年度は鉄道238.6万人/航空208.3万人(鉄道シェア53%)、続く1977(昭52)年度は鉄道165.3万人/航空258.3万人(鉄道シェア39%)、そして1978(昭53)年度は鉄道138.0万人/航空275.9万人(鉄道シェア33%)と、鉄道旅客の航空シフトが顕在化した。
1,000km超でも鉄道が高いシェアを獲得できたのは山陽新幹線の偉大な功績であったが、その成功は自らの相次ぐ運賃値上げにより、わずか1年で崩壊させてしまった。
(*5)定期航空便ではないが、1990(平2)年9月27日、延岡から宮崎空港へ飛行中の阪急航空機(川崎式BK117)が日向市山中で墜落、乗客・乗員10名全員が死亡した事故がある。同機は宮崎県延岡市に本社を持つ(株)旭化成が東京へ出張する社員のために飛ばしていたチャーター機であった。事故後、旭化成はチャーター機の使用を一切とりやめ、宮崎県が計画した延岡−宮崎間の鉄道高速化事業(総事業費24億円、所要時間72分→60分)に出資(3億円)した。同事業は、航空事故の犠牲の上に実現した鉄道整備として歴史に刻まれている。
(*6)御巣鷹以降の航空事故(原則として国内の航空会社が国内で起こしたものに限定したが、中華航空機は特に重大な事故なので加えた)
| 1988年 1月10日 |
米子発大阪行TDA670便(現JAS、YS11)
米子空港にて離陸失敗、オーバーラン。
乗客8名負傷。 |
| 1988年 1月18日 |
大阪発千歳行ANA779便(L1011)
千歳空港で着陸失敗、雪塊に突っ込み中破。
ケガ人ナシ。 |
| 1990年 9月27日 |
延岡から宮崎空港へ飛行中の阪急航空機(川崎式BK117)
日向市山中で墜落。乗客・乗員10名全員死亡。 |
| 1993年 4月18日 |
名古屋発花巻行JAS451便(DC−9−41)
花巻空港で着陸失敗して炎上。乗客・乗員58名負傷。 |
| 1993年 5月 2日 |
鹿児島発羽田行ANA(747−400D)
機内に白煙が立ち込めたため羽田空港に緊急着陸。
着陸後、脱出シューターを使用して避難する際、
乗客・乗員121名が負傷。 |
| 1994年 4月26日 |
台北発名古屋行中華航空140便(A300−600R)
着陸進入中に失速、墜落。
乗客・乗員271名中、264名が死亡。 |
| 1995年 6月21日 |
羽田発函館行ANA857便(747−100SR)
山形上空にてハイジャック、函館空港に緊急着陸。
乗客1名負傷。 |
| 1997年 1月20日 |
伊丹発福岡行ANA217便(777−200)
岩国上空にてハイジャック。機長の説得で福岡空港
に着陸。ケガ人はナシ。 |
| 1997年 9月 5日 |
香港発名古屋行JAL706便(MD−11)
知多半島上空にて操縦士の意思に反した機体振動
発生。乗客・乗員12名負傷。 |
| 1999年 7月23日 |
羽田発新千歳行ANA63便(747−400D)
羽田離陸直後にハイジャック。機長が殺害された後、
異常降下に陥り、羽田空港に緊急着陸。 |
| 1999年 9月30日 |
JAL機(747−400)、関西空港にてオーバーラン。
ケガ人はナシ。 |
| 2000年 2月16日 |
函館発札幌丘珠行ANK354便(YS−11A)
丘珠空港で着陸失敗、雪塊に突っ込み中破。
乗客10名負傷。 |
| 2000年 2月28日 |
JAS機(MD−90)、帯広(現とかち帯広)
空港にて着陸失敗、オーバーラン。ケガ人はナシ。 |
| 2000年 2月28日 |
北九州発羽田行JAS346便(MD−87)
羽田空港にて供用開始前(工事中)の滑走路に
誤着陸。ケガ人ナシ。 |
| 2000年 3月 9日 |
JAS機(DC−9)、青森空港にて着陸失敗。
オーバーラン。機体小破。ケガ人はナシ。 |
| 2000年 9月11日 |
名古屋発佐賀行ANA559便(A320)
佐賀空港進入中に機長が脳血管障害で意識
不明に。機長は病院に収容されたが、8日後
死亡。副操縦士が着陸させたため、その他の
乗員・乗客にケガ人はナシ。 |
| 2001年 1月31日 |
羽田発那覇行JAL907便(747−400D)
及びプサン発成田行JAL958便(DC−10)が
焼津上空にてニアミス。最接近時の高度差は
20〜60mと推定された。回避急降下中、907便
の乗客・乗員42名が負傷。 |
| 2001年 5月21日 |
関西発グアム行ANA173便(747−400)
公海上にて乱気流に遭遇。乗客・乗員20名
負傷。当時、機内にはシートベルト着用を促す
サインが点灯していなかった。 |
| 2001年 6月27日 |
名古屋発バンコク行JAL737便(DC−10)
離陸時にエンジン異常発生。
部品数百点が住宅密集地に落下。
小牧市内の男性1名が落下してきた部品に触れ
火傷。近隣の家屋や車にも被害が出た。 |
| 2001年 9月 6日 |
広島西発鹿児島行J−AIR571便(CRJ200)
機体に落雷を受けウイングレット損傷。
ケガ人ナシ。 |
| 2001年 9月20日 |
名古屋発鹿児島行ANA351便(A320)
エンジン停止して鹿児島に緊急着陸。
ケガ人ナシ。 |
| 2001年12月27日 |
新潟発那覇行ANA465便(A320−200)
富山県沿岸上空にて与圧低下。
同機は緊急降下の後、伊丹空港に緊急着陸。
ケガ人ナシ。 |
| 2002年 1月13日 |
福岡発高松行JAC81便(YS11)
山口市上空でエンジン停止、福岡に緊急着陸。
ケガ人ナシ。 |
| 2002年 1月21日 |
名古屋発函館行ANA391便(A321)
函館空港着陸時に激しいウインドシア(風向風力
の激変)に遭遇。着陸復航を試みたが、機体後部
が滑走路に激突。乗員3名負傷。 |
| 2002年 4月17日 |
ロンドン発成田行ANA202便(747−400)
着陸時に南西風に遭遇、エンジンカバーが滑走路
に擦れ小破。ケガ人ナシ。 |
| 2002年 9月27日 |
羽田発高知行ANA569便(767−200)
高知空港進入時に乱気流に遭遇。乗客1名負傷。
負傷した乗客はシートベルトを着用していた。 |
| 2002年10月 2日 |
羽田発新千歳行ANA59便(747−400)
栃木県上空にて操縦室より発煙、羽田に緊急着陸。
ケガ人ナシ。 |
| 2002年11月20日 |
ニューヨーク発成田行ANA47便(747−400)
着陸後にエンジン点検扉の欠損を確認。
飛行中脱落と推定。 |
| 2002年11月20日 |
名古屋発熊本行JAS423便(MD−90)
エンジントラブルで名古屋に緊急着陸。
ケガ人ナシ。 |
| 2003年 1月 4日 |
新千歳発釧路行HAC6253便(SAAB340B)
釧路空港で着陸時に雪塊に突っ込み停止。
ケガ人ナシ。 |
| 2003年 1月27日 |
インチョン(ソウル)発成田行
AIR JAPAN908便(767−300)
成田空港着陸時にオーバーラン。
ケガ人ナシ。 |
| 2003年 2月13日 |
成田発台北行JAA201便(747−200B)
東シナ海上空にてエンジントラブル。
那覇に緊急着陸。ケガ人ナシ。 |
| 2003年 2月20日 |
羽田発青森行JAS169便(A300−600R)
青森空港で着陸時にオーバーラン。ケガ人ナシ。 |
| 2003年 4月14日 |
新千歳発羽田行JAL540便(777−200・JAS機材)
エンジントラブルで羽田に緊急着陸。ケガ人ナシ。 |
| 2003年 5月24日 |
羽田発宮崎行JAS285便(MD−81)
機長室の窓から与圧漏れが確認される。ケガ人ナシ。 |
| 2003年 6月 1日 |
羽田発福岡発ANA245便(777)
機内で発煙・燃焼臭が確認されたため、広島に
緊急着陸。ケガ人ナシ。 |
| 2003年 7月31日 |
成田発ローマ行JAL409便(747−400)
離陸上昇中にエンジントラブルがあり、成田
空港に引き返した。
この際、茨城県総和町の工場内に部品落下。
建物屋根を破損。ケガ人ナシ。 |
| 2003年 8月 9日 |
鹿児島発与論島行JAC31便(YS−11)
着陸進入中に小形機とニアミス。ケガ人ナシ。 |
| 2003年10月 7日 |
羽田発八丈島行ANK821便(737−500)
着陸進入中に海上自衛隊の早期哨戒機(P3C)
とニアミス。ケガ人ナシ。最接近時の高度差は
30mと推定された。 |
| 2004年 1月 1日 |
鹿児島発徳之島行JAS979便(MD−81)
着陸時に左側主脚が折れ、左側主翼が接地。
乗客1名負傷。 |
(*7)たとえば2001年1月31日に発生した焼津上空でのニアミス(JAL907便、JAL958便)を、国土交通省航空・鉄道事故調査委員会の事故調査報告書(2002年7月12日)をもとに考えてみたい。
はじめJAL907便(羽田発那覇行、西行)はJAL958便(プサン発成田行、東行)より若干高い高度を飛んでいた。最接近の50秒前、担当管制官は管制卓のアラームにより、両機の接近の可能性を察知する。管制官はJAL907便に「降下」を指示、同機はこの指示に従い「降下」を開始開始した。実はこの指示は907便ではなく958便に対して行うべきものであったが、管制官が便名を取り間違えたために起きた誤指示であった。
まもなく907便と958便は接近、両機の衝突防止装置(以下TCAS)が作動した。この時907便のTCASは「上昇」を指示したが、管制官の指示に従い「降下」を続けた。一方958便はTCASの指示通り「降下」した。
担当管制官を指導中の指導管制官が事態の悪化に気づき、907便に「上昇」の指示を出そうとした。しかし、この際便名を「957便」と呼び間違えたため反映されなかった。一方958便のTCASは近づく907便に反応して「急降下」を指示、同機もこれに従ったため、両機はさらに接近した。
907便は雲上を飛行していたことが幸いし、ここで異常接近する958便を目視確認した。TCASは依然「上昇」を指示しており、管制からの新たな指示もなかったが、クルーはとっさに急降下でこれを交わそうとした。一方958便も異常接近する907便を目視、TCASは「急下降」を指示したままであったが、クルーは「上昇」に転じる判断を下した。
この結果、907便は958便の直下20〜60mを交差、空中衝突は回避された。
‥TCASと管制の指示の不一致が事態を悪化させたが、最終的にはTCASや管制の指示ではなく、目視によるとっさの判断で衝突を回避したことがわかる。事故調査報告書は、本事故を「主原因が管制官のミスにあり、これにTCASの運用規定の不備が競合したもの」と総括した。
この日上空の視界は良好で、両機が目視できたために事故は回避された。しかし、もし雲海の中での飛行で同じ状況が起きていたら‥。こうした偶然の連続を「安全に対する努力」で回避することが可能なのだろうか? 残された課題はあまりにも重い。
なお、事故後、米軍横田基地の空域が広すぎるために民間航空路の設定は狭くならざるを得ず、これが事故の素地を成すという指摘が一部の評論家や知事からあった。これは本事故に関しては適切なコメントであるが、我が国の航空事故を取り巻く状況に対する説明としては不十分である。というのも、羽田をはじめとする国内の主要空港やその周辺の空域は本事故の起きた焼津上空に比べてもはるかに過密な状態で日夜運用されており、当然事故の危険性もそれだけ高いと考えられるからである。過密空港の危険性は、世界でもっとも多くの死者を出した事故が、カナリア諸島サンタクルス・デ・テネリフェ島(スペイン領)テネリフェ空港で起きたKLMとパンナムのジャンボ機どうしの正面衝突事故(1977年3月27日発生。死者583名、重軽傷者58名)であることを考えれば容易に想像できる。
(*8)古い事故も含まれるので、以下に新幹線に係る重大と思われる事故を列記してみた。
| 1965年 5月 4日 |
東京発新大阪行17A列車(ひかり17号、後の0系12連)
名古屋駅停車時にスリップ。
ATC絶対停止区間を突破して380mオーバーラン。 |
| 1966年 4月25日 |
新大阪発東京行42A列車(ひかり42号、後の0系12連)
名古屋発車後、車掌が度重なる車軸からの火花を確認。
豊橋駅付近で非常停止。検査の結果、同列車の最後尾
1号車の車軸1本から折損によるキズを確認。 |
| 1966年 4月25日 |
営業列車通過後の新横浜−小田原間を走行していた
電気試験車(4連)が、保線作業機器をなぎ倒す。
飛んできた破片で保線作業員4名殉職。 |
| 1967年 7月23日 |
名古屋発新大阪行201A列車(こだま201号、後の0系12連)
岐阜羽島駅停車時にスリップ。ATC絶対停止区間を突破
して約1,000mオーバーラン。 |
| 1973年 2月21日 |
大阪運転所発新大阪行715A列車(回送、後の0系16連)
大阪運転所出発後、出庫線でスリップ。ATC絶対停止区間
を突破後、「210」信号等を受け、異常を感じた運転士が進路
未開通に気づき非常停止。総合指令所は後退を指示したが、
車両は既に分岐器を超え本線上に出ていたため、分岐器破損
して脱線。
なお絶対停止区間を突破した時、分岐器手前2.5km地点に東京
発新大阪行143A列車「こだま143号」(後の0系12連)が接近
していたが、ATCによる非常ブレーキがかかり、分岐器手前
467m地点で非常停止。追突を免れた。 |
| 1976年 7月 9日 |
新大阪発東京行210A列車「こだま210号」(後の0系16連)
三島から熱海近くまで13kmを無人走行。代わりの運転士が
席に着いたとき、列車はATCで所定の減速中であった。
国鉄は当初、事実を歪曲して報道発表。内部告発により無人
走行の事実が明らかとなった。 |
| 1977年 1月 8日 |
新大阪発東京行「こだま」」(後の0系16連)で主電動機支持
ボルト折損が発生したまま豊橋〜東京を走行、東京運転所帰
着後に発見された。 |
| 1983年 3月20日 |
大宮発新潟行153C列車(あさひ153号、200系12連)
越後湯沢駅到着時に床下より発煙、乗客2,000名が避難した。 |
| 1989年12月 7日 |
未明、名古屋運転所構内で入換中の新幹線車両(0系NH67、
16連)が絶対停止区間を突破。車止めを突き破った後に停止。
車種置換を進めていた最中でもあり、当該車両は車齢8年で
廃車。 |
| 1992年 5月 6日 |
新大阪発東京行238A列車(ひかり238号、300系J4、16連)
名古屋−三河安城間でブレーキホース破損。列車は非常停止、
現場で4時間以上立往生した。ボルトの緩みから駆動装置が
落下、地上で跳ねてブレーキホースを直撃したことが原因。 |
| 1995年12月27日 |
東京発名古屋行475A列車(こだま475号、0系16連)が三島駅
を発車する際、駆け込み乗車しようとした高校生の手を挟んだ
まま加速。高校生は列車に引きずられて、ホーム下に転落、
死亡。高校生はホームの公衆電話を利用した後、乗車中の列車
に戻ろうとして事故に遭った。
駆け込み乗車によるとはいえ、新幹線初の乗客死亡事故。
なお本件に係る民事訴訟では、JR東海の法人責任は認め
られなかったものの、安全対策部長と新幹線鉄道事業本部長
の責任を認め、使用者責任として同社から遺族に4,900万円
の支払いを命じる判決が、2001年3月7日、沼津地裁で言い
渡された。同社は東京地裁に控訴したが、最終的には同年11月、
6,000万円を支払い和解した。 |
| 1997年 5月 6日 |
岡山運転所構内で入換中の新幹線車両(0系Sk46、12連)で
入換運転士の居眠り運転発生。ATC絶対停止区間を突破後、
車止めを突き破って敷地外に飛び出し、公道上で停止。 |
| 1999年 6月27日 |
新大阪発博多行351A列車(ひかり351号、0系Sk17、12連)
小倉−博多間の福岡トンネル走行中、剥落したコンクリート片
(220kg)が9号車屋根を直撃、破損した。ケガ人はナシ。山陽
新幹線では深夜の一部列車を運休してトンネル総点検を行った。 |
| 1999年10月 8日 |
安中榛名−軽井沢間の一ノ瀬トンネル下り線でコンクリート片
(200kg)の落下が確認された。 |
| 1999年10月 9日 |
小倉−博多間の北九州トンネル内でコンクリート片5個(226kg)
の落下が確認された。トンネル総点検を受けての「安全宣言」後
の事故だけに不安が高まった。 |
| 2003年 2月26日 |
広島発東京行2126A列車「ひかり126号」(300系J、16連)、運転士
が居眠り。岡山駅のホーム半ばでATCによる所定の減速で停車、
居眠りが発覚した。運転士の証言から、新倉敷付近から岡山駅
まで約26kmの意識がないとのこと。この運転士は「睡眠時
無呼吸症候群」の疑いがあったとJR西日本は発表した。 |
(※)上表のほか、1991年に起こった100系X7編成の主電動機脱落に伴う車輪異常磨耗
状態での高速走行(東京から三島まで)も重大事故と考えられるが、会社からの発表が
なく(内部告発による情報のみ)事実関係を客観的に記せないので上表からは省いた。 |
(*9)鉄道総研WCRR01派遣団「JREA WCRR01(第5回世界鉄道研究会議)における発表論文の概要」『JREA』2002年2月号より。
(*10)運輸省「運輸白書 昭和61年版」内「(1)旅客輸送の動向」より。http://www.mlit.go.jp/hakusyo/transport/shouwa61/ind000901/001.html
なお文中で示した10.7%という数値は、事故発生以前の昭和57年度第2四半期から昭和60年度第1四半期までを回帰期間とする乗数型四半期モデルを構築、このモデルによる推計値と事故後の実績値を比較して求めたものである。またシェア変化の項で示した「事故前」は1985(昭60)年5〜7月、「事故後」は1985(昭60)年9〜11月を表す。 なお本文には記していないが、グリーン旅客の急増も特徴的である。新幹線の旅客需要は景気回復により事故前から増加していたが、事故後は増加幅が急伸、新横浜−小田原間で9%→26%増(普通車は9%→13%増)、小郡−小倉間で1%→42%(普通車は1%→6%)となった。このことから当時出張に航空機を利用していた企業の管理職クラスが新幹線グリーン車に振替えたことが読み取れる。
(*11)新幹線のATCは、状況に応じた速度を運転士に指示し、その速度を超えると自動的に減速されるような仕組みになっている。列車の最高速度(今回のケースでは270km/h+誤差5km/h=275km/h)を超えて加速しようとしても最高速度以下になるよう自動的に減速されるし、列車接近や駅停車などの場合も接近するにつれ徐々に速度が落ちるよう自動制御される。但し自動制御は30km/hまでで、そこから先は運転士が「確認ボタン」を押すこと(これを「確認扱い」という)によりATCの自動減速が解除され、運転士は所定の停止位置に停止させることができる。今回のケースでは、運転士が眠っていたため「確認扱い」がなされず、ATCの自動減速によりホーム半ばで停止したものである。なお「確認扱い」後、万一30km/hのままで停止位置を行き過ぎてしまっても、「絶対防護区間」と呼ばれる区間(50m)がその先に設けてあり、列車に対して出される「絶対停止信号」により、この区間内に停止するシステムとなっている。
(*12)新幹線の利用旅客は2001(平成13)年度実績、(財)運輸政策研究機構「数字で見る鉄道2003」より。但し事業者ごとに重複計算されている点に注意。航空の利用旅客も2001(平成13)年度実績、「数字で見る航空2003」より。