

丂丂丂丂丂丂丂

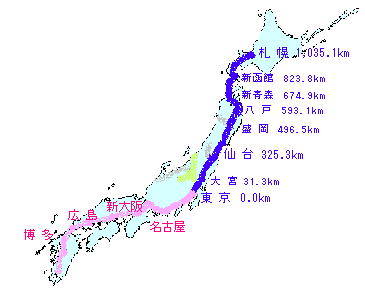
 | |
 | |
| 丂丂丂丂丂 丂丂丂丂丂丂丂  | |
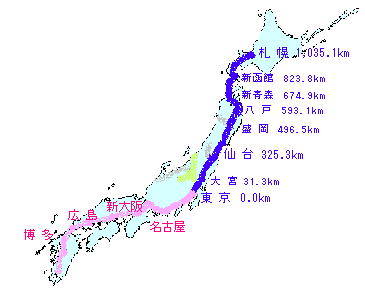 |
| _亅亅亅亅亅亅 | 墑挿 | 寁夋 嵟崅 懍搙 |
幚幙 嵟崅 懍搙 |
昗弨 嵟媫 岡攝 |
昗弨 嵟媫 嬋慄 |
廲嬋慄 敿宎 |
巤岺 婎柺 暆 |
婳摴 拞怱娫 嫍棧 |
320km/h 偺応崌偺 強梫帪娫 昞掕懍搙 |
300km/h 偺応崌偺 強梫帪娫 昞掕懍搙 |
| 搶嫗-戝媨 | 31.3km | 110km/h | 130km/h | 25侎 | 丂600m | 5,000m | 11.3m | 4.0m | 栺丂 19m 101.6km/h |
栺丂 19m 101.6km/h |
| 戝媨-惙壀 | 465.2km | 260km/h | 350km/h | 15侎 | 4,000m | 15,000m | 12.2m | 4.3m | 栺侾h38m 284.1km/h |
栺1h42m 273.6km/h |
| 惙壀-怴惵怷 | 178.4km | 260km/h | 350km/h | 20侎 | 4,000m | 15,000m | 11.7m | 4.3m | 栺 丂37m 289.3km/h |
栺 丂38m 278.0km/h |
| 怴惵怷-嶥杫 | 360.2km | 260km/h | 350km/h | 35侎 | 4,000m (6,500m) |
25,000m | 11.7m | 4.3m | 栺侾h14m 290.1km/h |
栺1h18m 276.2km/h |
| (嶲丂 峫) 崅嶈亅挿栰 |
117.4km | 260km/h | 300km/h | 30侎 | 4,000m | 15,000m | 11.2m | 4.3m | 丂丂 亅 | 栺丂 36m 195.7km/h |
| 乮嶲丂峫乯 搶嫗-怴戝嶃 |
515.3km | 200km/h (250km/h) |
270km/h | 25侎 | 2,500m | 10,000m | 10.7m | 4.2m | 亅 | 丂 俀h30m 206.1km/h |

丂戝媨亅惙壀娫偼丆嶳梲怴姴慄
壀嶳亅攷懡娫偱妋棫偝傟偨乽慡崙惍旛怴姴慄栐乿偺昗弨愝寁丆偡側傢偪260km/h塣揮傪慜採偲偟偨峔憿偲側偭偰偄傑偡丅
丂1-1丏搚栘峔憿暔 乣僐儞僋儕乕僩峔憿暔偺懡梡乣
丂嶳梲怴姴慄偱偼丆搶奀摴怴姴慄偱懡梡偝傟側偑傜傕儊儞僥僫儞僗偺栵夘偩偭偨搚惙峔憿傪偱偒傞尷傝攔偟丆慡慄偺傎偲傫偳傪僐儞僋儕乕僩崅壦嫶偲僩儞僱儖丆嫶傝傚偆偺傒偱峔惉偟傑偟偨丅搶杒怴姴慄傕偙傟偵弨偠偰偄傑偡丅偙偺寢壥丆峔憿暔偺斾棪偼丆戝媨亅惙壀娫偱丆崅壦嫶丒嫶傝傚偆
72亾丆僩儞僱儖 23亾丆楬斦(搚惙丒孈妱)俆亾偲側偭偰偄傑偡乮仏侾乯丅
丂傑偨愥偺塭嬁傪峫椂偟偰丆巤岺婎柺暆傕12.2倣乮挋愥宆崅壦嫶偺応崌乯偲峀偔庢傜傟偰偄傑偡丅
乮仏侾乯丗戝娧 晉晇乽杒棨怴姴慄崅嶈乣挿栰娫偺寶愝傪傆傝偐偊偭偰乿亀塣桝偲宱嵪亁1999擭俀寧崋p.17
丂墂偵偮偄偰傕丆彨棃偺搶奀摴丒嶳梲怴姴慄偲偺捈捠傗桝憲椡憹嫮傪峫偊丆桳岠挿偼430m(16椉亄30倣)傪妋曐偟偰偄傑偡丅奐嬈帪偺楍幵杮悢偼偦傟傎偳懡偔側偐偭偨妱偵丆暃杮慄乮亖懸旔慄乯傗偦偺弨旛岺帠偑懡偄偺傕摿挜偲偝傟傑偟偨丅偨偲偊偽幨恀偺暉搰墂偼彨棃偺慡崙惍旛怴姴慄栐寁夋傪尒墇偟偰丆墱塇怴姴慄乮僼儖婯奿乯偺暘婒墂偲側傞偙偲偑梊憐偝傟偨偨傔丆忋壓偺杮慄乮亖捠夁慄乯奺侾杮媦傃暃杮慄乮亖懸旔慄乯奺俀杮偺寁俇慄傪帩偭偰偄傑偡丅搶杒怴姴慄奐嬈偺10擭屻偵幚尰偟偨嶳宍怴姴慄乮儈僯怴姴慄乯偱偼丆岺帠旓愡栺偺偨傔丆庢晅慄傪壓傝戞俀暃杮慄偺傒偵愙懕偝偣丆怴嵼捈捠偺乽偮偽偝乿偼忋壓楍幵偲傕摨堦慄楬(椃媞埬撪忋偺14斣慄)偵敪拝偝偣偰偄傑偡丅
 16椉曇惉偺楍幵偑搊応偟偨偺偼奐嬈屻俋擭傪宱偨1991擭偺偙偲丅 奐嬈屻20擭傪宱偨偑丆忋傝戞俀暃杮慄傪巊偆掕婜楍幵偼崱偩偵側偄丅 2000/07/15丂(48俛亖暉搰敪15:49) 乮壓乯庢晅慄偐傜暉搰墂偵恑擖偡傞嶳宍怴姴慄偺怴嵼捈捠乽偮偽偝乿丅 岺帠旓傪愡栺偡傞偨傔丆庢晅慄偼壓傝戞俀暃杮慄偵岦偐偆侾杮偺傒丅 2000/07/27丂(132俵亖暉搰拝14:14)  |
丂搶奀摴怴姴慄偵斾傋傞偲丆椃媞愝旛傕廩幚偟偰偄傑偡丅慡墂偑崅壦俁憌幃偱丆僐儞僐乕僗傪俀奒丆儂乕儉傪俁奒偵抲偄偨峔憿傪昗弨揑偵梡偄傜傟傑偟偨丅幨恀偺愬戜墂偵偼悂偒敳偗峔憿偑梡偄傜傟丆奐曻姶偑墘弌偝傟偰偄傑偡丅
 夋柺嵍壓偺侾奒偑嵼棃慄丆夋柺嵍忋偺俀奒偑怴姴慄偺夵嶥丅 幍梉僔乕僘儞乮媽楋乯側偺偱丆幍梉偺忺傝晅偗偑巤偝傟偰偄傞丅 2000/08/09 14:25 |
丂偙偺傛偆偵丆夁忚側傑偱偵棫攈側愝旛偵巇忋偑偭偨偨傔丆寶愝旓傕敎戝側妟偵偺傏傝傑偟偨丅崙忣偑堘偆偲偼偄偊丆僉儘摉偨傝偺寶愝旓偼摨帪婜偵奐嬈偟偨僼儔儞僗俿俧倁偺幚偵10攞嬤偔偵払偟丆戝媨埲杒偱斾妑偟偰傕俈乣俉攞傕偺奐偒偑偁傝傑偡乮仏俀乯丅崙揝偺嵿惌帠忣偑昇敆偟偰偄偨偙偲傕偁傝丆奐嬈摉帪偼乽柍懯側搳帒乿乽夁忚愝旛乿偲偺斸敾傪嫮偔庴偗偰偄傑偟偨丅奐嬈屻栺10擭傪宱夁偟偰16楢楍幵傕愝掕偝傟丆1997擭偵偼愬戜埲杒偺暃杮慄偱懸旔傪峴偆掕婜楍幵偑愝掕偝傟傞偵帄傝傑偟偨偑丆偙偺愝旛搳帒偑亀怴姴慄偺寶愝旓偼敎戝偱丆崙揝偺嵿惌傪埑敆偟偨亁偲偺報徾傪恖乆偵怉偊晅偗偨柺傕斲掕偱偒偢丆斀徣偡傋偒揰偑懡乆偁傞傛偆偵巚偄傑偡丅
乮仏俀乯丗僽儔僀傾儞亖儁儗儞挊 廐嶳朏峅丒惵栘恀旤栿乽俿俧倁僴儞僪僽僢僋乿p.2偵傛傞偲丆俿俧倁僷儕撿搶慄(TGV-PSE=ParisSudEst)偺寶愝旓偼丆怴慄417.0km(Lieusaint
Moissy亅Sathonay娫媦傃巟慄)偱97.98壄僼儔儞(1990擭壙奿丆幵椉旓娷傑偢)丆摉帪偺儗乕僩偱栺2,645.5壄墌(侾僼儔儞=27墌)偩偐傜丆戝嶨攃偵尵偊偽僉儘摉偨傝6.34壄墌偱偁傞丅堦曽丆怴姴慄塣揮尋媶夛曇亀怴斉
怴姴慄亁pp.454-455乮擭昞乯偵傛傞偲丆搶杒怴姴慄忋栰乣惙壀娫492.9km偺寶愝旓偼俀挍8,010壄墌(徍榓57擭搙壙奿丆幵椉旓娷傑偢)偩偐傜丆僉儘摉偨傝56.83壄墌偲側傞丅傕偪傠傫搒怱晹偺忋栰亅戝媨娫偵敎戝側寶愝旓傪梫偟偨偙偲偼帠幚偩偑丆偦傟傪嵎偟堷偄偰傕備偆偵俈乣俉攞偺嵎偑偁傞丅側偍俿俧倁僷儕撿搶慄偲搶杒怴姴慄偺幵椉旓傪斾妑偡傞偲丆俿俧倁偑俉椉109曇惉偱栺82壄僼儔儞亖2,214壄墌偵懳偟偰丆搶杒怴姴慄偼12椉30曇惉偱1.244壄墌偲丆傓偟傠怴姴慄偺傎偆偑埨偄偨傔丆幵椉旓傪娷傔偨憤帠嬈旓偱斾妑偡傞偲丆壙奿嵎偑庒姳側偑傜弅彫偡傞丅
丂1-2丏婳摴峔憿 乣僗儔僽婳摴偲60kg儗乕儖偺慡柺嵦梡乣
丂嶳梲怴姴慄偱偼丆廬棃偺僶儔僗僩傪晘偄偨忋偵枍栘丒儗乕儖傪晘愝偡傞乽僶儔僗僩婳摴乿傪丆僐儞僋儕乕僩斅乮僗儔僽乯忋偵嬥嬶偱儗乕儖傪掲寢偟偨乽僗儔僽婳摴乿庡懱偵曄峏偟偰丆崅懍塣揮偵敽偆婳摴儊儞僥僫儞僗傪戝暆偵尭傜偟傑偟偨丅搶杒怴姴慄偱偼丆儊儞僥僫儞僗僼儕乕偵壛偊丆愥奞懳嶔偺堄枴傕偁傝乽僗儔僽婳摴乿偺巊梡斾棪偑忋偑偭偰偄傑偡丅僶儔僗僩婳摴偵傛傞愥奞偲偼丆掅壏偱幵懱偵搥傝偮偄偨愥夠偑夝偗偰僶儔僗僩忋偵棊偪丆徴寕偱僶儔僗僩偑挼偹偰幵懱傗憢僈儔僗傪攋懝偡傞尰徾偺偙偲偱偡丅偙偺寢壥丆搶杒怴姴慄偱乽僗儔僽婳摴乿偺愯傔傞斾棪偼忋栰亅惙壀娫慡懱偺83.8亾偵傕媦傫偱偄傑偡乮仏俁乯丅
丂巊梡偝傟傞儗乕儖傕丆摉帪偺搶奀摴怴姴慄傛傝懢偄60kg儗乕儖偑嵦梡偝傟偰偄傑偡丅搶奀摴怴姴慄偺儗乕儖偼侾倣摉偨傝偺廳偝偑53.3kg偺乽50俿儗乕儖乿偱偟偨偑丆奐嬈屻偺幚愌偐傜丆嵶偄儗乕儖偱偼儗乕儖偺杹栒偑挊偟偄偙偲偑傢偐偭偨偨傔偱偡丅
丂側偍1970乣80擭戙偺庒曉傝岺帠偵傛傝丆尰嵼偼搶奀摴怴姴慄傕慡慄偱60kg儗乕儖偑巊傢傟偰偍傝丆岎姺偝傟偨50俿儗乕儖偼惵敓僩儞僱儖偺傾僋僙僗傪扴偆峕嵎慄乮栘屆撪亅屲椗妔娫偺堦晹乯側偳偵揮梡偝傟偰偄傑偡丅
乮仏俁乯亀揝摴 岡攝廲抐恾偺椃丂搶杒慄丒墱塇慄亁乮彫妛娰,1986乯p.32
丂1-3丏岡丂攝丂乣崅懍壔偺偨傔偵戝暆娚榓乣
丂嶳梲怴姴慄偺嵟媫岡攝偼丆搶奀摴怴姴慄偺20侎傛傝娚傔丆怴娭栧僩儞僱儖忋傝曽偺椺奜乮18侎乯傪彍偄偰慡偰15侎埲撪丆10km埲忋偺暯嬒岡攝偼慡偰12侎埲撪偵梷偊傑偟偨丅搶杒怴姴慄傕偙傟偵弨偠偨岡攝忦審偱偡丅
丂偙偺婎弨偼丆搶奀摴怴姴慄偺娭儢尨晅嬤偱嵦梡偟偨嵟媫20侎岡攝嬫娫(10km偺暯嬒岡攝13侎)偱儌乕僞乕偺壏搙忋徃偑尷奅偵払偟偰偟傑偆嫵孭傪惗偐偟偨傕偺偱丆慡慄偱柍棟偺側偄楢懕260km/h塣揮傪峴偆偨傔偵愝掕偝傟偰偄傑偡乮仏係乯丅
乮仏係乯怴姴慄塣揮尋媶夛曇乽怴斉丂怴姴慄乿乮1984乯p.133
丂1-4丏嬋慄敿宎丂乣嵟彫R4,000偵奼戝乣
丂嶳梲怴姴慄偱偼嬋慄敿宎傕奼戝偝傟傑偟偨丅搶奀摴怴姴慄偱偼250km/h塣揮偑壜擻側敿宎偲偟偰R2,500傪昗弨嵟媫敿宎偲掕傔傑偟偨丅偟偐偟幚嵺偵250km/h偱憱傞偲忔傝怱抧偑偁傑傝傛偔側偄偲敾抐偝傟傑偟偨丅偦偙偱丆傛傝傛偄忔傝怱抧偱260km/h塣揮偑壜擻側傛偆丆R4,000傪嵟媫昗弨敿宎偲偟偨偺偱偟偨丅搶杒怴姴慄傕偙傟偵弨偠偰偄傑偡乮仏俆乯丅幨恀偺嶳梲怴姴慄彫孲墂峔撪偺嬋慄偑敿宎4,000m乮亖R4,000乯偱偡偑丆娚偔姶偠傞曽偑懡偄偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丠
 嶳梲怴姴慄 彫孲墂偵偰丅 嶳梲怴姴慄埲崀偺昗弨嵟媫嬋慄 俼4,000亖敿宎4,000倣偺嬋慄偼丆偙傫側姶偠偺嬋偑傝嬶崌丅 悽奅嵟懍偺墂娫暯嬒懍搙(峀搰亅彫憅丆261.8km/h)傪屩傞乽500宯偺偧傒乿偑堦弖偱旘傃嫀偭偰備偔丅 2002/03/09 丂501俙亖彫孲捠夁 8:44 |
丂僇儞僩偱懪偪徚偣偢偵忔媞偑姶偠傞墦怱椡偺偙偲傪乽挻夁墦怱椡乿偲偄偄丆偙傟傪懪偪徚偡偺偵杮棃昁梫側僇儞僩検傪乽僇儞僩晄懌検乿偲偄偄傑偡丅忔媞偑晄夣姶傪傕傛偍偝側偄僇儞僩晄懌検偺忋尷偼寁嶼忋105乣110mm偲偝傟丆搶奀摴怴姴慄寁夋帪偼20亾掱搙偺梋桾傪尒偰90mm傪乽僇儞僩晄懌検乿偺嵟戝抣偲偟偰偄傑偟偨丅偙偺抣傪慜採偵丆僇儞僩傪嵟戝偺200mm傑偱堷偒忋偘偨応崌偺R2,500偺捠夁懍搙偑250km/h偲側傞傢偗偱偡丅偪側傒偵丆R2,500偼1940擭偵寁夋偝傟偨乽怴姴慄乿乮偄傢備傞抏娵楍幵乯寁夋偺僗儁僢僋傪偦偺傑傑堷偒宲偄偩傕偺偱偡乮仏俇乯丅
丂偲偙傠偑搶奀摴怴姴慄奐嬈屻偺幚愌偱偼丆忔媞偺忔傝怱抧傪曐偮偨傔丆僇儞僩晄懌検偼嵟戝偱傕60mm丆忔傝怱抧偺揰偐傜偼30mm埲撪偵廂傔傞偺偑朷傑偟偄偲偄偆偙偲偵側傝傑偟偨丅偦偙偱壀嶳亅攷懡娫偱偼昗弨嵟媫嬋慄傪R4,000偲偟丆偦偺僇儞僩検傪155mm偵愝掕偟傑偟偨丅偙偺嬋慄傪260km/h偱憱峴偟偨帪丆僇儞僩晄懌検偼44mm偲側傝傑偡丅
丂尰嵼偼忔傝怱抧傪傗傗媇惖偵偟偰偱傕崅懍壔傪恾傞娤揰偐傜丆僇儞僩晄懌検傪110mm掱搙傑偱嫋梕偟偰嬋慄捠夁懍搙傪崅傔傞傛偆偵偟偰偍傝丆R2,500偼255km/h(僇儞僩検200mm偺応崌)偱乮仏俈乯丆R4,000偼300km/h(僇儞僩検155mm偺応崌)偱丆偦傟偧傟捠夁偡傞偙偲傪擣傔偰偄傑偡丅
丂偟偐偟尰嵼偺僇儞僩検傪慜採偵偟偨応崌丆嵟媫昗弨敿宎偱偁傞R4,000偺嬋慄嬫娫偱偺300km/h埲忋傊偺岦忋偼崲擄偱丆崱屻偺僗僺乕僪傾僢僾偺戝偒側壽戣偲側偭偰偄傑偡丅
乮仏俆乯怴姴慄塣揮尋媶夛曇乽怴斉丂怴姴慄乿乮1984乯p.132
乮仏俇乯妏杮椙暯乽怴姴慄丂婳愓偲揥朷乿(1994丆岎捠怴暦幮)p.10傛傝丅
乮仏俈乯戝濳 攷慞乽怴姴慄偺偧傒敀彂乿(1992丆怴挭幮)pp.125-128
1-5丏廲嬋慄敿宎 乣崅懍壔偺偨傔奼戝乣 丂廲嬋慄偲偼丆乽慄楬偺岡攝偑曄壔偡傞屄強偵偍偄偰丆幵椉偺晜偒忋偑傝偵傛傞扙慄杊巭傗椃媞偺忔怱抧側偳偐傜乮拞棯乯廲曽岦偵愝偗傜傟傞嬋慄乿傪偄偄傑偡乮仏俉乯丅 丂偙傟傪忋偺恾偱愢柧偟傑偟傚偆丅恾偺傛偆偵丆岡攝偺曄峏揰偱偼丆恾柺忋偼乽岡攝曄峏揰乿偲屇偽傟傞捀忋傑偱搊傝媗傔偰偐傜崀傝巒傔傞偙偲偵側傝傑偡丅偟偐偟幚嵺偵偼捀忋晅嬤偱彴偑嶤傟偰偟傑偆偙偲偑峫偊傜傟傑偡丅偦偙傑偱嬌抂偱側偄偵偟偰傕丆忋傝岡攝傪搊偭偰偄傞楍幵撪偵偄傞忔媞偵偼忋岦偒偺姷惈椡偑偐偐偭偰偄傞偺偱丆媫偵壓傝岡攝偵揮偠偨偲偼丆斀懳岦偒偺椡偑忔媞偵偐偐偭偰丆偪傚偆偳僕僃僢僩僐乕僗僞乕偵忔偭偰偄傞偲偒偺傛偆側晄夣姶傪姶偠傑偡丅楍幵偑崅懍偱偁傟偽偁傞傎偳丆偦偺塭嬁偼尠挊偱偡丅偦偙偱嵍恾偺傛偆偵丆岡攝曄峏揰晅嬤偵悅捈曽岦偺嬋慄傪擖傟丆妸傜偐偵忋傝岡攝偐傜壓傝岡攝偵揮偠傞傛偆偵偡傞傢偗偱偡丅偙偺嬋慄傪c嬋慄苽C偦偺敿宎俼傪乽廲嬋慄敿宎乿偲屇傃傑偡丅 丂廲嬋慄忋偺幵椉晜偒忋偑傝側偳丆埨慡柺偐傜偼幵椉偵偐偐傞廳椡壛懍搙亖俧偑0.1埲壓偑婎弨偱偡偑丆忔傝怱抧忋偼0.05俧埲壓偲偡傞偺偑朷傑偟偄偲偝傟偰偄傑偡丅崙揝偱偼偦偺2/3偵偁偨傞0.033俧傪栚埨偲偟偰偄傑偟偨丅 丂搶奀摴怴姴慄偱偼丆200km/h偱0.033俧丆250km/h偱0.05俧偲側傞廲嬋慄敿宎偲偟偰俼亖10,000m傪嵦梡偟偰偄傑偟偨丅偙偺悢抣偼丆愴慜1940擭偵寁夋偝傟偨乽怴姴慄乿乮偄傢備傞抏娵楍幵乯寁夋偺僗儁僢僋傪偦偺傑傑堷偒宲偄偩傕偺偱偡丅 丂偟偐偟嶳梲怴姴慄偱偼丆260km/h偱0.033G偲側傞俼亖15,000倣傪嵦梡丆埲屻偺怴姴慄傕15,000m傪婎弨偲偟偰偄傑偡丅偪側傒偵摨帪婜偵寶愝偝傟丆愝寁嵟崅懍搙300km/h傪屩偭偨僼儔儞僗偺俿俧倁亅Paris Sud Est乮僷儕撿搶慄乯偺廲嬋慄偼俼亖16,000倣偱偁傝丆2001擭俇寧偵幚巤偟偨摨慄偺僗僺乕僪傾僢僾(270km/h仺300km/h)偺嵺傕栤戣側偔懳墳偟偰偄傑偡乮仏俋乯丅 (仏俉)怴姴慄塣揮尋媶夛曇乽怴斉丂怴姴慄乿乮1984乯p.134 乮仏俋乯嵅摗朏旻乽悽奅偺崅懍揝摴乿(1997)p.308 |
丂1-6.揹婥宯摑偺夵椙 乣俙俿偒揹壔偲廳壦慄壔乣
丂
丂仜1-6-1.偒揹曽幃偺曄峏乮俛俿仺俙俿壔乯乮仏侾乯
丂嶳梲怴姴慄偱偼丆偒揹曽幃傪搶奀摴怴姴慄偺俛俿曽幃偐傜俙俿曽幃偵曄峏偟傑偟偨丅
丂偲偙傠偱丆夝愢偺慜偵乽偒揹乿偲偼堦懱壗偱偟傚偆偐丠
丂岎棳傪揹尮偲偡傞怴姴慄偱偼丆壦慄乮僩儘儕慄乯偐傜庴偗偰儌乕僞乕傪夞偟偨屻偺揹棳丆偄傢備傞婣慄揹棳偑儗乕儖偐傜戝抧傊楻傟傞偙偲偵傛偭偰丆廃曈偺捠怣慄側偳偵忈奞傪梌偊傞揹帴桿摫偑婲偒偰偟傑偄傑偡丅偙傟傪杊偖偨傔丆婣慄揹棳傪儗乕儖偐傜媧偄庢偭偰丆壦慄偲偼暿偺揹慄傪夘偟偰曄揹強偵曉偟偰傗傞昁梫偑偁傝傑偡丅偙傟傪乽偒揹乿偲偄偄丆婣偡偨傔偺揹慄傪乽偒揹慄乿偲偄偄傑偡丅偄傢偽乽儅僀僫僗偺壦慄乿偲偄偭偨偲偙傠偱偟傚偆偐丅
丂搶奀摴怴姴慄偱偼乽俛俿偒揹乿偲偄偆曽朄傪巊偭偰偄傑偟偨丅偙傟偼俛俿乮僽乕僗僞乕僩儔儞僗亖媧忋曄埑婍乯傪3.0km乮巗奨抧偱偼1.5km乯偛偲偵愝偗丆俛俿傪夘偟偰儗乕儖偵棳傟傞婣慄揹棳傪乽偒揹慄乿偵媧偄忋偘傞傕偺偱偡丅侾偮偺俛俿偑庴偗帩偮斖埻偼1.5側偄偟3.0km偱偁傝丆堎側傞俛俿偑庴偗帩偮嬫娫偺嫬奅偵偼僽乕僗僞乕僙僋僔儑儞偑愝偗傜傟傑偟偨丅
丂偙偺僽乕僗僞乕僙僋僔儑儞偱偼丆壦慄乮僩儘儕慄乯偵傕愨墢嬫娫傪愝偗側偗傟偽側傝傑偣傫丅偟偐偟愨墢嬫娫傪椡峴忬懺偱捠夁偡傞偲丆僷儞僞僌儔僼偲僩儘儕慄偺揹埵嵎偵傛傝傾乕僋乮揹婥壩壴乯傪惗偠丆憃曽嫟捝傔偰偟傑偄傑偡丅偲偄偭偰3km枅偵懩峴偟偰偄偨偺偱偼丆埨掕偟偨崅懍塣揮偑偱偒傑偣傫丅偦偙偱僽乕僗僞乕僙僋僔儑儞偺慜屻偵掞峈婍傪憓擖偟偰丆堦扷揹棳傪庛傔偰偐傜愨墢嬫娫偵擖傞傛偆偵偟傑偟偨丅偙傟偱傾乕僋偼恏偆偠偰嫋梕斖埻偵廂傔傞偙偲偑壜擻偵側傝傑偟偨丅偙偺曽朄偑奐敪偝傟偨偺偼奐嬈10儢寧慜偺1963擭12寧偱丆揹婥宯摑偼岺婜傪嬐偐俉儢寧偟偐妋曐偱偒側偄傎偳偺撍娧嶌嬈偲側偭偨偺偱偟偨丅
丂偟偐偟俛俿偒揹曽幃偺崻姴傪惉偡僽乕僗僞乕僙僋僔儑儞偼丆偙偺憓擖掞峈偺懠偵傕丆愨墢傪妋曐偡傞偨傔偺嬻婥幷抐婍傪偼偠傔丆峔憿偑戝曄暋嶨側傕偺偱偟偨丅揹婥宯摑偺屘忈偺戝敿偼僽乕僗僞乕僙僋僔儑儞偑愯傔傞傎偳偩偭偨偺偱偡丅偙偺偨傔僽乕僗僞乕僙僋僔儑儞偺側偄丆怴偟偄偒揹曽幃偲偟偰搊応偟偨偺偑俙俿乮僆乕僩僩儔儞僗乯曽幃偱偡丅
丂俙俿曽幃偱偼丆偒揹慄偲僩儘儕慄偺偁偄偩偵扨姫曄埑婍傪暲楍愙懕偝偣丆曄埑婍偺拞惈揰傪儗乕儖偵愙懕偝偣偰偄傑偡丅婣慄揹棳偼幵椉偺慜屻偺儗乕儖偵棳傟丆拞惈慄傪夘偟偰扨姫曄埑婍偺敿暘偺僐僀儖乮拞惈揰乣偒揹慄乯偵棳傟傑偡丅偙偺偲偒丆偙偺揹棳傪懪偪徚偡偩偗偺揹棳偑傕偆敿暘偺僐僀儖乮僩儘儕慄乣拞惈揰乯偵棳傟傞偺偱丆偙傟偑儗乕儖傪棳傟傞婣慄揹棳傪媧偄忋偘傞岠壥傪帩偪傑偡丅俙俿曽幃偺扨姫曄埑婍偼丆俛俿曽幃偺媧忋曄埑婍偲堎側傝丆僩儘儕慄偵暲峴偵愙懕偝傟傞偨傔丆僽乕僗僞乕僙僋僔儑儞偼晄梫偱偡丅
丂俙俿曽幃偺嵦梡偱丆僽乕僗僞乕僙僋僔儑儞攑巭偵敽偆儊儞僥僫儞僗僼儕乕壔偑恑傒丆曄揹強娫妘傪攞偺40乣50km偵偱偒傞偙偲偱宱嵪惈傕崅傑傝傑偟偨丅
丂屻偵僗僺乕僪傾僢僾偲掅憶壒壔偺椉棫偑媮傔傜傟傞傛偆偵側傞偲丆憶壒尮偲側傞曇惉拞偺僷儞僞僌儔僼傪尭傜偡搘椡偑側偝傟傞傛偆偵側傝傑偟偨丅僷儞僞僌儔僼傪尭傜偡埲忋丆侾偮偺僷儞僞僌儔僼偵棳傟傞揹棳偼戝偒偔側傝傑偡偑丆斀柺丆俛俿曽幃偺応崌僽乕僗僞乕僙僋僔儑儞偱敪惗偡傞傾乕僋傕戝偒偔側傞栤戣揰偑偁傝傑偡丅偦偺偨傔偵偼憓擖掞峈傪戝偒偔偡傞昁梫偑偁傝傑偡偑丆偁傑傝偵掞峈傪戝偒偔偡傞偲崱搙偼揹棳傪庛傔傞偳偙傠偐丆揹棳傪棳偝側偄乮愨墢乯忬懺偵嬤偯偄偰偟傑偆偺偱偙傟傕崲擄偱偡丅寢嬊丆僷儞僞僌儔僼偺嶍尭偼俛俿曽幃偱偼柍棟偱丆搶奀摴怴姴慄傕俙俿壔偝傟傞偙偲偵側傝傑偟偨丅
丂搶杒丒忋墇怴姴慄偼崙揝帪戙偵僷儞僞僌儔僼傪曇惉拞俇屄偐傜俁屄乮屻偵俀屄乯傑偱尭傜偡偙偲偑偱偒偨偺偱偡偑丆搶奀摴丒嶳梲怴姴慄偵偮偄偰偼尭傜偡偙偲偑偱偒傑偣傫偱偟偨丅
丂搶奀摴怴姴慄偺俙俿壔偼崙揝帪戙偺1984擭偐傜奐巒偝傟丆暘妱柉塩壔屻偺1991擭偵姰惉偟傑偟偨丅偙傟偵傛傝堦晹偺曄揹強偑攑巭W栺偝傟偨懠丆楍幵偺曇惉拞偺僷儞僞僌儔僼傕偦傟傑偱偺俇乣俉屄偐傜堦婥偵俁屄偵尭傝丆1994擭偵偼偲偆偲偆俀屄偲側偭偨偺偱偟偨丅
乮仏侾乯怴姴慄塣揮尋媶夛曇乽怴斉丂怴姴慄乿乮1984乯pp.154-179
丂仜1-6-2.堎憡偒揹曽幃偺曄峏乮忋壓慄暿仺曽柺暿乯乮仏侾乯
丂搶奀摴怴姴慄偱偼忋壓慄偺婣慄揹棳偺堎憡傪90搙偢傜偟偰偍屳偄傪懪偪徚偟偁偄丆増慄傊偺揹帴桿摫忈奞偑彫偝偔側傞偙偲傪慱偭偰偄傑偟偨丅偙傟傪乽忋壓慄暿堎憡偒揹曽幃乿偲尵偄傑偡丅
丂嶳梲怴姴慄偱偼栭峴楍幵偺塣揮偑寁夋偝傟偰偄傑偟偨偑丆偁傢偣偰抧忋愝旛偺曐庣傕峴偆昁梫偑偁傝傑偡丅偙偺偨傔怺栭帪娫懷偼丆曅曽偺慄楬傪曐庣偟側偑傜丆傕偆曅曽偺慄楬偵栭峴楍幵傪塣揮偡傞扨慄塣揮傪峴偆偙偲偵側傝傑偟偨丅扨慄塣揮偱搶奀摴怴姴慄偺曽幃傪偦偺傑傑嵦梡偡傞偲丆忋壓慄偱懪偪徚偟偁偆偲偄偆慜採帺懱偑曵傟偰偟傑偆偨傔丆揹帴桿摫忈奞偑惗偠傑偡丅傑偨搶奀摴怴姴慄偺曽幃偱偼丆忋壓慄偺堎憡偑堎側傞偨傔丆忋壓慄偺榡傝慄偺晹暘偵堎憡僙僋僔儑儞傪愝偗傞昁梫偑偁傝丆墂峔撪偺壦慄峔憿偑暋嶨偵側傞傎偐丆楍幵偑忋壓慄娫偺榡傝慄傪懩峴偡傞昁梫偑偁傝傑偡丅
丂偦偙偱忋壓慄傪傑偲傔偨儁傾傪嬫娫枅偵偮偔傝丆椬愙偡傞俀偮偺嬫娫偳偆偟偱揹帴桿摫忈奞傪懪偪徚偟偁偆乽曽柺暿堎憡偒揹曽幃乿偑嵦梡偝傟傑偟偨丅偙偺曽幃偩偲丆扨慄塣揮偱傕埨掕偟偨偒揹偑峴偊傑偡丅傑偨忋壓慄偺堎憡偑摨偠側偺偱丆榡傝慄偵堎憡僙僋僔儑儞傪愝偗傞昁梫偑側偔側傝丆扨慄塣揮偱昿敪偡傞傢偨傝慄捠夁拞傕椡峴偡傞偙偲偑壜擻偲側傝傑偟偨丅
丂側偍搶奀摴怴姴慄傕慜弎偺俙俿壔偵偁傢偣丆峔撪偺壦慄愝旛傪娙慺壔偡傞偨傔乽曽柺暿堎憡偒揹曽幃乿傊夵廋偡傞岺帠傪峴偭偰偄傑偡丅
乮仏侾乯怴姴慄塣揮尋媶夛曇乽怴斉丂怴姴慄乿乮1984乯pp.154-179
丂仜1-6-3.廳壦慄壔偲崅懍壔懳墳
丂崅懍塣揮偱僷儞僞僌儔僼偺捛悘惈傪崅傔傞偨傔偵搶奀摴怴姴慄偺壦慄乮僩儘儕慄乯梡偲偟偰摫擖偟偨乽崌惉僐儞僷僂儞僪僇僥僫儕乿偼丆侾楍幵摉偨傝楢懕俇乣俉屄偺僷儞僞僌儔僼偑捠夁偡傞応崌偵偼偐偊偭偰捛悘惈傪懝偹傞偙偲偑傢偐偭偨偨傔丆僷儞僞僌儔僼偺墴偟忋偘偵懳偟偰曄埵偺彮側偄廳壦慄乽僿價乕僔儞僾儖僇僥僫儕乿乽僿價乕僐儞僷僂儞僪僇僥僫儕乿傪摫擖偟偰偄傑偡乮仏侾乯丅偙偺壦慄偼僩儘儕慄偺抐柺愊偑170暯曽mm傕偁偭偰丆嫮晽偱傕梙傟偵偔偔丆抐慄摍偺怱攝傕側偄峔憿偱偡乮仏俀乯丅
丂偟偐偟偦偺屻偺尋媶偱丆偝傜側傞崅懍壔偵懳墳偡傞偵偼丆壦慄偼寉偄曽偑椙偄偙偲偑傢偐偭偰偒傑偟偨丅摿偵僩儘儕慄偺怳摦偑墶攇偲側偭偰揱傢傞g摦揱攄懍搙蓷駧詡獘邆脗瓊苼C僷儞僞僌儔僼偑捠夁偡傞嵺偵僩儘儕慄偑嫮偔嬋偘傜傟丆棧慄偑懡敪偟傑偡丅徻偟偔偼乽俀亅俁丏惙壀亅怴惵怷娫乿偱夝愢偟傑偡偺偱丆偙偙偱偼棧慄棪傪幚梡揑側斖埻偵梷偊傞偵偼僷儞僞僌儔僼偺捠夁懍搙偼僩儘儕慄偺攇摦揱攄懍搙偺俈妱掱搙傑偱偵梷偊傞昁梫偑偁傞偙偲傪婰偡偵偲偳傔傑偡丅
丂嶳梲丒搶杒丒忋墇偺奺怴姴慄偵巊傢傟偰偒偨僩儘儕慄亖乽僿價乕僐儞僷僂儞僪僇僥僫儕乿(抐柺愊170暯曽mm)傪挘椡1.5t偱堷偭挘偭偨応崌丆攇摦揱攄懍搙偼324km/h偱偁傝丆嫋梕懍搙偼230km/h掱搙偟偐偁傝傑偣傫乮仏1乯丅攇摦揱攄懍搙偼丆僩儘儕慄傪堷偭挘傞挘椡偲丆抐柺愊偺暯曽崻偺斾偵斾椺偡傞偺偱丆懍搙傪忋偘傞偵偼僩儘儕慄傪寉偔偟丆嫮偔堷偭挘傟偽傛偄偙偲偵側傝傑偡丅偦偙偱傛傝寉偔偰嫮搙偺偁傞僩儘儕慄偵挘傝懼偊傞偙偲偑昁梫偱偡偑丆搶杒丒忋墇怴姴慄偱偼慡慄偱僩儘儕慄偺挘傝懼偊傪峴偆偺偼搳帒懳岠壥偵媈栤偑偁傞偲偟偰丆廬棃偲摨偠乽僿價乕僐儞僷僂儞僪僇僥僫儕乿(抐柺愊170暯曽mm)偺傑傑偱挘椡傪1.8t傑偱堷偒忋偘丆攇摦揱攄懍搙傪389km/h傑偱堷偒忋偘傞曽朄傪偲傝傑偟偨丅偙傟偵傛傝僷儞僞僌儔僼捠夁懍搙偲偟偰偼272km/h傑偱懳墳偱偒傞偙偲偵側傝丆275km/h塣揮偑壜擻偲側偭偰偄傑偡丅
丂側偍搶奀摴怴姴慄偱偼丆250km/h埲忋偱憱峴偡傞嬫娫偵偮偄偰廬棃偺乽僿價乕僐儞僷僂儞僪僇僥僫儕乿偵懼偊偰峾恈偵摵傪姫偄偨俠俽俢僩儘儕慄(抐柺愊170暯曽mm)傪2.0t乮廬棃1.5t乯偱堷偭挘偭偰偄傑偡丅偙偺応崌偺攇摦揱攄懍搙偼416km/h丆僷儞僞僌儔僼捠夁懍搙偲偟偰偼291km/h傑偱懳墳偱偒傑偡乮仏俀乯丅嶳梲怴姴慄偱偼偙傟偵壛偊偰丆堦晹嬫娫偱峾偵傾儖儈傪姫偄偨俿俙僩儘儕慄(抐柺愊150暯曽mm)傪2.0t偺挘椡偱挘偭偨嬫娫傕偁傝丆偙偺応崌偺攇摦揱攄懍搙偼500km/h埲忋丆僷儞僞僌儔僼捠夁懍搙350km/h埲忋偺惈擻偑妋曐偝傟偰偄傑偡乮仏俁乯丅
乮仏侾乯怴姴慄塣揮尋媶夛曇乽怴斉丂怴姴慄乿乮1984乯pp.154-179傛傝丅
乮仏俀乯丗徏杮夒峴乽揹婥揝摴乿p.140傛傝丅
乮仏俁乯丗奀榁尨峗堦乽怴姴慄乿p.141傛傝丅
丂1-7.憶壒丒怳摦杊巭懳嶔
丂搶奀摴怴姴慄偱偺嫵孭傪惗偐偟丆奐嬈帪偐傜慡嬫娫偵崅偝俀倣偺杊壒暻傪愝抲偟偨傎偐丆巗奨抧偵偮偄偰偼丆傛傝幷壒岠壥偺崅偄媡俴帤宆杊壒暻乮崅偝5.5倣乯傗僨儖僞宆杊壒暻傪奐敪丆愝抲偟偰偄傑偡丅峾嫶偼偡傋偰俹俠僐儞僋儕乕僩嫶偵曄峏偝傟傑偟偨丅
丂乧埲忋偑嶳梲怴姴慄偲偺嫟捠揰偱偡丅偟偐偟搶杒丒忋墇怴姴慄偼丆嶳梲怴姴慄偱偺嫵孭傪摜傑偊丆偝傜偵夵椙偑巤偝傟偰偄傑偡丅
丂1-8丏壸廳愝寁 乣廳検偺憹壛偵懳墳丆壿暔偼峫椂偣偢乣
丂嶳梲怴姴慄(壀嶳亅攷懡娫)偲搶杒怴姴慄偱愝寁偑堎側傞揰偲偟偰偼丆壸廳寁嶼帪偵壿暔揹幵偺戝検塣峴傪峫椂偟偰偄側偄偙偲偑嫇偘傜傟傑偡丅
丂嶳梲怴姴慄偱偼壿暔楍幵偺塣峴偑寁夋偝傟偰偄偨偨傔丆椃媞揹幵梡偺俹昗弨妶壸廳偲壿暔揹幵梡偺俶昗弨妶壸廳傪憐掕乮偄偢傟傕幉廳偼16t乯丆戝晹暘偺峔憿暔偑傛傝塭嬁偺戝偒偄俶昗弨妶壸廳偱愝寁偝傟偰偄傑偟偨丅
丂偙傟偵懳偟丆搶杒怴姴慄偱偼乽傎偲傫偳椃媞揹幵偱偁傞偺偱俶昗弨妶壸廳偼峫椂偟側偄偑丆幵椉偑260km/h塣揮偺偨傔偺弌椡岦忋丆愥奞懳嶔丆堎廃攇懳嶔摍偺廳検憹壛偺梫慺偑懡偔嵟戝幉廳偼17t掱搙偵側傞偙偲偑梊憐偝傟偨偨傔丆幉廳17t偵懳偡傞俹昗弨妶壸廳傪嵦梡乿偟偰偄傑偡乮仏俁乯丅扐偟乽偙傟偺傒偱偼丆僗僷儞偺挿偄嫶傝傚偆偼嫮搙偑彫偝偔側傞偺偱丆幉廳17t偺俹昗弨妶壸廳偺傎偐偵廬棃偳偍傝偺幉廳16t偺俶昗弨妶壸廳傪偁傢偣偰嵦梡乿偟偰偄傑偡乮仏侾乯丅
乮仏1乯怴姴慄塣揮尋媶夛曇乽怴斉丂怴姴慄乿乮1984丆擔杮揝摴塣揮嫤夛乯pp.136-137丅杮暥偺捠傝丆俹昗弨妶壸廳偼椃媞揹幵梡偺妶壸廳偱丆幵懱挿20m丆幉嫍2.2m偺楍幵傪憐掕偟偰偄傞丅偙傟偵懳偟俶昗弨妶壸廳偼摦椡暘嶶僞僀僾偺壿暔揹幵傪憐掕偟偨妶壸廳偱偁傝丆幵懱挿13.5m丆幉嫍2.2m偺楍幵傪慜採偲偟偰偄傞丅
丂1-9. 俙俿俠偺夵椙丂乣俀廃攇壔丆婳摴夞楬偺抁弅丆媡慄260km/h壔乣
丂怴姴慄偺埨慡偺崻姴傪惉偡俙俿俠偵偮偄偰傕戝夵椙偑壛偊傜傟傑偟偨丅
丂仜1-9-1.怣崋攇偺俀廃攇壔(怣崋抜偺捛壛)
丂傑偢怣崋攇偺乽俀廃攇乿壔偑嫇偘傜傟傑偡丅偡側傢偪崱傑偱侾庬椶偺廃攇悢傪憲偭偰幆暿偟偰偄偨俙俿俠怣崋乮侾廃攇幃乯傪丆俀庬椶偺廃攇悢傪梡偄丆偦偺慻傒崌傢偣偱幆暿偡傞乽俀廃攇幃俙俿俠乿偵曄峏偟傑偟偨丅
丂偙偺偙偲偱丆俙俿俠怣崋偺怣棅惈偑崅傑傝傑偟偨丅摿偵俁庬椶偁傞掆巭怣崋偺偆偪丆柍揹棳忬懺傪怣崋偲偟偰擣幆偝偣傞偨傔僲僀僘乮嶨壒揹攇乯偺塭嬁偑栤戣帇偝傟偰偄偨乽俷2怣崋乿偲丆儖乕僾僐僀儖忋傪捠夁偡傞偙偲偱怣崋傪庴怣偡傞偨傔撉傒庢傝僄儔乕偺婋尟偑巜揈偝傟偨乽俷3怣崋乿偵偮偄偰丆愱梡偺廃攇悢偺慻傒崌傢偣偑妱傝怳傜傟偨偙偲偼丆怴姴慄偺埨慡惈傪崅傔傞庢傝慻傒偲偟偰拲栚偝傟傑偡乮偦傟偧傟偺掆巭怣崋偺堄枴偵偮偄偰偼丆昞俀偺乮仸俁乯嶲徠偺偙偲乯丅
丂摨帪偵怣崋偺庬椶傪廬棃偺俉庬椶乮偆偪俀庬椶偼抧忋巕敪怣偲柍揹棳忬懺乯偐傜嵟戝30庬椶傑偱憹傗偡偙偲傕壜擻偵側傝傑偟偨丅偙偺惉壥傪妶偐偟丆搶杒丒忋墇怴姴慄偼愝寁帪偐傜愝寁嵟崅懍搙偵懳墳偡傞怣崋抜(庡10.0Hz仌暃16.5Hz)偑梡堄偝傟偰偄傑偟偨丅寁夋抜奒偱偼偙偺怣崋抜偼乽260km/h怣崋乿偲側傞梊掕偱偟偨偑丆徍榓58擭俉寧23擔偐傜栺侾廡娫偺尰帵帋尡傪宱偰摨俋寧侾擔傛傝乽240km/h怣崋乿偲偟偰巊梡偝傟丆尰嵼偵帄偭偰偄傑偡乮仏侾乯丅
丂昞俀偲昞俁偼丆侾廃攇帪戙偺搶奀摴丒嶳梲怴姴慄偺怣崋尰帵偲丆俀廃攇偵側偭偨尰嵼偺奺怴姴慄偺怣崋尰帵傪斾妑偟偨傕偺偱偡丅
丂側偍搶奀摴怴姴慄偺俙俿俠偼1990擭搙偵丆嶳梲怴姴慄偺1992擭搙偵丆偦傟偧傟俀廃攇曽幃偺俙俿俠偵峏怴偝傟偰偄傑偡丅
乮仏13乯怴姴慄塣揮尋媶夛曇乽怴斉丂怴姴慄乿乮1984乯p.226媦傃p.455
| 乮昞俀乯侾廃攇曽幃偺崰偺搶奀摴丒嶳梲怴姴慄偺俙俿俠怣崋 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乣乽怴斉丂怴姴慄乿p.226傛傝乣丂丂丂丂丂丂 |
| 怣崋庬暿 | 怣崋攇 | |
| 210km/h(220km/h) | 侾侽俫倸 | |
| 160km/h(170km/h) | 侾俆俫倸 | |
| 110km/h(120km/h) | 俀俀俫倸 | |
| 70km/h | 俀俋俫倸 | |
| 30km/h | 俁俇俫倸 | |
| 掆 巭 |
俷1 | 俁俇俫倸亄俹揰 |
| 俷2 | 柍揹棳 | |
| 俷3 | 柍曄挷 | |
| 乮昞俁乯俀廃攇曽幃偲側偭偨尰嵼偺怴姴慄偺俙俿俠怣崋 丂丂丂丂丂丂丂乣徏杮丂夒峴乽揹婥揝摴乿p.254媦傃乽怴斉 怴姴慄乿p.226傛傝乣丂丂丂丂丂丂 |
| 侾俀丏侽俫倸 | 侾俇丏俆俫倸 | 俀侾丏侽俫倸 | 俀俈丏侽俫倸 | 俁俀丏侽俫倸 | 俁俉丏俆俫倸 | |
| 侾侽丏侽俫倸 | 俀俀侽km/h 丂丂亅 |
俀俈俆km/h(仸1) 俀係侽km/h(仸2) |
愗懼怣崋 俀俇侽km/h (仸4) |
俀俁侽km/h 俀侾侽km/h |
俀俆俆km/h (仸5)丂丂亅 |
俷3怣崋 俷3怣崋 |
| 侾俆丏侽俫倸 | 丂丂亅 丂丂亅 |
丂丂亅 丂丂亅 |
侾俈侽km/h 侾俇侽km/h |
丂丂亅 丂丂亅 |
丂丂亅 丂丂亅 | |
| 俀俀丏侽俫倸 | 侾俀侽km/h 侾侾侽km/h |
丂丂亅 丂丂亅 |
丂丂亅 丂丂亅 |
丂丂亅 丂丂亅 |
丂丂亅 丂丂亅 | |
| 俀俋丏侽俫倸 | 丂俈侽km/h 丂俈侽km/h |
丂丂亅 丂丂亅 |
丂丂亅 丂丂亅 |
丂丂亅 丂丂亅 |
丂丂亅 丂丂亅 | |
| 俁俇丏侽俫倸 | 丂丂亅 丂丂亅 |
俁侽侽km/h(仸3) 丂丂亅 |
丂丂亅 丂丂亅 |
俁侽km/h 俁侽km/h |
丂丂亅 丂丂亅 | |
| 係侾丏侽俫倸 | 丂丂亅 丂丂亅 |
丂丂亅 丂丂亅 |
丂丂亅 丂丂亅 |
俷2E怣崋(仸6) 俷2E怣崋 |
丂丂亅 丂丂亅 | |
| 惵帤偼搶奀摴丒嶳梲怴姴慄丆愒帤偼搶杒丒忋墇怴姴慄 乮仸侽乯丗俀偮偁傞乽怣崋攇乿偺偆偪丆僞僥偺楍傪乽庡怣崋攇乿丆儓僐偺楍傪乽暃怣崋攇乿偲屇傇丅 乮仸侾乯丗搶奀摴怴姴慄偱偼270km/h怣崋乮亖嵟崅懍搙乯偱偁傞丅 乮仸俀乯丗俤俀宯側偄偟俤俁宯丆200宯偺摿掕偺曇惉(俥90乣93曇惉)偱慻惉偝傟偨楍幵偵偮偄偰偼丆僩儔儞僗億儞僟傪巊偭偰幵椉懁偲抧忋偱乽崅懍嫋壜乿忣曬傪傗傝偲傝偟偰丆塅搒媨亅惙壀娫媦傃忋栄崅尨亅塝嵅娫乮壓傝慄乯偱240km/h怣崋傪庴怣偟偨応崌丆275km/h怣崋偵撉傒懼偊傞丅傑偨200宯偺摿掕偺曇惉乮俫曇惉側偳乯偱偼摨條偵245km/h怣崋偵撉傒懼偊傞丅 乮仸俁乯丗嶳梲怴姴慄惣柧愇亅攷懡娫偱偺傒尰帵偝傟傞丅 乮仸係乯丗杒棨乮挿栰乯怴姴慄乮崅嶈亅挿栰娫乯偱偼260km/h怣崋偲偟偰擣幆偡傞丅 乮仸俆乯丗255km/h怣崋偼搶奀摴怴姴慄偵偍偗傞俼2,500偺嬋慄惂尷梡怣崋丅 乮仸俇乯丗俷2E怣崋偼廬棃偺俷2怣崋偲摨偠尰帵撪梕丅扐偟掆揹帪偼俙俿俠怣崋揹棳偑棳傟側偄偺偱丆柍揹棳亖廬棃偺俷2怣崋偲側傞丅 乮仸俈乯丗壓埵偺嵟崅懍搙偺楍幵偱偼丆俙俿俠怣崋傕壓埵懁偵撉傒懼偊傜傟傞丅偨偲偊偽嵟崅懍搙偑270km/h偺300宯幵椉偺応崌丆300km/h怣崋傪庴怣偟偰傕丆塣揮戜偵偼乽270km/h怣崋乿偑昞帵偝傟傞偙偲偵側傞丅 乮仸俉乯丗斃憲攇偺廃攇悢偼丆壓婰偺捠傝丅 亂庡怣崋攇丒60Hz嬫娫亃壓傝慄丗840Hz側偄偟1,020Hz丂忋傝慄丗720Hz側偄偟900Hz 亂庡怣崋攇丒50Hz嬫娫亃壓傝慄丗850Hz側偄偟1,000Hz丂忋傝慄丗750Hz側偄偟900Hz 亂暃怣崋攇亃揹尮廃攇悢傗忋壓慄傪栤傢偢1,200Hz 乮仸俋乯丗嬻棑偼尰嵼怣崋偑愝掕偝傟偰偄側偄偙偲傪帵偟偰偄傞丅偙偺偙偲偐傜丆尰帵傪懡條壔偝偣傞壜擻惈偑廫暘偁傞偙偲偑傢偐傞丅 | ||||||
乮幨恀係乯 |
|
1973擭偵婲偒偨僆乕僶乕儔儞帠屘乮捁帞帠屘乯偺嫵孭偐傜丆僐僀儖傪俀廳壔偟偰怣棅惈傪岦忋丅 2002/04/28丂9:30丂搶杒怴姴慄 惙壀墂忋傝杮慄(12斣慄) 怴惵怷曽偵偰 |
丂仜1-9-2.暵嵡嬫娫偺抁弅
丂崅懍塣揮偱偁傝側偑傜塣揮帪妘傪弅傔傞偨傔丆侾偮偺暵嵡嬫娫傪廬棃偺2.4乣3.0km偐傜1.2km偵曄峏丆彮偟偱傕楍幵偲楍幵偺娫妘傪弅傔傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵偟傑偟偨丅
丂仜1-9-3.媡慄塣揮壜擻側愝旛乮憃曽岦260km/h塣揮偺幚尰乯
嶳梲怴姴慄偱偼弴曽岦260km/h丆媡曽岦210km/h偩偭偨塣揮懍搙傕丆搶杒怴姴慄偱偼椉曽岦偲傕260km/h塣揮偑壜擻側傛偆偵夵傔傜傟傑偟偨丅揹婥愝旛乮壦慄僙僋僔儑儞乯傕憃曽岦260km/h塣揮偑壜擻側傛偆愝寁偝傟偰偄傑偡丅偙傟偵傛傝丆栭峴楍幵塣揮帪傕摿偵尭懍偡傞偙偲側偔扨慄塣揮偑壜擻偲側傝傑偟偨乮仏俀乯丅
乮仏俀乯丗怴姴慄塣揮尋媶夛曇乽怴斉丂怴姴慄乿乮1984乯p.175
丂俀亅10. 懴姦懴愥愝旛偺廩幚
丂杒擔杮偵怴姴慄傪憱傜偣傞偨傔偵丆旔偗偰偼捠傟側偄壽戣偑愥偺栤戣偱偟偨丅摿偵搶奀摴怴姴慄偱偼娭儢尨抧嬫偱偺愊愥偵傛傝丆枅擭楍幵抶墑偺旐奞偑憡師偄偱偍傝丆揝摴偺摿挜偱偁傞掕帪惈傪庣傞揰偐傜傕枩慡偺懱惂偑偲傜傟偰偄傑偡丅
丂戝媨亅惙壀娫偺応崌丆傕偭偲傕懡偔愥偑崀傞杒忋抧嬫偱傕丆10擭妋棪偱偺嵟戝愊愥怺偼75cm掱搙偱偁傝丆慄楬忋偺愥傪楍幵偺僗僲僂僾儔僂乮愥偐偒婍乯偱慄楬偺奜懁偵挼偹旘偽偟丆慄楬榚偺崅壦嫶撪偵挋傔傞懳嶔偱廫暘偲敾抐偝傟傑偟偨丅
丂偙偺偨傔丆幨恀偺傛偆偵搶杒怴姴慄傪憱傞楍幵偺愭摢偵偼僗僲僂僾儔僂偑愝偗傜傟偰偄傑偡丅
 乽挋愥曽幃乿偼僗僲僂僾儔僂偐傜偺攔愥偑慜採偲側傞丅 200宯偺宱尡偐傜僗僲僂僾儔僂偼彫宆壔偝傟丆掅憶壒壔偺偨傔撍婲傕傎偲傫偳側偄丅 2000/08/09丂16:00崰丂愬戜憤崌幵椉強偵偰乮尒妛拞偵嫋壜傪摼偰嶣塭乯 |
丂捠忢偺僗儔僽婳摴偺儗乕儖柺(R.L.亖Rail Level丆埲壓摨偠)偼丆崅壦嫶偺彴柺偐傜40cm傎偳偺偲偙傠偵偁傝傑偡偑丆愊愥怺30cm埲忋偑梊憐偝傟傞嬫娫偱偼丆僗儔僽婳摴傪22cm偐偝忋偘偟偨彴柺崅62cm(R.L)偲偟丆僗儔僽婳摴偺奜懁傪栺50cm峀偔偲偭偨乽挋愥幃崅壦嫶乿偲偟傑偟偨乮仏侾乯丅
丂扐偟丆杒忋巗奨抧偺栺3km偵偮偄偰偼丆愊愥怺50cm掱搙偑梊憐偝傟傞忋丆愥偺晳偄忋偑傝偵傛傝増慄柉壠摍偵塭嬁傪媦傏偡偙偲偑寽擮偝傟傞偨傔丆悈傪嶵偄偰婳摴忋偺愥傪徚偡傛偆偵偟偰偄傑偡丅偙傟傪翋釙麕偲屇傃傑偡丅乽徚愥曽幃乿偼幨恀偺傛偆偵忋墇怴姴慄偺柧偐傝嬫娫偺愥懳嶔偺曽朄偲偟偰抦傜傟偰偄傑偡丅
丂嶵偄偰偄傞悈偼悈壏12乣16亷偵曐偨傟丆悈検偼侾噓摉偨傝侾儕僢僩儖乛暘掱搙丆塉検姺嶼60乣70mm偱傎傏廤拞崑塉偵旵揋偟傑偡丅忋墇怴姴慄偱偼斾妑揑壏偐偄僩儞僱儖撪偺桸悈傪棙梡偱偒傞嬫娫傕偁傝傑偡偑丆杒忋抧嬫偺応崌偼儃僀儔乕偵傛傝愳偺悈傪暒偐偟偰巊梡偟偰偄傑偡乮仏俀乯丅
乮仏侾乯丗亀揝摴
岡攝廲抐恾偺椃丂搶杒慄丒墱塇慄亁乮彫妛娰,1986乯p.38
乮仏俀乯丗怴姴慄塣揮尋媶夛曇乽怴斉丂怴姴慄乿乮1984丆擔杮揝摴塣揮嫤夛乯pp.149-150
丂丂丂丂徚愥偵偼12乣16亷偺壏悈傪梡偄丆嶵悈検偼侾噓摉偨傝侾儕僢僩儖乛暘丆崀悈検姺嶼偱60乣70mm偲廤拞崑塉暲傒偱偁傞丅
 忋墇怴姴慄 墇屻搾戲墂峔撪丂Max偁偝傂317崋 俀奒惾傛傝乯 1999/12/19 乮317俠亖墇屻搾戲拝12:59 俤侾宯俵俇曇惉乯 |
丂堦曽丆墂晹偵偮偄偰偼栭娫棷抲偺壜擻惈傗忔媞僒乕價僗傕峫偊丆愊愥偑梊憐偝傟傞堦僲娭丒杒忋丒惙壀偺俁墂偵偮偄偰墂晹慡懱傪暍偆壆崻偑愝偗傜傟傑偟偨丅愬戜墂傕拞墰晹偼壆崻偱偡偭傐傝暍傢傟偨峔憿偱偡丅墂慡懱傪暍偆壆崻偼丆忋墇怴姴慄忋栄崅尨埲杒偲嫟偵丆偦偺屻怴愝偝傟偨悈戲峕巋丒怴壴姫偺椉墂偵傕摜廝偝傟偰偄傑偡丅
 偙偺懠丆堦僲娭丒悈戲峕巋丒杒忋丒怴壴姫傕墂慡懱傪壆崻偱暍偭偰偄傞丅 2002/04/28 丂9:35丂俤係宯俹係曇惉(31B摓拝屻) |
丂俀亅11.丂傑偲傔乣楢懕偟偨300km/h塣揮偑壜擻乣
丂偙傟傜傪僩乕僞儖偟偨寢壥丆戝媨亅惙壀娫偵偮偄偰偼丆愬戜丒惙壀晅嬤偺堦晹傪彍偄偰丆尰嵼偱傕楢懕偟偨300km/h塣揮傪壞搤栤傢偢峴偆偙偲偑壜擻偱偡丅岡攝偵偮偄偰傕娚偄婯奿偱愝掕偝傟偰偄傞偨傔丆14乣15侎偺僩儞僱儖嬫娫傪娷傓孲嶳亅暉搰娫側偳傪彍偄偰300km/h偺掕懍塣揮偑偱偒傑偡偟丆慜弎偺嬫娫偱傕岡攝偺嫍棧偼挿偔側偄偺偱丆295km/h掱搙傑偱棊偪偨偲偙傠偱嵞壛懍偱偒傞傛偆側慄宍偲側偭偰偄傑偡丅
丂偦傟埲忋偺僗僺乕僪傾僢僾丆偨偲偊偽320km/h壔偵偮偄偰偼丆尰嵼偺僇儞僩検傪慜採偲偡傞偲丆昗弨嵟彫嬋慄偱偁傞R4,000偲R5,000偱惂尷傪庴偗傞偙偲偵側傝傑偡丅偡側傢偪戝媨亅惙壀娫偱25儢強偺俼4,000(戝媨丒愬戜丒惙壀廃曈偺惂尷偲側傜側偄屄強傪彍偔)偲俁儢強偺俼5,000乮摨忋乯偱偼丆惂尷懍搙偑偦傟偧傟300km/h丆315km/h偲側傝傑偡丅偝傜偵崅懍偺330km/h壔偱偼丆R6,000傕325km/h偺惂尷屄強偲側傝傑偡丅扐偟僇儞僩検偺堷偒忋偘傪慜採偲偡傟偽丆R4,000偑320km/h丆R5,000偼370km/h埲忋偲側傝丆栤戣偼偐側傝彫偝偔側傝傑偡乮仏侾乯丅
乮仏侾乯搶杒怴姴慄寶愝帪偺奺嬋慄偺僇儞僩検偼丆R4,000亖155mm丆R5,000亖120mm丆R6,000亖100mm丆偱偁偭偨丅偙偺僇儞僩検偱丆偨偲偊偽R4,000傪260km/h偺楍幵偑捠夁偟偨偲偒偺忔媞偑姶偠傞僇儞僩晄懌検偼44mm偲側傞丅摉帪偺崙揝偼忔傝怱抧偺揰偐傜丆僇儞僩晄懌検偼60mm埲撪丆偱偒傟偽30mm埲撪偵廂傔傞偺偑朷傑偟偄偲偟偰偄偨丅
丂尰嵼偺俰俼偼懡彮忔傝怱抧傪媇惖偵偟偰傕嬋慄捠夁懍搙偺岦忋傪恑傔傞娤揰偐傜丆僇儞僩晄懌検偼110mm傑偱嫋梕偟偰偍傝丆偙偺帪偺惂尷懍搙偼丆R4,000亖300km/h丆R5,000亖315km/h丆R6,000亖325km/h偱偁傞丅偟偐偟僇儞僩検帺懱傪尷奅偺190乣200mm傑偱堷偒忋偘傞慜採偱偁傟偽丆R4,000亖325km/h丆R5,000亖370km/h埲忋偲側傝丆320km/h塣揮偱偼帠幚忋丆惂尷偱偼側偔側傞丅扐偟僗儔僽婳摴偺僇儞僩検堷偒忋偘偼丆夁嫀偵傎偲傫偳椺偑側偄偨傔丆媄弍揑丒宱嵪揑専摙偑昁梫偱偁傞丅