「だからオマエの事、大好きだよオレは」
睦言のような甘さでシャンクスは囁いたが、うかうかと騙されるものかとベックマンは自戒する。
「…今話してたのは、そういう事じゃあないだろう」
不自然にならないように歯で咥えた煙草を離し、白煙に溜息を混ぜて吐いた。
シャンクスの言葉は大いにベックマンを動揺させていたし、自身もその動揺を自覚していた。この人の狙いが自分を動揺させる事にあったのなら、その狙いは成功した事になる。それは少し癪だ。
しかしながらシャンクスは、ベックマンのそうしたちっぽけなプライドをすら容易く打ち崩す人間だった。
「オレにはオマエの言葉が、そういう事言って欲しいように聞こえたけどな?」
「…アンタの口から出る"好き"ほど厄介なモンはねェな…」
「どーゆう意味だよ」
「アンタの"好き"は、細分化されてねェってことだ」
すると、シャンクスはベックマンをちらりと一瞥した。 薄い唇に、うっすら笑みを刷く。人を食ったような笑みは、決して自分以外の仲間に向けられる事はない。
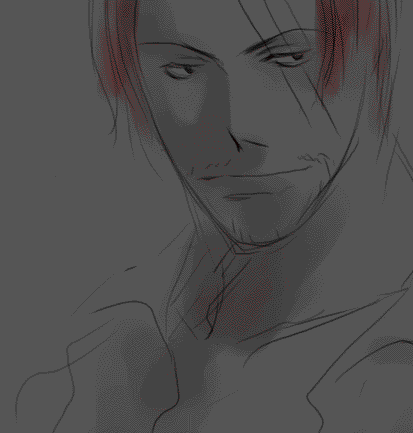
出来の悪い子供を見るような斜めからの視線を、ベックマンは真っ直ぐ受けた。
室内なのに微風が吹いたような気がした。シャンクスの、空っぽの左袖が揺れた所為かもしれない。
「"好き"に意味はいらねェだろう」
予想通りの言葉に、自嘲を滲ませて苦笑する。彼ならばそう言うだろう。
海も。仲間も。船も。冒険も。ルフィも。
何もかも「好き」に間違いない。そんなことは知っている。わかっている。わかってはいるのだが。
割り切れぬ気持ちは表情に表れたのか、シャンクスは喉を鳴らして笑う。
「なんで好きなのか。どういう好きなのか。考えるのは面倒だろう。好きは好き、嫌いは嫌い。それでいいじゃねェか」
ベックマンは大きく溜息をついた。シャンクスの短絡的とも言える考え方に内心で舌打ちしながら、それでも羨ましいと思う。そんな風に割り切ってしまえていることが。彼のように単純に割り切ってしまえるものであれば楽だったのだろう。自分の、心が。
音もなくシャンクスは近寄り、ベックマンの頬を右手の甲で撫ぜた。目を細めて微笑っているのは、逆光でもわかる。慈しむような優しい表情。
だが、その眼がどんな色をして自分を見ているのかは、髪が落とす陰でわからない。
「悩む必要なんてねェ。さっきのオレの言葉に裏なんてないことくらい、わかれよ」
そこで一度口を閉ざし、苦笑した。
「…言葉は難しいな…」
言いたい事が逃げる。
シャンクスの言葉にベックマンは深く同意を示し、煙草をサイドテーブルに置いた灰皿に押し付けて消した。
憂鬱を色にすれば、真横から自分を射るこの月光のような蒼になるのだろうか…。 思って見上げた月は十六夜。
欠けた部分と欠けてゆく部分、どちらが不安の大きさか…思考は口付けによって中断された。